第3章:論理力&俯瞰力(3)音空間を俯瞰・要約する(文脈)

感受力&即応力
音楽は時間芸術である。音楽が流れている間に、さまざまな物語が進んでいく。どう始まり、どのような経過を経て、どう終わるのか。西洋音楽はそのストーリーの展開方法を進化させてきた。それがフレーズの流れであり、和声の進行であり、一部形式、二部形式、三部形式、ロンド形式、ソナタ形式・・・といった形式の展開である。
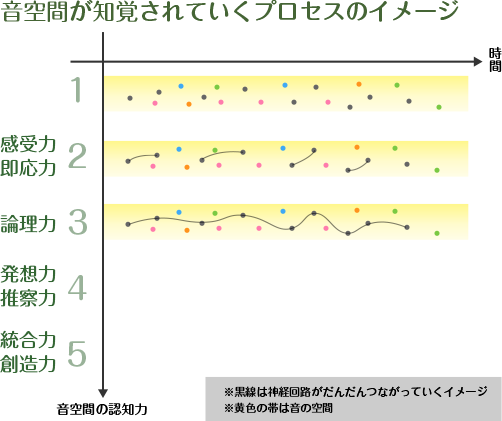
語られる物語や語り口が複雑になると、どんな文脈なのかが見えにくくなる。そこで、全体を俯瞰して特徴を捉えたり、要約する力がより求められてくる。英米などの大学でよく使われているというシェンカー分析によれば、シェンカーは「前景・中景・後景」という音型的還元によって、楽曲構造を段階的に捉えようとした。前景はほぼ楽譜に書かれてある表層部分、中景は動機的特徴や広域の和声的・対位法的動き、後景は基本構造(和声の基本線&バス分散化)である。そしてこのような基本構造がフレーズ、部分、楽曲全体に内在しているとした(『調性音楽のシェンカー分析』p56、59、p123―p125、アレン・キャドウォーラダー、デヴィッド・ガニェ共著、角倉一朗訳、音楽之友社、2013年)。
この音型的還元・和音への還元を経ることで、楽曲構造が簡略化して捉えられ(※)、和声がどのように線的進行を生み出しているのか、和声の諸原理が調的構造の中でどう働いているのか、ドミナントがどのように拡張・強化されているのか、といったエッセンスが浮き彫りになる。表面的には露わにされないが、内部で緊張感や推進力を高めている動き、といった内的な動機や相関関係もある。最近、内声を際立たせるという演奏を聴くことがあるが、その程度はさておき、内なる動機や伏線を読み解く試みなのかもしれない。なお、シェンカー分析はバロック、古典、ロマン派を中心に論じられている。全ての曲が明瞭に3つの構造から成るわけではないとしているが、考え方としては有用だろう。
人間の身体構造でいえば、肌・表皮(前景)⇒血流・筋肉の動き(中景)⇒骨格(後景)、と捉えられる。つまり外に見えている肌・表皮の内部では、筋肉や血流がどのような力学で動き、それらをどんな骨格が支えているのか、を探究していくのだ。
ストーリー展開が複層的に理解できていると、重要な音が聞こえて文脈が伝わりやすい演奏、構成感・構築力のある演奏になる。国際コンクールで聴いた演奏の中から、いくつかピックアップしてみたい。
2012年度リーズ国際コンクールでは、2人の英国出身ピアニストに共通してストーリーの読解力を感じた。クリストファー・マッキガンさん(Christopher Mckiggan、英国)のベートーヴェンのソナタOp.110は、音の行間を読みながら物語のごとくフレーズを繋げていき、必要な文脈を際立たせ、すっきりとクールなベートーヴェンであった。アレクサンダー・ウルマンさん(Alexander Ullman、英国)のベートーヴェンのソナタOp.110もストーリー性を意識した上で、テンポの緩急、ディナーミク、間の使い方などに個性が感じられた。(リーズ国際コンクール第二次予選)
ちなみに英国のギルドホール音楽演劇学校の初見クラスでは、2~3分位の曲を20分間で暗譜してから弾くという課題があるそうだ。大きく全体の流れを把握する力が求められる。(2013年度福田靖子賞オーディション審査員ロナン・オホラ先生)
さらに曲を俯瞰すると、調性や曲調の変化が相対的に捉えられ、全体が立体的な表情を帯びてくる。2015年度ショパン国際コンクールのセミファイナリスト、チー・ホー・ハンさん(Chi Ho Han、韓国)のスケルツォ4番Op.54はプレストで軽くさらっと始まり、再現部ではくっきり行進曲風に、そのフレームワークの中で、中間部では一音一音の意味や音色のバランスなどを考えながらじっくり歌う。すっきりしたさじ加減の構成力を見せた。また前奏曲Op.28では24曲全体のストーリーラインが考えられていた。中でも18番は最高音Fに入る絶妙な間の取り方や、最後の和音も十分にためてからfffで打鍵されるなど、高いエネルギーで前奏曲全体のクライマックスを迎え、19番以降は新たな命が吹き込まれて再出発し、24番は全てを振り返りながら決然とバス音Dが三度鳴らされた。(1次予選 、3次予選1日目「静かなクライマックス」)
同コンクール優勝のチョ・ソンジンさん(Seong-Jin Cho、韓国)も、俯瞰の視点から大きく曲想をとらえ、対比的な表現を試みていた。幻想曲Op.49は静寂の表現が深遠で、レント・ソステヌートは瞑想的なコラールのように、コーダは激情と夢想の対比が際立ち、最後は全てをのみ込むような決意に満ちた和音で締めくくった。幻想曲の性質を十分にとらえ、美しい幻想の断片の集合体のような印象に。(一次予選1日目)。文脈・曲間のフレージングまで考えられた前奏曲Op.28については前回述べたとおりである。
ストーリーラインを読み解いたら、それをどう語るのか、どんな音で伝えるのか?まず冒頭は物語のエッセンスを伝えてくれたり、問いかけや謎かけをしたり、物語全体を貫くテーマが示される。後はそれを展開しながら、解決に向けて進んでいく。いわゆる「説得力のある演奏」というのは、緊張が解決した瞬間に訪れる「!」という感覚でもあるだろう。シェンカーは、1曲全体の最上位にある線的進行を基本線と呼んだが、それは最初の頭音(倍音)から最後の基音へ下行する動きであり、音楽的緊張の解放と一致するとしている(『調性音楽のシェンカー分析』p124)。
冒頭から最後まで高い緊張感をもってストーリーを語っていたのは、2010年度ショパン国際コンクール優勝のユリアンナ・アヴデーエワさん(Yulianna Avdeeva、ロシア)。ノクターンop.62-1は最初の二音にすべてのエッセンスが込められ、打鍵が深く、陰影を帯びた音色と効果的な弱音によって、様々な表情を曲と楽器から引き出す。またスケルツォ4番op.54は、問いかけのような冒頭に対して、テーマを経て、中間部が一つの答えのように応答する。この中間部は別世界の美しさで、後半も変幻自在な色合いを帯びたパッセージが続き、最後に全てを解決する力強いコーダで締めくくられた(2010年度ショパン国際コンクール1次予選、優勝者インタビュー「真摯にショパンと向き合って」)
問いや緊張をどこまで持続させるか。ソナタの場合、第1楽章での問いが最終章で解決するという解釈もあるだろう。リーズ国際コンクール5位入賞のアンドリュー・タイソンさん(Andrew Tyson、米国)のベートーヴェンソナタOp.81a『告別』は、第1楽章冒頭3音目のぐっと内に入り込む音でこれからの展開を予感させ、行間にも多くの意味を含み、聴き手の集中力も逸らさない。第2楽章は抑制されたテンポの中で内省的にハーモニーを奏で、第3楽章は一転して緊張から解放され、歓喜の表情に。最後の主題の再現では、第1楽章からの物語がすべて凝縮されたようなエッセンスが詰まっていた。曲と正面から向き合いながら、自分の内面とも真摯に対話することによって、余計なものがそぎ落とされ、真実の音が出ていた(リーズ国際コンクール)
- 一部表記を変更しました。

