第67話『名もなきシェフの肖像(Ⅰ)♪』

より多くの芸術家と交流し、『夢の浮橋』の楽譜を集めるためには、19世紀で通用するコンポーザー・ピアニスト(作曲家兼ピアニスト)に成らねばならない。現代に一時帰国した鍵一は、京都貴船※1の叔父のアトリエに身を寄せた。古都の風景に19世紀パリの思い出を重ねつつ、『夢の浮橋変奏曲』※2の制作が進む。
款冬華
※3このごろ、鍵一は貴船の家に料理旅館の名残りを見つけた。叔父を手伝って裏庭の雪を掻いたとき、それは偶然に掘り出された。
「かまどですね?」と鍵一が弾んだ声を投げると、
「かまどなんだ?」と叔父はシャベルを付いて素ッ頓狂な返事をした。「タヌキの小屋かと思ってた」
確かにそれは、動物が寒さをしのぐための小屋に見えなくもなかった。ただし、19世紀のレストラン『外国人クラブ』の煉瓦のかまどによく似ていた。異国の地で友に再会したような心地で、鍵一は喜んでツララを解き、煤を拭いた。すると、自分の手で19世紀パリの味を再現してみたくなった。
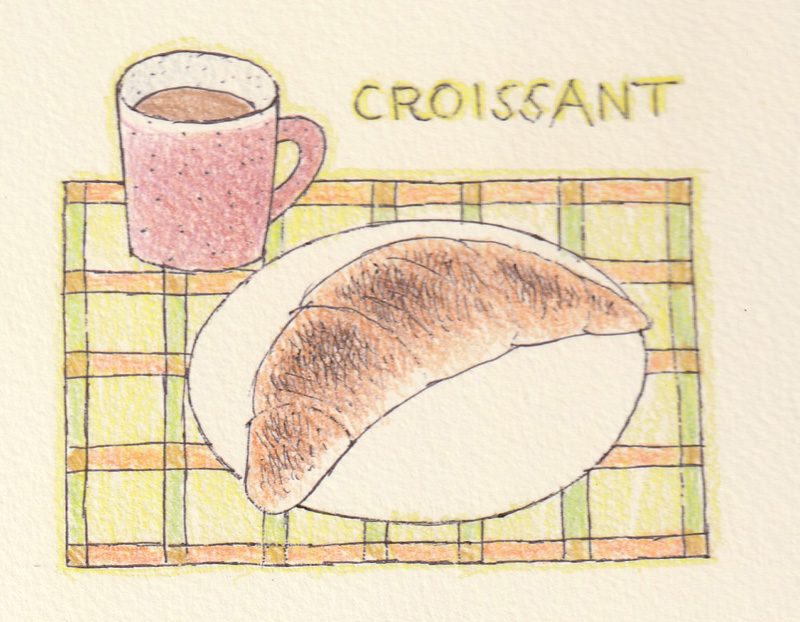
早朝にパン生地をこねるのは楽しかった。チェルニーのフーガを弾く要領で、両手首をやわらかく使って生地をひきのばす。 Allegro ma non troppo ※4で練り丸め、両手の交差を活かして転がし、この小麦粉と塩と水と酵母の構造物をまろやかに練り上げてゆく。
♪チェルニー作曲:フーガおよび多声音楽演奏のための教則本 Op.400
さらにバターを練り込むと、指の跳躍とともに生地がべたつく。耳たぶほどのやわらかさをめざしてAllegro comodo※5でこねてゆきながら、鍵一は『外国人クラブ』でのひとときを思い起こした。1838年の春、鍵一が身支度をして一階へ下りてゆくと、開店前のレストランは金色の匂いに満ちていた。……

――回想 シェフの肖像(1838年4月)
「おはようございます。いい匂いですね」
「おう、余熱であとすこし」
シェフは腰をかがめて、煉瓦造りのかまどを覗き込んでいる。鍵一も厨房を覗いてみて、そのしつらえの様子に圧倒された。天井まで届く大きな調理用暖炉。壁に吊り下げられたフライパンの数々。大小さまざまの鍋。ありとあらゆる種類の包丁。三つの蛇口のついた洗い場。棚にはスパイスやハーブを詰めたガラス瓶が所狭しと並んでいる。ぴかぴかに磨き上げられたそれら道具類が、料理人の腕の確かさを物語っていた。
「ケンイチがパリへ来て、もう一週間か」
シェフはかまどの鉄板を微妙に手前にずらして、「どうだ、パリの空気は。慣れたか」と火加減を調整した。
「はい、まだ散策も出来ていませんが……あの砂のおかげで※6夜はぐっすり眠れていますし、毎日ごはんが美味しいです。急に押しかけたのに、いろいろ良くして頂いて……本当にありがとうございます」
「好きなだけ居ていいぞ。サロン・デビューを目指そうッていう若い奴が居ると、店に活気が出ていい」
「ありがとうございます。あの、なにか手伝いましょうか」
「気持ちだけ貰っとくよ」と笑った。「手に怪我でもされちゃア、俺がフランツ・リストに怒られる。それに、素人に厨房をウロチョロされちゃ迷惑だ。ここは俺の仕事場なんだから」
「はいッ、すみません……メニューの味見や、レシピの代筆でしたら、ぜひやらせて下さい」
「そのうちな。当面のおまえの仕事は、プレイエルのピアノを練習することと、フランス語の勉強をすることだ。それから、猫に名前を付けることか」
「ああ、それでしたら……」
言いながら、ぱっちりした金色の目を思い浮かべた。夕暮れのオペラ座にひらりと現れた猫※7は、鍵一の傍でのびのびと暮らしていた。朝の窓を開けば、軽やかな身のこなしでどこかへ消えてしまう。かと思えば、夕暮れの窓辺でセーヌ川の夕焼けを眺めていたりする。鍵一がプレイエルを弾き出せば、「お手並み拝見」とばかりに、ピアノの上で目をほそめている。
(……考えてみると、ぼくはあの猫にずいぶん助けられた。猫を追いかけてパリ音楽院の角を曲がろうとして、リストさんにぶつかッて。そのご縁で、このレストランに連れてきてもらえた。猫をテーマにした即興演奏会では、3 人のヴィルトゥオーゾの方々の素晴らしい演奏を聴けた※8。一緒にいると、これからも良いことがありそうな気がする)

「あの猫は、『フェルマータ』と名付けました。金色の目が、音楽記号の『フェルマータ』の形に似ていたもので」
「いい名前だ。イタリア語で『停留所』ッて意味だな」
「停留所……」
その言葉を呑み込む前に、大量の香ばしい湯気が鼻先へ突き出された。
「さあお待ちどう、焼きたてのクロワッサン」
「わッ、ありがとうございます」
大皿へ盛られたクロワッサンがつやつやと輝いている。早速ひとつを取って頬張ると、熱いバターが指先に沁みた。
「熱ッ……美味しいです……!」
「フム、やっぱり鉄製よりも、煉瓦造りのほうがいいな」
厨房で思案する料理人に、鍵一は興味をもった。
「鉄のかまどと煉瓦のかまどでは、なにか違うのですか?」
「うん、鉄のかまどは最新式でね。強い火力を保てるから、グラタンやスフレも焼きやすい。でも熱の当たりが強すぎて、繊細な焼き上がりを追求するには不向きだ。昔ながらの煉瓦造りのかまどはレパートリーが限られるけど、温度の微妙な調整がしやすい。俺は両方試してみて、煉瓦のかまどに落ち着いた」
「フランス料理の世界にも、さまざまな変化があるのですね……!」
「料理の道具だけじゃない、パリでは今、至るところで旧式と最新式が入り混じってるんだ。たとえば……そうだな、午後にでもセーヌ川に行ってみるといい。昔ながらの帆船と最新式の蒸気船が両方見られる。眺めるなら断然帆船がいい。からっと晴れた日に、白い帆を立てた船が白鳥みたいに優雅にセーヌ川を下ってゆくのは、見ていて気持ちのいいもんだよ。その点、蒸気船なんてのは情緒もへったくれもないね。小雨のじとじと降る日に、煤だらけの蒸気船が真っ黒な煙を吐いてセーヌ川を遡ってく様子なんかは、なんだかちょっとね、笑っちゃうよね」
シェフは肩を揺すって、からっと晴れた日の洗濯物のような笑い声をたてた。
「ただし、蒸気船は格段にスピードが速い。このパリに 500 軒以上ひしめいてるレストランで新鮮な牡蠣やサーモンが食べられるのは、蒸気船がすばやく魚介類を運んで来てくれるからだ」
「そうなんですね……!そういえば、先日教えていただいたパリの 2 つの橋も、旧式の石造りの橋と、最新式の鉄製の橋でしたよね。確か『ポン・ヌフ』※9と、『ポン・デ・ザール』※10。このクロワッサンの焼き方にも、新旧それぞれのパリの様子が……熱ッ」
「ハハハ、たくさん食え。日本人にはクロワッサンなんて珍しいだろ」
シェフは鍵一の様子を嬉しそうに眺めて、自分もひとつを取って齧った。
「クロワッサンてのはおもしろいパンでね。どうやら 17 世紀から存在したらしいけど、どこの誰が最初に創ったのかは分からない。レシピの原本も発見されてない。
クロワッサンの発祥について、俗説ならいろいろあるんだ。17 世紀のウィーンの軍隊が、敵国トルコのシンボルになぞらえた三日月型のパンを食べて士気を高めた、とかさ。王妃マリー・アントワネットが御輿入れの時に、レシピをフランスに持ち込んだ、とかさ。どれも証拠がないけどね。
まア、ひとつだけ確かなのは、俺たち料理人は自分のかまどを持つと、三日月を焼かずにはいられないッてことだよ。レシピに工夫を凝らして、自分なりのクロワッサンを創り上げようとする」
「パリの他のお店では、また違ったクロワッサンが食べられるのでしょうか」
「うん、いま人気なのは、パレ=ロワイヤルの近くの、オーストリア人の店。ティータイムからオペラがハネるころまで、紳士淑女のみなさまでごった返してるよ。甘いクロワッサンでさ。ジャムを練り込んだり、中にクリームを挟んだり。オーストリア人にとっては、クロワッサンはウィーン菓子の一種なんだな。
まア、俺としちゃア、クロワッサンにはバターだね。絶対にバター。そいつを珈琲と一緒に、朝飯として客に出す。
そうだケンイチ、珈琲淹れてやるよ。どんなのがいい」
「ありがとうございます。なんでもいいです」
「おいおい、『なんでもいい』は駄目だろ」と、ほがらかに咎められた。
「このパリじゃ、自分の意思をハッキリと言葉にしなきゃ駄目だ。たとえ珈琲一杯のことでもさ」
「はいッ、すみません……」
「だいいち、珈琲大国フランスでは星の数ほど珈琲豆の種類があるんだから。うちの店だって30種類は常備してる」
「えッ、そんなにたくさん。あの、ぼく、珈琲にまったく詳しくなくて」
「今の気分を好きに言えばいいんだよ。それに合わせて、俺がベストな一杯を創ってやる。
たとえばカンカン照りの夏に飲みたい珈琲と、雪のちらつく冬に飲みたい珈琲は違うだろ。オペラ座に繰り出してド派手なグランド・オペラを楽しむぞというときの珈琲と、格調高いイタリア座で古典の名作に聴き入った後の珈琲は違うしさ」
「そ、そうですね、ええと……ちょっと待って下さい」
温かな三日月の皿に、胸の内を映してみる。言葉は湯気に誘われて、少しずつ陽に透けた。
「日本からパリに来て7日目の朝で、まだ少し眠たくて……でも、わくわくしてます。今はこの、バターのたっぷり入ったクロワッサンに合う、すっきりした珈琲が飲みたいような……あッ、でも猫舌なので、ぬるめのほうがありがたいです」
「よしわかった!」
シェフは大きくうなづくと、さっそく数種類の珈琲豆をブレンドして、ごりごりとミルを曳き始めた。

ふと、『猫のワルツ』を弾いたときの緊張がよみがえって※11、鍵一はひざこぞうを掻いた。見ればプレイエルのピアノは布で覆われて、店の奥でスヤスヤと眠っている。食器棚の上に、窓のそばに、向こうのテーブルの端に、芸術家たちの肖像画が輝いている。『ピアノの魔術師』ことフランツ・リストの肖像※12、『博学のヒラー』ことフェルディナント・ヒラーの肖像※13、『フランス・ピアノ界のエトワール』こと、シャルル=ヴァランタン・アルカンの肖像※14を見つけて、鍵一は深呼吸した。
やがてシェフが珈琲カップをふたつ持って来て、鍵一の斜向かいに座った。
「うちにある肖像画。みんな、今日もいい顔してるだろ」
「はい、まだお名前を存じ上げない方もいらっしゃいますが……」
「みんな、俺の店を気に入ってくれた芸術家の連中だ。若くて才能があって、野心とエネルギーを持ってる。俺の店にはそういうやつらが集まる」
「このレストランは、芸術家の集会所なんですね」
「最近じゃ『フェルマータ』……芸術家の『停留所』、というべきかな。才能あるやつらがそれぞれの旅路で途中下車して、俺の店に集って、また旅立ってゆく。気づけばみんなスターになってる。
なあケンイチ、おまえは久々の新顔なんだ。おまえがこれからどんなふうにパリを開拓してゆくのか、楽しみだよ」
「ぼくはたいした才能も自信も無いですけど……サロン・デビューめざして、がんばります」
「ハハハ。まあ、飲め。『パリ到着7日目の眠気覚まし、希望に満ちた猫舌のための一杯』」
差し出された珈琲をひとくち飲むと、なるほど、パリッと背筋が伸びる。
「今の気分にぴったりです。なんだか、勇気が湧いてきました……!」
「よし、好きなだけ飲んで食え。パリで名を上げるには体力が要るぞ」
「はいッ、いただきます」
珈琲を飲み、クロワッサンに手を伸ばしてふと、鍵一は重大なことに気づいた。
「名を上げる……名前、といえば……すみません!肝心のシェフさんのお名前を、まだ伺っていませんでした」
「ん?俺に名前なんてないよ」
「えッ、名前が……ない?」
「俺はね、この世にはもう居ない人間なんだよ」
「ええッ?」
おののく鍵一の前で、料理人は愉快そうに笑った。
つづく


日本最大級のオーディオブック配信サイト『audiobook.jp』にて好評配信中♪
第1話のみ、無料でお聴きいただけます。
幻の名曲『夢の浮橋』のモチーフを活かし、鍵一が作曲するピアノ独奏曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。
実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいました。
♪『夢の浮橋変奏曲』制作プロジェクトのご紹介
♪神山 奈々さん(作曲家)
♪片山 柊さん(ピアニスト)
フキノトウの花が咲く頃、の意。古代中国が発祥の暦「七十二候((しちじゅうにこう)」のうち、1/20~1/24頃にあたる時期。
音楽用語で『快活に速く、しかし速すぎないように』の意。
音楽用語で『ほどよく速く快活に』の意。
第5話『Twinkle Twinkle Little Start(きらきら光る小さなスタート)♪』をご参照ください。
第2話 『令和(Beautiful Harmony)♪』をご参照ください。
第3話 『ねこのワルツ♪』をご参照ください。
パリのシテ島の西端を挟んで、セーヌ川左岸と右岸を結ぶ橋。パリに現存する最古の橋です。
パリのフランス学士院とルーヴル宮殿を結ぶ橋。ルーヴル宮は第一帝政時代に『芸術の宮殿』と呼称されていたため、橋の名はPont des Arts(芸術橋)となりました。
※8をご参照ください。