第3話 『ねこのワルツ♪』

「さて、ケンイチ君。『Le Club des étrangers(外国人クラブ)』へようこそ」
フランツ・リストがレストランの扉を押しひらくや、こうばしい湯気が流れてくる。鍵一がそっと店内を覗きこむと、ふたりの紳士と目が合った。
(先客はふたりだけ……まさに、音楽家の秘密の隠れ家!)
「遅うなって、すまんなあ。音楽院の角で、素敵なアクシデントに遭うてしもて」
「あやうく、きみを待たずに『大彗星のヴィンテージ※1』を開けちゃうところだったよ」
大柄の紳士が向日葵のように明るく笑う。細身の紳士は肩をすくめて、
「リスト君は音楽院の悪魔に呪われてるんだよ。おでこに魔除けのお札でも貼っておいたら?※2
で、誰? その新入りの子」
紫陽花色の瞳で鍵一を見つめた。21世紀からワープして来たことまで見透かされそうな、その涼しい眼差しにおののきながら、鍵一は必死に音楽史の知識をたぐりよせる。
(リストさんのお友達なら、きっとこのおふたりも有名な音楽家……! でも、誰なんだろう。19世紀の音楽史に、こんな方々いらしたっけ)
「この子、日本人のケンイチ君ていうねん」
ふいに名前を呼ばれて、心臓が1オクターブ跳ねた。
「音楽の勉強のために、黄金の国ジパングから旅して来よってん。でも今はひとまず、猫探し中やねん。金色の眼の、つまさきの白い、フサフサの猫。おふたりさん、見てへん?」
「今日は猫一匹見てないなア。というか、このあたりにそんな猫いたっけ」
「猫の眼のような三日月なら、さっき見たけど」
「ウチは確かに見たことあるんよ、『ファウスト』のメフィストフェレスのような、すばしこくてミステリアスな猫」
「ハハハ。そりゃ、犬の見間違いでしょ」
音楽家たちはくつろいだ仕草で、飛び入りの訪問者のためにグラスや食器を並べ始めた。ぼんやりと戸口に立ち尽くしていた鍵一、
「ようこそケンイチ君、歓迎するよ」
大柄の紳士に握手を求められてようやく、我に返った。
「あの、急にお邪魔してすみません、ピアニストの卵の、鍵一と申します!」
「おれはドイツのフランクフルト出身でね、外国から来た音楽家同士、仲良くやろうや」
「ありがとうございます……!」
差し出された手を握ると、まるで焼きたてのライ麦パンのように、この紳士の手はふっくらと熱かった。感激しながらも鍵一は、相手が誰だかわからない。スパークリング・ワインのラベルを検めている紫陽花色の瞳の紳士が、
「今日は3人で静かに晩餐を楽しむつもりだったけど。ま、面白いものが見られるならいいか」
淡々と呟くのも耳にして、やっぱり誰だかわからない。ドイツ出身の音楽家は鍵一のいでたちを面白そうに眺めて、テーブルへ促した。
「日本人に会うのは初めてだ。ちょうど最近、シーボルトの日本研究書を読む機会があって、日本に興味を持っていたんだよ。すてきな民族衣装だ。長い船旅は大変だったろうに、このパリまで、よくぞ無事で辿り着いたねえ。さア、座って、座って」
「はいッ、お邪魔します」
テーブルの脚でひざこぞうをしたたかに打って、鼓動が速くなる。
(シーボルト! 江戸時代、日本に初めてピアノを持ち込んだドイツ人の医師だ。わッ、すると今、本当に日本は江戸時代なんだな。
それにしても、おふたりに名前を尋ねるのは失礼かしら。いや、インタビューのために遥々19世紀まで来たのだから、むしろ早く尋ねないと。いや、待てよ。もしリストさんと同じくらい有名な方々だとすると、面と向かって『どなたですか』とは聞きづらい……!)
「よし、今夜はケンイチ君の歓迎会や。まずは乾杯しよか」
鍵一の逡巡をよそに、音楽家たちは談笑しながらスパークリング・ワインのボトルを開けると、グラスになみなみと注ぎ始めた。金色の泡が星のようにきらめく。見惚れているうち、自分のグラスに注がれそうになって鍵一は慌てた。
「あッ、すみません、ぼくまだ18歳ですので、お酒はちょっと……あの、日本の法律では、お酒は20歳になってから、なんです」
音楽家たちがキョトンと振り向く。
「じゃ、日本では食事中に何を飲んでるの」
「ええと、お茶……でしょうか」
「お茶なんや!」
リストがのけぞって、鍵一ものけぞった。紫陽花色の瞳の紳士がちらりと微笑む。
「ケンイチ君って貴族の生まれなの」
「いいえッ、まったくの平凡な庶民でして、父は役人、母はアマチュアのピアニスト、叔父はちょっと変わった人ですッ。ぼく自身は山羊座の生まれです……ッ」
口走りながら耳まで赤くなった鍵一へ、
「いいねえ、山羊座!」
と、ドイツ出身の音楽家は朗らかに笑いかけた。
「確か、タールベルクさんも山羊座じゃなかったっけ。ねえリスト君、昨年きみがタールベルクさんとピアノ対決をしたときにさ、ベルジョヨーゾ大公妃様のサロンで、それぞれの星座が話題に上ったよねえ、何かの話の流れで」
(大公妃様のサロン?)
「ウチ、他人の誕生日や星座はご婦人のしか覚えられへんねん。それにしてもあのピアノ対決は、ウチの圧勝やったなア」
(ピアノ対決?)
「パリ音楽院のピアノ科では、リスト君の曲よりもタールベルクさんの曲のほうが、よく演奏されてるみたいだけどね」
(タールベルクさん!)
音楽家たちは親しい話を続けながら、鍵一のために厨房から炭酸水をもらってくれた。この店のシェフが「新顔だね、ごゆっくり!」と陽気な声を投げて、オードブルの皿をテーブルへどんどん並べてゆく。聞き慣れぬ単語を急いで心の手帳に書きつけながら、
(そうだ、19世紀のフランスでは珈琲が普及していて、紅茶といえば上流階級が嗜むものなんだ)
いつか西洋史の授業で習ったことを思い出して、はっとした。
「乾杯! それにしてもケンイチ君、あんたほんまにラッキーやで。パリに来て初日に、一流の音楽家とテーブルを囲めるなんて」
「はいッ、光栄です……!」
「まずはこの猫だるまみたいな太っちょの好青年。日本でも、ウチと同じくらい有名やろ?」
リストは大柄の紳士の肩へヒョイと手をかけて、giocoso※3で紹介してくれようとする。ドイツの音楽家のふっくらした手の感触が、まだ鍵一の手のひらに残っている。全身からagitato※4で汗が噴き出してきた。
(この時代の有名な音楽家というと、ロッシーニ?にふくよかさは似ているけれど、お顔立ちが違う。メンデルスゾーン?のような品の良さもあるけれど、この人はもうすこし庶民派? うう、わからないッ)
言い詰まって苦しまぎれに頭を下げた、
「すみません! 緊張のあまり、お名前を失念いたしましたッ」
「だいじょうぶかケンイチ君、時差ボケやな。芸術大国ドイツの誇る『博学のヒラー』こと、フェルディナント・ヒラー君やん」※5
(初耳!)
「ハハハ、おれの名前なんて覚えなくていいよ。それでなくとも、外国人の名前って覚えにくいよねえ」
「い、いえ、いま思い出しました!」
「おれが初めてパリに来たのは、ケンイチ君と同じくらいの歳だったよ」
と、ドイツの音楽家の声が温かい。
「まず最初に驚いたのは、パリの物価が高いこと。実家では湯水のように飲んでいたカートッフェルズッペ※6が、パリのレストランでは高級料理としてメニューに載っていたりしてねえ、本当にびっくり。他にもカルチャーショックがいろいろと。思えば本当に、パリで暮らした7年間は大冒険だったよ。ケンイチ君も頑張ってね。困ったときは、相談に乗るよ」
「はいッ、恐縮です」
(カートッフェルズッペ)
思いがけず師匠の得意料理の名を聞いて、鍵一は肩のちからが抜けた。
(B先生が仰っていたとおり、ドイツの方にとってはお味噌汁のようなものなんだな。野菜たっぷりの、濃厚なじゃがいもスープ……)
「ケンイチ君」
と、リストがallegria※7に、今度は紫陽花色の瞳の紳士を示してみせる。
「このすらっとしたシャルトリュー猫※8みたいな美青年にも、会いたかったやろ?」
(こちらも難問! シューマン?にしては線が細いし、ベルリオーズ?にしては落ち着いた雰囲気……ああ、わからないッ)
「すみません! さっき音楽院の角で転んだときに、記憶が飛びましたッ」
「だいじょうぶかケンイチ君。『フランス・ピアノ界のエトワール』こと、シャルル=ヴァランタン・アルカン君やで」※9
(こちらも初耳!)
「アルカン君はパリ生まれ、パリ育ちの音楽家だから、本来はこの『外国人クラブ』に入会する資格は無いのだけど」
と、無口の友に代わって、『博学のヒラー』ことフェルディナント・ヒラー氏がgentile※10に話してくれる。
「ショパン君のすすめでここへ来たら、この隠れ家のようなコミュニティが気に入ったらしいよ。サロンより落ち着けて、音楽院の勤めより楽しい。ここなら俗世の事に煩わされずに純粋に芸術のことだけを考えていられる、というわけでね」
「アルカンさん、お会いできて光栄です……!」
フランスの音楽家は表情を変えずに鍵一を見遣って、
「シェフの創作料理も興味深いから」
と言い添えた。

(B先生の仰ったとおり、1830年代のパリには、ショパンやリスト以外にもすばらしい音楽家が居たんだ。まさに『歴史の空白地帯』……! よ、よし、ぼくのフランス語が通じる限り、さっそくインタビューを!)
音楽家たちの会話の切れ目を見計らって、鍵一は前のめりに踏み込んだ。
「皆さんは、昔からのお友達なのですか?」
「せやで、パリで出会った音楽仲間」
リストが気楽に返してくれる。グラスを傾けながら、ヒラー氏が楽しそうに会話に乗った。
「リスト君がパリに来たのは、あれはもう15年も前だっけ」
「せやな、1823年。ヒラー君がもう少し後にパリへ来たんやけど、前評判がすごくて。あのフンメル先生の一番弟子がワイマールから来るという事で、パリの社交界がその話で持ちきりやった」
「ワルシャワからショパン君が来たときのほうが、インパクトが大きかったと思うけどね」
(ヒラーさんの話すフランス語は、さわやかな五月の風みたいだ)
と鍵一は聴いていた。このドイツ出身の音楽家の声は肉厚ながら、どこか風を纏っているような軽やかさがあるのだった。
「なつかしいわア」と、リストがしみじみと宙を仰いで、楽しい記憶を思い描く様子。
「今思えば、皆がこのパリに居たというのんは、奇跡のように貴重な時間やったなア。ショパン君、ヒラー君、アルカン君。それにベルリオーズ先輩や、ドラクロワさんも」
「えッ、あの『幻想交響曲』で有名なベルリオーズさん! それにフランス絵画の巨匠、ドラクロワさんも、お知り合いなのですか」
「この店に飾ってある肖像画は全部、ドラクロワさんの作品やで。あした、明るくなったらよう見てみ」
鍵一が店内を見回すと、薄暗い食器棚の上に、窓のそばに、向こうのテーブルの端に、見慣れた顔も見慣れぬ顔も、ろうそくの朧げな光に照らされている。思い切って、鍵一は尋ねてみることにした。
「失礼ですが皆さん、年齢はおいくつなんでしょうか」
「いくつに見える?」
悪戯っぽくリストに返されて鍵一が言葉に詰まると、ヒラー氏が笑った。
「リスト君とおれは27になったよね。なんかね、おれたち誕生日も近いの。ハハハ。彗星年の生まれ、ね」
「彗星年?」
首をかしげた鍵一に、音楽家たちはスパークリング・ワインのボトルを示して見せた。彗星のデザインのラベルに、『1811年』の年号が輝いている。
「おれとリスト君の生まれ年・1811年は、なぜかヨーロッパ全土で葡萄が豊作だったんだよ。同じ年に巨大な彗星が現れたことから、この年につくられたワインを『彗星年のワイン』、というんだ。彗星と葡萄の関係は定かではないけれど、なにか我々の想像を超えた宇宙の法則を見出せるような……おもしろい現象だよねえ」
「なんだかロマンティックですね……!」
「年齢の話に戻ると、ベルリオーズ先輩は今年35歳、かな?」
ヒラー氏がアルカン氏を見遣ると、
「ドラクロワさんは年齢不詳だよね。ま、芸術家というのは本来そうあるべきなのかもしれないけど」
フランスの音楽家は静かにスパークリング・ワインを飲んでいる。脇からリストが嬉しそうに口を挟んで、
「モロッコの旅から帰って来はってから、またパワーアップしはったね。パリの街角で虹色の気配がしたら、もうね、大抵ドラクロワさん」
と、フランス絵画の巨匠とはやはり親しい間柄らしかった。ヒラー氏がうなづく。
「ドラクロワさんは、フランス政府からの依頼で大きな作品を手掛けていらっしゃることが多いんだよねえ。今年はシェイクスピアの『ハムレット』を題材にした版画や、ショパン君とジョルジュ・サンド殿の肖像画にも取り組むと仰っていた。いつ会ってもエネルギッシュな人だよ」
「そうなのですね。なんとなく、皆さんの様子がつかめてきました……!」
ムズムズとひざこぞうを叩きながら、鍵一は夕暮れのオペラ座での出来事を思い出していた。
(『外国人クラブ』の皆さんとお近づきになれば、ショパンさんとジョルジュ・サンドさんにも、またお会いできそうだな。サンドさんには、お借りしたハート型のハンカチを返さないと)
ショパンとサンドの住まいについて鍵一が尋ねようとした、そのとき。湯気立つ大皿が、テーブルの真ん中にドドンと置かれた。
(ナマズ!)
「パリ名物、ナマズの蒸し焼き! ケンイチ君、どんどん食べよし。あんた、さっきから全然食べてへんやん」
「はいッ、いただきます」
じつにのびのびと、その巨大な川魚は大皿に身を横たえていた。ほっこりと蒸し上がった白身に、あざやかなオレンジソースが染みている。音楽家たちが笑い合いながら取り分けるのに混じって鍵一も、白身のやわらかそうなところを自分の皿へ取った。セーヌ川の匂いがする。その熱いひときれを呑みこんだとき、鍵一はいま、自分が19世紀の人間になったのだという、目眩のような感覚におそわれた。
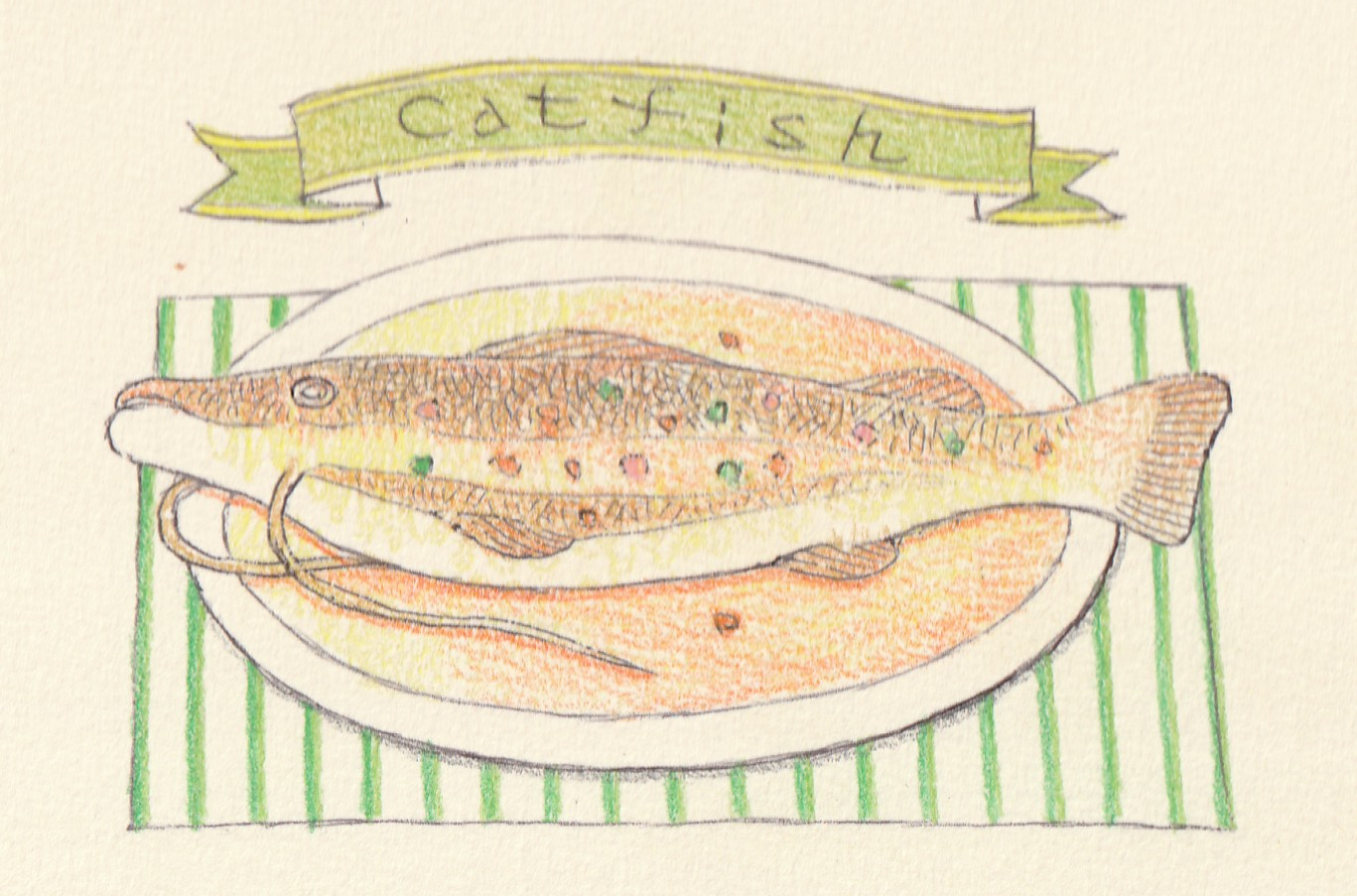
「ショパンといえば、ケンイチ君。このレストランに面白いものがあるで。……ケンイチ君?」
「えッ? あ、はいッ」
「このパリを代表するピアノメーカーのひとつ、プレイエルのピアノや」
「プレイエル……?」
立ち上がったリストが店の奥の覆いを取ると、琥珀色のグランド・ピアノが現れた。木目の美しい側板から、華奢な脚がすらりと伸びている。燭台に火が灯されると、譜面台のやわらかな影が響板に映った。
「美しいピアノですね……!」
「まだまだ改良中やけどな。ピアノは発展途上の楽器やから、皆でアイディアを出し合って、ピアノメーカーと一緒に改良に取り組んでるんや」
(改良)
そのこぢんまりした19世紀のピアノが、どのようにして21世紀のピアノに進化してゆくのか、鍵一には想像もつかない。ただ、目の前にある鍵盤楽器が、構造も、なりたちも、21世紀のピアノとはまるで別物であることだけは、ろうそくの光の揺らぎとともに強く感じ取れた。
(これは本当にピアノなのかしら。宇宙人に遭遇したような、ふしぎな感じ……)
「なにせ、ショパン君が広告塔だからね。プレイエルのピアノは売れに売れて。おかげでカミーユ・プレイエルさんは多忙過ぎて、ピアノのメンテナンスに来る時間もなさそうだ」
と、アルカン氏の流れるようなフランス語には皮肉めいた響きが入り混じっている。
(この人の性質はすこし、ショパンさんに似ているような)
鍵一がその内訳を考える間もなく、リストが鍵盤をさらりと撫ぜた。
「せっかくやし、弾こか、このピアノ」
「えッ、いいんですか。皆様の生演奏を聴けるなんて……夢みたいです!」
「なにかテーマを決めて、4人それぞれ、即興で演奏を披露しようやないか」
「おお、いいね」
「4人……? まさか、ぼくも弾くんですか?」
「当たり前や。ケンイチ君、ピアニストの卵やろ」
いちどは引いた汗がまたドッと噴き出る。ピアノを習い始めて今日に至るまでの記憶が走馬灯のように駆け巡り、目がちかちかし、耳が熱くなり、師の顔が浮かび、オロオロとひざこぞうを掻く間に、音楽家たちはもう即興演奏のテーマについて話し合っている。「花?」「鳥はどう」「風は」などと言い合ううち、ふいにリストが振り向いた。
「せや、今夜はケンイチ君が、演奏のテーマを決めてええで」
「テーマ? テーマ、ですか。ええと」
うろたえながら店内を見回して、テーブルの上のナマズ料理に目が留まる。
(ナマズ……キャット・フィッシュ……猫!)※11
「あの、テーマは『猫』でいかがでしょう?」
「ええやんか。じゃ、ケンイチ君が一番手やで」
促されてピアノの前に座った鍵一は、戸惑いながら、その19世紀のプレイエルのピアノを見回した。※12弦が飴細工のように細い、鍵盤の数が6オクターブ半しかないピアノを、鍵一は今まで一度も弾いたことがなかった。試みに、両手をそっと鍵盤に置いてみる。和音を鳴らしてみた途端、あまりにもやわらかな感触におののいた。
(このピアノ、弾きづらい……! 鍵盤が細くて、浅くて、そっとふれただけでも音が出る。音量が出ない。ロングトーンが伸びない。21世紀のピアノより、ピッチがだいぶ低い……)
「エラール社※13の華やかで頭の回転の速い子に比べると、ウチとしてはちょっと物足りひんけど。素直でおとなしくて、ええ子やで。気長に育てていくつもりや。
さア、ケンイチ君。曲はなんでもええよ」
「はいッ、只今」
(ええと、このプレイエルのピアノで『猫』を表現するなら……ええと、猫、猫、ショパンさんが広告塔を務めていらっしゃるという、このピアノで……。あッ、そうだ、ショパンさん作曲の、『猫のワルツ』!)
ショパンのメモをくわえた猫が、脳裏をサッと跳んで行く。鍵一は深く息を吸うと、鍵盤へ指を置いた。
「そ、それでは僭越ながら、披露いたします。題して『吾輩は猫である』※14」
「おっ、なんだろう」
「吾輩は猫である。名前はまだニャい。日本で生まれ、海をはるばる渡り来て、どこへ行くべきか、とんと見当がつかぬ」
「迷子の子猫?」
「薄暗いパリの夕暮れをむやみに駆けたらゴツンと音がして、眼から火が出た。ニャアニャア泣いているところをリストさんに拾われ、ついてゆくと音楽家の集会所らしき屋敷へ着いた」
「ええやん、ええやん。素敵なアクシデント!」
「この屋敷のうちでしばらくはよい心持に座っておったが、しばらくすると非常な速さで運命が回転し始めた……! 吾輩はご指名にあずかり、3人の偉大なる音楽家の御前にて、3拍子のワルツを奏するのである……」
♪ショパン作曲・ワルツ第4番ヘ長調 Op.34-3 通称『ねこのワルツ』※15

つづく


1811年はヨーロッパ全土でワインが大豊作であった。
同年に巨大彗星が現れたことから、この年のワインは『彗星年のワイン』と称され、珍重されている。
『外国人クラブ』にて音楽家たちが飲んでいるのは、老舗ワイナリー、ヴーヴ・クリコの1811年製シャンパーニュ。
なお、1811年は音楽界の大彗星、フェルディナント・ヒラーの生まれ年でもある。
当時非常な人気を誇っていたフランスオペラの傑作『悪魔のロベール』に引っ掛けた、アルカン氏のジョーク。
なお、第2話にてオペラ座で上演されていたロマンティック・バレエの名作『La Sylphide(ラ・シルフィード)』は、この『悪魔のロベール』がきっかけとなって制作された。
音楽用語で『おどけて、滑稽に』の意。
音楽用語で『激情的に、急速に』の意。
連載の第1話をご参照ください。
音楽用語で『快活に、陽気に』の意。
フランス原産の猫の品種。名前の由来は、かつて飼われていた修道院の地名から。
『フランスの宝』『ほほえみ猫』とも称される上品で美しい猫。
音楽用語で『穏やかに』の意。
ナマズの英語名。
ピティナ鍵盤楽器事典より
国立音楽大学の楽器学資料館では、企画展『ショパンが愛したピアノ』を開催中♪
PTNA 鍵盤楽器事典より
朝日新聞デジタル2019年4月1日版より 夏目漱石『吾輩は猫である』冒頭
ロンドンとライプツィヒで1838年12月、パリで1839年1月に出版された曲。
1838年5月時点では、日本人の鍵一がこの曲を知るはずはない。
さて、音楽家たちの反応やいかに……?