第44話『エラール・ピアノの歴史♪』

パリ・サロンデビューをめざして、オリジナル曲『夢の浮橋変奏曲』※1を創る事となった鍵一は、作曲に集中するため、1838年の大晦日にひとり船旅へ出た。英仏海峡を臨む港町、ル・アーヴルにて、鍵一は楽器製作者のエラール氏と再会する。幻の名曲『夢の浮橋』の謎を追い続けてきたエラール氏は、エラール社の秘密を鍵一へ打ち明けるのだった……!
「入りたまえ。エラール社の歴史を見せてあげよう」
天窓から射し込む陽の光が、数十台のピアノをやわらかく照り返している。整然と並ぶ楽器たちはそれぞれに光を纏って、この巨大な倉庫に息づいていた。伸び上がって見渡すままに、それら様々なかたちが鍵一の目を驚かせた。ロココ調の華やかな装飾あり、六本脚あり、ガラスのペダルあり、箪笥のようなスクエア型あり……
「凄い数のピアノですね、それに一台ずつ、造りも装飾も違うのですね……!」
「チェンバロも含まれているがね。このル・アーヴルの楽器庫で保管している楽器はすべて、叔父のセバスチャンの代からの代表的なモデルだ。顧客の楽器にメンテナンスを施す際に、過去のモデルの構造を参照することが多いのでね。このように年代順に並べて、設計図とともに管理している」
巨大な倉庫の天井にピエール・エラール氏の声が響いて、床が氷のように冷たい。見ればピアノの脚はみな、温かそうな靴下を履いている。
「叔父は1752年、家具職人の息子としてストラスブール※2に生まれた」
エラール氏はピアノの間を縫ってゆっくりと歩いてゆきながら、目尻に微笑を滲ませた。
「工作と発明に天賦の才があったらしい。幼いころ、『内部の構造を知りたいから』という理由で家の柱時計をばらばらに壊したが、翌日には元通り完璧に組み立てて家族を驚かせたそうだ。親の仕事場に散らばっていた廃材を使って、カラクリの玩具を創るのも巧かった。字を覚えると独学で建築学や幾何学を修めた。
16歳からパリのチェンバロ・メーカーで働き始めると、すぐに師匠より巧くなり、それが元で叔父は解雇されてしまった。次の勤め先では、師匠が叔父の創ったチェンバロを自作の品だと偽って売り出すという事態が起きた。その秘密はまもなくして明るみに出て、却って叔父の名声を高めることになったがね」
愉快そうに話すエラール氏へうなづきながら、鍵一は京都の叔父※3を思った。
(ぼくは叔父さんの芸術家気質を受け継いだと両親から言われてきた。もし本当にそうなら尚更、『夢の浮橋変奏曲』は京都の叔父さんの家で作曲したい。21世紀の京都へワープしたら、曲が完成するまで居候させてもらえるように、叔父さんへ頼んでみよう。……)
「これは叔父が創った最初のスクエア・ピアノだ」
と、エラール氏は一台のスクエア・ピアノに手を掛けた。敏捷な小鹿のように引き締まった印象の、長方形のケースの内部を、鍵一は屈み込んで眺めた。鍵穴の傍に『Érard』の飾り文字が堂々と美しい。
「さる公爵夫人が、叔父をロワール地方の美しい城へ招いて、楽器製作を支援してくださったのだ。その幸福な日々の中で、最新式のスクエア・ピアノは創り出された。当時のことを、叔父は私に何度も語り聞かせた。
いわく、若き日の叔父は素晴らしい環境で、好きなだけ創作活動に打ち込めたのだという。工房には設計図を何枚も広げられるほど巨大な大理石のテーブルがあり、東向きの窓からは明るい庭が眺められた。欲しい材料や道具を願い出れば、数日後には最新の品が届けられた。工房内の専用の鈴を鳴らすと、厨房から食事を運んでもらえた。おかげで集中力を途切れさせることなく、叔父は新作のピアノを創り出すことができた。
……その経験から得られた教訓を、叔父は私によく言いふくめた。創作に打ち込める環境を確保することが、いかに重要かという事だ。社交術を磨き、上流階級に名を売り、有力な後ろ盾を得られるように立ち回ることもまた、一流の楽器職人の務めなのだと。……これは音楽家も同じことだがね」
「はい、よくわかります」
鍵一は19世紀パリのヴィルトゥオーゾたちが楽しげに、時には面倒そうに口にしていた『社交行事』という言葉を思い返していた。大理石の床にシャンデリアの影が揺れる大使館のサロン。葉巻とチョコレートの薫りに満ちた銀行家の夜会。季節の花に彩られた王宮の行事。さて、パリ社交界について鍵一がアルカン氏に尋ねたとき、パリ生まれ・パリ育ちの音楽家は淡々とこう言ったのだった、
『パリに住んでいる以上、社交生活というものは水と同等に大切だからね。日々くちびるを潤し、時には浴びねばならない』。※4

「楽器職人として独立した叔父は、25歳という若さでパリのブルボン通りに店を構えた。しかし、出る杭は打たれる。異例の出世を遂げた叔父は、ギルドから数々の妨害を受けた」
「すみません、ギルドというのは……?」
「旧体制下の同業組合だ。楽器製作だけではない、18世紀にはあらゆる分野においてギルド制度が根付いていた。組合加入者へ安定した利益をもたらすかわりに、技術の改良や新たな創造を阻むのがギルド制度の難点だな。1776年にギルド廃止の勅令が下され、大革命※5後の1791年には同業組合を組織することが禁じられ、ようやくこの国のギルド制度は崩壊したのだ」
「そういえば、『外国人クラブ』のシェフが仰っていたことがありました。18世紀半ばにパリで初めてレストランを開いた人は、組合の目をかいくぐって上手にメニューを創ったものだと……たしか、煮込み料理の話です」
「ブーランジェ※6のレストランのエピソードだろう。彼が『羊の足の白ソース煮』を自分の店のメニューに加えたとき、仕出し屋が権利侵害の罪でブーランジェを訴えた」
「あッ、それです。ギルド制度では、煮込み料理を売ることができるのは仕出し屋だけだったんですよね」
「そう、しかし裁判では、『羊の足の白ソース煮』の調理方法を詳しく検分した結果、『調理する際にソースの中で羊の足を煮ているわけではないため、このメニューは煮込み料理には該当しない』という判決が下されて、ブーランジェは無罪放免になった。この事件以後、ますます彼の店の評判が高まったというわけだ」
「おもしろいエピソードだと思いますが、もし裁判で負けたらブーランジェは罪人ですよね……」
「それだけギルドが力を持っていたという事だな。焼肉屋は、焼いた肉は売れるが煮込み料理を売る権利はない。煮込み料理を売る権利は仕出し屋が独占している。豚肉の専門業者は鶏肉を売ってはいけない。そんな制度下で新たなアイディアを形にするのは至難の業だろう。
さて、楽器製作の業界もまた然りだ。横並びの状態から頭ひとつ抜け出すには、抜け道を探さなくてはならない。
さて、きみならどうする」
「難しいですね、上流階級の有力者を味方につける……にしても、やはり同業者との衝突は避けられないと思います」
「叔父は大胆な策を思いついた。マリー・アントワネット様にピアノを献上し、ルイ16世閣下から直々にピアノ製作の許可を得ることだ」
「あッ、なるほど」
エラール氏はロココ調※7の美しい装飾を施されたピアノを示した。
「これは叔父がマリー・アントワネット様に献上したピアノと同じモデルだ」
と、鍵盤の下に手を差し込むと、ゆっくりとレバーを左へ引き出した。すると鍵盤がゆっくりと左へ動いた。
「動きましたね……!」
「このレバーを操作すれば、簡単に移調※8ができる。マリー・アントワネット様がどのような曲を歌われる際にも、その音域に合わせて弾くことができるピアノだ」
「トランスポーズ・ピアノ……画期的なアイディアですね」
「マリー・アントワネット様は大変喜ばれ、ルイ16世閣下に進言してくださった。かくして叔父は、フランス王室の特免状を持つ唯一のピアノ製作者になった。ルイ16世閣下の特免状の前では、ギルドも形無しだ。ブルボン通りの叔父の工房はますます繁盛する事となった」
その18世紀フランス宮廷文化の華ともいうべきピアノを、鍵一はつぶさに見た。淡い薔薇色の地に金色の蔦模様があしらわれ、譜面台には小鳥の舞いあそぶ細かな彫刻がみられる。ピアノ内部の弦は絹糸のように細い。
なにより、21世紀の電子ピアノによくみられるトランスポーズ(移調)の機能を備えていることが、鍵一の胸をときめかせた。
「あの、よろしければ少し、弾いてみてもいい……ですか?」
「もちろん。ただし打鍵はごく弱めに」
鍵一は猫脚の椅子をそっと引いて、ピアノの前に腰掛けた。鍵盤に軽く指を置くや、銀色の鈴のような音が鳴る。
(ベルサイユ宮殿の音……)
つづけて指を動かすと、貴婦人のドレスの衣擦れが、金銀の細工を凝らしたグラスの輝きが、18世紀の薔薇の薫りとともに漂って来る。自分をベルサイユ宮殿への闖入者のように感じて、鍵一は息をひそめて弾いた。
♪ラモー作曲 :クラヴサン曲集と運指法 第1番(第2組曲) ロンドー形式のジグ
弾き終えると余韻すら残さず、18世紀は鍵一から遠のいた。こそばゆい指を引っ込めて、鍵一はそっと椅子を立った。感想を言おうと振り向くと、エラール氏は可笑しそうに鍵一を見つめていた。
「きみはそんな古めかしい曲をどこで知ったのかね」
「えッ……古めかしい、ですか?ラモー作曲の『クラヴサン曲集と運指法』を、ぼくは日本の師匠に教わった……のですが」
「現代のヨーロッパ音楽界で、ラモー氏の名を知る者はほぼいないだろう。私もヅィメルマン教授のサロンで一度聴いたきりだ」
鍵一が恐れたほどには、相手は追及しようとしなかった。鷹揚にうなづいて、
「弾き心地はどうだったかね」
と、声の調子を明るめた。鍵一は内心ホッとした。
「なんとも恐れ多いですが……とても繊細なピアノだと思います。このピアノの音が、18世紀のベルサイユ宮殿に響いていたのですね」
「王妃のお気に入りの離宮、プチ・トリアノン※9でも、よく奏でられていた事だろう。マリー・アントワネット様は、あの陰謀渦巻くベルサイユ宮殿において、純粋に音楽を愛した唯一の御方であったように思う。もし大革命が起こらず、つつがなく歳を重ねておられたら、叔父と私は最新式のハープも喜んで献上していただろう」
「エラール社では、ハープも創られているのですか?」
「本格的に制作を始めたのは1800年代からだと聞いている。
あいにく、このル・アーヴルにはハープを置いていないが、パリの工房には歴代のモデルが揃っている。いずれきみにも見せよう」
「ぜひ、ぜひお願いいたします。ハープの音色も聴いてみたいです。できれば、マリー・アントワネット様の生きておられた時代の曲で」
思わず本音が出て、話題はまた18世紀へ逆戻りしてしまった、鍵一は耳を赤らめながら、まるで言い訳のように早口になった、
「先程の曲も、この18世紀のピアノで弾くと、まるで別の曲のように感じられましたので……。当時の曲は、やはり当時の楽器で奏でられると、真価を発揮するのだと思います」
すると鍵一の顔を見守っていたエラール氏の顔が、みるみるうちにほころんだ。期せずして、この熟練の楽器製作者の心は明るく動いたらしかった。足早に奥へ進むと、
「次はこのピアノだ。どう思うかね?」
また一台のピアノに手を掛けて鍵一を振り向いた。鍵一は急いで寄って、よくよく眺めた。
「……5オクターヴ半、ですね」
「叔父が1803年に、ベートーヴェン氏へ進呈したものと同じモデルだ」
「えッ、あのベートーヴェン先生に……!」
「叔父は18世紀末の大革命の荒波をかいくぐり、亡命先のロンドンで当地のピアノ・メーカー、ブロードウッド社に学び、アクションの研究を重ねて、ようやくこのピアノを創り出した。ベートーヴェン氏へピアノを送ったのは、当世一流の音楽家によるピアノの評価が欲しかったからだ。叔父の目論見は当たった。新作のピアノはベートーヴェン氏の創作意欲を掻き立てることが出来た。膝ではなく足で操作するペダルや、5オクターヴ半という音域の拡大が気に入られたらしい。ピアノ・ソナタの第21番『ワルトシュタイン』※10や、第23番『熱情』が、叔父のピアノで作曲された」
「では、あの大胆な跳躍や高音域を響かせる箇所は、このピアノだからこそ生まれた表現なのですね……!」
「そのとおりだよ、きみ。ぜひ弾いてみたまえ」
促されて、鍵一はおそるおそるピアノの前に座った。途端、懐かしい感覚におそわれた。
(このピアノ、なんだかホッとする……)
5オクターヴ半しかない小ぶりのピアノに、しかし鍵一が21世紀で弾き慣れたグランド・ピアノの面影が重なった。
思い切って、和音を前のめりに踏み込んでみる。不意の来客に午睡を覚まされた老紳士のように、ピアノは不満げに鳴った。つづけてアルペジオ※11を弾き鳴らしてみれば、不機嫌に鳴り渡る声の太さが頼もしい。迷わず鍵一は弾き始めた。
♪ベートーヴェン作曲 :ピアノ・ソナタ 第23番「熱情」 Op.57 ヘ短調
弾き終えてなお、鍵盤の快い感触が鍵一の指に宿っていた。
「どうかね」
「鍵盤の戻りが速いですね……!音に厚みがあって、和音がよく鳴ります。いつも弾いている『外国人クラブ』のプレイエルのピアノよりもタッチが重くて、ぼくとしては心強いです」
「ベートーヴェン氏には『鍵盤が重い』と不評だったようだがね」
「えッ、そうなんですか。ぼくの感覚では、もっと重くても良いくらいですが」
「ウィーン式の軽やかなタッチに慣れていたベートーヴェン氏には、弾きづらく思われたのだろう」
「どんなピアノなら、ベートーヴェン先生を心から満足させることができたのでしょうか」
「叔父いわく、ベートーヴェン氏は生涯、ピアノという楽器に満足することは無かったようだ。彼の思い描く理想のピアノを、当時の技術ではどの楽器製作者も創ることが出来なかった。1819年に発表されたピアノ・ソナタ第29番は、その好例だろう」
「『ハンマークラヴィーア』※12ですね。確かに、当時の曲にしては音域が広すぎるような」
「高音域はウィーンのシュトライヒャー製ピアノ※13、低音域はイギリスのブロードウッド製ピアノでしか弾けなかった。……叔父は『ハンマークラヴィーア』の楽譜を見て衝撃を受けたと言っていた。あの曲がヨーロッパ中の楽器製作者を奮起させ、ピアノの進化を後押ししたのだ、とも」
(そうだ、あのときベートーヴェン先生は未来の音楽を書いていたんだ。ピアノの進化が待ちきれずに……)
心の手帳に書き留めたエラール氏の言葉が、19世紀ウィーンで目の当たりにした光景に繋がった。※14
……夏の陽射しの照り付ける窓辺で、『楽聖』は一心不乱に羽ペンを動かしている。ふりみだした栗色の髪に粒々の汗がきらめく。五線譜を掻くペン先が力強い音を立てている。突如としてベートーヴェンは立ち上がり、倒れた椅子を踏み越えてバケツを取り上げるや、頭から冷水を引ッかぶる。コブシを天へ突き上げ『フロイデ!(Freude)』と叫んだかと思えば猫背になり、部屋中をさまよい歩きながら、手近にあるものへ次々と音符を書き付けてゆく。机に書く、壁に書く、わしづかみにしたワイングラスがつるりと落ちて割れるのも構わず壁に窓に床に書き殴る……
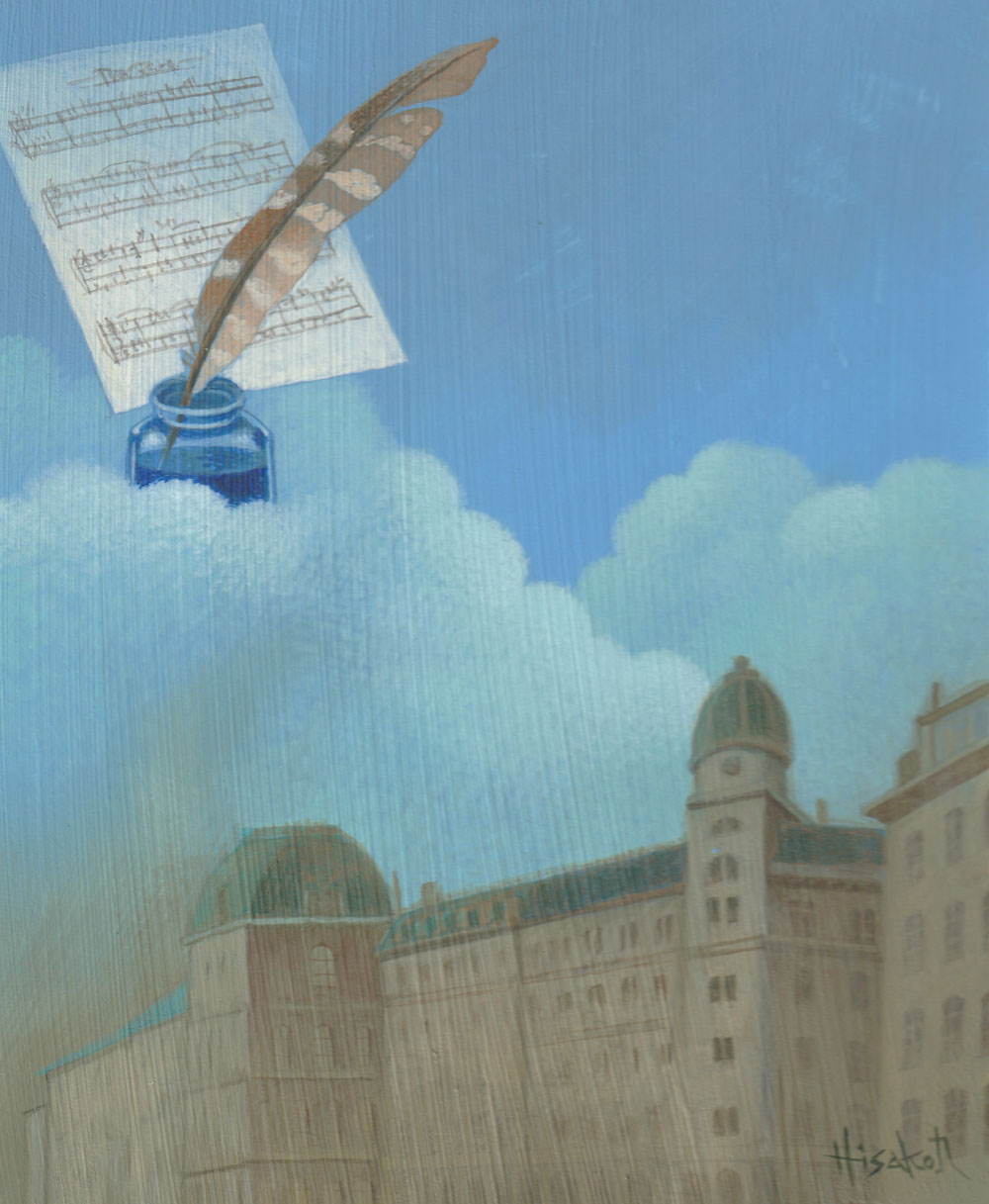
「さて、リスト君の曲は弾けるかね」
ふいに聞かれて「ええ、少しなら」と口ごもりながら、まだ鍵一の鼻先にはベートーヴェンの幻影がたゆたっていた。エラール氏は微笑を浮かべて、壁際の一番奥のグランド・ピアノへ手を掛ける。
「これは1824年に、リスト君がロンドン王立劇場で弾いてくれたピアノと同じモデルだ。彼は13歳にして、エラール社の良き広告塔になってくれた」
エラール氏の示した7オクターヴのグランド・ピアノは、この楽器庫の中に圧倒的な存在感を放っていた。見るからに頑丈なしつらえの、張りつめた弦の太さは、『ピアノの魔術師』の高い技巧と大胆な演奏に耐え得る造りであることを表していた。
「リストさんから、当時セバスチャン・エラールさんにとてもお世話になったと伺っています。ロンドン公演のみならず、生活の援助もしてくださったと」
「さしもの天才少年も、外国人であることを理由に、パリ音楽院から入学を断られた※15のは痛手だったのだろう。一方、エラール社は、新作のグランド・ピアノの魅力を世に知らしめてくれる音楽家を必要としていた。叔父がリスト君に救いの手を差し伸べたのは、互いにとって好機だったという事だ。実際に、リスト君のロンドン公演の大成功によって、我がエラール社はブロードウッド社をも凌ぐ存在だと認められることができた」
「一流の音楽家と、一流のピアノ・メーカーが力を合わせた成果ですね」
「時の運も重要だがね。もし大革命の渦中であれば成し得なかったことだ。……さあ、弾いてみたまえ」
鍵一をピアノの前に座らせると、エラール氏は高音の鍵盤を軽く連打してみせた。
「これはベートーヴェン氏に進呈したイギリス式のピアノへ、さらにアクションの改良を加えたグランド・ピアノだ」
「では遠慮なく」と、『ラ・カンパネラ』の高音域の一節を弾いてみて、その鍵盤の反応のすばやさに鍵一は驚いた、
「速いですね、さっきのピアノよりも、さらに鍵盤の戻りが速く感じられます。かといって鍵盤が軽いわけでもなくて……音の伸びも良いですね。打てば響く、というこの感触、心地良いです。このアクションはどういう仕組みなのですか?」
「ダブル・エスケープメント式という。ハンマーの動きの無駄を廃して、従来よりも速い打鍵ができる仕組みにした。1821年に、叔父が特許を取得したアクションだ」※16
エラール氏は鍵一を促して、ピアノ内部の打鍵の様子を見せた。鍵一が注意深くハンマーの動きを観察すると、なるほどハンマーが最小の動きで弦を打っている。
「勉強になります」
「さあ、どんどん弾いてみたまえ」
「では、では、遠慮なく」
♪リスト作曲 :パガニーニ大練習曲集 第3曲 「ラ・カンパネラ」 S.141 R.3b 嬰ト短調
途中まで聴き入っていたエラール氏が、「ほう」と白い息を吹いた。
「斬新なアレンジだな。原曲はリスト君の『パガニーニによる超絶技巧練習曲集』※17のようだが」
(しまったッ、これは改訂版のほうの『ラ・カンパネラ』だった……1839年にはまだ存在しない版だ)
「いいえッ、あの、リストさんがいつか、こんな感じで弾いていらしたような」
あわてふためく鍵一をおもしろそうに眺めて、エラール氏は何事かを深く了解したようにうなづいた。
「弾き心地はどうかね」
「はいッ、豊かで明るい音だと思います。弾いていると気持ちまで明るくなりますね」
「そうだろう、これがショパン君に『エラール・ピアノはいつでも素晴らしい音を出せるので、体調のすぐれない時はエラールを弾くようにしている』と言わしめた、我がエラール社の誇るグランド・ピアノだ」
エラール氏は胸ポケットから絹のハンカチーフを取り出すと、愛おしそうに鍵盤を撫でた。叔父から甥へと受け継がれた楽器製作者の誇りが、幾多の美しい皺として、その手に刻まれていた。
「……ショパンさんも、エラール・ピアノを弾かれるのですね。てっきり、プレイエルばかり弾いていらっしゃるのかと」
「パリで活躍する現代の音楽家なら必ず、プレイエルとエラールの両方を弾くものだろう。ショパン君の手で奏されるエラール・ピアノの音色もまた美しいものだ。
ただ、楽器製作者として私が頼りにするのは、やはりフランツ・リスト君だな。ベートーヴェン氏と同じく、彼には音楽の未来をひらく力がある。リスト君とともに、エラール・ピアノはこれからも進化を遂げるだろう」
うなづいて、鍵一はこの巨大な楽器庫を見渡してみた。各時代の音楽家と共に歩んできたエラール社の歴史が、1839年の元旦の淡い午後に息づいていた。数十台の楽器をひとつ、ひとつ、眺めるほどに、チェンバロの銀色の弦から、ロココ調のピアノの金色の蔦模様から、精巧なアクションを備えたグランド・ピアノの鍵盤から、透明の音楽があふれだして来る。鍵一は耳を澄ませた。
潮騒。
寄せては返し、静まっては響きを増してゆく音楽が、地上をなみなみと満たし、海鳥の声と交叉しながら、大いなるものへ祈りを捧げる。……ひときわ大きな潮に揺り戻されて、鍵一は我に返った。
「エラールさん。幻の名曲『夢の浮橋』の上演に使われた楽器……製造ナンバー『1811』のピアノは、いったいどれなのでしょうか?」
つづく


日本最大級のオーディオブック配信サイト『audiobook.jp』にて好評配信中♪
第1話
幻の名曲『夢の浮橋』モチーフを活かし、鍵一が作曲するピアノ独奏曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。
実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいます。
♪『夢の浮橋変奏曲』制作プロジェクトのご紹介
♪神山 奈々さん(作曲家)
♪片山 柊さん(ピアニスト)
第19話『前略 旅するあなたへ(Ⅲ)♪』をご参照ください。
第37話『花の眼、水の歌―アルカン氏の肖像(Ⅲ)♪』をご参照ください。
1789年のバスティーユ牢獄襲撃を皮切りに、フランス全土で巻き起こった市民革命。国民公会の決定により、ルイ16世と王妃マリー・アントワネットは1793年に処刑されてしまいます。
18世紀半ばまで、パリの街には『レストラン』なる業態の店はなく、市民が外食する際は、居酒屋や、宿屋・仕出し屋の定食テーブルを利用していました。
1765年ごろ、パリのルーヴル宮の近くで、ブーランジェという人物がレストランを始めると、瞬く間に大人気になりました。
メニューは簡素なもの(ブイヨンや、ゆでた鶏肉の粗塩添え、卵料理など)でしたが、『相席ではないテーブルで、落ち着いて食事をすることができる』『大皿料理ではなく、1人1品ずつ好きな料理を注文できる』など、従来の居酒屋や定食テーブルには無かったサービスを提供しました。
音楽用語で『楽曲の調の主音を別の音に移すこと。』の意。トランスポーズ。
音楽用語で『和音の音を一つずつ順番に鳴らす奏法。分散和音の一種。』の意。
第13話『音楽の都ウィーン♪(1809→1837)』をご参照ください。