第69話『名もなきシェフの肖像(Ⅲ)♪』

より多くの芸術家と交流し、『夢の浮橋』の楽譜を集めるためには、19世紀で通用するコンポーザー・ピアニスト(作曲家兼ピアニスト)に成らねばならない。現代に一時帰国した鍵一は、京都貴船※1の叔父のアトリエに身を寄せた。古都の風景に19世紀パリの記憶を重ねつつ、『夢の浮橋変奏曲』※2の制作が進む。
雪深き1月下旬、裏庭に煉瓦のかまどを見つけた鍵一はクロワッサンを焼く事にした。パン生地をこねながら、19世紀パリのレストラン『外国人クラブ』でのひとときが思い出される。
――回想 シェフの肖像(1838年4月)
「そんなわけで、俺は名前と父親をなくしたんだ」
名もなきシェフは
Brioso
※3に話を続けた。
「14歳になるまで、ル・アーヴルの親戚の家で暮らした。面白い町だった。風はいつも潮の匂いがする。外国船の汽笛がひっきりなしに響く。晴れた日には海の向こうにイギリスが見える」
「ル・アーヴル、というのは、ええと……」
「大西洋に面した港町。ケンイチもル・アーヴルからパリへ来たんだろ?」
「えッ?ええと、そうでした!日本から船で旅をして来て、初めてフランスの土を踏んだのが、その……ル・アーヴルだったように思います」
慌ててひざこぞうを掻いて、鍵一は英仏海峡の港町を思い浮かべた。無数の船の行き交う景色がふと、ふるさと横浜の風景に重なった。
「魚を焼く店がたくさんあったろ。向こうで何か食ったかい」
「いいえ、特になにも……あの、早くパリへ行きたくて急いでいたものですから。でも、獲れたての海の幸は美味しいんでしょうね」
「うまいよ、なにせ新鮮だから、シンプルに蒸したり焼いたりするだけで充分うまい。
まア、でも俺はやっぱり、親父の作る手の込んだ料理が恋しかったなア。何種類ものソースを使って仕上げる豪華な料理。市場にどっさり並んだ魚を見るたびに、パイの包み焼きやムニエルを作ってみたくてウズウズした」
うなづいて鍵一は、この料理人に尋ねてみたいことがあった。その質問は相手を困らせるかもしれないと思いながら、「ひとつ伺いたいのですが……」と、おそるおそる言い出した。
「シェフさんはどうして、そんなにも料理人になりたいと思われたのですか」
「ん?かっこいいから」
鍵一が拍子抜けするほどに、答えは明快に来た。
「料理人てのは骨の折れる仕事でさ。腕を上げて王侯貴族やブルジョワのお抱え料理人になったところで、親父みたいな目に遭うかもしれない。でも、その大変さを補って余りあるほど、料理人はかっこいい仕事だと思うんだ。なぜかッて、料理は人を励ますことができる。料理は人にちからを与えることができる。そういう仕事はかっこいいし、価値があると俺は思う」
山盛りのクロワッサンが朝陽を受けて輝いている。やわらかな珈琲の味が、鍵一の腑に落ちた。
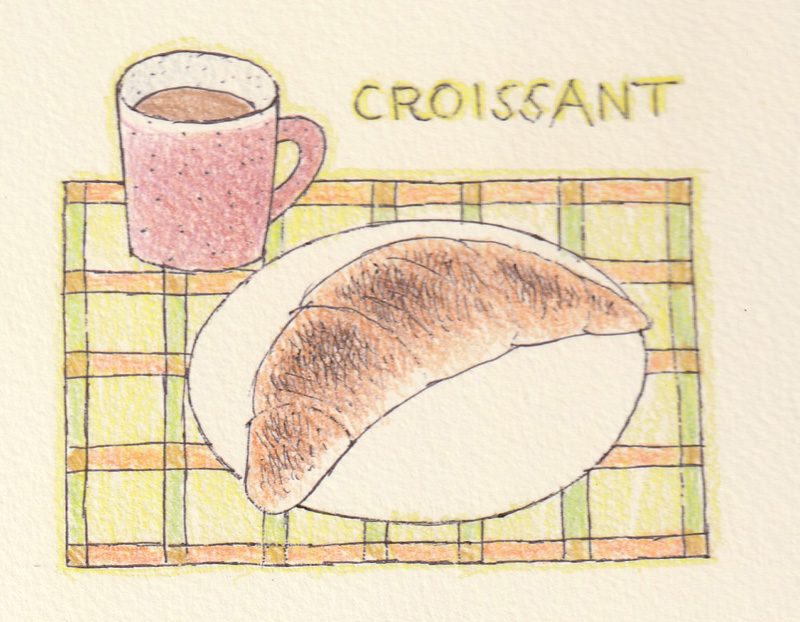
「人を励ます仕事……音楽家もそうですよね」
「言われてみりゃそうだな」
「でも、そこまでの音楽家に成るには、物凄く勉強が必要ですよね。リストさんやヒラーさんや、アルカンさんのような方の音楽であれば、多くの人の活力になると思いますが……」
「ケンイチは日本で音楽を勉強してきたんじゃないのか」
「はい、目標としていたコンクールで、いちおう優勝はしたのですが……」
「コンクール?」
「あの、日本にはピアノのコンペティションというものがありまして、そこで一等賞を貰ったのです。でもそれが終わると、自分が何をしたいのか分からなくなりました。目標を見失ってしまったというか……これといって弾きたい曲もないですし、ヴィルトゥオーゾの方々のように作曲ができるわけでもないので……」
「なるほどね。まア、人生は長いんだ。うまいものを食いながら、ゆっくり考えりゃいいんじゃないか」
シェフはクロワッサンをひとつ取ると、「冷めてもうまいぞ」と鍵一へ手渡した。明るい三日月のかたちが、鍵一の心を暖かく照らした。
「いただきます。……あの、シェフさんはル・アーヴルへ移住されてから、どうやって料理の修業をされたんですか?」
「うん。まず、魚河岸のレストランで下働きをやらせてもらった。魚の目利きから出汁の取り方まで、全部そこで覚えた。でも、やればやるほど物足りなかった。調理場のなにもかもが、パリから一歩も二歩も遅れてる。料理人のバイブルたるタイユヴァンの書※4を誰も知らない。ここは俺の居るべき場所じゃない。そう思うようになった。
14の年に母親が亡くなって、いよいよ考えたんだ。パリへ戻って料理の修行をしようとね。そこで、カレーム先生のことが頭に浮かんだ」
「カレーム先生……シェフさんの師匠ですね」
口のなかに甘い記憶が広がる。
パリ到着の晩に「千枚の葉(mille-feuille)」として供されたデザート※5が、まさにその人のレシピであった。
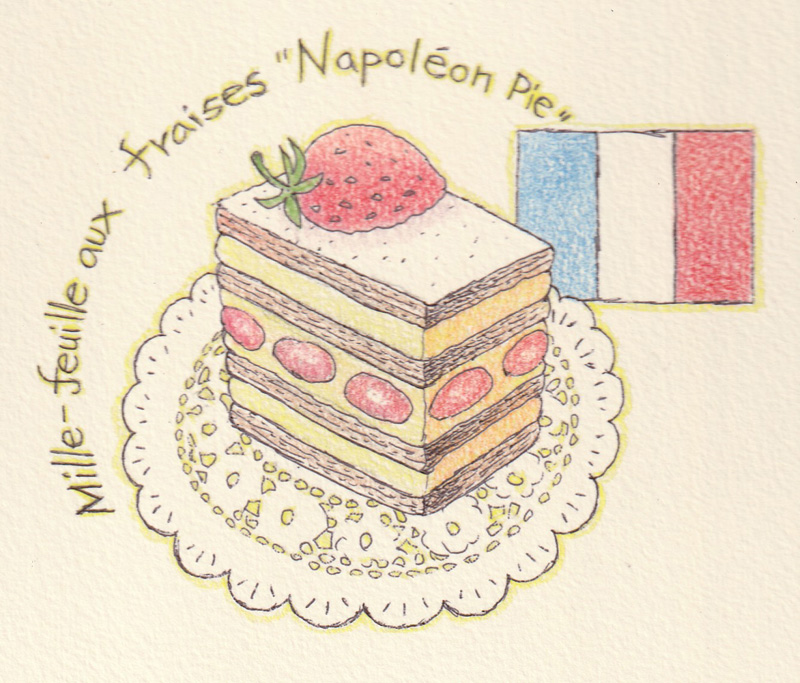
「そう、アントナン・カレーム。『国王のシェフ』かつ『シェフの帝王』と異名を取った、偉大な料理人だよ※6。パリ中の名立たる晩餐会を仕切ってたからね。リスト君をはじめ、音楽家のなかにもファンが大勢いた。
俺とカレーム先生が初めて会ったのは、ほんの子供の頃だ。俺が4つで、あの人は10か11……でも、もっと大人びて見えた。その時のことを、今でもよく覚えてる。
陽ざしの明るい五月の庭だった。俺は親父の厨房の勝手口で、ひとりで遊んでた。ちっちゃなテントウムシを取ろうとして手を伸ばしたとき、目の前に大きな影がさした。見上げるとその人が立っていた。水のたっぷり入ったバケツを提げて、ニコニコ笑ってさ。
当時、カレーム先生はまだ料理の修行はしていなかった。親に捨てられたあの人は、居酒屋の使いッ走りをしてたんだ。カレーム先生がうちの厨房に水を届けてくれたのは偶然だったけど、俺にとっては最高にありがたい出会いだった。
俺が料理人の子だとわかると、あの人は自分の書いた絵を見せてくれた。古代ギリシャの神殿の絵だ」
「古代ギリシャ、ですか……?」
「あの人は子供のころから、古代建築に興味を持ってたんだ。自分で読み書きを覚えてさ。仕事の合間をぬって図書館に通って、版画を何十枚も模写してた。
初めてその絵を見たとき、俺はなんだか分からなかった。でもすごくきれいだ、と思った。俺がそう言うと、あの人は嬉しそうにして、また見せると言った。それから約束どおり、うちへ水を届けに来るたびに新しい絵を見せてくれた。
最後に会ったのは、例の事件※7の数日前だ。見せてくれたのはパルテノン神殿の絵だった。すばらしく精巧で、子供ながらに見惚れたよ。こいつは凄いやと俺が褒めると、カレーム先生は妙なことを言った。
『僕は一流の料理人に成って、料理のちからで国を立て直す。この絵は夢に近づくための第一歩だ』と」
「一体どういうことなんでしょうか……?」
「ハハハ、俺にもわからなかった。ただし、カレーム先生が大きなことを企んでいる気配だけはヒシヒシと感じた。その企みと近いところに、俺の生きる道もあるんじゃないかと考えた。……
どうにか船賃を片道分だけ工面して、パリゆきの船に乗ったよ。ル・アーヴルからパリまで、3週間くらい掛かったかなア。真冬のセーヌ川が凍ってて、船が全然進まなくて。頼れる大人もいなくて、金もなくて、名前もなくて。財産といえば、先祖代々受け継がれた例の砂※8くらい。カレーム先生の存在だけが希望の光だった。……忘れもしない、1803年の冬だ。もう30年以上前のことか」
「『外国人クラブ』の皆様は、まだ生まれていないころですね。リストさんもヒラーさんも、アルカンさんも」
「ケンイチもまだ生まれてないな。1803年……そうそう、ベートーヴェン先生が、英雄ナポレオンに捧ぐ曲を創っていたころだ」
「いわくつきの、あの名曲ですね。ナポレオンが皇帝になったという知らせを聞いて、ベートーヴェン先生が激怒して楽譜を破いたという。交響曲、第3番……!」

つづく


日本最大級のオーディオブック配信サイト『audiobook.jp』にて好評配信中♪
第1話のみ、無料でお聴きいただけます。
幻の名曲『夢の浮橋』のモチーフを活かし、鍵一が作曲するピアノ独奏曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。
実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいました。
♪『夢の浮橋変奏曲』制作プロジェクトのご紹介
♪神山 奈々さん(作曲家)
♪片山 柊さん(ピアニスト)
音楽用語で『陽気に・快活に』の意。
14世紀の宮廷料理人・ギヨーム・ティレル(通称:タイユヴァン)が著した料理書。
第5話『Twinkle Twinkle Little Start(きらきら光る小さなスタート)♪』をご参照ください。
フランス出身のシェフ、パティシエ。宮廷料理人として活躍し、『国王のシェフ』かつ『シェフの帝王』と称されました。
第68話『名もなきシェフの肖像(Ⅱ)♪』をご参照ください。
第5話『Twinkle Twinkle Little Start(きらきら光る小さなスタート)♪』をご参照ください。