第68話『名もなきシェフの肖像(Ⅱ)♪』

より多くの芸術家と交流し、『夢の浮橋』の楽譜を集めるためには、19世紀で通用するコンポーザー・ピアニスト(作曲家兼ピアニスト)に成らねばならない。現代に一時帰国した鍵一は、京都貴船※1の叔父のアトリエに身を寄せた。古都の風景に19世紀パリの記憶を重ねつつ、『夢の浮橋変奏曲』※2の制作が進む。
雪深き1月下旬、裏庭に煉瓦のかまどを見つけた鍵一はクロワッサンを焼く事にした。パン生地をこねながら、19世紀パリのレストラン『外国人クラブ』でのひとときが思い出される。
――回想 シェフの肖像(1838年4月)
「俺はね、この世にはもう、居ない人間なんだよ。だから、名前がない」
「えッ、どういうことでしょうか……?」
おののく鍵一の前で、料理人は
Allegrissimamente
※3に笑った。テーブルの上からクロワッサンをひとつ取ると、朝の光にかざし見る。
「なあケンイチ。おまえはこのフランスという国の歴史をどれくらい知ってる」
「あまり詳しくは存じ上げませんが……たしか18世紀の終わりに、大きな革命が起きたんですよね」
「そうだよ、その大革命のせいで、俺は名前をなくしたんだ。
せっかくだから話してやろうか。このフランスの50年間の歴史と、俺自身の50年間の歴史をさ」
「はい、ぜひ伺いたいです……!」
「1789年、バスティーユ牢獄に革命軍の旗がひるがえった日に、俺は生まれたんだ」
料理人はゆっくりと話し出した。鍵一は珈琲を飲みながら、この料理人の明るい声に耳を傾けることにした。
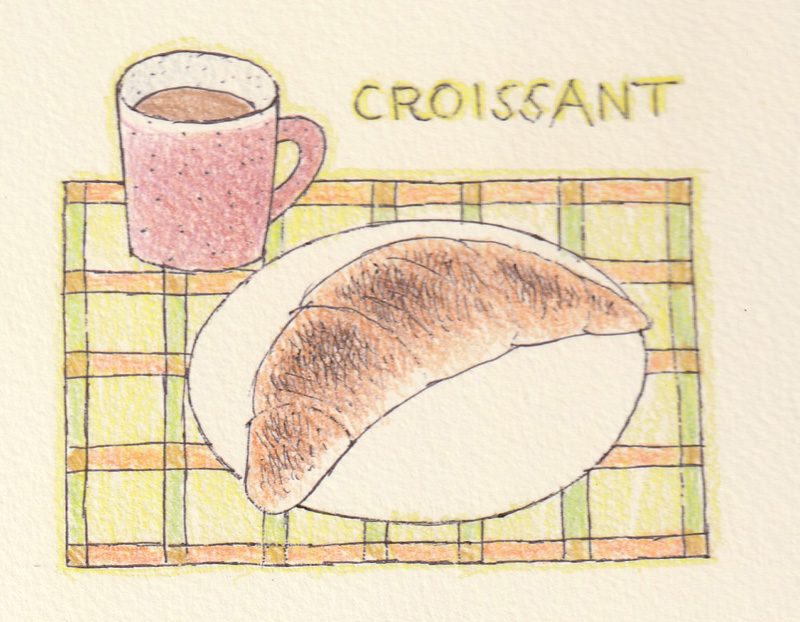
「そもそも、どうしてフランスで大革命が起きたかって、当時、王様に不満をもつ人が大勢いたからだ。1789年、フランスにはルイ16世という王様がいてさ。政治が下手で、特に金のやりくりが下手だった。まア、おじいさんのルイ14世の時代からすでに財政は火の車だったらしいけどね」
「ルイ14世というのは、どんな王様だったのでしょうか?」
「150年前にヴェルサイユ宮殿を造った王様だよ。美味いものが好きで、派手好みの御方だったらしい。ケンイチはヴェルサイユ宮殿を見たことあるか」
「いいえ、まだ……」
「あの豪華絢爛なヴェルサイユ宮殿を見りゃア、ルイ14世がどんな王様だったか分かるよ。宮殿の隣にはでかい農園をつくって、珍しいくだものや野菜をどっさり植えてた※4。そこから採れた食材で、300人以上の料理人に毎日ごちそうを作らせたんだ」
「豪華ですね……!」
「ただし、でかいことをやるには、それだけ金が掛かるんだよな。孫のルイ16世の時代に、ヴェルサイユ宮殿の金庫はすっからかんになった。王妃マリー・アントワネット様の贅沢好きも財政難に拍車をかけた。有能な政治家が改革に乗り出すと、王様はその政治家をクビにしてしまう。さらに自分たちに有利な法律を作って、国民から金を巻き上げようとしたらしい。
そして1789年7月。ついにパリの市民が立ち上がって、王様への反撃を始めた。バスティーユ牢獄を占拠したのは、約10年にわたる革命への第一歩だったんだなア」
「10年間も革命をなさってたんですか」
「そうだよ。だから俺たちフランス人は『大革命』って呼んでる。俺の母親いわく、革命が起きた当時のパリの熱気はすさまじかったそうだ。街ゆく人がみんなぎらぎらした顔つきをして、毎日妙な天気で。急に雷が落ちたかと思えば、空いちめんが真ッ赤な雲に覆われたり。それが災いの前触れなのか、幸いのしるしなのか分からずに、ひたすら恐ろしかったと、俺の母親はそう言ってた。何はともあれ、50年前の事件だよ」
「フランスの歴史に残る大事件でしたね……!悪い王様の時代に生まれると、国民は生きてゆくのが大変なんですね」
「まア、大変な時代ではあったけど」と、美味そうに珈琲をすする。
「ルイ16世が悪い王様だったのかどうかは、俺にはわからんね。俺はルイ16世に会ったことはないし、当時の話は全部、親から聞いた。自分で見聞きしてない事柄について、良いの悪いのッて判断することはできない」
「確かにそうですね……」
「それに、王様の家に生まれたからって、みんなが王様に向いてるとは限らない。人間、向き不向きッてもんがあるからね。俺は王様に同情するよ」
「……ルイ16世は、本当はどんな御方だったんでしょうか」
「噂じゃ、錠前づくりがご趣味だったんだそうだ。錠前屋の家に生まれていれば、腕のいい職人になってたかもしれないな」
「錠前ですか」
鍵一は錠前づくりに熱中する王の姿を想像した。その人はヴェルサイユ宮殿の片隅で猫背になりながら、錠をためつすがめつする。白いふっくらした手で不器用に金具を扱いながら、より堅固な物を造ろうとする。しかしラッパが鳴り、扉がノックされると、静寂に満ちた時間は終わる。次々と供される食事、政治家たちの讒言、内乱の報告、財務大臣の嘆き、城の窓を照らす稲光。それらは彼の造る錠では防ぎきれないのだった。……身震いして鍵一は、大革命における重要人物をもうひとり思い出した。
「あの、ルイ16世の御后様のマリー・アントワネットさんの話は、日本でも有名です。食べ物が無くてフランス国民が困っている、という話を聞いて、『パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃない』と仰った方ですよね?」
「古いフレーズを知ってるなア。でも、それはたぶんアントワネット様の言葉じゃない」
「あれッ、すみません。ぼくの記憶違いでしょうか」
「きっと、あの本の内容が間違って翻訳されたんだな」
シェフは立ち上がると、窓辺の棚から一冊の本を抜き出した。
「ジャン・ジャック・ルソーの『告白』。ルソーはひと昔前に活躍した思想家で、作曲もしてたらしい。※5これは自伝的作品なんだが、第6巻の……このあたりだな。ケンイチ、読めるか」
「はい、簡単なものでしたら、なんとか。ええと……このページですね。
『そのとき私は、王妃の心無い言葉を思い出しました。凶作に苦しむ農民に対して《パンがないなら、ブリオッシュを食べればよい》と、その王妃は言い放ったのです』……?あの、これは?」
「もちろん、アントワネット様の言葉じゃない。なぜかッて、この本が書かれた1765年、アントワネット様はまだフランス王妃じゃなかった。小さなお姫様として、ウィーンの宮廷にいた頃だ」
「では、『パンがなければお菓子を食べればいいじゃない』のフレーズは、別の王妃様のご発言だったのですね……!」
「ちなみに『ブリオッシュ』てのは、ふんわりした甘いパンのこと。
ただね、アントワネット様の華やかな暮らしぶりがフランス国民の反感を買っていたのも事実だ。芸術には理解ある御方だったから、俺としては悪く言いたかないけどね。かの有名なエラール・ピアノも、アントワネット様のおかげで大きく発展したんだ」
「エラール……パリで有名なピアノ・メーカーですか?」
「うん、フランツ・リスト君と縁の深いピアノ・メーカーで、ハープでも有名だ。創業者のセバスチャン・エラールさん亡き後は、二代目のピエールさんが跡を継いで頑張ってる」
うなづいて鍵一は、初めて聞く楽器メーカーの名を胸に刻んだ。どうやら1838年パリには、自分の未だ知らぬ物事が想像以上に多く在るらしかった。

「かつてはアントワネット様も、エラール・ピアノを弾いてらしたのでしょうか」
「いたくお気に入りだったらしい。ただ、大革命の後はそれが祟って、セバスチャン・エラールさんはロンドンへ亡命する羽目になった。1789年に勝利をおさめた革命軍は、ルイ16世やアントワネット様を牢屋へ入れて、ついで、王族に関わりのある人間を片ッ端から処刑したんだよ。エラールさんも、王妃にピアノを献上した罪であやうく捕まるところだったんだが、早々にロンドンへ渡って難を逃れた」
「ピアノを王族に献上しただけで死刑になるなんて、怖い時代でしたね」
「本当にそうだよ。俺の親父なんて、王族のために料理を作っただけで死刑になったからね」
「えッ、殺されたということですか……?」
耳を疑った鍵一へ、シェフは軽やかにうなづいた。
「俺の親父は、パリではちょっと名の知れた料理人だったんだよ。大貴族の屋敷で料理長を務めてた。だけど、バスティーユが襲われた後は身の危険を感じて、親父はひそかに独立の準備を進めていた。雇い主が王族と親しい貴族だったんで、下手すりゃ巻き添え食うからね」
「料理人の方が独立、というのはつまり、自分でレストランを開くことですか?」
「そうだよ。当時、独立する料理人はたくさんいた。大革命のトバッチリを逃れるなら、他にもいろいろ方法はあったけどね。フランスを出て、イギリスやドイツの貴族の屋敷で働くとか。金持ちのブルジョワのお抱え料理人になるとか」
「フランス料理の世界にも『大革命』が起きていたのですね……!」
「うん、宝石箱をひっくり返したみたいにさ。王侯貴族の屋敷に閉じ込められてた料理人たちが一斉に世の中へ散らばったんだ。
例えばボーヴィリエという凄腕の料理人がいた。もとはプロヴァンス伯爵のお抱え料理人で、パリに自分のレストランを構えて独立した。宮廷並みのサーヴィスと豪華なメニューを売りにして、大評判を取ったんだ。他にも、パリには名店がたくさん出来た。特にパレ=ロワイヤルの周りは大繁盛でさ」
「フランス料理の名店ですか……!」
「『ロシェ・ド・カンカル』も有名だな。生牡蠣が名物で、メニューが豊富。ポタージュ、オードヴル、魚、鳥、子牛に羊、なんでもとびきり美味く食わせる高級店だ。かの文豪バルザック先生の御用達でもある。そうそう、ショパンも『ロシェ』の生牡蠣を気に入ったと言ってたな」
「えッ、ショパンさんが」
どきりと心臓が跳ねた。同時に、オペラ座の夕暮れに受け取った謎のメッセージ※6がきらりと頭をよぎった。
(『Le pont du rêve(夢の浮橋)』……あれは一体どういう意味だったんだろう)

「ショパンさんは、よくそのお店にいらっしゃるのですか?」
「どうだろうな。ただ、ポーランド人たちの晩餐会が開かれるときは、必ず顔を出してるそうだ。ふるさとの懐かしい話があるんだろう」
「なるほど……」
「他にも良い店はたくさんある。『フレール・プロヴァンソー』は、その名のとおり南フランス、プロヴァンス地方の郷土料理を出す店だ。あの店のブランダードは一級品だね。干した鱈をじゃがいもやクリームと混ぜ合わせて、にんにくを効かせて濃厚な味に仕上げる。そのままパンに付けて食っても美味いし、グラタンとして焼き上げてもいい」
「美味しそうですね」
「ハハハ、今度作ってやるよ。俺は昔、あの店の厨房でちょいと働いた事があるんだ。レシピはこの手が覚えてる」
Agiatamente
※7に笑って、名もなきシェフは続けた。
「……さて、俺の親父も独立の波に乗ろうとしてたのが、一足遅かったんだなア。それに、運も悪かった。
あるとき、雇い主の命令で極秘の晩餐会がひらかれたんだが、それが王党派のクーデターの密談だった。王族が政権を取り戻すための作戦会議だったんだが、どこからか情報が漏れて、革命派に踏み込まれてさ。テーブルを囲んでた王族、王党派の貴族、厨房で料理をしてた親父が取ッ捕まって、牢屋へ放り込まれた。母親と俺はすぐにパリを出て、親戚の家に匿ってもらった。それきり親父とは会えずじまいだ」
相手の口調があまりに明るいので、鍵一はどう返してよいやら分からない。曖昧にうなづいて、「大変な時代でしたね」と言った。シェフは笑った。
「親父の最期の言葉は、『鴨肉のコンフィがまだ生焼けだったんだ!』だそうだ。ハハハハ、料理人だよね。
しかも、これには後日談があって。親父が取ッ捕まって3週間後くらいに、政府が処刑者の名簿を公表したんだ。そしたらなんと、俺の名前が載ってたんだよねえ」
「処刑者の名簿……つまり、殺された人の一覧に、ご自身のお名前があったということですか?」
「うん。親父と俺の名前はよく似ていたから、たぶん役人が書きまちがえたんだな。
まア、そんなわけで、俺の存在はこの世から消えたんだ。体はここにあるけどね、社会的には死んだ人間。市民権もないし、税金を納める義務もない。気楽なもんだよ」
からっと笑って、名もなきシェフは窓を見遣った。朝の小鳥のさえずりが眩しい。
鍵一は2分の2拍子でそっとひざこぞうを叩きながら、『ラ・マルセイエーズ』のメロディを思い起こしていた。リストやドビュッシーらに翻案され、21世紀にもフランス国歌として親しまれる音楽に、生焼けの鴨肉や、怒り狂う群衆のイメージを重ねるのは難しかった。努めて想像をめぐらした脳裏に、青・白・赤の大きな旗がひるがえった。
つづく


日本最大級のオーディオブック配信サイト『audiobook.jp』にて好評配信中♪
第1話のみ、無料でお聴きいただけます。
幻の名曲『夢の浮橋』のモチーフを活かし、鍵一が作曲するピアノ独奏曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。
実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいました。
♪『夢の浮橋変奏曲』制作プロジェクトのご紹介
♪神山 奈々さん(作曲家)
♪片山 柊さん(ピアニスト)
音楽用語で「とても陽気に」の意。
「王の菜園」と称されたこの農園では、現在もさまざまな食物が栽培されています。京都の伝統野菜の栽培も。
フランス出身の思想家、作曲家。童謡『むすんでひらいて』の原曲の作曲者でもあります。
第5話『Twinkle Twinkle Little Start(きらきら光る小さなスタート)♪』をご参照ください。
音楽用語で「のんびりと、気楽に」の意