第25話『花雨の庭♪』

船窓に鳥らしき影を見て、鍵一も風が欲しくなった。カンカン帽でシャツの襟元を仰ぎながら、二等室大部屋の熱気から逃れてデッキへ出る。途端、ミゾレ混じりの川風に煽られて「ワッ」よろけた。思わず掴んだポールが火傷しそうに冷たい。跳び上がってデッキを跳ねて、跳ねて、階段の下へ這い込んで鍵一は手袋を嵌めた。なめらかな白絹が手指をつつんで、ホッと溜息をつく。
(リストさんが心配してくださったとおり、冬の船は進みが遅いなア。……でも、焦ってもしかたない。ゆるゆるとゆこう。時間だけはたっぷりあるんだ)※2
帆船は冬枯れの農村を進んでいた。薄墨を溶き流したような雲が彼方の山々を覆って、水車小屋にも、麦畑にも、教会の屋根にも、シャーベットのような雪がうすく積もっている。沈黙の黒。祈りの白。日々の労働の規則ただしい灰色。その他の色は世界から消え去ってしまったように思われた。額にかざした手袋の、ふと見た袖口の刺繍が美しい。
(B先生からお借りしたこの手袋……あのとき、ショパンさんはなぜ、この手袋を見てあんなに驚いたんだろう?それに『夢の浮橋』というキーワード……)※3
猫のフェルマータを懐へ入れて、ショパンと出会った半年前の夕刻のことをぼんやり思い出していた……そのとき。
「やあケンイチ君!久しぶり」
ふいに声が降って来た。
「あれから、きみはいちどもオペラ座へ来なかったね。待っていたのに」
慌てて辺りを見回して、誰もいない。するとフェルマータが天を仰いで「ニャア」と鳴いた。仰げば、声の主は甲板から面白そうに鍵一を覗き下ろしている。その顔に見覚えがあった。

galoppo
※4で階段を降りてくるその背の高い青年が、オペラ座のドアマンに違いなかった……!つい半年前、鍵一が初めて1838年にワープして来た時、チョコレート色の扉の傍に控えて、眉をひそめて、不審者への拭いきれない不安と、抑えきれない好奇心にくちびるを歪めていたその人が今、あっけらかんと白い歯をみせて、鍵一の肩をポンと叩いた。
「お久しぶりです……!エー、その節は」
「不審者のケンイチ君が、いつのまにかフランツ・リストの弟子になっちゃって。さては強運の星の下に生まれたな?」
「弟子だなんて、100年早いですよ。確かに運は良かったですけれど」
「せっかくの大晦日なんだから、パリで音楽家の先輩方とレヴェイヨンを囲めばよかったのに」
「皆さん故郷へ帰られたり、ご家族と過ごされたりしますから……それに、ぼくは作曲の課題を仕上げないと」
「サロン・デビューを目指しているって、風の噂で聞いたけど?」
「ええ、そのために、オリジナル曲の作曲がどうしても必要でして」
「冬休みの宿題というわけだね」
ふたりして階段の下のワイン樽に腰を下ろして、ロープの隙間からわずかに室内の温風が漏れてくるところへ身を寄せた。
「冷えますね」
「でも、静かに過ごしたい時はあるよね」
と、相手は大部屋に湧く笑い声へ目配せしてみせた。鍵一は親しいものを感じて、話相手のできたことが嬉しい。
「どうしてぼくの名前を?」
「この半年間、きみの動向をひそかに窺ってた。ジャンルは違えど、僕も立場は同じだから」
「あなたは?」
「『名無しの詩人』」
と名乗って、相手は手持ちの白カビのチーズと、シナモン入りのビスケットを分けてくれた。この半分凍りかけた食べ物も、寒空の下で噛みしめると歯に沁みるほど甘い。
「詩人さんなのですね」
「パリで4年粘ったけど、文壇デビューならず……!憧れのバルザック大先生とお近づきになれたかと思いきや、牡蠣をきっかけに筆を折り、シッポを巻いて地元ジヴェルニー※5へ逃げ帰る、世にもブザマな『名無しの詩人』」
相手が明るく笑うので、鍵一はどんな顔をすればよいやら分からなかった。猫のフェルマータが鍵一の懐に入ったまま、しっぽでフサフサと鍵一の胸元をくすぐる。
「牡蠣、ですか?」
「この調子だと、ジヴェルニーまでだいぶ掛かりそうだな」
『名無しの詩人』は身を乗り出して船の進みを眺めて、鍵一をふりむいた。
「余興がてら、僕の話を聴いてくれるかい?」
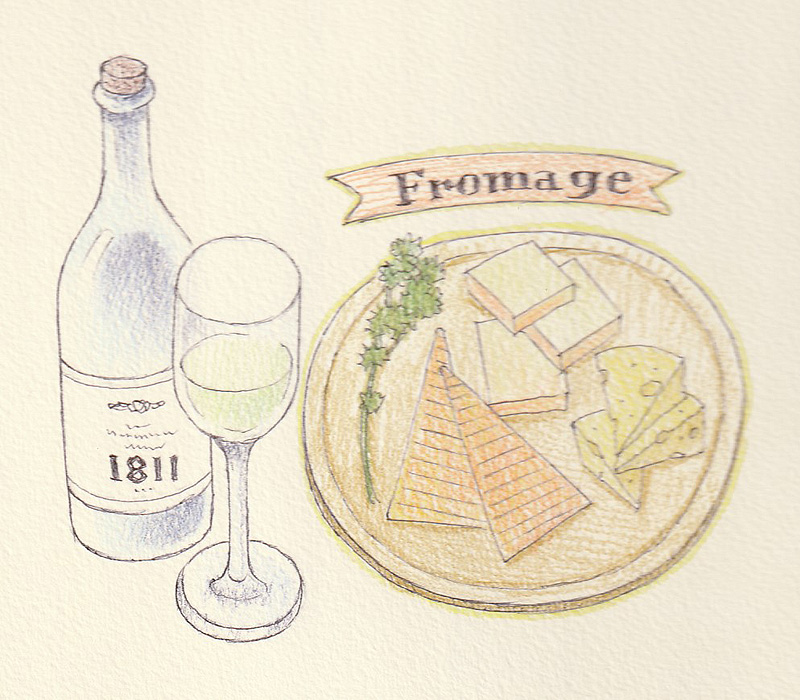
「うちは先祖代々、ジヴェルニーの庭師なんだ。僕は長男だから、否応なく親父の跡を継ぐことになってた。山手の小さな古城のご主人様を神みたいに崇めて、まいにちクマデやハサミを担いで、ご主人様のために庭を造るんだ。子供のころは何の疑問もなく親父を手伝って、僕も庭園の小川の粘土壁をスコップで押し固めたり、バラの苗を等間隔に植えたりしてた。手先は器用なほうだったし、僕の身体には湿った土の匂いが染みついてた。何の疑問もなく……!
ところが15歳の春。城の書庫の虫干し※6を手伝っているときに、僕は運命の1冊に出会ってしまった。なんだと思う?」
「ゲーテ大先生の『ファウスト』?」
「いや、1831年刊行の、ほら。あの人気作家の大ベストセラー」
「ジョルジュ・サンドさんの……?」
「『あら皮』だよ。バルザック先生の傑作小説『あら皮』」
「あら」と反射的に膝を打ってみせながら、鍵一にはバルザックがどんな人物なのだか、その小説がどんなだか分からない。※7
「すみません、まだきちんと読めていなくて……どんな小説でしたっけ?」
「読みなよ。読まなきゃ損だよ。まずストーリーが超絶おもしろいんだから。悩める主人公の青年が、ある日ふしぎな道具を手に入れる……」
ふと『三種の神器』を思い浮かべて、鍵一を不安がかすめた。
(トランクに入れて一等客室へ預けちゃったけど、大丈夫かな。未完の音楽史、音楽記号の福袋、それに鍵盤ハーモニカ……!あれがないと、僕は現代の日本に帰れないんだ)
「なんでも望みを叶えてくれる『あら皮』を手にして、主人公はひととき幸せになるんだけど」
(あとで一等客室へ確かめにゆこう)
「望みが叶うたび、『あら皮』が縮んでゆく……と同時に、主人公の寿命もちぢむんだ。衝撃のラストはぜひ、夜中に独りで読むといいよ」
(望みを叶えてくれるふしぎな道具……という点では、『あら皮』も『三種の神器』も似たようなものじゃないか。ぼくもこうして19世紀パリを探検している間に寿命がちぢんでいたりして……ゾミッ。でもそんな危険なものを、B先生がぼくに渡すかしら?)

「でもねケンイチ君。15歳の僕が小説『あら皮』に夢中になった理由は、ストーリーに惹かれたからじゃないんだ。チャームポイントは描写なんだ」
「なんですって?」
「描写。説明文とは違うよ、描写だよ」
「描写と説明文はどう違うのでしょうか」
「僕に聞くなよ。僕は小説家じゃないんだから。……でも、あきらかに違うんだ。バルザック先生の小説の中の描写は、僕がそれまで読んだどんな文章とも違ってた。たとえば、主人公が銀行家の招待で豪遊するシーンがね、僕は大好きなんだけど」
と、『名無しの詩人』は夢見るような顔つきで両手をひろげて、するとなぜか、鍵一よりも幼く見えた。
「『さあ!僕が望むのは王侯貴族に似つかわしい豪華な饗宴であり、すべての物事が善き方へ取り直された時代に似つかわしいドンチャン騒ぎだ!』……主人公が叫ぶと、ふしぎな『あら皮』のちからでその望みは現実になる。琥珀を溶かしたようなシャンパーニュとともに、フワフワの白いパン、牡蠣、テールスープ、ありとあらゆる実り豊かなごちそうがどっさり運ばれてくる……」
(おなかすいたな……)
「その文章には、この世のすべての華やかなものへの『憧れ』ともいうべきものが詰まっていて」
語り手は鼻をすすりあげて、ポケットから白ワインの小瓶を取り出した。手渡されて鍵一が断ると、「日本人の戒律って厳しいんだね……モーツァルトだって5歳から飲んでたッていうぜ」気の毒そうな目をして、それでも美味そうに飲んだ。
「読んでいてソワソワするような、やけに腹が減ってくるような、そんな描写なんだ。僕なんかが説明しても、なかなか伝わらないんだけど」
「わかりますよ。この旅がひと段落したら、ちゃんと読みます」
(あったかい宇治抹茶入りの煎茶、炊き立てツヤツヤの白いご飯、シジミの味噌汁……)
「そんなわけで、バルザック先生の描写に引きずられて」
「ええ」
「僕の中でパリに対する甘い幻想がふくらんでいった。有望な文学青年として、華やかなパリに身を投じてみたいという欲に駆られた。僕は当時15歳で、親父から庭師の仕事を本格的に教わる年齢だったけど……わかるだろ?僕はバラの樹を円錐形に刈り込むことなんかより、バラの花の薫りを綴ることに夢中になってしまった。
筆を執って、生まれて初めて詩を書き始めたんだ。ほんとうは『あら皮』のような長編小説を書きたかったんだけど、到底無理で。詩なら短いからなんとかなるだろうという……今思えば浅はかな考えで、それでも3年かかって、ようやくそれらしきものが出来た。すぐパリの出版社に送ったよ」
「どうでした」
「待てど暮らせど返事が来ない。で、パリへ行って出版社に問い質そうと思ったわけ」
「18歳の時ですよね」
「そう4年前、僕は18歳だった……!」
いつのまにかミゾレは大粒の雨に変わり、斜めに船へ叩きつけていた。遠く山並みは霞んで、農村の風景はたやすく雨音に掻き消された。
「思い出すなア」と、『名無しの詩人』は湿った栗色の髪を撫で付けて笑った。
「家出同然でパリゆきの船に飛び乗った日が、笑っちゃうくらいのドシャ降りで」
「4年ぶりですか?ジヴェルニーの御実家に帰るのは……」
相手はうなづいて、白ワインの小瓶をひとくち飲んだ。
「また雨に見送られる」
ふたり黙って、雨音の景色を聴いている。
つづく


花が雨のように散ること。また、その花。特に天上から降る花をこう呼び、神仏の加護の証とみなします。 (出典:コトバンク)
ル・アーヴルは英仏海峡を臨む港町です。1836年から、蒸気船によるパリ⇔ル・アーヴルの定期運航が始まりました。
第20話『旅人より草々(ベートーヴェンのお墓のレプリカに寄せて)♪ 』をご参照ください。
第2話 『令和(Beautiful Harmony)♪』をご参照ください。
英語で『ギャロップ』。馬術においては『全速力・早駆け』を意味する。音楽用語では『軽快な4分の2拍子の輪舞』。
フランス・ノルマンディー地方の河口都市。印象派絵画の巨匠クロード・モネが晩年を過ごし、名作『睡蓮』を描いたことで有名です。
書物・衣類等を干して風を通し、虫食いやカビを防ぐこと。
印刷所の事業に失敗し多額の借金を負いますが、小説『あら皮』(1831年刊行)が大ヒットし、一躍人気作家に。美食で知られる音楽家・ロッシーニとも親交がありました。