第20話『旅人より草々(ベートーヴェンのお墓のレプリカに寄せて)♪ 』

♪ベートーヴェンのお墓のレプリカの話
13歳の春、ぼくは母から、京都の叔父に会うことを固く禁じられてしまいました。きっかけは『ベートーヴェンのお墓のレプリカ事件』です。
当時ぼくが在籍していたのは、日本一校則が厳しいので有名な学校でした。学校には身だしなみから言葉遣いにいたるまで実に100を超える規則があり、違反すると罰が下されます。その中に、『男子は髪が耳に掛かってはいけない』という規則(身だしなみ第9条・通称『第九』)がありました。もし違反すると、『音楽資料室にて、ベートーヴェンのお墓のレプリカをひとりで磨く』という罰が下される事になっていました。
なるほど、とぼくは思いました。『校則を破れば、ベートーヴェンのお墓のレプリカを磨くことができるんだ』と。
ぼくは師匠の弾くベートーヴェン・ソナタを聴いて音楽家を志した子供でしたから、ベートーヴェンを心から敬愛しています。そのお墓を磨けるという事は、たとえレプリカであっても、ぼくには大きな喜びなのでした。
ぼくはさっそく、わざと髪が耳に掛かるようにして登校し、願いどおりに罰を言い渡されました。
早朝の音楽資料室で、初めてベートーヴェンのお墓のレプリカに会えたときの嬉しさは忘れられません。年月を経て黄ばみ、埃を被っていましたが……それは大変美しいものでした。ウィーン中央墓地に在る実物を忠実に模したレプリカで、見上げるほど大きなメトロノームのかたちでした。ぼくは指先で雑巾を小さく丸めて、『LUDWIG VAN BEETHOVEN』のアルファベットの一字一字、生没年『1770-1827』の数字のひとつひとつの溝まで、丹念に磨きました。磨きながら、音楽にまつわるさまざまなことに思いを巡らせました。
当時、ぼくは師匠のB先生から、新たにピアノの先生を紹介されたばかりでした。B先生は、かねてよりご専門であった音楽史研究に注力すべく、すべての音楽事業から撤退なさり、芸術大学の学長のポジションも退き、門下生をそれぞれ、資質と進路に見合った教師へ引き渡していらしたのです。小さいころからレッスンを受けてきたぼくも、もれなくその対象でした。さて、B先生がそうまでして没頭なさりたい音楽史研究とは、いったいどれほど面白いものなのでしょうか。……と、時々手を休めて、心の中でベートーヴェンに尋ねてみたりもしました。
そうしているうち、音楽資料室の天窓から朝陽が射し込みます。憧れの音楽家の名は燦然と輝き、メトロノームのかたちをした大きなお墓は白い光に包まれます。まるでベートーヴェンその人が目の前に立っているような心地がして、ぼくは濡れた雑巾を握りしめたまま、しばらく身動きもできないほどでした。
以来、たびたびぼくが校則を破って罰を受けたのは、言うまでもないことです。ある日とうとう、ぼくは指導教官に呼び出されました。
『おかしいじゃないか』
と、指導教官は厳しい口調で戒めました。
『校則は破ってはいけないものだ。破らせないために罰則を設けている。それをお前……喜んでベートーヴェンの墓なんか磨く奴があるか』
『何がおかしいのですか』
と、ぼくは聞き返しました。
『ぼくは音楽の道を志しており、ベートーヴェンは尊敬する音楽家です。そのお墓を磨きたいというのが、どうしてそんなにおかしいのですか』と。
……ぼくは純粋に疑問に思ったのでそう尋ねたのですが、指導教官は激怒し、『看過しがたい反抗的態度』と、ぼくの成績表の備考欄に赤字で書きつけました。すぐに家にも連絡が行き、母は泣いて怒りました。(父は爆笑していましたが)
母いわく、
『あの芸術家崩れの与太者(=京都の叔父)に、あんなにたびたび鍵一を預けるのではなかった。鍵一の魂を腐らせた元凶が京都であり、叔父がその下手人に違いない』
とのことで、ぼくに京都および叔父との一切の接触を禁じました。
学校側では、ベートーヴェンのお墓のレプリカをどこかへ移してしまいました。指導教官によると『修理に出した。完了時期は未定』とのことで、それ以上のことは教えてもらえませんでした。
ぼくは気落ちし、それきり京都へゆくことも、ベートーヴェンのお墓のレプリカの所在を尋ねることも、やめてしまいました。
(実のところ、ぼくにはそれらを追い続けるための時間のゆとりも、気持ちのゆとりもなかったのです。事件後、ピアノを続ける条件として、母から『毎学期末のテストで学年9位以内に入ること』を課されたため、ぼくは必死で勉強しなければなりませんでした。同級生900人の中で毎回9位以内に入るというのは、ぼくには非常に努力の要ることでした。語学と歴史以外の科目は、からきし駄目だったもので……)
今こうして思い返してみますと、やはり後悔が残ります。ぼくはあのとき、京都の叔父のことも、ベートーヴェンのお墓のレプリカのことも、もっとしぶとく追い掛けてゆくべきだったのじゃないかと思います。それに……自分の信念を表現するのに、もっとスマートな方法があったのではないか、と。
今回、京都で作曲に取り組みながら、ぼくはそういった事についても考えたいと思っています。帰国時の滞在先を実家ではなく京都の叔父の家と決めたのは、そのためです。
(京都で取り組むべきことは、他にもいろいろあります。作曲法をきちんと学ぶこと。文学や美術に関する教養を身につけること。パリで書き溜めた備忘録を整理すること……等々。
以前サンドさんが仰って下さったとおり、ぼくは遠回りをすべき人間なのだと思います。自分の音楽に辿り着くために、焦らず一歩ずつ踏んでゆこうと思います)
♪ふたたび、旅について
旅に出る日を、ぼくは前もって決めませんでした。渡り鳥が風を聴き分けるように、ぼくも自分の五感をつかって、出立の好機を捉えたいと思ったからです。何日も待ちました。本当は雪の降り出す前にパリを発ちたかったのですが、セーヌ川の岸辺を吹きわたる北風はいつも、『否』と聞こえました。
さて、ぼくには、旅人の資質がないのかしら……と思った矢先にふと、その時が訪れたのです。
頭の中の氷が溶けたようでした。
ぶつかり合い、軋みながら、記憶の塊がゆっくりと時空の底を流れてゆく音が、ぼくにはハッキリと聞こえたのです。ぼくは耳を澄ませました。12月のパリのざわめきに混じって、『可』と、南風は伝えてゆきました。……
今日、ぼくは旅に出ます。『夢の浮橋 変奏曲』の楽譜を仕上げて、春にはかならずパリへ戻ってきます。またお目に掛かれますと幸いです。
サンドさんもぜひ、良い旅をお続け下さいますよう。ショパンさんにもどうぞ、よろしくお伝え下さい。
1838年12月31日 鍵一
パリ 『外国人クラブ』レストラン2階の自室にて
追伸
すみません、五線譜で鶴を折りたかったのですが、折り方を失念してしまいました。試行錯誤するうち、なんだか舟のかたちになりまして……でも、航海の御守りとしては、これで良いのかもしれません。この手紙に同封いたします。Bon Voyage(ボン・ヴォヤージュ)。

鍵一は手紙に封をすると、手早く身支度をして暖炉の火を消した。窓を開け放つや冬の冷気が、ひょうと流れ込んでくる。小鳥が三羽、色づいた樹の梢から次々に飛び立って行った。
「よし、フェルマータ。行こうか」
「ニャ♪」
♪チェルニー(ツェルニー)作曲 :ベートーヴェンの愛好されたワルツによる変奏曲 Op.12 変イ長調
鍵一が階下へ降りてゆくと、朝のレストランは珈琲の薫りにみちている。ふたりのヴィルトゥオーゾは即興の連弾を続けながら同時にふりむいて、鍵一の旅支度を見るなりリストはくちびるを尖らせ、ヒラーは微笑んでそのまま、華やかに息を合わせて弾き収めた。
「Bravo!」
鍵一が拍手すると、ヒラーが立ち上がって大仰にお辞儀してみせて、笑った。
「ケンイチ君。やっぱり、帰国の決心は変わらない?」
厨房から香ばしい匂いが流れて来る。鍵一は「ええ」うなづくと、カンカン帽を取って胸に当て、
「半年間、本当にお世話になりました」
深く頭を下げた。リストはまだピアノ椅子に腰かけたまま、
capriccioso
※1に鍵盤の上で指を遊ばせている。
「リストさん。ヒラーさん。迷える子猫を拾ってくださった御恩は忘れません。ぼくはかならず、春に戻ってきます。『夢の浮橋 変奏曲』の楽譜を、ぼくなりに仕上げ」
「ほんまに帰るんか」
リストが鍵盤に手を置いたまま、独りごとのように尋ねた。面食らって鍵一が、
「ええ」
答えると、
「帰れるんか」
と、質問が変わった。鍵一がヒラーへそっと目で助けを求めると、このヴィルトゥオーゾは笑って肩をすくめた。『リスト君は大胆不敵な男だのに、こういう時はどうも心配性で困るね』というように。
(作曲に専念するため一時帰国、というプランを後押ししてくれたのは、誰よりもリストさんなのに……)
鍵一はモゾモゾと旅の荷物を抱えなおすと、
「御心配には及びません。乗合船でセーヌ川を下ります」
つとめて
vivace
※2に言った。
「今朝は太陽も出て、比較的暖かですから、川が凍ることはないでしょう。一昨日の雪解け水もだいぶ流れて、川の水位が下がりました。少なくともジヴェルニー※3まではすんなり行けるはずです。……って、リストさんがこないだ教えてくれたじゃありませんか」
「あれは春から秋までの話や」
澄ましてリストが腕組みした。
「冬の船は、ケンイチが思うてるより進まへんよ」
「もし雪がどっさり降って船が立ち往生するようなことがあれば、川辺に宿を取って絵でも描きます。ぼく、こう見えて少しばかり絵心があるんですよ。ドラクロワさんほどじゃないですけれど」
「うそつけ。クリスマスにベルリオーズ先輩と落書き対決して負けたやろ」
「時間だけはたっぷりありますから、ゆるゆるとセーヌ湾をめざします。港には日本領事の伝手がありますので、あとは日本ゆきのオランダ船へ乗り込むまでです」※4
「海賊が出るで。潮も速いし。今年も貿易船が何隻も沈んだんや」
「大丈夫ですよ。ぼくはヨーロッパの造船航海技術を信頼しています。なにせ、ピアノという複雑な楽器をこんなにもすばらしく発展させる国ですから」
鍵一が明るく言い切ると、この1838年パリの大スターはかるく鼻息を吹いて、そしらぬ顔で弾き出した。
♪ショパン作曲 :エチュード集(練習曲集) 第3番「別れの曲」 Op.10-3 CT16 ホ長調
耳にムズムズとこみあげてくる寂しさをこらえて鍵一が「シェフさん」小声で厨房をふりむくと、
「食ってけ」
ぬッとプレートが突き出された。いつものクロワッサンと珈琲が湯気をたてている。
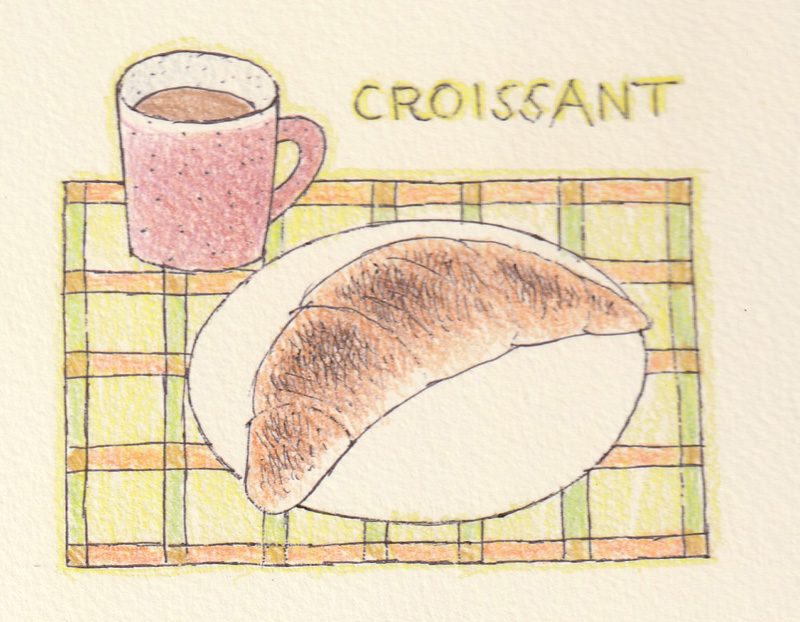
つづく


音楽用語で『気ままに』の意。
音楽用語で『快活に』の意。
フランス・ノルマンディー地方の河口都市。
印象派絵画の巨匠クロード・モネが晩年を過ごし、名作『睡蓮』を描いたことで有名です。
1838年当時、江戸幕府は鎖国政策を取っていました。そのため、長崎に入港を許されたのは、中国とオランダの商船のみでした。