<第15回>暴君ベートーヴェン
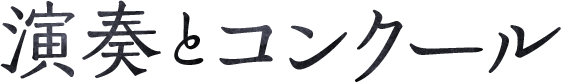
拍手に迎えられ、客席に一礼し、ピアノへ向かおうとした時、舞台奥に掲げられたチャイコフスキーの肖像幕の視線を感じ、これにも敬意を表して一礼することに。
落ち着いてピアノに向き合い、バッハ「平均律」の第一曲を弾き始めます、しかし、3秒と経たないうちにペダルが効かないことに気付き、見るとソステヌート・ペダルを踏んでいました。これはやはりあがっていたのか。
それでも音楽は何事もなかったhかの如く、ひとりでに流れていき、ボーッと遠景を眺めているような感じです。「宮城道雄の『春の海』を連想しました」とは山口さんの評。謂わば、これが「波乱への前奏曲」でした。
次のベートーヴェンで、会場は一気に笑いの連続を引き起こします。私にも予想外でした。それは私の作品解釈が、余りにもベートーヴェンの傍若無人ぶりにフォーカスしてしまったためです。
私が弾いたOp.78は、選曲ミスと言えなくもありませんでしたが、「定番」の重いソナタを弾く気の無かった私は、なるべく短く済ませたい、との思いが働いたことは確かです。しかしこの「テレーゼ」は、却って作曲者の素顔に大胆に迫るものでした。
有名な「熱情」の後に、何でこんな変なソナタが続くのか、といった印象は、ソナタだけを追うからで、良く見ると、Op.76・77・78と続く一連のピアノ作品は、種々の様式による「異色三部作」としてまとめられていたことが判ります。79も加えられなくはありませんが、こちらは「異色」になっていません。その代り、Op.79 はタイトルが示す通り「ソナチネ」であるにもかかわらず、なぜか「ソナタ」の一つとして数えられている謎があります。誰も変だと思わないことも含めて、不思議です。
Op.78から私が感じ取ったのは次のような情景でした。
一楽章では在郷のやんちゃ坊主が、思い切り似合わない上品ないでたちで、都会に出て行きます。これは「ネコを被った」ベートーヴェンで、嬰ヘ長調という調性が、いかにも上ずった、嘘っぽい調子をよく表しています。変ト長調だったら、こうはなりません。
ところが二楽章で作者は本性を顕わにし、「こんなことやってられるか」とばかり、着ているものをかなぐり捨て、自嘲的にはしゃいで暴れ回ります。
これをそっくりそのまま、臆面もなくステージで演じたのでした。観衆は湧きに湧いて、私も連られて着ている礼服を脱ぎ捨てたくなってきました。自分でも制御できない大波に乗せられたようで、演奏も少なからず乱れてしまったのが「致命傷」になったのではと感じます。
選曲をパリでよくやらされたOp.10-2にしていれば――この曲を選んだ参加者はいませんでした――波乱は生じなかったのでしょうが、このベートーヴェンによって、会場はすっかり「笑いのモード」に切り換わってしまいました。(2019.1.9)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

