<第10回>課題曲について―スクリャービンとリヒテル
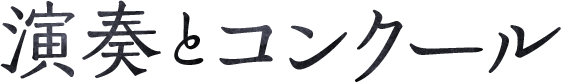
私が一次予選で弾いたスクリャービンとラフマニノフのエチュードは、誰の音源も聴かないまま演奏しました。
スクリャービンのOp.65-1は右手が終始9度で動き回り、無調に近い夢幻的・神秘的な効果をもたらす作品で、手の小さなピアニストには対応できない内容です。
私にこういう曲があるということを教えてくれたのがリヒテルだったことを思い出し、ここでその折の記憶を少しお伝えしておこうと思います。
私が渡仏した翌年の1975年6月末から7月初めにかけて、師のライツィン氏はリヒテル氏がプロデュースしていたトゥールの音楽祭の一環として、メレの農場倉庫の会場で、数名の門弟たちの披露演奏会を兼ねた公開レッスンを行ったことがありました。
私は最年少の16歳ながら、ステージの最後にプロコフィエフの第7ソナタを弾いたのでした。
この曲を含めて、間もなく一時帰国した私は7月30日に金沢で最初のリサイタルを行ったことを思い出します。そして東京で宮沢明子氏にこの時のプログラムを通して聴いてもらった際、ぜひレコーディングしておくように言われ、自作も含めて9月にその運びとなります。商品化は2年後でしたが、このレコードを聴いた中村紘子氏が感じ入ったとかで、プロデューサーに連絡が入り、それが「チャイコフスキー」への伏線として繋がることになります。
さて、トゥールでは音楽祭の期間中、我々一行はロベール・ヴァン・ド・ヴェルド氏一家のお世話になりました。彼は音楽祭を支えていた中心人物で、「メトード・ローズ」の著者の孫にあたります。このヴァン・ド・ヴェルド氏邸にリヒテルがしばしば食事や練習に訪れていたのでした。
広間の大きなテーブルを囲んで、20人ほどがリヒテルを中心に食事をしました。
ライツィン氏を挟んで2つ隣に座った時に、リヒテル氏から話を伺えました。最も衝撃的だったのは、ショスタコーヴィチの病状が既に深刻な状態にあるということでした。「彼の交響曲ではどれがお気に入りですか」という私の質問に「一番好きなのは8番だ。次いで6番かな。最新の15番もいい。あのロッシーニが出てくるやつね。あなたはどれですか」「4番です」すると笑って「悪くないじゃないか」――こうしたやり取りがありました。
その後、手の大きさの話になり、「私はドからファまでは届きますが」と言うと、氏は「自分はドからラまでだ」と手を拡げてみせたのにはたまげました。そうした流れで「スクリャービンに9度だけで弾くエチュードがあってね」と話してくれた訳です。後年、パリの楽器店で偶々見つけ、「これだったのか」と思い、コンクールで弾こうと考えました。
リヒテルは上機嫌で、食後も広間のピアノに向かってあれこれ弾き、皆で曲名を当てるクイズをやりました。彼が弾いていたのはグノーの「ファウスト」やムソルグスキーの「ボリス」等、ほとんどがオペラだったのが興味深いところです。
我々が公開演奏を行った同じ日の夜のステージで行われたリヒテルの壮絶な「ハンマークラヴィーア」の名演は、その会場の熱気とともに、今なお鮮やかに思い起こすことができます。アンコールでリヒテルは終楽章のフーガを再び繰り返したのでした。(2018.10.17)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

