<第12回>委嘱作品について
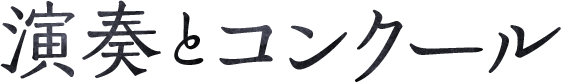
チャイコフスキー・コンクールの課題曲で忘れ難い印象を残したものに委嘱新作がありました。
1982年の回では、審査員長を務めた、旧グルジアの作曲家、オタール・タクタキシヴィリの新作が送られて来て、それを見た私は絶句しました。これが今日のソビエト音楽なのかと。
様式が古い、といったレベルの話ではなく、音楽が貧しいという感じです。正直、学生でももう少しましな曲が書けるだろう、と思える程、弾くのが恥ずかしい内容でした。
滅多に楽譜を捨てることの無い私が、さすがに捨ててしまい、タイトルも憶えていませんが、右手の三連符の音型が連続するトッカータ風の曲だったと思います。
これを参加者全員がさらったわけですが、その後レパートリーにした人がいたとは思えません。これが西欧の前衛かぶれの青年の偏見だったのか、他の参加者たちの意見を聞きたいところです。今となっては、逆に希少な物証としてとっておくべきでした。
しかし、この作曲家がこのような曲ばかりを書いて相応の地位や権威を得ていたとは考えにくく、彼の代表作とはどういうものだったのか、知らずに向き合ったことが残念でした。私は未だタクタキシヴィリのオペラも交響曲もピアノ協奏曲も、知る機会がないままです。
私が主張したいのは、チャイコフスキーのような大コンクールでは参加者は皆、命懸けの覚悟で出てきているわけですから、せめてレパートリーとして使える新作を用意する配慮が要るということです。ベテランのなおざりな作品より、若手作曲家のオーディションで公募するなどした方が賢明です。著名コンクールの委嘱曲をまとめた楽譜集やCD化も検討されるべきでしょう。
加えて、私がコンクール体験者としてつくづく実感したことは、その名称や権威度はどうあれ、自分自身が敬意を払えないような作曲家や演奏家の審査を受けるべきではない、ということです。勿論これはプロを目指す人たちに対してのことですが、誰が審査にあたるのか、は相当大きな問題です。特に作曲の場合、結果がまるで異なります。参加する側も審査員を「審査」する権利がありますから、落とされて不平を言うくらいなら出ないことです。
因みに私は作曲家として、コンクールやオーディションでの受賞歴がありません。音楽祭で取り上げられたことさえ一度もなく、総て落選・選外とされてきました。
その一方で、コンサートに自作を入れると最も好評なのは決まって自作曲で、CDは無いのか、楽譜は出版しないのかとよく聞かれます。敢えて中村紘子氏にご指摘頂かなくとも、私が演奏より作曲に適性があることは自他共に認めていました。実際、私はどのような編成・規模の作品でも書くことができますが、それが何故、「公の場」では蹴られてしまうのか。
結果的に私は生涯をかけて音楽史の闇に深く沈潜し、この未開の「底無し沼」を洗いざらい探索・整備する本来の天命へと導かれることになります。作曲家として私一人の名を残すより、三百名の未知の天才たちの名を残した方が有意義なことは明らかです。
これまでの調査によって、実在した名曲の9割以上は埋もれてしまっている状況が見えてきました。最高の作品だけが『クラシック』として時代を超えて伝わったのだという通説は、実際に歴史を調べたことのない人の言葉です。この「大嘘」はあたかも天動説の如く、反証するリスクの高さから、「きっとそうに違いない」「そういうことにしておこう」と、業界ぐるみで根拠のない思い込みを正当化してきたのでした。しかし、各作曲家をパーツとした驚嘆すべき歴史絵巻が今、序々に姿を現そうとしているのです。(2018.10.19)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

