<第11回>課題曲について――ラフマニノフ・チャイコフスキー
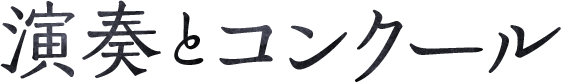
一方のラフマニノフについては、未だその音楽の本質を理解できずにいました。当時の私にとってラフマニノフはかなり鬱陶しい存在で、彼の自作録音に接して目を開かれるのは数年後のことです。特に「バルカロールOp.10-3」の演奏には感嘆しました。
そしてほとんどのピアニストが、今も私と同じ勘違いに陥っています。久しく誤ったラフマニノフ像が定着してしまっており、これは演奏関係者にとって由々しき問題なので、この機会に述べておきたいと思います。
楽譜の視覚的な印象もあって、ラフマニノフを重厚で情念的な音楽ととらえがちですが、事実は正反対で、敏捷で軽やかに、きびきびと動かなくてはラフマニノフにならないのです。尤も、巨大なスケール感は維持しつつも、ですが。
楽想そのものはロシア流の濃厚な叙情とは云え、それを非情なまでの客観性と諦念をもって乾燥・中和させ、かつ迅速に処理することが求められます。ベタつかず、決してヒート・アップしてはならないのです。このスタンスはそのままショパンにも通じるものでしょう。この二人は同じ年回り(一白水星)の性格を持っているからです。激しくとも、温度を上げてはなりません。
ピアノでロシア音楽といえば一般的なイメージとして、まずチャイコフスキーとラフマニノフ、それも協奏曲を思い浮かべます。これらの分厚い和音がもたらす壮麗さは彼らの本質ではないにもかかわらず、そういうマナーがこの国の作曲家に浸透してしまったのはなぜかといえば、アントン・ルビンシテインの圧倒的な感化力にありました。ルビンシテインの第4、第5協奏曲が無ければ、チャイコフスキー、ラフマニノフの協奏曲もあり得ませんでした。“ルビンシテインを知らずして、彼らの音楽を弾くなかれ”と言いたいところです。
ところがそのルビンシテインとなると、知られている曲は「へ調のメロディ」だけだったりします。このヒット曲は彼の本質から最も遠いもののひとつで、ベートーヴェンにおける「エリーゼのために」といい勝負です。真のルビンシテインを知るには、ビューローやサン=サーンス等、各曲が音楽家の友人たちに捧げられた「6つの前奏曲とフーガOp.53」や稀代の名手、タールベルクに献じた「幻想曲Op.77」のような作品を見る必要があります。
またチャイコフスキーの如く、自身がピアニストで無かった人の作品は当然ながらピアニスティックな書法でないため、この場合はオーケストレーションを喚起させる工夫が必要です。と同時に、低俗に堕さない気品やエレガンスが極めて重要な要素として浮上してきます。
この点に関してニコライ・ルビンシテインの右に出る者はいません。兄とは対照的に、ごく僅かなピアノピースしか遺さなかったニコライですが、その優美さと洗練は史上屈指です。私がピアニストの理想的なモデルとして筆頭に挙げたいのは、このニコライ・ルビンシテインであることをお伝えしておきたいと思います。(2018.10.18)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

