<第9回>課題曲について―プロコフィエフ
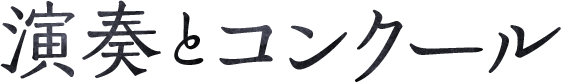
チャイコフスキー・コンクールの1次と2次、各予選曲の所要時間は約40分と60分でした。私は現代に近いものほど弾きやすいので―これは至って自然なことだと思えるのですが―当然2次予選の曲目に違和感が少なく向き合えました。逆に1次は悲惨で、気分よく弾けるのはスクリャービンしかありませんでした。
やはり楽しいと思えない曲を弾くのは無理があり、嫌いな食材を何とか食べられるよう、味付けや調理法に苦慮するようなもので、どうしても好きでやっている人にはかなわないところがあります。ブゾーニとペトリの演奏をモデルに取り組んではみたのですが。
私がすべての課題曲の中で、最も力を入れたのは2次冒頭のプロコフィエフ「第9ソナタ」でした。サン=サーンス、ブゾーニと並んで、この巨匠はピアニストとして私を魅了しました。言い換えれば、プロコフィエフの演奏を聴くまで、私は彼の作品をまるで分かっていなかったのです。彼の演奏の何が私を驚かせたのでしょうか(先を読み進める前に、考えてみてください)。
2つの理由があります。第一に、これはブゾーニとも共通しますが、時間軸の中での創意、つまり「演奏を作曲する」という観点です。第二には土着的な朴訥さと知的な洗練の見事な調和です。その雄弁さ、非凡さに感服しました。
課題としては、プロコフィエフの(9曲の)ソナタから1曲、というものでしたが、参加者たちの選曲ぶりを見ると、案の定3番と7番が群を抜いていて、6割以上の人がどちらかを選んでいます。逆に少なかったのは5番の1名、次いで1番、4番、9番の各3名でした。
「ソナタ第9番Op.103」は献呈されたリヒテルのレコードがありますが、あの第8番の驚異的な名演に比べると、今一つパッとせず、作品の真意を掴みあぐねているようです。これは正にリヒテルへの友好的な挑戦状とみられます。
プロコフィエフはリヒテルの巨大な能力を熟知しながらも、彼に欠けているものを鋭く見抜いていました。「さあ、君はこれを表現できるかな。やってごらん」というプロコフィエフのいたずらっぽい表情がありありと窺えます。
そして私はこの曲に限っては、被献呈者よりも作曲家の意図に近づける自信がありました。2次でこれを弾けていたら、そのインパクトは1次の比ではなかった筈です。
ではリヒテルに欠けていたものとは何か?――このようなことは軽々しく言挙げしかねますが、大きなヒントとして「字体」で考えることが可能です。リヒテルの演奏は「楷書」であり、ホロヴィッツは「行書」です。プロコフィエフは「草書」を求めていたのです。
因みに現代の演奏家の大多数は「楷書」ならぬ「写植」です。楽譜を写真のように再現するのが作曲者に忠実だと思い込んでいる人が多いため「草書」と「下手クソ」の見分けがつかなくなってきています。しかし、自然な乱れ、崩れ、ぼかし等がないと「絵」にならないのです。(2018.10.8)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

