<第8回>コンクールに備えて
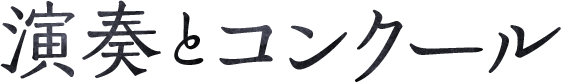
今、第7回チャイコフスキー・コンクールのプログラムを改めて眺めてみると、121名の参加者がいたことが判ります。一人1ページ宛に写真・プロフィール・演奏曲目が載せられていて、ロシア語による国名では日本がしんがりで、14名の日本勢が並んでいます。
私を除く13名の方が国内で選抜されたと思われますが、私とは宿舎のホテルも異なり、顔を合せることはありませんでした。
当時の国際情勢もあって、ここでは中国や韓国の躍進ぶりは未だ見られず、日本人はアメリカの32名に次ぐ多さです。日本での国内予選がどのくらいの規模だったのか、私は知りません。
棄権者も数名あって、二年前のショパン・コンクールで物議をかもしたイーヴォ・ポゴレリチなどは出なかったようです。
参加者の中には若きエミール・ナウモフがいて、二次予選の故国作曲家の選曲では私とナウモフが自作を持って出ていました。音楽院の廊下で子供のようにおどけていたのがナウモフだったと後に知りました。
コンクールは2つの予選と、本選で2曲の協奏曲が課されていました。私は選曲も練習も、一切人の助言を受けませんでしたが、ただ自宅でさらっていた訳ではなく、一次と二次の曲目にそれぞれアントン・ルビンシテインの大作(第1ソナタOp.12と6つのエチュードOp.23)をカップリングして、AB両プログラムを設定。各2回の大ホールでのコンサートを行って、準備に当てました。Bプロの一回は、金沢市を通じて、姉妹都市・ベルギーのゲント市まで出かけて行いました。暗譜の覚悟を確立するため、敢えて楽譜を持って行かなかったことを覚えています。
ゲント市のホールには満員の聴衆が詰めかけ、大盛況で終演後、多くの市民が列を作ってサインと握手を求めに来ました。こんなことは後にも先にもなかったことです。特にプロコフィエフとルビンシテインの大作に讃辞が集中しました。自費の渡航だったのですが、それを知ったゲント市側は市の使節としてそれはおかしい、と交通費まで支給してくれて恐縮しました。
ただ、2曲の協奏曲については当時共演者がおらず、それでもホールを何度も借り切って、公開リハーサルを行いました。とにかく可能な限りの準備に尽力しました。
私が選んだ課題曲を挙げておきますと、
<第1次予選>
J.S.バッハ:平均律第一巻から第1番
ベートーヴェン:ソナタOp.78
ショパン:練習曲Op.10-5
リスト:超絶技巧練習曲第9番「回想」
スクリャービン:練習曲Op.65-1
チャイコフスキー:「四季」より「一月・炉端にて」
<第2次予選>
プロコフィエフ:ソナタ第9番 Op.103
シューベルト=リスト:「愛の便り」「水の上で歌う」「アヴェ・マリア」
ストラヴィンスキー:ソナタ(1924)
チャイコフスキー:「ドゥムカ」Op.59
委嘱新作(タクタキシヴィリの小品)
自作:「ピアノ曲1971」
(協奏曲については本連載の第6回を参照)
―以上のようなものでした。
(2018.9.16)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

