<第7回>国内予選への不参加
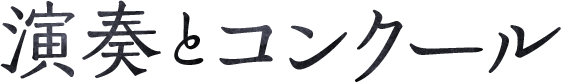
私が出場した1982年の第7回チャイコフスキー・コンクールの参加にあたって、日本では国内の選抜予選が行われていました。しかし私はこれに参加せず、直接旧知の日ソ協会に依頼し、ソ連大使館を通じて参加証を得ていたのです。
私の母はモダンバレエの舞踊家で、それまでに門下生を率いて3度のソ連公演を行っていました。郷里金沢の姉妹都市、イルクーツク市からの招聘を皮切りに、1974年にはモスクワ、レニングラード(現ペテルスブルク)公演を行い、私はピアノ伴奏者として同行し、その足でパリ留学の途につきました。従って私が最初に見た外国はソ連で、イルクーツクの大観衆の前でバレエの伴奏ピアニストとしてステージに立ったのは10歳の時です。幕開けにソロでチャイコフスキーの「トロイカ」を弾きました。
こうしたソ連との親善活動の実績から、日ソ協会や大使館が動いてくれたのですが、私が何故「チャイコフスキー」の国内審査を避けてこんな方法を取ったかというと、1980年に開催された日本で最初の国際コンクールの参加を拒否された経験があったからです。
パリ時代の師からの案内で応募したこのコンクールは、事務局から「書類選考の結果、貴方の参加は認められませんでした。申込金(2万円)は返却できません。この件についての問い合わせは一切お断りします」という旨の一方的な通知が届きました。これは詐欺に近い対応です。
理由は不明ですが、師事している先生や学歴を記入する欄に「独学」と書いたのが論外とされたのかもしれません。日本の音楽界に不信感を持った私は、「チャイコフスキー」の国内審査からも締め出される事態を予想したのでした。
実際私はどこの音楽学校・音大も出ていません。作曲は完全な独学。ピアノも演奏家として本気で取り組む覚悟を持ったのは人への師事をやめた後でした。そもそも中学校卒業以来、受験の経験が無いのです。
パリで師事したフローレンシア・ライツィン氏もまた、私のパリ音楽院入学を強硬に反対しました。ニューヨークでワンダ・ランドフスカ門下だった彼女はアルゼンチン出身で、「パリ音楽研究所」という私塾を開設し、名誉顧問として、スヴャトスラフ・リヒテルの名を戴いていました。リヒテルが指導に来ることはありませんでしたが、シュナーベルの息子やバレンボイムの父、バドゥラ=スコダ、ハイドシェック、ゲルバーといった人たちが時折公開講座に訪れました。その度に私も「ベートーヴェンやショパン作品」のレッスンを受けさせられた一方で、最後には決まって私の即興演奏が求められ、盛り上がったところで「お開き」というのが習わしでした。
しかし、私の関心は専ら現代音楽と作曲にあり、こうした環境への不満が次第に募っていったのです(続く)(2018.9.14)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

