<第6回>「チャイコフスキー・コンクール」の真実
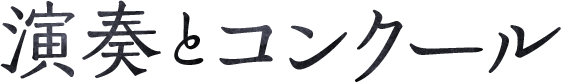
ピアノ・コンクールについての本といえば、中村紘子著「チャイコフスキー・コンクール」(1988)が圧倒的に知られているようで、既に文庫本化され、海外での翻訳もされていると聞きました。ピアノ関連書の参考文献リストに必ずと言っていい程、上がっています。
私は読む気が無いので持っていませんが、知人が持ってきて、見せてくれたことがあります。この文中に登場する「中村オサム氏」は私のことで、著者は1986年のコンクールをテーマとした本の中で、わざわざその前回の1982年のコンクールにおける、私の印象を取り上げています。ここには私に対する、中村氏の複雑な思いが見て取れます。
当時23歳だった私は、誰の指導も受けることなく、自力でこのコンクールに出場したのですが、ドビュッシー以降の音楽にしか興味が無かった私には、どのみち「一般的なピアニスト」になる気などありませんでした。そうした私の演奏に対し、審査員だった中村氏は、貶すとも誉めるともつかない微妙な論調で、所詮コンクールの価値観とは異なるもの、として遺憾の意を示していたように思います。
しかし、実際には私の演奏について、他国の審査員が驚く程の最低点を付け、二次予選も聴きたがる意見を押さえて、一次を通してなるものかと頑張ったのは、他ならぬ中村紘子氏でした。「彼は作曲家であり、このようなコンクールに通すことは道を誤らせる」というのが、その主張だったと言います。
何故、私がこうした内情を知っているのか?天の計らいか、運命のいたづらか、私自身も予期しなかった事情によって、中村氏の審査の動向は私に筒抜けに伝わっていたのです。
この件については、思い出したくない出来事として封印し、発表を控えてきましたが、天運循環し、36年振りの九紫戌歳を迎えたのを機に公開することは、コンクール再考の上からも時宜を得ていると判断しました。道義に従って事を明らかにするのが、年の本義だからです。
私に「チャイコフスキー」への参加を勧めたのは、かつての師・宮沢明子氏でしたが、私には場違いな、このコンクールに参加した直接の動機は、ロシア音楽界の礎を築いたアントンとニコライ・ルビンシテイン兄弟への敬意からでした。2曲選ぶ必要のあった協奏曲は、アントンが初演したサン=サーンスの第2番と、チャイコフスキーが第1協奏曲でニコライの共感を得られず、献呈を取り下げながら、再びニコライに捧げ直した第2番を用意していました。しかし、ニコライの早逝によって彼による初演は実現されず、チャイコフスキーはピアノ三重奏曲「ある偉大な芸術家の思い出に」を書いて、その死を悼みます。
ニコライ・ルビンシテインが若きチャイコフスキーの第1協奏曲を評価しなかったのは無理からぬことで、例えば冒頭のピアノの両手の和音の上昇形は、その前年に初演され、アルカンに捧げられたアントン・ルビンシテインの第5協奏曲(独奏アントン、指揮ニコライ)からの剽窃を思わせ、ニコライ一流の流儀からは程遠い内容だったためです。因みに、私以外の日本人参加者全員を含めた、全体の9割以上が1番を選んでいましたが、作品としてのクオリティが2番の比でないのは明らかです。(2018.7.20)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

