<第4回>ショパンと「ショパン・コンクール」
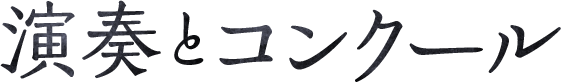
ピアノ・コンクールの最高峰と目される「ショパン・コンクール」にショパン本人が出たとしたら、まず予選落ちは免れないでしょう。
理由ははっきりしています。「楽譜の表示を守らない」「音が弱過ぎる」といったことに加えて、そもそもショパンの音楽が、大ホールでの鑑賞に適さないことを、あからさまに示すだろうからです。
それどころかショパンは、自分の作品が熾烈な競技大会の演目として用いられていることに激怒し、耳を塞ぎ、半狂乱になって「もうやめてくれ!!」と絶叫するかもしれません。ショパンの性格を考えると、これはあり得る話です。
実際にショパンの演奏を聴いた、当時の人たちの証言から、彼は同じ曲を、二度と同じようには弾かなかったことが確認できます。それが出版された楽譜の指示を無視したものであっても、聴き手にはその方がより素晴らしい、と思わせる演奏だったといいます。
ショパンに限らず、大音楽家は皆、そのようでした。楽器も含めて、その時と場所によって、望ましい演奏が自在に変化するのは当然のことで、昼夜・季節・天候を問わず、いつも同じになる方がおかしいのです。
よく音楽研究者たちが、同じ曲の異なる版との違いを見比べて「どれが真実のオリジナルか」を突き止めようとしますが、正解が一つしかない、という思い込み自体が、既に誤っていることに気付いていません。
楽譜が「作品としてのオリジナル」になるのは20世紀に入ってからのことで、19世紀の音楽に「原典版」はナンセンスだと私は考えます。なぜなら、原典とは基本的に自筆譜であると同時に、ショパンやリストにとって本来の「オリジナル」は、楽譜に書き取られる以前に存在している「流動して止まない楽想」にあるからです。
つまり、重要なことは「楽想」というオリジナルは、人間の所産ではないということです。わかり易く言えば、「あの世」からもたらされるインスピレーションを、時代と風土の交点としての人間が心・技・体を用いて顕現化を完成させるのが芸術です。従って芸術の真贋を見分けるのは簡単で、「あの世」が関与しているか否かにかかっています。その点で音楽は、彼岸と比岸をつなぐ、最も簡便な手段であり、あくまで向うからの情報を受け止め、具体化する技術として、作曲や演奏の練習、訓練が求められる仕組です。
演奏の自在性を実感・実践しにくくなった最大の理由は録音技術の登場です。何度も繰り返し聴かれる、という意識が人間の表現を不自由なものにしてしまいました。音楽の表現は、録音されようとされまいと、常に一回きりのものなのです。
楽譜ではなく、楽想をオリジナルとしてとらえるとはどういうことか。その手掛りとして、以前私が例外的にコンサートのアンコールで弾いた、ショパンの「雨だれ」を挙げておきましょう。「あの世との共働作業」を実感した体験でしたが、コンクールでこれをやったら落ちてしまいます。 (2018.6.22)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。 金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。 その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。 この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

