<第3回> コンクールがもたらしたもの
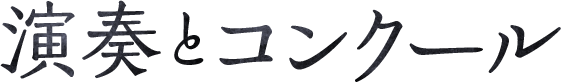
日本を含めて、コンクールが世界規模で急増し出すのは、1980年代に入ってからです。‘80年代の10年間で世の中は激変しました。
東西冷戦の終結、デジタル社会の到来、日本は昭和から平成へと移りました。
音楽の世界でも、レコードがCDへと姿を変え、「前衛」が事実上の終焉を迎えます。
それまでのレコード文化を全否定するかのような、業界の強引なCD一本化は致命的な暴挙でした。当初、CDのサイズは、もっと小さくなる予定だったと聞いたことがあります。コンパクトにさえなれば便利だろう、という合理主義者の発想です。
しかし、レコードをアートと考える筋から「適切なサイズというものがある」との猛反発を受け、現在の形となったようですが、CDの容量は、「ベートーヴェンの第九」が収まる長さを基準にしています。
これも乱暴な話で、「第九」を通して聴くには便利だ、という理由だけで、あらゆる音楽作品がその容量でごちゃまぜに詰め込まれてしまうのは、たまったものではありません。人間の集中力は20分程度が限界で、それは丁度LPレコードの片面分に相当します。
私は今でも音楽鑑賞は専らLP盤で、CDは内容が良くても「参考音源」としてチェックするだけで、二度とかけないものがほとんどです。「情報」としか認識できないからです。
容量が40分に満たないようなCDは、それだけで販売店からクレームが来るそうですが、物品の量り売りではあるまいし、30分の曲を速度を落として50分にすれば文句はないのか、と言いたくなります。
価値のある物は小さくても高価です。私は5分の曲でも名曲、名演であれば、それだけで一枚にすべきだと考えています。商品のサイズに対して箱を合わせるべきであって、逆にするのは芸術を馬鹿にしています。
結局、CDの登場から30年を経た今日、レコードは絶滅するどころか着実に支持者を増やしているのに対し、ネットからのダウンロードによって、命運が危ぶまれているのはCDの方です。
合理性や便利さ、というのは呉々も要注意で、リスクが必ず隠れています。茶室の入口を自動ドアにするような不粋さは、芸術の敵と言うべきでしょう。
平成も最後の年に至って過去を振り返ってみると、あらゆる音楽ジャンルの作品も演奏も、録音・再生の音質やピアノの音色までもが、結果的に1970年代を超えられなかったことが明らかになってきています。
コンクールも例外ではなく、数が増えたことでピアノ人口の技術的な「底上げ」は達成したものの、同時に「上」まで下がってしまい、時代を突き抜けるような大演奏家、巨匠といった人は出て来なくなりました。実現したのは「高度な均一化」です。
デジタル社会と連動して栄えてきたコンクールの成果を、私たちは受け止めなくてはならない時期に来ています。これは必ずしも否定的な意味ではなく、新たな時代が要請するところの価値観・方向性に対応する上で、必要な行程です。(2018.6.20)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。 金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。 その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。 この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

