<第1回> コンクールの魔力
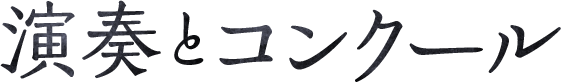
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。 金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。 その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。 この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)
この度、ピアノ・コンクールを再考するという観点から、これまで私が見聞きしたこと、感じたこと、また今後の展望について著すことになりました。一つには、こうした内容について、率直な発言をできる人が非常に少なく、演奏関係者は余り触れたがらないという現実があります。
ここでは、私自身が体験したチャイコフスキー・コンクールの顛末も含めてお伝えし、コンクールの功罪やそのあり方を見直す機会として頂くことは、意味があろうかと思います。
日本は今や世界に冠たるコンクール王国です。2018年現在、国内コンクールの総数はピアノに限っても200を超えるといわれます。その最大手、ピティナでは毎年4万人を上回る参加者があると聞いて驚嘆しました。
これだけの規模になると、受験戦争の一角を担う社会現象と見るべきで、良くも悪くも国民が一丸となって動いてしまう、日本人の性質をよく表しています。
音楽教育の中心、ステータスとして定着しているコンクールですが、その多くは「学力テスト」に該当するとみられます。今日のコンクールは、優れた演奏家を育成するというよりは、学習者全般のレベルアップと、ステージへの夢を抱かせるセレモニーへと移行しつつあります。
しかしながら、新時代の産業として立つコンクールは、芸術とは反対の方向へ進みかねない状況です。現に今日のピアノ関係者にとって「お客様」は聴き手ではなく、生徒になってしまっています。この構図が改まらない限り、聴き手は際限なくベートーヴェンやショパンを繰り返し聴かされる状況が続きます。
いわゆるプロの登龍門としての国際コンクールの様相も、半世紀前とは大きく異なります。かつてのように、優勝者には大手レコード会社や音楽事務所がバックアップして、活動を保障してくれる時代ではなくなっています。コンクールやピアニストが余りにも増え過ぎたこと、しかも皆同じような教育を受けた、同じようなレベルの、同じような曲しか弾けない演奏家ばかりでは、活動が成立しないのは当たり前です。
私は、これは大変な才能の労費・損失だと考えています。元来才能に恵まれた人たちが、幼い頃から人生を賭して多くの努力と出費を強いられた挙句にこの状況では、何かが間違っているとしか思えません。そうした不条理な現実を忘れるべく、一過性の華やかな幻夢を求めてコンクールが必要とされているとしたら、かなり怖い話です。
私の少年時代の師、宮沢明子氏の「コンクールは麻薬よ」という言葉は核心を突いています。一度やり出すと止められない、という訳です。確かに実力はつくし、度胸もつきます。しかし度が過ぎると、肝心な原点を忘れがちです。
自覚症状の無い「コンクール依存症」には要注意です。参加者も指導者も、音楽との関わり方を誤らないために。(2018.6.7)

