<第2回> 競技としてのコンクール
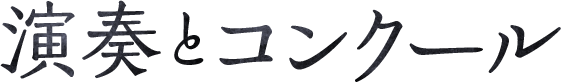
コンクールは競技であり、戦いです。従って勝たなくてはなりません。しかしながら、スポーツのように記録を計ったり、試験のように一つの正解を求めるものではないので、このあたりの曖昧さが評価の矛盾を抱えることになります。
国際コンクールなどでは、国家レベルでのせめぎ合いや、派閥同志の露骨な潰し合いが横行するのでなおさらです。こういうことがあるので、演奏家たちはコンクールの実態について語りたがらないのです。
今、私の手許に「田中希代子ピアノリサイタル第2集」という、ドビュッシーの前奏曲を集めた半世紀以上前のレコードがありますが、その後の日本人ピアニストに、これを凌ぐ名演があっただろうか、と思わせる内容です。
この田中氏は1955年のショパン・コンクールで10位に終わったということですが、この時の優勝者だったハラシェヴィチや、2位のアシュケナージのレコードを聴く限り、音楽の造形感覚や表現力において、田中氏より優れているとは思えません。こうしたケースは特別なものではなく、常について回るのがコンクールの宿命といえそうです。
一般的に審査は、演奏の表現力、作品へのアプローチの仕方、といった点について「公正に」判断し難いため、どうしても技術面に注意が向けられるのはやむを得ません。
結果、きれいな音でミスをしない人が勝ち残ることになりますが、このような演奏が音楽として魅力的かどうかは別問題です。
コンクールに出る以上は、「鑑賞」ではなく、「審査」を前提に準備しなくてはならない訳で、ここには人を楽しませる、という音楽の最も重要な意識が欠けています。
当然、音楽愛好家がお金を払って聴きたいのは、魅力のある演奏であって、失敗しない演奏ではありません。上手でつまらない演奏より、下手でも面白い方がまだお金を取れます。
演奏する側と聴く側、この両者の意識のずれが、クラシック音楽の需要と供給のすれ違い、空回りを生み出しているのです。多くの人は、この事態を理解できていないようです。
コンクール経験者の「落とし穴」は、傷のない演奏さえできれば、作品を上手く表現できたかのように錯覚することです。この呪縛から脱するのは容易ではありません。どこまでミスタッチをしないで弾けるか、というテレビ番組が成立するのも、数多くのピアノ関係者をターゲットにしているからでしょう。一般人のほうがくだらないと感じます。
いっそのこと、技術競技に特化したコンクールをやってみるのも有効かもしれません。
スケール全調をミス無しで何秒で弾けるか。他にアルぺジオ、トリル、オクターヴ、三度、連打等の各種目を設け、総合一位を競います。採点はオリンピック同様、終演後すぐに会場の電光掲示板で表示する。これなら圧倒的に公正です。これくらいのことをしないと、「呪縛」を解くのは難しいのでは。(2018.6.19)
金澤攝氏の連載記事「音楽と九星」第一部では、たびたびピアノ演奏のあり方に関わる提言がなされていました。このたび開始する連載「演奏とコンクール」は元々、同連載の第二部に入る前の「コラム」として構想していましたが、短期連載へと拡大して、掲載することになったものです。 金澤氏は音楽家として長年にわたり、千人以上におよぶ作曲家と、その作曲家たちが遺した作品を研究し続けています。ピティナ・ピアノ曲事典は、氏が音楽史を通観する「ビジョン」を大いに頼ってきました。その金澤氏がコンクールに関わっていたのは約40年前、コンテスタントとしてでした。現在はピアノ指導には携わっておらず、続く本文でも言及されているように、昨今の音楽コンクールの隆盛ぶりに驚かれています。 その金澤氏による「コンクール」論は、コンペティションにピティナ会員の方々には新鮮に感じられるかもしれません。共感されるかもしれませんし、あるいは異論・反論を述べたくなるかもしれません。 この連載では、まずは氏の提言を連載しますが、「演奏とコンクール」は多くの音楽家にとって切実なテーマであるはずです。ゆくゆくは様々なコンクール関係者、ご利用される方々にも寄稿をお願いし、21世紀における「コンクール」ひいては「ピアノ演奏」のあり方を考えていく契機にしたいと考えています。(ピティナ「読み物・連載」編集部 実方 康介)

