第64話『美味しいうつわ♪』

美味しいうつわ♪
その日の夕食時、鍵一は水琴窟を話題に上げた。
「昔、叔父さんと水琴窟を掘りかけた事がありましたよね」
「そうだっけか」と宙を仰いで、叔父は濃厚なカートッフェルズッペ※3を一口、二口、美味そうにすすると「ああ」と思い出した。
「夏だよな。ちょいと洞水門※4、……水琴窟の構造を参照したくて掘ったんだが。甕の埋め込みが意外に深くて、ぜんぶは掘り切れなかったなア」

「あの夏、ぼくは自由研究で水琴窟のレポートを書くつもりだったんですよ」
「かわりに植物図鑑の見本を貸してやったじゃないか」
「若冲ですよね」
それは江戸時代の絵師、伊藤若冲※5による植物画の下絵集であった。通称、
花卉図
※6。晩年の若冲が京都伏見・石峰寺の天井画として描いた。明治初期に古美術商から人手に渡り、京都岡崎・信行寺へ寄進されたものである。直径約33センチの円に描かれた150枚以上の草花は、子供の眼にも美しかった。サボテン、向日葵、牡丹、梅。百合、蓮、紫陽花、ハイビスカス。
小学生の鍵一は若冲を手本に、首尾よく貴船の庭の植物図鑑を描き上げた。夏休み明けに、若冲の下絵も添えて学校へ提出した。帰りの下足箱で靴を履き替えていると、担任が慌てて廊下を駆けてきた。『鍵一君、これは職員室じゃ預かれませんよ!』と若冲の端をつまんで返された。後ろから教頭が『半紙に包みなさい、せめて半紙に!』と駆けてきた。書道用の半紙に若冲を包んでもらっているところへ美術教師と社会科教師が駆けてきて、『ちょっと若冲に会わせてください』『教頭!なぜ我々に若冲をちょっと会わせないんですか』と、ちょっとした騒ぎになった。若冲、若冲と慌てふためく大人たちを見てようやく、鍵一は若冲の何たるかをふんわり理解した。……
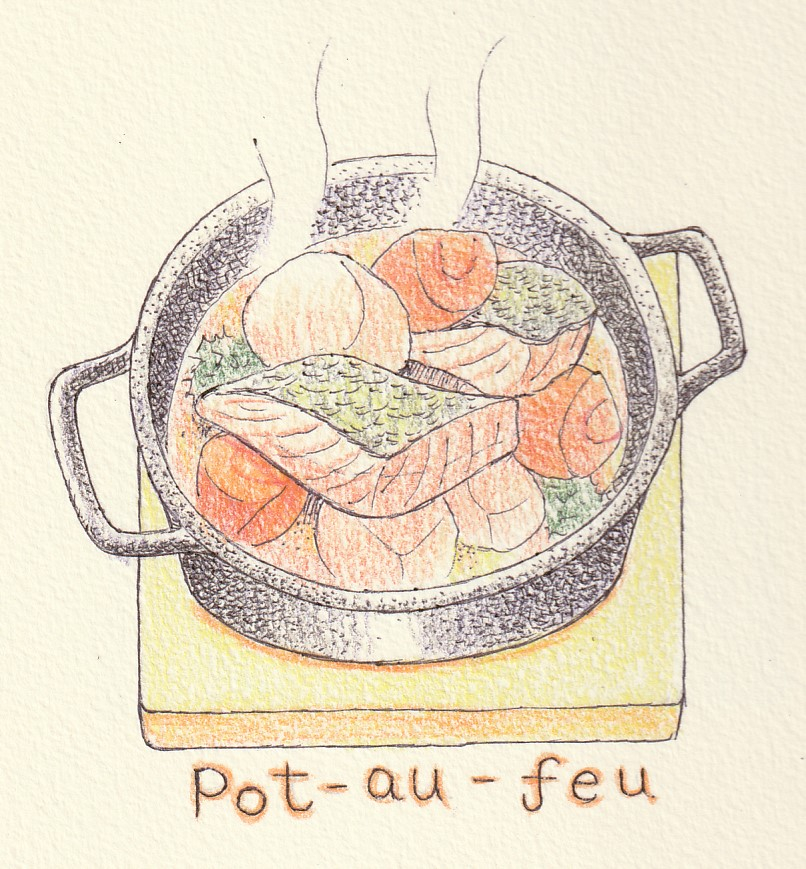
「それにしても鍵一、いつのまに料理を覚えたんだ」
食卓にずらりとならんだ皿を見渡して、叔父は
gicheroso
※7に笑った。
「すみません、作り過ぎました……」
「いや、美味いよ。たいしたもんだな」
「パリ留学中にレシピを覚えたんです。お世話になったレストランを少し手伝っていたので」と、これは本当の事を言った。
「留学して良かったじゃないか」と叔父は鮭の皮をつまんで、猫用の器に入れてやる。すぐさまフェルマータが飛びついた。
「パリ音楽院の編入試験の都合だか何だかで、B先生がおまえをいきなり留学させた時は、どうなる事かと思ったが。ピアノ、作曲、料理も勉強できるんなら一石三鳥だ」
「いいえ、ぼくはレシピを書き留めたり、生地を丸めるのを手伝ったりした程度で……でも、料理はおもしろいです」
「じいちゃんに似たな」というので、鍵一は興味をもった。
「料理をする人だったんですか」
「料理人だよ」
まんまるのクロケット※8を口へ放り込んで、叔父はにやりとした。
「おまえのじいちゃんは料理人だった。この家はもともと料理旅館なんだ」
「初耳です……!」
「京都の旦那方の集う店でさ。時々は茶会をひらいてみたり、連歌をやってみたり、観月会を催したり。親父も客に混じって大いに遊んでた。水琴窟も、お仲間と一緒に創ったそうだ」
どうりで楽しい音が、と鍵一の言い掛けたところへ、叔父の携帯電話が鳴った。
「ハイ、古美術の鉄平堂でございます。ええ、はア、誠に結構ですな。では明日また掛けます」
すぐ切ってまたクロケットを頬張っている。電子音の『水の戯れ』が、思いがけず清らかなものとして耳に残った。
「叔父さんはラヴェルが好きなんですか」
「ラベル?」
「……何でもありません」と、鍵一もクロケットを頬張った。19世紀パリで食べたクロケットのほうが、ローズマリーが効いて香ばしかったと思う。「ところが」と、叔父は携帯電話を脇へ押しやって話を続けた。
「あるとき、親父は贋作を掴んじゃってね」
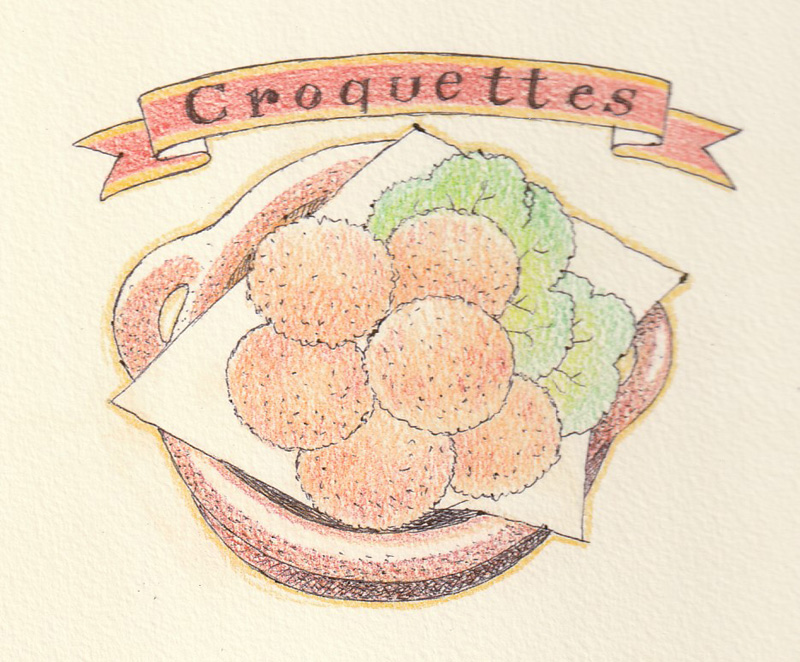
「贋作……ニセモノ、ですか」
「出入りの骨董商から勧められて買った壺が、精巧な贋作だった。パリ万博※9に出品されたマボロシの逸品なる、京七宝※10の壺。名工・
並河靖之
※11の作というのは大嘘で、作者は無名の職人だった」
「でも、きれいな壺だったんでしょう」
「俺は実物を見てないんだ」と、おひつの中をヒョイと覗いた。しゃもじを取って、好物のおこげのところだけ掬って食べた。
「贋作でも、買った本人が気に入ってりゃそれでいいんだけど。親父は審美眼に自信があったんだろう、気落ちしちゃってね。家業も傾いた。贋作が元凶だというんで、ばらばらに割り壊して厄落としをしてもらったらしいんだが……」
「駄目でしたか」
しゃもじを貰って、鍵一も自分の飯茶碗に山盛りをよそった。叔父は白身魚のポトフに箸をのばした。
「まア、やきものは、相当の目利きでも鑑定が難しいんだ。戦後の古美術業界を揺るがした『永仁の壺』事件※12なんてのはその例で。陶磁器の専門家たちが鎌倉時代の古瀬戸だと太鼓判を押して、重要文化財にまで指定されたんだが、じつは20世紀前半に創られた壺だった。そういう事が起き得る業界なんだよ」
叔父はしばらくポトフを食んでいた。伊根の寒ブリ※13を呑み込み、金時ニンジン※14をかじり、「うん!」と頷いて、
「起きた事はしょうがない」
いつもの気楽な調子で続けた。
「この貴船の家と土地、家財道具、書画骨董の類、ほとんど売り払って横浜へ引っ越す事になった。まア、一家と言っても、移住メンバーは親父だけで」と、可笑しそうに汁をすする。
「おふくろは俺たちが子供のころに亡くなってるし。俺は17歳で、絵の師匠の家に下宿させてもらってた。京都の美術学校を出たら、奨学金でイタリアに留学するつもりだった。だるまちゃんは東京で大学生をやっていて、移住騒動のときはギリシャにいた」
「ギリシャ?」
「プトレマイオス※15の研究で」と、48星座を制定した天文学者の名を恐竜の学名のように呼んだ。鍵一は見知らぬ祖父をどう呼ぶか迷って、
「お祖父さんはひとりで移住されたんですか」と鉄瓶から煎茶を注いだ。宇治の薫りがひろがる。
「うん。横浜で小さな造船業の会社を任されたら、意外に親父は商才を発揮したんだよな。小金を溜めて、それなりに家は持ち直した。貴船の土地と家を買い戻したいと親父は常々言ってたんだが、まア間に合わなかったね。早死にで」
笑って外を見遣った。雪見障子は曇って、今夜は風もない。鍵一の耳を驚かせた水琴窟も、今は雪の海に眠っている。
「結局、俺とだるまちゃんがここを買い戻せたのは、親父が死んで8年後」
「お祖父さんも天国で喜んでいますね」
「どうだろ。俺たちが貴船を買い戻したのは、親父のためじゃない。自分たちの楽しみのためだもんな」
「叔父さんと父にとって」と、鍵一は尋ねてみた。「貴船はどういう場所なんですか」
「秘密基地」
簡潔な答えがクロケットを平らげた。
「まア、家のかたちは当時とは全然違うけどね。昔のまま残ってるのは、庭の樹と水琴窟ぐらいか。贋作の破壊力はすごいもんだ」
「……骨董は難しいですね」
「まアな。ただ、正真正銘のお宝も無いわけじゃない。親父が最後まで手放さなかったコレクションがある。たとえば、おまえが飯を食ってる茶碗」
どきりとして鍵一は箸を止めた。台所の食器はどれでも自由に使えと言われて、満天の星を映したような瑠璃色の器を飯茶碗にしていた。
「曜変天目茶碗※16。南宋時代の唐物。うちにあるとは人に言うなよ」
「えッ、あの、はいッ」
「それから、おまえの相棒の」と、フェルマータが舐めている古い硝子杯を指さした。台所の流しへ無造作に置かれていたのを、鍵一が拾ってきたのである。手のひらに収まるほどの小ささで、台脚が安定していて、フェルマータの食器にちょうど良かった。
「葡萄唐草文瑠璃坏(ぶどうからくさもんるりのつき)。葡萄酒や琵琶と一緒にシルクロードを渡って来たやつ。正倉院宝物の瑠璃坏※17の、ふたごの弟ッてとこかな」
「わ、わ……!」
慌てる鍵一をよそに、フェルマータは満足そうに目をほそめた。『吾輩の食器は美相である。是れ料理の着物なり※18』と言わんばかりに、前足でギュッと坏を抱えた。
「わ、割れたらどうするんですか」
「継ぎ合わせりゃいいじゃないか。へへへ。こいつらも倉庫で埃を被ってるよりはいいだろう。ただし、俺が許可したもの以外は使うなよ。古い器にはたいてい鉛※19が付いてる」
笑って「ああ、美味かった。ごちそうさん」と箸を置いた。鍵一は自分の持っている茶碗をつくづくと見た。祖父の愛した瑠璃色は、わずかに傾けるたびCapriccioso
※20に煌めいた。
つづく


日本最大級のオーディオブック配信サイト『audiobook.jp』にて好評配信中♪
第1話のみ、無料でお聴きいただけます。
幻の名曲『夢の浮橋』のモチーフを活かし、鍵一が作曲するピアノ独奏曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。
実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいました。
♪『夢の浮橋変奏曲』制作プロジェクトのご紹介
♪神山 奈々さん(作曲家)
♪片山 柊さん(ピアニスト)
ドイツ・オーストリア料理として親しまれるじゃがいもスープ。
水琴窟の原型。1597年頃に18歳の小堀遠州が考案し、師の古田織部を驚かせました。
伊藤若冲(1716-1800)は京都の絵師。錦市場の青物問屋に生まれ、絵師として活躍しました。動物画、植物画のほか、「野菜涅槃図」など、個性的な作品を多く残しました。錦市場の営業許可をめぐり奔走するなど、青物問屋の主人らしい一面も。
音楽用語で『陽気に、楽しげに』の意。
フランス伝統の、小さな揚げ物料理。日本では明治時代より『コロッケ』という独自料理に進化しました。
並河靖之(1845-1927)は京都の七宝工芸家。その作品は明治期に海を渡り、パリ万博等で高く評価されました。
京都府与謝郡の伊根町(いねちょう)は、伊根湾に面した町。舟屋の町並みや浦嶋太郎伝説、ブリ漁などが有名です。
プトレマイオスは2世紀頃の天文学者、地理学者、音楽学者。英語名はトレミー。ピタゴラスの天球音楽説を継承し、独自の『宇宙の音階』を提唱。プトレマイオスが著した『ハルモニア論』は、17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーの天文観に大きな影響を与えました。
京都の美食家として知られる、北大路魯山人の言葉。
音楽用語で『気ままに、気まぐれに』の意。