第38話『花の眼、水の歌―アルカン氏の肖像(Ⅳ)♪』

――回想 アルカン・シャルル=ヴァランタン氏の肖像(1838年6月)
「アルカンさん、パリのサロンというのはどういう場所なのですか?」
「きみ、そんなことも知らずにサロン・デビューを目指してるの」
「なんとなくのイメージはあります。上流階級の方々が芸術家のみなさんをお招きして、芸術談義というのでしょうか、音楽や文学の話をなさったり、実際に演奏や詩が披露されたり……
ただ、ぼくは、そこで何が起きているのかをもっと知りたいのです。どんな方がその会を主催なさって、どなたが招かれて、その場でどのような会話や演奏が行われるのか……といったことを。いつかその場所へ、ぼくも伺いたいと思いますので」
さも呆れたというふうに相手は曇天を仰いで、その紫陽花色の瞳に薄墨を刷いたような色が混じった。黙ってシャルト通りを行きながら鍵一は、アルカン氏が話し出すまで待つことにした。
行く手にセーヌ川が見えるや、川風がまともに吹きつけて来る。我知らず鍵一は隣をゆく音楽家と同様に前傾姿勢になった、ふたりして競うように早足で歩いてとうとう、セーヌ川のほとりへ出た。
意外にも、川と橋の風景は明るいのだった……!
夕立の気配をまったく意に介さず、6月のセーヌ川には大小さまざまの船が浮かんでいる。右岸と左岸を結ぶいろいろの橋の上を、馬車や人が行き交っている。
アルカン氏はすべるように川沿いの遊歩道へ下りてそのまま、ノートルダム大聖堂の方角へ進み始めた。遅れじと付いてゆく鍵一に、
(ずっと前にもこうして誰かと川沿いを歩いた)
という記憶が、ベルリオーズ作曲『幻想交響曲』第3楽章のティンパニで表される遠雷のように、しずかに轟いた。
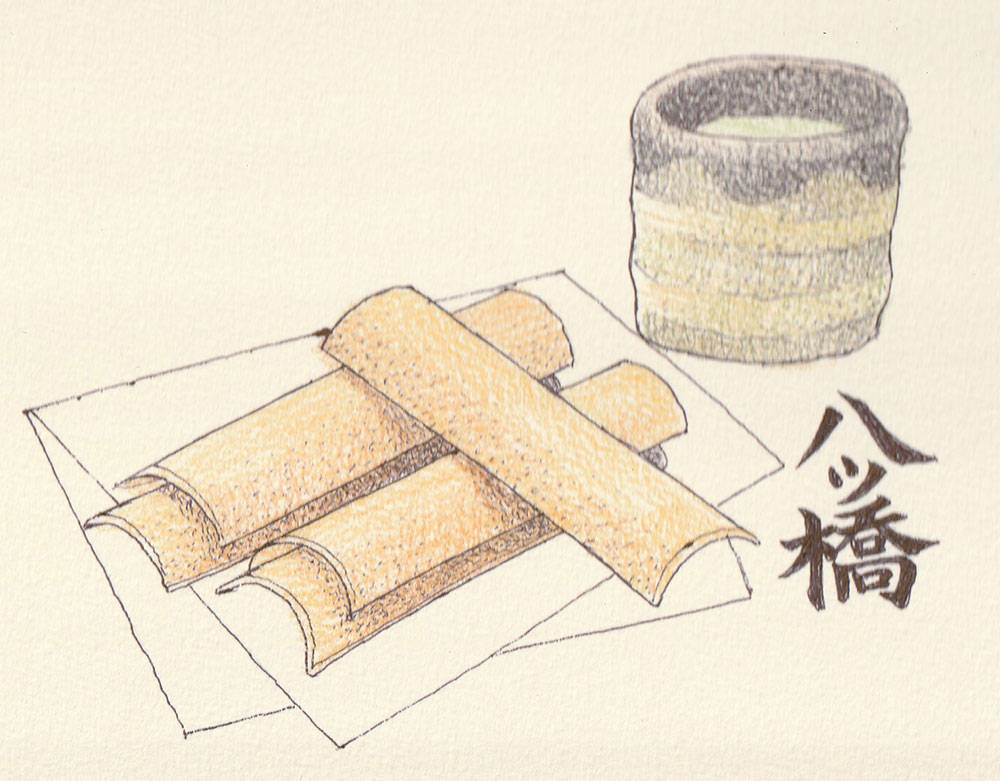
考えるまでもなく、その相手は京都の叔父であり、歩いたのは京都の鴨川だった。
すると唐突に、この深緑色の、たっぷりと水を湛えて流れゆく19世紀のセーヌ川が、京都の鴨川へ繋がっているように見えてくる。
(この川沿いをずっと歩いてゆけば、そのうち京都に辿り着けるかもしれない)
川と橋の景色を眺めゆくほどに、歩くほどに、その突拍子もない予感が濃くなる。1838年のパリのセーヌ川はあまりにも自然に京都の鴨川に合流して、吹き揺れるリラの樹はいつのまにか柳に変わっている……。川風に特有の涼しさは鍵一へ、京都の思い出を運んで来た。
(一度だけ、6月に京都で紫陽花をみた。小学校高学年のころ)
もちろん、横浜の実家の庭にも紫陽花は咲いていた。季節の花、というテーマで美術の宿題をおこなうには充分な素材ではあった。土がアルカリ性なら赤色に、酸性なら青色に花の色が変わることをふまえて、11歳の鍵一はそのギザギザの葉の葉脈やら、花びらのように見えるガクやらをつぶさに観察して、途中までスケッチしたのち、『なにか違う』と感じて鉛筆を置いた。カレンダーを確認した。リビングへ行って、寝転がっていた父へ挙手をした。
『お父さん、京都の紫陽花の絵を描きたいのですが。
6月は祝日がないので、学校を休むことができません。土日の1泊2日では時間が足りません』
国家公務員たる父の対応は迅速だった。
『だるまちゃんに相談する』
といって、その場で京都の叔父※2に電話をかけた。叔父がすぐアイディアを出してくれた。いわく、『雨の日』という祝日を国家に内緒で第2金曜日に制定し、勝手に3連休ということにして、2泊3日で京都に遊びに来れば?おれはサザビーズ※3のカタログをチェックしたり吟行したり天ぷらを食ったりするのに忙しいから、鍵一が来てもロクにお構いはできませんけど?という。
父は感心して『さすがだるまちゃんだ。京都人の発想だ。18まではおれと同じ横浜の家で育ったはずなんだけど』と、しきりに叔父をほめて、すぐ京都ゆきの新幹線の切符を鍵一に持たせた。
おかげで鍵一は2泊3日で、京都の紫陽花をじっくりと描くことができた。鍵一の思い描いたとおり、たしかに京都の紫陽花には美が宿っていた。西陣の機織りの音を聴きながら、鍵一は無心に紫陽花をスケッチした。その天人の羽衣のような色合いを写し取ろうと夢中になった。水をふくんで重たく垂れた花は円山応挙の幽霊画に似て、夕闇のせまる路地で出会うとどきりとした。日が沈むと叔父がふらりと現れた。叔父の後をついて鴨川沿いを歩いてゆくと、仄明るい天ぷら屋に着いた……
(すると今、こうして隣を歩く人は、じつは叔父さんなのじゃないか)
という思い付きに、鍵一は可笑しくなった。
振り仰ぐとまともに目が合った。叔父ではなかった。『フランス・ピアノ界のエトワール』こと、25歳のアルカン・シャルル=ヴァランタン氏は紫陽花色の目を細めて、
「今年2月のショパン君の御前演奏は記憶にあたらしい」
唐突に話し出した。この音楽家は親友の名誉のために、サロンでのエピソードを慎重に選んでいたらしかった。
「今年の2月、ショパン君はルイ=フィリップ王の招待を受けてテュイルリー宮へ出向いた。それ自体はめずらしいことじゃない、彼はパリに居をさだめてより、たびたび王族のサロンへ赴いているから。
もちろん僕も、王宮へ招待されれば応じる。けれど、僕が王族のサロンへゆくのと、ショパン君がゆくのとでは、意味が大きく異なる。彼はポーランドという国家を背負って、フランスの王宮へ、ポーランドの優美とポーランドの洗練を示しにゆくのだ。彼が王太子妃や、外交官や、やんごとなきご婦人方とともに円卓に着き、銀のスプーンでスープを掬うとき……そしてプレイエルのピアノで、彼の作曲したノクターン※4やマズルカ※5をこの上なく優雅に弾いてみせるとき、賛美されるのはポーランドであり、大理石の床に映るのは柳の影なのだ。
その御前演奏では、ルイ=フィリップ王の妹君のアデライード大公妃からモチーフを賜り、ショパン君が変奏曲を即興して、王族の賛辞を一心に受けたということだった。
アデライード大公妃が植物画をよくお描きになることも相まって※6、僕はその小春日和に、テュイルリー宮のサロンに巨大な柳の樹が根づいたという……鮮烈な印象を受けた」
「柳……?」
「ポーランドといえば柳だ、きみ。ショパン君にとってのワルシャワの風景は、ヴィスワ川と、橋と、柳なのだそうだ。あの国が真の意味でロシアから独立を勝ち取るまでは、彼がその風景を目にすることはないだろうけど」※7
反射的に鍵一は、京都の鴨川沿いの柳を思い浮かべた。薫風が葉を渡る日にパリのセーヌ川沿いをどんどんと歩いてゆけば、いずれは京都の鴨川に着き、さらにゆけばワルシャワのヴィスワ川へ着ける気がしていた。
(でも、京都の鴨川の遊歩道にも、ワルシャワのヴィスワ川の遊歩道にも柳が植わっているとすると……川沿いを歩き続けながらぼくは、ワルシャワに入ったことさえ気づかないかもしれない)
「王族のサロンと大使館のサロンは性質が異なるものだけれど、ともにパリ社交生活の華といえる」
アルカン氏の言葉に揺り戻されて、鍵一は川と橋と柳の幻影から抜け出した。ただし、歩き続ける行く手には相変わらず数多の橋が架かり、緑の薫りを濃くした樹々はますます川風に揺れていた。
遠雷。

「大使館のサロンというのは、どういった場なのでしょうか?」
「イギリス大使館やオーストリア大使館のサロンには『ヴィルトゥオーゾ』という称号に値する音楽家だけが招かれ、のびのびと泳ぐことができる。機知。才覚。礼儀。教養……あらゆる美徳が問われる」
独り言のように淡々と流れゆくアルカン氏のフランス語が、ややもすると川風に吹き攫われる。ようやく夕立を警戒し始めたらしい大型船は帆をたたみ、蒸気船は白波を湧き立てて全速力で川下へ逃げて行く。その汽笛の尾をかいくぐって、鍵一は隣をゆく音楽家の声に耳を澄ませた。
「……ルイ14世風のシャンデリアの下で、社交という名の甘美な水のやりとりが行われる。場の全員がその流れに加わらねばならない。音楽家とて例外ではない。パリ上流の景色……大公が狩りの話題のたびに取り出す葉巻の薫りや、伯爵夫人の耳元に揺れる涙型の大きな真珠や、政治と芸術をひとつの皿に盛りつけて洒落のスパイスを利かせる事にかけては天才的な手腕を持つ外交官の微笑……に気圧されてはいけない。踊ること。水の動きを読み、流れに乗り、優雅に振る舞うこと」
(優雅に振る舞うこと)
鍵一は心の中で、そのフレーズをあやふやに真似てみる。噴水。花瓶。銀のスプーン。いつか西洋史の図説で見た、『太陽王』ルイ14世の肖像画。大きなかつらと、メヌエットを踊るのに適した優美な脚。ヴェルサイユ宮殿の大広間に輝くシャンデリア。
すると、『ヴィルトゥオーゾ』という言葉がポッと燈った。
(『ヴィルトゥオーゾ』……演奏技術に優れているのみならず、徳の高い音楽家、人格の優れた音楽家。確かに、そういう人でなければ、上流階級の方々に混じって優雅に振る舞うことはできそうもない。リストさんはみずから渦を創り出して周りを巻き込みそうだし、ヒラーさんはどんな流れでも乗りこなせそう。ショパンさんやアルカンさんも……)
鍵一の朧げなイメージのなかで、19世紀パリ上流階級のサロンの社交術は、きわめて流れの速い清流であった。岸辺から眺めるぶんには、それはとてもゆるやかな流れに見える。陽の光に温められたやさしい水が、夢の国へ誘ってくれるように見える。しかし凡人が不用意に足を踏み入れれば、たちまち流れに呑まれて、あるいは助け舟にしがみついたとしても、一瞬の遅れが命取りになる。ひとたび沈んだ者のつまさきには藻が重く絡まり、二度と浮かび上がることはできない。……
こめかみに汗が湧く。思わず鍵一は音楽家の言葉を遮った、
「アルカンさんは、どのように社交界での振る舞い方を習得されたのですか」
「いつのまにか心得ていた」
と、音楽家は目をしばたたいた。その視線の先に、対岸のフォブール・サン=ジェルマン界隈の上空だけが藤色に晴れている。貴族の邸宅の居並ぶその一帯は、希少なチョコレートをふんだんに使って焼き上げられたタルトに似て、この雷雨の予感の濃い午後にも香気を放っていた。
「いつのまにか、ですか?」
「僕は幸運にもパリの『沼地(Marais)』に生まれ、セーヌ川の水で育ったおかげで、パリの社交の場で苦労したことはない。あたかも自然の法則のように、どう振る舞えばよいかが見える。カルクブレンナー氏※8のように、殊更に貴族めいた振る舞いをする必要もない。外国から来たヴィルトゥオーゾたちのように、国の威信を背負って華麗に泳いでみせる必要もない」
「パリ生まれ、パリ育ちの音楽家の方は皆そうなのでしょうか」
「さあね。そんな事をわざわざ、人と話さないよ。だいいち……」
テュイルリー公園の樹々がざわめいて、音楽家の言葉がセーヌ川へ舞い落ちる。拾い損ねた鍵一が前のめりに耳を寄せると、アルカン氏の変幻自在の瞳の色と同じく、話題はもう転調※9していた。

「そういえば、『外国人クラブ』の晩餐の戯れに、皆でパリ社交界の地図を描いてみようとしたことがあった。あのとき僕らは無性に、馬鹿げた遊びをやりたい気分だった。ヒラー君が買ってきてくれた大判のパリの地図を、テーブル一杯にひろげて……僕らは有力なサロンの主の私邸公邸へ星の印を付けていった。アントワーヌ・アポニイ伯爵、エレーヌ・ド・メクランブール=シヴラン王太子妃、ノアイユ公爵、ベルジョヨーゾ大公妃、ヴォーデモン大公妃……
まず貴族王族のサロンだけでも、地図上に天の川が描けるほど。芸術家の私的なサロンを線で結ぶと、僕らは美しい星座を描くことさえ出来た。
幸運にもそのときすでに、僕とリスト君はすべての星印の場へ招かれた事があった。ヒラー君とショパン君には未開拓の地があったので※10、僕らは先達ぶって、それぞれのサロンの特徴を面白おかしく、かなり脚色しながら教えたのだった。
たとえば、あの大衆オペラの権化たる愛すべき『贅肉さん』、ロッシーニ氏がまだイタリア座の総支配人を務めていたとき※11、ケルビーニ院長のサロンでは毎週月曜に……※12」
その涼やかなフランス語を、あらためて鍵一は音楽のように聴いていた。それは今まで聴いたどんなフランス語とも違っていた。ショパンの優美なフランス語とも違う、ジョルジュ・サンドのうるわしいフランス語とも違う、リスト独特のフランス語とも違う、ヒラーの風を纏ったフランス語とも違う。
パリの声だ、と鍵一は思う。
(無数の真珠がセーヌ川の川底を転がってゆくような……あるいは、水辺の景色の点描画が丁寧に描かれてゆくような)
その声で語られさえすれば、皮肉は水の底にゆらめく陽光になり、風刺はすばしこい魚のうろこになる。フランス音楽の巨匠たちに脈々と受け継がれた『jeu perlé(真珠のように粒立ちの良い音からなる演奏)』の伝統の源泉を、鍵一は今ここに見た気がした。……
「……パリのサロンの概況といえば、まあこういった具合」
「えッ、ええ」
……と、相手の声に気を取られて、肝心の内容をまったく聴いていなかったことに慌てる。もういちど最初からお願いできますか、とは言えずに、
「でッ、では、いま仰った中で、アルカンさんが最も重要だと見なしていらっしゃるサロンは何処ですか」
苦しまぎれに尋ねると、答えは明瞭だった。
「ヅィメルマン教授の『神殿』」
「神殿?」
「あれほど審美眼の鍛えられる場はない」
(そういえばショパンさんは今日、スクワール・ドルレアンのヅィメルマン教授の家に招かれているのだった)※13
鍵一は先ほど訪れたショセ=ダンタン地区にひときわ眩しく輝く、あの古代ギリシャ風の外観を思い起こした。純白のスクエア・ケーキのような建物の中で日夜、音楽史が遊び、千の眼を光らせ、ぎちぎちと前進しているに違いなかった。
♪ショパン作曲 :変奏曲「パガニーニの想い出」 CT229 イ長調
「ぼくもいつか伺いたいです、『神殿』へ」
思い起こす音色とともに本音が出たのを、音楽家は横目で見た。
「きみの母国語では何と形容するのだろうね。我が身をかえりみず、大それた望みを抱く者のことを」
「アルカンさん、ぼくもいつかは、『神殿』へ伺えるでしょうか?」
「可能性はあると思うよ。きみが自作の曲をエラールやプレイエルのピアノで弾きこなすことが出来、礼儀作法が完璧で、当世一流の芸術家たちや上流階級の方々と機知に富んだ会話ができるのであれば、ね」
紫陽花色の瞳に苦笑を滲ませる相手に、思い切って鍵一は尋ねてみることにした。

つづく


第1話のみ、無料でお聴きいただけます。
第19話『前略 旅するあなたへ(Ⅲ)♪』をご参照ください。
1744年にロンドンで創業された、世界最古の美術品オークションハウス。
ピアノ独奏曲のジャンルのひとつ。19世紀に活躍したピアニスト兼作曲家ジョン・フィールドが提唱し、その後、ショパンが大きく発展させました。
ポーランドの民族舞踊および舞曲。
『バラの画家』『花のラファエロ』として知られる植物学者ルドゥーテから絵画の指南を受け、植物画をよく描きました。
ポーランドの首都ワルシャワのワジェンキ公園には、『柳の樹の根元に座り、葉を渡る風の音に耳を澄ませるショパン』の像があります。毎年、ショパン像の下ではピアノのコンサートが開催されます。
19世紀パリで活躍した音楽家・カルクブレンナー氏は、貴族や王族といった上流階級とよく交流し、自身も貴族のように振る舞いました。
音楽用語で、『楽曲や楽章の中で、ある調から別の調に変化すること』の意。
リストは1823年、ヒラーは1828年、ショパンは1831年にパリに到着し、親しく交流しました。
ロッシーニ氏は1824年から約2年間にわたりイタリア座の総支配人を務め、パリの音楽界へ大きな影響を与えました。
1822年よりパリ音楽院の院長を務めたケルビーニ氏は、毎週月曜に芸術家や社交界の人々を自身のサロンに招いていました。ロッシーニ、マイアベーア、ショパン、リストなど、当世一流の音楽家たちも彼のサロンに招かれ、互いに交流しました。
イギリスの建築家エドワード・クレシーが1830年~1832年に建設した、スクエア型の集合住宅。時を同じくして、オルレアン家のルイ=フィリップが国王となった事から、王家の名を取って、『スクワール・ドルレアン』と呼ばれるようになりました。