第35話『花の眼、水の歌―アルカン氏の肖像(Ⅰ)♪』

パリ・サロンデビューをめざしてオリジナル曲を創る事となった鍵一は、作曲に集中するため、1838年の大晦日にひとり船旅へ出た。ル・アーヴル港ゆきの船内にて、オリジナル曲『夢の浮橋変奏曲』※1の構想は着々と進む。パリ滞在中に書き溜めた備忘メモを整理しながら、鍵一は19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表そうと試行錯誤する。
星の輪。あるいは惑星のかたち。
水無月になると街中に灯り、『七変化』と異名をもつ。つねに淡く浮遊している印象の。雨の匂いのする。
その花を、ついぞ鍵一は19世紀パリの街角で見かけることはなかった。
それでもパリ滞在中、折にふれてその花に思いを馳せていたのは、『フランス・ピアノ界のエトワール』こと、アルカン・シャルル=ヴァランタン氏の瞳を見る機会にたびたび恵まれたからであった。
(紫陽花色の瞳……)
今また、1838年の大晦日の夜をすすむ帆船のなかで、鍵一は花を思い起こしていた。パリ滞在中に書き溜めた備忘メモを整理しているうち、乾いたインクが青黒く変色しながら、はからずも美しいかたちに滲んでいるのを数枚見つけていた。たわむれに鉛筆をとって、そのふしぎなかたちのしみに葉と茎を描き加えてみる。
(なるほど)
と見る間に、鍵一の手のなかで花はうまれた。
(いや、肝心のメモの内容が……)
溜息で燭台の火が揺らめく。頬杖をつく鍵一の傍で、猫のフェルマータは五線紙に寝そべって、スヤスヤと船を漕いでいる。その額を鍵一がチョコチョコと撫ぜると、金色の眼がぱっとひらいた。ヒョイと起き上がってそのまま伸びをするや、ふわりと宙を跳んで絨毯に着地した。扉をかりかりと掻き出すのを、
「甲板には出ちゃダメだよ」
鍵一が開けてやると、猫はスルリと出て行った。廊下の向こうからレヴェイヨン※2の華やぎが、笑い声とアコーディオンの音色の入り混じって響いて来る。
鍵をかけずに書斎の扉を閉めて、鍵一はあらためて備忘メモを取り上げた。
(いつ、なにを書き留めようとして、このメモを書いたんだっけ。『アルカンさん』と左上に大きく書きつけたのだから、アルカンさんに関するメモには違いないけれど。インクが滲みすぎて『E』と『C』の区別もつかないし……日付くらい書いておけばよかったな)
さて、暖炉の火に透かし見て、燭台の火にかざし見て、縦から読んだり横から読んだりして、鍵一は自分が半年前に書いた文字をようやく解読した。
・スクワール・ドルレアン
・パガニーニを『翻訳』
・音楽史という巨大生物
・19世紀パリ社交界の泳ぎ方
・ヅィメルマン教授の『神殿』
・ポーランドと柳
・ギド・マン(ハンドガイド)
・てまりずし
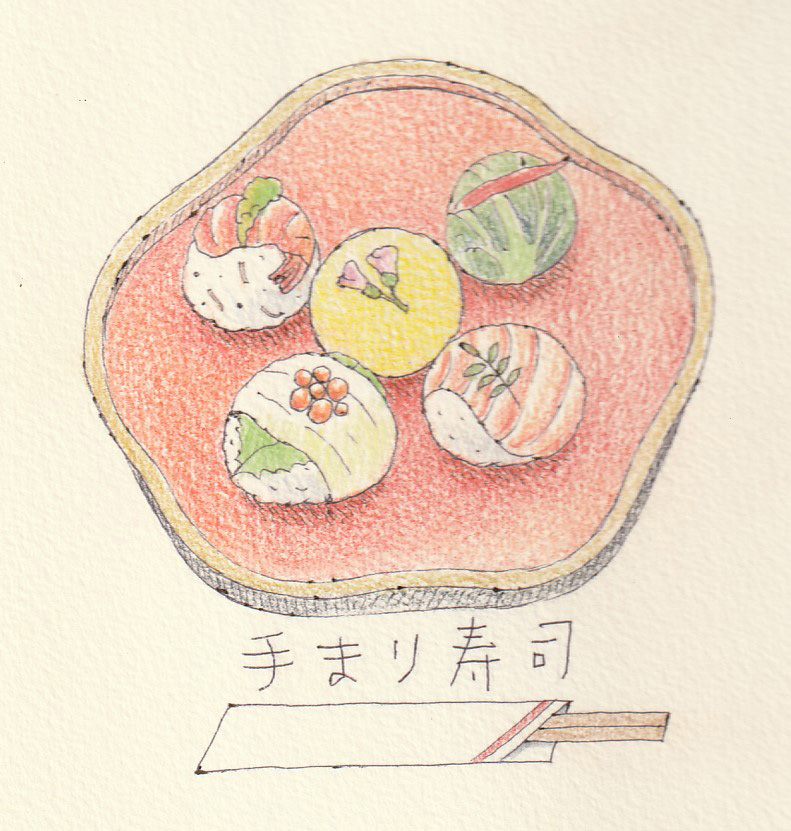
汗のしみこんでブヨブヨになった紙の上へそっと両手をすべらせながら、鍵一は半年前の自分の、蒸れるような焦りを思い出した。
(そうだ、これも1838年6月の出来事だ……!
ヒラーさんが故郷ドイツからホワイトアスパラガスの鉢植えを持ってパリへ戻っていらして、『プレイエルのピアノで遊んでごらん』と、アドバイスをくださって……その翌日のメモだな。ヒラーさんから頼まれたお届け物を、アルカンさんのところへ)※3
と、思い当たることがあった。
(ヒラーさんはわざと、ぼくに用事を頼んでくださったのか。ぼくがたくさんの人に会えるように、と……)
思い返せばあのとき、ヒラー氏は整理が済んだトランクをわざわざ開けて、いろいろな品々を取り出してはテーブルにならべた。アルカン氏宛の包み。エラール事務所宛の手紙。パリ音楽院のヅィメルマン教授宛の楽譜。さらに、友人ショパン宛の気楽な伝言。
さて、ナポレオン金貨(それが20フランという、ショパンのピアノレッスン1回分に相当するほどの値打ちの貨幣であることを、鍵一は後になってから知った)を『手間賃』として置いて風のように去って行った、音楽家の大きな背中がなつかしい。
実際のところ、ヒラー氏の心遣いを、当時の鍵一はすべて活かせたわけではなかった。
パリ音楽院ではヅィメルマン教授への面会すら叶わず、仏頂面の門番へ楽譜を預けたのみであった。ピアノメーカー・エラール氏の事務所を訪ねると、ロンドン出張中のエラール氏に代わって小僧が出てきた。頬のてかてかと赤い、豆ダヌキのようなその少年は鍵一のいでたちをしげしげと眺めて、
「今日中に行ってよね」
と、手紙と引き換えにアルカン氏への届け物を押し付けた。お使いの駄賃の銅貨(1スー。1日分のパン、あるいは芽の出たジャガイモ1袋がぎりぎり買える程度)をもらいながら、鍵一はまるで自分が、エサをもとめて19世紀パリの街をさまよう野良猫になったような心地がした。
(あの日、唯一お会いできたのがアルカンさんだった……!1838年6月の涼しい午後)
ろうそくの火影が紙の上へ長く伸びてきて、記憶の結び目をほどいた。とろりと溶け流れたアルカン氏の肖像が、中空に流水紋を描き出してゆく。
――回想 アルカン・シャルル=ヴァランタン氏の肖像(1838年6月)
『モーゼのピアニスト アルカン』
と書かれた扉の前に、鍵一は佇んでいた。
『フランス・ピアノ界のエトワール』と名高いこの音楽家が厳格なユダヤ教徒であることを、もちろん鍵一は『外国人クラブ』のシェフから聞いて知っていた。
ワープ初日、レストランで夕餉を囲みながら、音楽家が「いつか、ヘブライ語の聖書をすべて音楽に『翻訳』してみたい」と話していたのも聞いていた。
先月、まだ19世紀パリを歩き慣れぬ鍵一がマレ地区のユダヤ人街に迷い込んだとき、その地名の由来どおり『沼地(Marais)』らしい黄檗色の、古風な煉瓦造りの建物の立ち並ぶ路地をさまよい歩き、やがて噴水の音……大理石で出来たドラゴンの口から温かい水のほとばしる音……を聞きつけてそちらへ足早に、よろけて、聴いて、駆けて、ここだと思って角を曲がると巨大なシナゴーグ※4が立ち現れて言葉をうしなった……その近辺に音楽家の生家があるということも、記憶に新しかった。
……ところがいざ、音楽家の住まうアパルトマンの扉の前へ来て、いかなる来訪者をも拒むようなこの表書きに接したとき、どのように扉をノックすべきか、わからなくなってしまったのである。
(海も割れんばかりに叩くべき……?)
振り返ると中庭の噴水がまぶしい。四角い建物が中庭を取り囲む、このロンドン式の集合住宅は『スクワール・ドルレアン』※5というのだと、シェフに教えられた。
描いてもらった地図を見るまでもなく、パリで最も『ファッショナブル』とされるショセ=ダンタン地区にひとたび足を踏み入れれば、その古代ギリシャ様式の、純白のスクエア・ケーキのような外観と青空とのコントラストは目を惹いた。階段を3階まで上るあいだには、マドレーヌ大通りからイタリア座大通りにかけて賑々しい行列が眺められた。6月の晴天に際して、ルイ=フィリップ王御一行がゆるりと移動中なのだった。
……じつに、鍵一はつい1時間ほど前、王様の行列にバッタリと出くわしていた。慌てて建物の影に逃げ込んで、しかしヒラー氏の話してくれた『良い子は絶対真似しちゃいけないフランツ・リストの名言※6』を思い出して、見物をこころみたのであった。
なるほどヒラー氏の言うとおり、『フランス国民の王』は宝石をちりばめたサーベルを提げ、ぴかぴかに磨き上げられた靴を鳴らして、往来をウロウロなさっていた。王様が鷹揚に片手を上げて、道ゆく労働者へ「やあ、友だち」、憲兵へ「やあ、同僚」と声をかけるたびに、軍服の左胸に付けた勲章が初夏の陽光に反射して稲妻のように光った。
護衛兵のなかには鼓笛隊がいて、王様がなにか言うと、3回に1回くらいの割合で太鼓をたたき、ラッパを吹いた。見れば見るほど、鍵一にはその法則性がよくわからなかった。
さらに見物していると、妙な現象に気づいた。王様が来ると、大通りから人々がサーッと消えるのだった。カフェのギャルソンは急用を思い出したそぶりで店の奥に引っ込み、テラスの客たちは何食わぬ顔をして席を立ってゆく……しかし王様が通りすぎると、みんな戻ってきて、グラス磨きやおしゃべりや食事を再開するのだった。急ぎで大通りを行かねばならない人々だけが、王様に深々と頭をさげ、申し合わせたように『はい閣下!』『恐れ入ります閣下!』と紋切り型のあいさつを述べて、王様がよそを向くと、小走りにその場を離れて行った。
(この王様は幸せなのかしら)
疑問が浮かんで、しかし左胸に勲章をつけたこともない鍵一に、ルイ=フィリップ王の心の内がわかるはずもなかった。見物に飽きた鍵一がカフェ・トルトーニ※7のテラスの喧騒をやりすごして路地を進み、このスクワール・ドルレアンの入口正面の美しいファサードを仰ぎ見る時も、鼓笛隊の楽の音はかすかに届いて来ていた。
……陽が翳ってきた。
窓から吹き込む風が、廊下をすべって鍵一の袴の裾を涼しく吹き抜けてゆく。あちこちからピアノの音の聴こえるのが、いかにも文化人の方々の住処らしかった。
(人の用事を預かって来たのだから)
と、鍵一は扉のノックのしかたを考え始めた。
(ベートーヴェンの交響曲第5番『運命』の、冒頭のモチーフらしく叩いてみようかしら?
あるいはフランスの音楽家の曲を、リズミカルにノックで表現……アルカンさんがパリ出身の音楽家だから……サン=サーンス、が活躍するのはもうすこし後の時代だな。フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル、サティ……ぼくが知ってるのは皆、19世紀後半以降に活躍した人か。
よし、ここは安全策として、ベルリオーズさん作曲『幻想交響曲』の第5楽章『ワルプルギスの夜の夢』より、グレゴリオ聖歌『怒りの日』のテーマを!)
勢いよくコブシを振り上げた鍵一の目の前で、ふいに内側から扉が開いた。紫陽花色の瞳が見ひらかれた。
「すん」
と鍵一は飛び退いて、すぐ真っ赤になった。
「すッ、すみません、いまお声掛けしようと思っていたんです」
「……なにか用?」
「お届け物が」
「どうも」
ヒラー氏からの包みと、エラール事務所からの封筒の中身をアルカン氏が玄関口で検めるあいだ、鍵一は薄暗い部屋の奥に、音楽家の書斎らしき神聖な小部屋を見た。天井まで届く巨大な本棚に、分厚い蔵書がみっしりと詰まっている。
「まだ何か?」
冷ややかに問われて鍵一は我に返った。
「すごい蔵書ですね。聖典……ですか?」
音楽家の瞳に薄青い侮蔑の影がさす。「すみません」と小声に汗が噴き出す。相手は黙って後ろ手に扉をしめると、戸締りをして「出掛けるので」と、鍵一の傍をすりぬける。
「お供します」
「別にいいよ。大きな荷物もないし」
足早に階段を下りてゆこうとする背中へ思い切って、
「お供させてください」
鍵一が言いなおすと、音楽家は振り向いた。紫陽花色の瞳は曇天を映して、しずかに透き通っている。
「いいよ、別に」
あっさりと許可して、音楽家は階段を下りてゆく。小走りに鍵一も続いた。

(さて、この人にインタビューしたいけれど、うるさく尋ねて嫌われてもいけない)
アルカン氏に付き従ってスクワール・ドルレアンの中庭を横切りながら、鍵一は考えていた。
(宗教の話題にふれるのはやめておこう……いつもレストランで読んでいらっしゃる音楽雑誌の内容について、まず聞いてみようかしら)
すべるように音楽家は歩いていた。やや前傾姿勢で、さして急いでいる様子もないのに歩の進みは速く、鍵一はつねに小走りでついてゆかねばならなかった。
「あの」と言い掛けてふと、鍵一の耳が光を捉えた。
♪ショパン作曲 :アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ Op.22 CT149 変ホ長
あちこちの部屋からピアノの音が折り重なって中庭へ降り注ぐ中に、ショパンの曲がひときわ
galante
※8に聴こえていた。
「上手ですね……!」
思わず声を上げた鍵一を音楽家は振り向いて、立ち止まった。
「何」
「ここではいろんな方がピアノを弾いているんですね、ショパンさんの曲も、あんなに上手に」
「あれは本人だと思うよ」
「えッ」
「今日はヅィメルマン教授の家に招かれているはずだから」
「ヅィメルマン教授……どうりで午前中、音楽院ではお会いできませんでした」
音楽家はちらりとその棟を見上げて、またすぐ歩き出した。涼やかな音色に後ろ髪を引かれながら、鍵一も後へ続いた、
「ショパンさんが、この近くにお住まいなんですか」
「うん。きみが訪ねて行っても、居留守を使われると思うけど」
「居留守……」
「ふいに訪ねてショパン君が歓迎してくれるのは、音楽仲間でも僕とヒラー君くらいじゃなかろうか」
「リストさんは……?」
「どうだろう。彼ちょっと騒々しいところがあるから」
「ショパンさんとアルカンさんは、仲が良いのですね」
「さて、友情の定義とはなんだろうね」
そこで会話は途切れた。回廊を行きながら、鍵一は粘った。
「ショパンさんにお会いするには、どうしたらいいのでしょうか。まず手紙を書いて、訪問日時をご相談すべきでしょうか?」
「書く分にはきみの勝手だよ。まず返事は来ないと思うけど」
この人と話している感じはだれかに似ている、と鍵一は思う。記憶を探ってみると、あのワープ初日の出来事に思い当たった。
(ああ、ショパンさんに少し似ているんだ!この……本音のつかめない、ひんやりとした感触。ショパンさんとアルカンさんとリストさん、それにヒラーさんが仲良しというのは、ちょっと意外な感じもするけれど)
「ヒラーさんが」
伝言を思い出して鍵一が言い掛けると、音楽家は友の名を聞き付けて、ちらりと鍵一を見た。
(ヒラーさんかショパンさんの名前を出せば、この人はいろいろ話してくれそうだな)
「何」
「ヒラーさんからショパンさんへのご伝言で、『たまには外国人クラブへ顔を出したらどうか』とのことでした」
「……僕から伝えておこう」
回廊を抜けて小さな中庭を通り過ぎると、音楽家は別の建物のエントランスを通って、スクワール・ドルレアンの敷地を出た。
鍵一は黙って付いてゆきながら、アルカン氏から何事かのコメントを引き出せそうな芸術家をもうひとり思い付いた。
「もしかしてジョルジュ・サンドさんも、この付近にお住まいでしょうか?」
「うん。でも彼女は滅多に、人を家に上げないから」
「皆さんなかなかお会い出来ませんね……」
「きみがもし、美しい庭を所有していたとして」
「はい」
「きみが丹精した薔薇や、きみが夏の夜に涼むべき月見亭や、アレトゥーサの泉のごとく清からん※9と心を砕いて造った噴水がその庭にあるとして」
「はい」
「闖入者を拒むのは当たり前じゃなかろうか」
「……はい」
大邸宅の立ち並ぶショセ=ダンタン地区を行きながら、涼しく湿った風が首筋をかすめる。
(サンドさんにハンカチを返せるのは、当分先になりそうだな)
鍵一はレストラン『外国人クラブ』の2階の自室に仕舞ってあるハンカチをぼんやりと思い浮かべて、アルカン氏の発した名前をあやうく聞き逃しそうになった。
「オロール・デュドゥヴァン男爵夫人」
淡々と音楽家は言った、
「ジョルジュ・サンドの本名」
「では、もしお会いする機会があれば、『オロールさん』とお呼びしたほうがよろしいでしょうか」
「きみが彼女と親しい間柄であるならね」
男爵夫人という肩書のある人が、いかにしてフレデリック・ショパンと恋仲になり得たのか、鍵一にはよくわからなかった。ただ、『オロール(Aurore)』がフランス語で『夜明け』という意味であることが、うすむらさき色のハンカチの匂やかな印象とともに、記憶に刻まれた。

つづく


19世紀の音楽家・チェルニー氏から贈られたモチーフを活かし、鍵一が作曲するオリジナル曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。
実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいます。オーディオドラマやコンサート等でお聴きいただけるよう、現在準備中です。
神山 奈々さん(作曲家)
片山 柊さん(ピアニスト)
フランスの慣習となっている、大晦日の晩餐会。フランスの人々は日が暮れるとすぐ友人同士で集まり、夜更けまで豪華な食事を楽しみます。クリスマスをレヴェイヨン・ド・ノエル(Réveillon de Noël)、大晦日をレヴェイヨン・ド・サンシルヴェストル(Réveillon de Saint Sylvestre)と呼び分けることもあるようです。
第32話~第34話をご参照ください。
ユダヤ教の会堂。
イギリスの建築家エドワード・クレシーが1830年~1832年に建設した、スクエア型の集合住宅。時を同じくして、オルレアン家のルイ=フィリップが国王となった事から、王家の名を取って、『スクワール・ドルレアン』と呼ばれるようになりました。
フランツ・リストがルイ=フィリップ王に対し、『あなたが王位に就いてからも、この国が良くなったわけではありませんね』と言い放ったエピソード。
第32話『鹿と福耳―ヒラー氏の肖像(Ⅰ)♪』をご参照ください。
文化人の集う人気レストラン。イタリア座大通りに面し、アイスクリームが美味しい事で有名でした。19世紀フランスを代表する文豪・バルザックの小説にもよく登場します。
音楽用語で『優雅に・優美に』の意。
妖精アレトゥーサが泉に姿を変えた、というギリシャ神話に拠ります。