第32話『鹿と福耳―ヒラー氏の肖像(Ⅰ)♪』

パリ・サロンデビューをめざしてオリジナル曲を創る事となった鍵一は、作曲に集中するため、1838年の大晦日にひとり船旅へ出た。
ル・アーヴル港ゆきの船内※1にて、オリジナル曲『夢の浮橋変奏曲』の構想は着々と進む。パリ滞在中に書き溜めた備忘メモを整理しながら、鍵一は19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表そうと試行錯誤する。
――回想 フェルディナント・ヒラー氏の肖像(1838年6月)
リラの花の清々しい薫りが青空に吹き流れ、ノートルダム大聖堂の鐘の音に初夏が照り映えて、1838年のパリは6月の暦を迎えていた。
その1ヵ月余の鍵一の進歩といえば、フランス語の上達したこと(じつに、火急の必要に迫られて、乾いた土に水のしみこむようにフランス語は上達した。一時的にでも日本語を自分から引き離そうとして、鍵一は師の持たせてくれた『未完の音楽史』さえ、ほとんど読むことはなかった)、レストラン『外国人クラブ』のシェフと打ち解けたこと(陽気で人の好いシェフは、パリをあちこち案内してくれた。鍵一は、シェフがかつて大貴族の屋敷で料理長をつとめていたことを知った。『俺の雇い主? あの大革命の時、亡命に失敗してギロチンに掛けられたよ』と、さして残念でもなさそうに元料理長は話した)、レストラン『外国人クラブ』の店内に飾られた肖像画がドラクロワの手によるものと知ったこと(するといつか、ドラクロワに会う機会があるのかもしれなかった)、馬車を見慣れてきたこと(じつにさまざまな馬車が19世紀パリの街を走っていた! 昼間は2人乗りの二輪馬車に、細身のフロックコートをエレガントに着こなした紳士とその従者、あるいはリボンのついた華やかな帽子のご婦人と、その親しい間柄の紳士……という組み合わせが多かった。黄昏時になると、劇場付近では美しい箱型四輪馬車がみられた。昼夜問わず、大通りの四つ角にはたいてい、客待ちのタクシーよろしく辻馬車が連なっており、これは庶民も利用するものらしかった)、居候先のレストランと公共洗濯場を行き来する道すじを覚えたこと(鍵一はみずから、毎日の洗濯をかって出た。シェフに貸してもらったシャツを着て、女中や学生に混じってシャボンまみれになりながら洗濯物を洗っていると、自分がほんとうに19世紀パリの人間になった気がした)、そして少々の雨でもすぐぬかるみ、悪臭のたちこめる19世紀パリの道を、以前よりはブーツを汚さずに歩けるようになったこと(上下水道の整備されていない事がいかに都市生活を阻むかということを、鍵一は身をもって知った)……等々、当面の生活に必要な事柄ではあった。
(いや、肝心のピアノが)
と、鍵一はピアノ椅子に座ったまま、その日何度目かの深い溜息をついた。目の前のプレイエルのピアノは、あいかわらず可憐に佇んでいる。
(リストさんやヒラーさんが弾いてらしたときは、このピアノが綺麗に鳴っていたのにな。速いパッセージの音の粒がそろっていて、和音もちゃんと響いてた)
ひざこぞうで手のひらの汗をぬぐう。手首のちからをぬいて、できるかぎりふんわりと鍵盤へ指をおろす。オクターブのロングトーンは弾き手の意思に反して、ふっと途中で風にさらわれたように立ち消えた。
(やっぱりだめだ、ぼくが21世紀のモダン・ピアノで練習してきた奏法では、このプレイエルのピアノがまったく上手く弾けない……! ワープ初日の晩の余興はなんとか乗り切ったけれど、真剣勝負の場で通用するとは思えない)
フランツ・リストから『課題』として与えられたエチュードの楽譜集をぱらぱらとめくりながら、しかし指番号の書き込みをすることも、ペダリングのプランを確認することも、今は徒労のように思われた。
(パリ到着2日目、リストさんがエチュードのレッスンをつけてくださる……と思いきや、さる伯爵夫人のお使いの方がいらして。※2
『しもた、忘れとった! すまんなケンイチ君、また今度』
と言うなりあのスーパー・スターは、大急ぎで出掛けてしまわれたのだった! 以来いちどもお会いできていない。ヒラーさんも……故郷のフランクフルトへ戻られたとシェフから聞いたけれど、次はいつパリにいらっしゃるんだろう?
アルカンさんは時々おひとりでレストランにいらっしゃるけれど、話しかけづらいんだよなア……たいてい音楽雑誌を持ち込んで、食事の合間に読んでいらっしゃるから。で、食事が済むとサッサと帰ってしまわれる。それに)
と、神秘的な空気を纏ったヴィルトゥオーゾのそっけない対応を思い出すたびに、鍵一は身体が透きとおりそうなほど心細くなる。
(アルカンさんのテーブルへお皿を運びがてら、
『じつはプレイエルのピアノが上手く弾けなくて、ですね……エチュードの練習がなかなか……』
なんて、ぼくがしどろもどろに切り出した時。あの方は誌面からちらりと顔を上げて、
『まあ、そうだろうね』
と一言。そのまま、食事に入ってしまわれた。ああ、ぼくの切り出し方やタイミングがまずかったなア……レッスンをお願いできるような雰囲気じゃなかった。
この時代のピアノについて、B先生からお借りした『未完の音楽史』になにかヒントがあるかと思って読んでみたけれど、これといって役に立ちそうな情報はなくて……そもそも、19世紀パリの項は、サン=サーンスの名前が登場するまでは、オペラのことしか書かれていなかったし。
『福袋』の中身に至っては、リピートもダ・カーポも、シャープもフラットも、音楽記号のかたちをした木工細工にしか見えない……とてもじゃないけど、ピンチを助けてくれるようには思えないんだよなア。あれはほんとうに『福袋』なのかしら?)
「ケンイチ、留守番たのむ」
張りのある声に肩を叩かれて、鍵一はピアノ椅子から跳ねた。勝手口から麻袋を担いだシェフが、
「水売りが来たら、桶に2杯分な」※3
テーブルに銅貨を置いて行く、
「ぼく、汲んできましょうか」
「いや、裏の井戸水は皿洗い用にする。最近じゃサンタントワーヌのほうが水質がいいから、あらかじめ俺が知り合いに注文しておいたんだわ」
「ということは、今夜は白身魚のポトフですね?」
笑って「仕入れ次第」手を振ってみせて、「それにおまえ、音楽家の連中が来るかもしれないだろ。インタビューの機会を逃すなよ」シェフは表へ出て行った。
ノートルダム大聖堂の鐘の音がゆっくりと午後を報せている。
開け放した窓から、小鳥のさえずりがきらきらと飛んで来る。迷路のように入り組んだこの地区の共同井戸から、誰かが水を汲み上げている。涼しい音をたてて滑車が回る。水を張って重たくなった桶が木陰に並べられてゆく。
ふと明るい水音とともに、井戸の傍の桐(シェフの話によれば、ドイツ人の医師シーボルトが数年前に日本から持ち帰ってきた苗が、たちまちヨーロッパじゅうに根付いたらしかった)の梢から飛び立つ小鳥の羽ばたきを、鍵一の耳は聴くともなく聴き届けた。
(そうだ、ワープの最大の収穫は、この耳じゃないか)
と、鍵一はつとめて自分を励ました。たしかに、鍵一の耳は以前よりやわらかく、かつ鋭くなっていた。車の走行音も、コンビニエンスストアの扉の開閉音も、横断歩道のアナウンス音もない19世紀パリでは、耳はごく自然に、かすかな響きへ吸い寄せられるようになっていた。
……と、窓辺に大きな人影が見えた。すぐ扉がひらいて、向日葵のような笑顔が覗いた。
「おお、ケンイチ君。元気?」
「ヒラーさん……! ご無沙汰しております」
額をぬぐいながら「やア、パリは大変な陽気だね。すぐそこの井戸で水をもらって助かった」、フェルディナント・ヒラー氏が巨きなトランクをドサリと下ろすと、初夏の香しい土の匂いがひろがった。
「どう、ケンイチ君。パリを楽しんでる?」
「はいッ、シェフにお世話になっておりまして、生活にはだいぶ慣れました。まだまだ、サロン・デビューには程遠い状況ですけれども」
「フランス語の発音が上達したねえ、元気そうで何より」
旅支度を解くのを手伝いながら、鍵一はみるみるうちに心の晴れるのを感じて、
(ああ、ぼくはこの人にもずっと会いたかったのだ)
と思う。音楽家は店内を見まわして、
「シェフは居る?」
「さきほど買い出しに」
「オヤッ。入れ違いになっちゃったねえ」
「夕方には戻られると思います、行き先はいつもの市場ですから」
「ほい、おみやげ。シェフに頼まれてた」
と、トランクの中から妙な縦長の包みを出した。「なんでしょう」と鍵一は包みをひらいて、心臓が跳ねた。植木鉢に山盛りの土。そのてっぺんから、白い細長いものが5本ヒョロンと生えている。
「……指?」
「ホワイトアスパラガス!」
陽気に笑って、ヒラー氏はその春野菜を「おお、生えたなア」と愛おしそうに眺めて、旅のあいだに生長したらしかった。
「おれの地元、フランクフルトの春の風物詩。パリに7年住んでいた間も、毎年春には必ず、これが目当てで故郷に帰ってた。切っちゃうと日持ちしないから、鉢植えごと持ってきたよ。その日よけをまたかぶせておこう。白さを保つには、陽に当てないのが肝心だからねえ」
「はいッ。そういえば、B先生……ぼくの日本の師匠も、この時期のカートッフェルズッペにはよく白いアスパラガスを入れていらっしゃいました。鉢植えだと、こういう生え方なのですね」
「なかなかブキミだよねえ。でも味は天下一品! おれのおすすめは、こいつをさっと湯通しして、7種のハーブを調合した緑のソースをかける。緑のソースは、ドイツ語で『グリューネゾーセ』といってね、かの文豪ゲーテ先生の好物でもあった。この時期の前菜にぴったりだよ」※4
「さわやかで美味しそうですね。ええと、フランクフルト名物・7種のハーブのソース……と」
鍵一が懐から紙束を出してすばやく書き留めるのを、
「へえ、レシピを書き溜めてるんだ」
「シェフがオリジナル・レシピの料理本を出版なさるという夢をお持ちだそうで。ぼくが少しお手伝いを」
「完成が楽しみだねえ。ちょっと見せて」
ヒラー氏はレシピの束をめくって、「フム、フム。おお、だいぶ書いたね。おれたち常連客の発案したメニューもばっちり。これはいいぞ、カレーム大先生の遺作『19世紀のフランス料理術』※5の続編、にもなり得そうだね」嬉しそうにうなづくと、ピアノの譜面台から鉛筆を取って、『フランクフルト名物・7種のハーブ』の項へ書き添えた。
『パセリ アサツキ ミツバグサ
チャービル クレソン ソレル ルリチシャ』
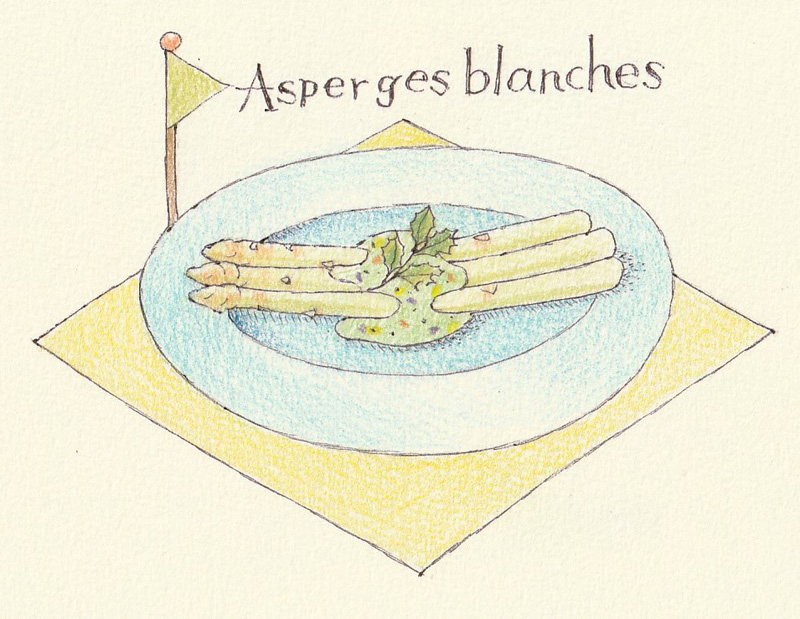
トランクの中身の整理が済むと、ヒラー氏はやにわに椅子を4つならべて、その上にゴロリとあおむけに寝そべった。「ほーう」と息を吹いて、大きな熊のようなあくび。
「だいじょうぶですか」
「もちろん! 久々にこの店の天井を見たくなっただけだよ。……ケンイチ君、珈琲を一杯もらえるかな」
「不味かったらすみません」
「ハハハ、濃ければ何だっていいよ。これからまた出掛ける用事があってね」
厨房の棚からサイフォンの道具※6を取り出しながら、鍵一はいつ、プレイエル・ピアノの奏法について話を切り出すべきか迷っていた。マッチを擦ると、アルコールランプの芯にそっと火を移す。
「長旅お疲れさまでした」
「最近話題の鉄道とやら※7を、パリ-フランクフルト間でも早く拝みたいねえ」
「馬車ではどれくらい掛かるのですか、フランクフルトまで」
「早駆けで片道7日間。いつもはもう少し掛かるかな。今回は先を急いでいて素通りしちゃったけど、たいていはバーデン=バーデンという温泉街に寄り道して、古代ローマゆかりの大浴場とワインを楽しむんだ」
「温泉!」
珈琲の粉の計量にモタついている間に、フラスコの底からぶくぶくと泡が湧いてきた。
「日本にもあるかい、温泉」
「そこらじゅうからお湯が噴き出してますよ、火山大国ですから」
と、湯が噴きこぼれそうになるのを慌てて、アルコールランプの火を吹き消した。
音楽家はあおむけに椅子に寝そべったまま、
「おお、時空を飛べる道具があれば、今すぐ日本の温泉に行きたいよ」
笑って頭の後ろで手を組んだ。

「でも、いいもんだよ。春から初夏にかけての旅はさ。街道いっぱいに木蓮や林檎の花が咲いて、まいにち天気が良くて、日毎に緑が輝いて……馬車の中で作曲が捗る」
「酔いませんか。馬車の中で細かい音符を書いたりして」
「ハハハ、おれはもう慣れたよ。書いておかないと忘れちゃうしさ、移動中にササッと曲を書く癖がついてる」
「日頃から作曲のアイディアを練っておられるのですか?」
「というより、俺は読んだ本も観たオペラも会った人の名前も、書き留めておかないとすぐ忘れちゃうんだよ。でも日記なんて書くのはまだるっこしいから、ぜんぶ曲にしちゃうわけ」
「すごいですね……!」
うなづきながら鍵一の手元で、やたらに泡立ってはいるものの、妙に焦げくさい珈琲が仕上がった。淹れなおそうか、どうしようかと鍵一の逡巡するうち、ドイツの音楽家は「おお、ありがとう。ヨッコイショ」と起き上がって、自ら食器棚をひらいて珈琲カップをふたつ取り出すと、
「それに、フランス領なら道が整備されてるから、馬車の中で音符を書くのもたいして苦にならない。その点では、交通網を整備してくれたナポレオン殿に感謝だなア」
等分に珈琲を注いで、ひとつを鍵一へ手渡した。テーブルに着いておそる、おそる、自分の淹れたその飲み物をすすってみて、意外に味は悪くない。ホッとするともう少し、この1838年の時代背景を探ってみたくなった。
「皇帝ナポレオン一世は……どこかでまだ生きているのでしょうか」
「どうだろうねえ。まだフランスに棺が戻ってきていないようだから。南大西洋の孤島からひそかに脱出して、イギリスかアメリカあたりへ亡命しているかもしれないねえ。願わくば、安らかに眠っていてほしい」
「ヒラーさんにとっても、やはり『英雄』には程遠い御方ですか」
「ハハハ、誰が皇帝に成ろうが、おれは献呈すべき楽譜を破いたりしないけど。※8まア、音楽活動の時期が重なっていなくて良かったとは思うよ。
国が戦争をやっていると、我々のスポンサーたる王侯貴族やブルジョワ殿の財政が、どうしたって軍事に傾くからねえ……芸術方面への援助が減るのはシンプルに困る。年齢によっては、徴兵されるかもしれないしね。ナポレオン殿が対仏同盟軍に囲まれてライプツィヒから敗走したとき、おれはまだヨチヨチ歩きのポッチャリした坊やだった。
ついでに、革命も御免こうむりたいねえ。初代エラール氏のように、王族の巻き添えで亡命というのもなかなかしんどい」
「えッ、エラールさんが……?」
と、ワープ2日目にリストから紹介されたピエール・エラール氏の鋭い眼光を思い浮かべて、しかし違う人物なのだと思いなおした。
「セバスチャン・エラール氏は」
と、ヒラー氏は美味そうに珈琲をすする。
「かのマリー・アントワネット妃へピアノを献呈したために、あやうく処刑者名簿に名前が載るところだった……という、嘘のような本当の話」
「王族や貴族でなくても、ですか……!」
「18世紀末のロベスピエール氏の恐怖政治では、誰が処刑されてもおかしくなかったというから。まったく剣呑な時代だったよねえ。
そういった背景を鑑みると、セバスチャン・エラール氏の功績はますます輝かしいものだね。亡命先のロンドンでもピアノの改良に取り組んでいたんだよ。あの技術革新の国から、ちゃんと得るべきものを得ていた。そうして出来上がったのが、イギリス式のアクションを取り入れた、画期的なグランド・ピアノ……!
誇張でもなんでもなく、おれはその出来事が、今後数百年……数千年にもわたって語り継がれるべき、音楽史における重要な転換点の一つだったと思うんだ。初代エラール氏が最新式のピアノを携えてパリへ戻って来たとき、当時の音楽家たちはきっと歓声を上げて、拍手喝采で彼を迎えたのだろうと思うよ。そのむかし、若きナポレオン殿がパリへ凱旋した時のように」
一言一句を心の手帳に書き留めながら、
(この人のフランス語の発音は、いつも風を纏っているような)
と鍵一は考えた。それがドイツ語圏の訛りなのか、ヒラー氏独特のものなのかは判別できずに、しかしこのドイツ出身の音楽家の穏やかな声は、心地良く鍵一の心に吹き寄せた。
「それにしてもケンイチ君」
と呼ばれて顔を上げると、音楽家は瞳を輝かせて、鍵一の顔を見まもっていた。
「きみはおもしろいことを言うねえ、皇帝ナポレオン『一世』だなんて。帝政の復活を期待してる?」
「いッ、いいえ、特に深い意味は」
ひざこぞうを掻いて鍵一は、1848年からヨーロッパ中で巻き起こる『諸国民の春』をきっかけにこの国の統治者となり、19世紀後半にパリの大改造をおこなう皇帝ナポレオン三世の存在を、ひとまず忘れることにした。
「ルイ=フィリップ王ですよね、今のフランスの政治の中心は」
「そうそう、『フランス国民の王』を名乗るあの御方。
まア、おれ個人としては、フランスという大国の激動の歴史の中で、ああいう毒にも薬にもならなさそうな人がひととき、玉座に座るのは喜ばしいことだと思うよ。世の中が平和になったし」
「『フランス国民の王』ですか。実際はどんな御方なんでしょうね」
「雰囲気は気さくなんだけど、実際話すと、やっぱりブルジョワ寄りの人だねえ」
「えッ、お話しされたことがあるのですか、王様と?」
「ハハハ、こっちから会いに行かなくたって、王様はそのへんをウロウロなさってるよ。お供を大勢連れて、よくマドレーヌ大通りで皆に声をかけていらっしゃるから、ケンイチ君もそのうち会えるんじゃない?」
「でも緊張しますね、王様相手に迂闊なことは言えませんし……」
「リスト君が数年前」
と言い掛けるなり吹き出して、ヒラー氏はそのまま笑い出してしまった。つられて鍵一も笑ってしまいながら、この音楽家の豊かな笑い声をもっと聴いていたいと思う。
「リストさんがどうなさいました」
「エラール氏の工房でリスト君がね、最新式のピアノを試弾していたときに」
「ええ」
「王様がひょっこりやって来た」
「王様は本当にどこにでもいらっしゃるんですね……!」
「ルイ=フィリップ王は親しげにリスト君に声をかける、
『やあリスト君。むかし、私の家で演奏を披露してくれたことがあったね。あのとき、きみはまだヒヨッコで、私は国王ではなくオルレアン公爵だった。あれから実に多くのことが変わったね』
澄ましてリスト君の答えていわく、
『ええ、閣下。しかし、この国が良くなったわけではありませんね』」
「……!」
「ワハハ、彼らしいよね。その一件が祟って、リスト君は王様から勲章をもらい損ねたんだけど、全然気にしてないしね、彼。ハハハハ、良い子は真似しないでね」
「ハア、すごいエピソードですね……ヒラーさんなら、どう対応なさいますか」
「王様に?」
「リストさんと同じシチュエーションで王様に声をかけられたとしたら」
「そうだな……まず深々と一礼し、そしてうやうやしくご尊顔を拝しつつ、
『はい、閣下。お言葉を賜り恐悦至極に存じます。もしお時間が許すようでしたら、ここで一曲奏しまして、閣下のうるわしき御代を称えたいと存じますが、いかがでしょうか』
と、即興で国王好みのブルジョワふうワルツを披露。そうして上機嫌で王宮へお帰りいただく」
「なごやかですね……!」
「ハハハ、おれは風見鶏だからねえ。リスト君のように、相手が誰であろうと『恐れず、ひるまず、侮らず』というポリシーを体現する芸術家は立派だと思うけれど、おれはそうじゃない」
ヒラー氏は珈琲を飲み干すと「ごちそうさま」と、椅子をならべた簡易寝床へふたたび、ゴロンと横になった。
「この世に確実という事柄が無いのと同じく、この国における音楽家の地位だって、決して永年安泰というわけじゃない。いくら時流に乗って持て囃されたとしても、いくらその芸術に偉大な価値があってもだよ。足場もおぼつかないのに、わざわざ波風を立てることはないじゃないか。何事もなごやかにやりすごして、勲章だろうが猫じゃらしだろうが、もらえるものはもらっておけばいいんだ。いずれ大業を成すときに、それらがきっと役に立つ」
「良い子はヒラーさんを真似すべきですね」
「ハハハ、そのかわり、歴史に名を残せないかもしれないよ。リスト君のエピソードは後世に語り継がれるだろうけど、おれの言動はそもそもエピソードになりづらいだろうからね」
と、こともなげに言った。
そうなのですね、とも、いいえそんなことは……とも言われずに、鍵一は珈琲カップを厨房へ片付けながら、はっと手を止めた。
(B先生はきっと、こういう御方の事こそ『音楽史』に書き入れるべきと考えていらっしゃるのだ)
と、二階の自室の戸棚に仕舞い込んだままの『未完の音楽史』の中身を思い浮かべる。
(アフリカで発見された有史以前の木琴の痕跡……JAXA宇宙音楽プロジェクト……日本ピアノ黎明期……この世の音楽にまつわるすべてを記録しようという、B先生の壮大な試み……! そこにフェルディナント・ヒラーさんの名前が加わることでなにか、音楽史が違ったふうに見えてくるのかもしれない。
そうだ、ピアノ奏法の相談をしたいのは山々だけれど……それよりぼくはもっと、この人にインタビューをすべきなんだ。ドイツの音楽界の状況や、パリのサロンや、この時代に生きている音楽家について……!)
「ヒラーさん」
振り向きざまに鍵一が呼びかけると、
「んご」
と、ふくよかないびきをかいて、音楽家は眠りに落ちていた。

つづく


19世紀の音楽家・チェルニー氏から贈られたモチーフを活かし、鍵一が作曲するオリジナル曲。19世紀の旅で出会った芸術家たちの肖像画を、変奏曲の形式で表した作品です。
実際には、作曲家の神山奈々さんが制作くださり、ピアニストの片山柊さんが初演をつとめて下さいます。オーディオドラマやコンサート等でお聴きいただけるよう、現在準備中です。
ル・アーヴルは英仏海峡を臨む港町です。1836年から、蒸気船によるパリ⇔ル・アーヴルの定期運航が始まりました。
リストは1837年~1839年、恋人のマリー・ダグー伯爵夫人と共に、イタリアやウィーンなどを旅し、各都市でコンサートを開催しました。
上下水道の整備されていなかった19世紀パリでは、飲料水は貴重でした。きれいな水を手に入れるためには、井戸か給水泉へ汲みに行く必要がありました。また、水を市内で売り歩く『水売り』という商売がありました。
アントナン・カレームは、19世紀初頭に活躍したフランス料理のシェフ・パティシエ。
レストラン『外国人クラブ』のシェフの師匠です。多くの創作料理を編み出し、料理本を出版しました。1833年没。
19世紀初頭に考案されたサイフォン式が主流でした。
フランス最初の鉄道は、1832年にサン=テティエンヌ-リヨン間で開通しました。
音楽家シャルル=ヴァランタン・アルカンは、この新たな文明の利器を題材としたピアノのエチュード『鉄道』を、1844年に出版しています。
『英雄』とは、ベートーヴェンが1804年に作曲した交響曲第3番(通称『英雄』)のこと。フランス革命を支持していたベートーヴェンは、ナポレオンが皇帝に即位したという知らせを聞いて激怒し、ナポレオンに献呈するはずだった楽譜の表紙を破いた……とされています。