第16話『歌を継ぐひと♪』

「ぼくに創れるでしょうか、『夢の浮橋』変奏曲だなんて……」
鍵一は自分に授けられた楽譜の断片を、暖炉の火に透かし見た。8小節ほどのそのフレーズは美しい弧を描いて五線譜に遊び、鍵一の想像を超え、遥か遠くへたなびいてゆくように見える。チェルニー氏は微笑して、
「作曲の試行錯誤をするうち、きみは磨かれるだろう。人として。音楽家として。悉く。否応なしに」
歌うように予言した。
「しかし、ケンイチ君。作曲は苦手かね?」
「日本ではいちおう、作曲法は学びました。対位法も……巧く創れたためしはありませんが、理論はひととおり。でも苦手です。作曲も即興も。『自由にやれ』と言われるのが、いちばん困ります。音楽家失格ですね……」
鍵一がうなだれると、チェルニー氏の大きな手が肩に置かれた。
「誰もが霊感を得て作曲をしているわけではないよ。多くの音楽家は、地道な修練によって、ひとひらの才能を開花させるのだ。なかにはリスト君のように、天才的なセンスで美しい和声の水脈を掘り当てる音楽家もいるが」
「残念ながら、ぼくは……」
「そうだね。きみは天才ではない。しかし才能の片鱗はある。だからこそ、きみは惑うのだ」
はっとして、鍵一はチェルニー氏の目をまともに見た。
未だかつて、師のB氏でさえ、鍵一をこれほど明確に言い当てた事はなかった。肩に置かれた大音楽家の手が温かい。
「ケンイチ君。重大な事実を教えてあげよう。
リスト君は天才であるがゆえに、私の元で根本から基礎を鍛え直さねばならなかった。11歳の神童に、私が最初に何を教えたと思うかね?『正しい姿勢で椅子に座り、鍵盤に指を置くこと』だよ。そこから始めた基礎訓練が、彼を真のヴィルトゥオーゾに成らしめたのだ」
(そうだ、あのときリストさんは確かに仰っていた……!『今のウチがあるんは、チェルニー先生が基礎をみっちり教えてくれはったおかげや。超絶技巧いうても、もとをただせば基礎の積み重ねやし』……と)※1
思い起こしたリストの声は初夏のレモネードの色に混ざって、鍵一の胸に甘酸っぱく沁みた。
「あのまま我流で弾いていたら、リスト君の煌めきは10代のうちに消え失せていただろうね。
対して、きみの場合だ」
鍵一の肩をかるく叩くと、チェルニー氏はゆったりと立ち上がった。まどろむ猫たちに毛布を掛けてやりながら、なおも話し続ける。
「きみは初めて目にするこのピアノに、じつに正しい姿勢で座った。演奏中、きみの心は傍目にも明らかなほど乱れていたのに、きみの指はひとりでに動いて、最後までベートーヴェン先生のピアノ・ソナタを弾き終えた。長年にわたる素直な基礎の習得が、どれほど強靭にきみを支えていることか……!きみはもっと自覚するがいい。それは、リスト君とは違った仕方で、きみを真のヴィルトゥオーゾに成らしめるものだ」
鍵一は絨毯に座り込んだまま、白くひょろ長い自分の手指を眺めた。
(ホワイトアスパラガス……この指で一体、何ができるんだろう)
ふと見ると、フェルマータがチェルニー氏の長椅子でスヤスヤと寝入っている。このミステリアスな猫も、今は他の猫と同じように、桃色の肉球をみせて、フサフサのおなかをかすかに上下させながら寝息をたてていた。鍵一は羽織を脱いで、この相棒猫にそっと掛けた。
……その瞬間、小さな流星が、鍵一の胸中を流れ落ちた。あまりに突然で、あまりにかすかな煌めきに、うろたえて鍵一は顔を上げた。チェルニー氏がうなづいた。
「ケンイチ君。才能は片鱗で充分だ。開花させる方法なら、いくらでもある」

チェルニー氏はピアノの燭台に火を灯すと、ゆったりと椅子に腰掛けた。
「作曲の上達法として、まず私がきみに勧めるのは『写譜』だ。先人の優れた作品を、一音ずつ五線譜に書き写すことだよ。試みたことは?」
「いいえ……」
口ごもりながら鍵一の脳裏に、油絵具の匂いにみちた京都の叔父のアトリエが浮かんでいた。
「たとえばドラクロワの作品を、若い画家が模写するようなもの……でしょうか?」
「そのとおり。ただし、『どのように』模写するかが重要だと私は思う。表面だけを真似ても意味がない」
「?」
「ベートーヴェン先生に弟子入りしたとき、私は10歳の少年だった。レッスンをしてもらえない間はひたすら、先生の自筆譜を書き写していたよ。たとえばこの曲」
チェルニー氏は懐かしそうに中空を仰ぎ見ると、ふと流れるように弾き始めた。この初老の大音楽家の運指の軽やかなことに、鍵一は驚いた。澱みなく紡ぎ出される絹糸のような音が、光を纏いながら白銀色の景色を織り上げてゆく。
♪ベートーヴェン作曲 :ピアノ・ソナタ 第12番Op.26 変イ長調
作曲年:1800年 出版年:1802年
「最初のうち、写譜はひどく難航した。曲を書き写すどころか、私はベートーヴェン先生の書かれた音が『A』なのか『B』なのか、それすら判別できなかった」
と、チェルニー氏は弾きながら話を続ける。
「なにせ、ベートーヴェン先生は楽譜の書き方も型破りだ。先生の自筆譜はまるで暗号のようで、出版社の写譜師をも悩ませるほど難解だった」
鍵一はワープで目の当たりにした『楽聖』の様子を思い出して、思わずフフと笑った。チェルニー氏も弾き続けながら微笑んだ。
「さらには先生の独創性が、未熟な私を苦しめた。セオリーを大きく逸脱した和声進行や、斬新な楽曲構成……それらが書き誤りなのか、意図的なのか、私にはわからない。尋ねようとすれば、『俺の作曲の邪魔をするな』と追い払われる。
悩んだ末、私は先生を徹底的に『観察』し、『真似』することを始めた。先生の頭の中を知るには、それがいちばん良い方法だと思ったのだ。
できるかぎり先生と食事を共にし、先生の散歩にくっついて行き、先生の故郷の訛りを真似て話した。先生が怒れば私も怒ってみた、先生がアクビをすれば私もアクビをしてみた。先生の演奏する機会があれば、必ず楽屋裏で聴いた。場内に入れない時は、冷たい石塀に耳を吸いつけて、風に乗ってかすかに運ばれてくる音楽を聴いた。聴くとすぐ弾いてみた。息遣いまで先生そっくりに、何十回、何百回と弾いてみた。
……そうして1年経ち、2年経つうちに、だんだんと、ベートーヴェン先生の思考のしくみがつかめるようになってきた」
「思考のしくみ……?」
耳慣れぬ言葉を鍵一がくりかえすと、チェルニー氏はうなづいて、そのまま1楽章をゆるやかに弾き終えた。
「ベートーヴェン先生にとって、音楽とは何なのか。先生にとって何が重要で、何が些末なことなのか……そういった事が理解できるようになると、楽譜に表された先生の創作意図も、少しずつ理解できるようになった。
あるとき、いつものように先生の新作の楽譜を書き写しながら、私はごく自然にこう思ったのだ。『ベートーヴェン先生なら当然、こう書くだろうな』……と。
1803年の春だった。それは私の中に、ベートーヴェン先生の『思考のしくみ』が宿った瞬間だった」
鍵一の心の中を、春一番が吹き抜けていた。……暖かな南風は、五線譜を書く『楽聖』の栗色の髪をたなびかせる。ひときわ強い風が、机に積み上がった楽譜を舞い上げる。部屋中に散らばる楽譜たち。チェルニー少年は急いで楽譜を拾い集めて、一目見ただけで正しい順番に並び替える。……師弟の幻影は止むことなく、鍵一の胸を打った。チェルニー氏はピアノの蓋をそっと閉めると、鍵一を振り向いた。
「よいかね。写譜は、自分の曲を創ることへの第一歩だ。偉大な音楽家の『思考のしくみ』を理解することは、きみという人間の創造力を広げ、また深めてくれるだろう
次の段階では、覚えた『思考のしくみ』を実際に使ってみるといい。優れた音楽家の名作の一部を、自分の作品に取り入れて活かすのだ。現代のヴィルトゥオーゾは皆、この方法に長けている。むろん、きみの師匠のリスト君もね。『夢の浮橋』の変奏曲を創るさいには、ぜひリスト君に相談したまえ」
鍵一はしっかりとうなづきながら、和歌を詠む技法に似たものがあったような気がする。
(何だったろう。『鳥』に関係した言葉のような……)
窓の外で、夜の鳥がホウと鳴く。チェルニー氏は燭台の灯りを吹き消した。
「……さて、夜も更けた。互いにそろそろ休もう。ケンイチ君。またいつでも、私のレッスンルームに来なさい」
チェルニー氏が鈴を鳴らすと、扉がひらいて小間使いが控えている。鍵一は急いでフェルマータを抱き上げると、この偉大な師へ深く、深く頭を下げた。

客間では、ドラクロワとベルリオーズが長々と寝そべって、それぞれの夢を漕いでいた。フェルマータを彼らの傍へそっと丸めて寝かせると、鍵一は窓をちからいっぱい引き開けた。若く熱い額がたちまち、涼しい夜風に受け入れられる。窓の夜に月はとうに溶けて、漆黒の彼方には天の川が
tranquillo
※2に流れている。
(夢の浮橋……!)
と、鍵一は身を乗り出して、その朧げな光の川を見つめた。
(ぼくは幻の名曲『夢の浮橋』の、楽譜の一部を受け継いだ……!たった8小節だけれど、ぼくも『夢の浮橋』の継承者のひとりなんだ)
鍵一は今、自分が巨大な音楽史の流れの中に居るのを感じていた。泣き出したいほどに、大声で叫び出したいほどに、それは親しく温かい感覚だった。おそるおそるコブシを天へ突き上げて、
「フロイデ(Freude)」
小声で呟いてみる。ムズムズと力が湧いてきた。
(パリへ帰ろう……!ぼくには創るべき曲がある。会うべき人たちがいる。リストさんのところへ……『外国人クラブ』のレストランへ、今すぐに帰ろう。
お世話になったチェルニー先生には、せめて御礼の品を……何か、何か無いかしら)
風呂敷包みを探ると、固い丸いものに手がふれる。掴んでみれば、ツンと鼻をつく匂い。
途端、先ほどの答えがひらめいた。
(『本歌取り』だ)※3
それから夜更けまで掛かって、鍵一は手持ちの五線譜へ、和歌をひとつ書きつけた。魔よけの玉ねぎを文鎮代わりに、そっと窓辺に置いておく。
夢の間の 渡せる橋におく星の 白きを見れば夜ぞ更けにける
(古来より音楽家たちに受け継がれてきたという、名曲『夢の浮橋』。天の川の白い煌めきを眺めて、その曲を想っていると、いつのまにか夜が更けていましたよ)
鍵一は鍵盤ハーモニカを構えると、深く息を吸った。
(チェルニー先生、ありがとうございました。この学びは一生忘れません。いつか、ぼくの創った『夢の浮橋 変奏曲』を聴いていただけますように……!)
♪リスト作曲 :ポジリポの夏の夜(ドニゼッティ) S.399 R.153
作曲年:1838年
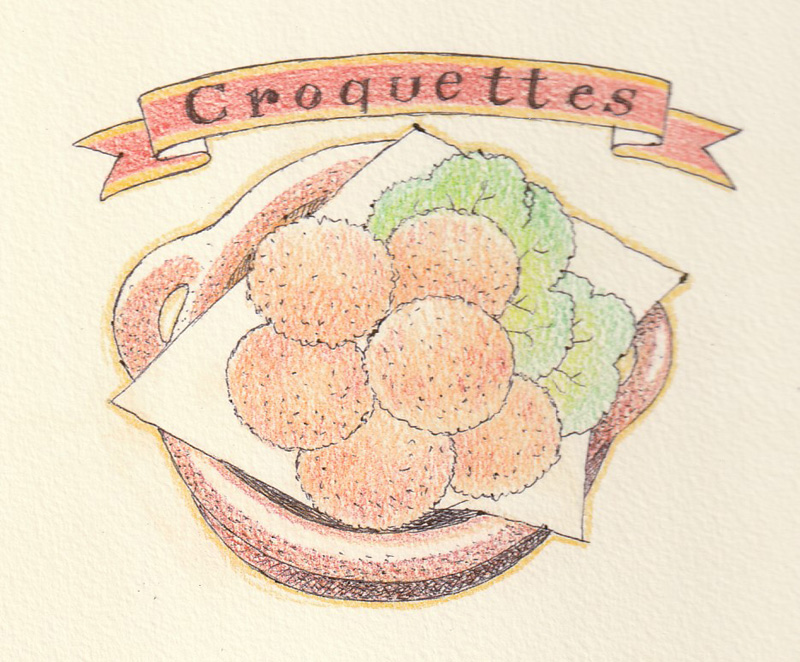
もんどりうって3人したたかに扉へ頭をぶつける。ふっと意識が遠のいた鍵一、
「どこ行ってたんや!?ちょうど探しに行こうと思てたとこや」
頬をぺちぺち叩かれて、はっと目をひらいた。青く美しい瞳が屈み込んで、心配そうに鍵一を見守っている。
「リストさん……!」
やにわに身体を起こすと、自分を包む懐かしい匂いに鍵一は「ホ……」体中が溶けそうなほど深い溜息をついた。
「おかえり、迷子の子猫ちゃん」
フェルディナント・ヒラーがおどけた仕草でワイングラスを掲げる。アルカン, シャルル=ヴァランタンがちらりと一瞥をくれて、
「まさか3人と1匹が一緒に帰ってくるとはね。さて、誰がメフィストで、誰がファウスト?」
くちびるの端に笑いを滲ませている。すると厨房から大皿を両腕に載せて来たシェフが、
「ケンイチおまえ、玉ねぎ全部食っちまったろ。クロケット※4に入れようと思ってたのにさ」
見れば満月のようなまんまるのクロケットが、カラリと揚げたての山盛り。
鍵一の隣で跳び上がったドラクロワが、「アワワ、ワ、ワ」よろよろと店の中へ飛び込むと、テーブルのクロケットをひとつ口へ押し込んで、息せき切ってモゴモゴ喋り出す、
「アタシたち、ウィーンに居たのよ、ベートーヴェン先生のおうちに行ったのよ!それからついさっきまでチェルニー先生のお屋敷で眠ってたわ……ッ、でもここ、パリの『外国人クラブ』よね?今って西暦1838年よね?一体どうなってるのッ?」
「ぼくたち3人、なぜか同じ夢を見ておりまして……ッ」
しどろもどろに説明しながら、鍵一はすべてを音楽家たちに話してしまいたい衝動に駆られる……しかしグッとこらえた。
「ベルリオーズさんを芸術橋から担いで帰る途中に、足が滑ってぼくたち3人、セーヌ川へドンブラコ……!あわや三途の川を渡りかけたところを、通りすがりの御方に助けられたんです」
「一片の人情が、世の中を親密にさせる……(出典:シェイクスピア『終わりよければ全てよし』)」
と、ギターごと床にひっくり返っていたベルリオーズが呟いた。続けて『ポロロロ、ロロ、ポロロン』美しいメロディをつまびく。
「ほ」
音楽家たちは顔を見合わせて、それからリストが最初に吹き出した。
「なんや、よう分からんけども……!ひとまずベルリオーズ先輩の『言葉と音楽のマリアージュ』の探究※5は、うまいこといかはったようやな。ドラクロワもケンイチもフェルマータも、無事に帰って来た。めでたし、めでたしや♪さあ、晩餐会を始めようやないか」
それから一同大騒ぎで、音楽家たちは3人と1匹を助け起こして毛布にくるむやら、ワインを注ぐやらクロケットを盛り付けるやら、世話しながら笑いさんざめく。厨房からまた盛大に湯気が立ち昇って、次の創作料理が仕上がりつつある。
(B先生から引き継がれた『音楽史編纂』のミッション。ショパンさんがくれた謎のメッセージ。リストさんと約束したサロン・デビュー……)
山盛りのクロケットをぼんやりと眺める鍵一の膝へ、
「ニャ」
フェルマータがヒョイと跳びついて、そのまま気持ちよさそうに丸くなった。
(もしかすると、幻の名曲『夢の浮橋』が、すべての鍵を握っているのかもしれない……)
「さあさあ、ケンイチも熱いうちに食べよし♪」
リストに促されて「はいッ」鍵一がクロケットにかぶりつくと、とろりたっぷり熱々クリーム。
「美味ッ」椅子から飛び上りながら鍵一は、音楽家たちの笑顔の肩越しに、『外国人クラブ』の窓辺の風鈴が星灯りに照らされてきらめくのを、確かに見た。
つづく


第7話『檸檬色のエチュード♪』をご参照ください。
音楽用語で『穏やかに、静かに』の意。
和歌の技法の1つ。すぐれた古歌の一部を取り入れて、オリジナルの新たな歌を詠む技法です。鍵一が詠んだ歌の本歌は、『かささぎの 渡せる橋におく霜の 白きを見れば夜ぞ更けにける』(作:大伴家持)
フランス伝統の、小さな揚げ物料理。日本では明治時代より『コロッケ』という独自料理に進化しました。
『幻想交響曲』ほか、『夏の夜』にも『言葉と音楽のマリアージュ』の思想が活かされています。