第6話『風鈴♪』

師匠のB氏より極秘ミッションを引き継がれたことから、彼の運命は一変する。
19世紀パリへワープした鍵一を待ち受けていたのは、ショパン、リスト、アルカン、ヒラーという、綺羅星の如き音楽家たちであった。
リストのすすめでサロン・デビューを目指す鍵一だったが、最初の修行課題はいきなりの難問で……!?
7月6日は『ピアノの日』♪
ピアノなるものが海より来たりて、江戸時代の人の耳を驚かせた記念日です。
同じ頃ヨーロッパでは、12才のリストがベートーヴェンに褒められ、
13才のショパンはワルシャワで音楽の勉強中でした。
舟の形をしたこの美しい楽器は、多くの運命を結び合わせますニャ……
(ニャ……?)
はっと鍵一は目を覚まして、窓が眩しい。傍らに白黒ねこのフェルマータ※2が気持ちよさそうに伸びて、まだスヤスヤと眠っている。
(そうだ、昨夜は『外国人クラブ』のレストランの2階に泊めてもらったんだっけ。
今日は1838年5月、パリ滞在2日目……!)
ベッドから降りるや勢いよく窓をひらいた。途端、朝陽に迎えられて「おお!」思わず身をのりだした鍵一の目の前に、パリの初夏は光に満ちている。
彼方にはモンマルトルの丘の緑が輝き、麓よりゆるゆると流れ来るセーヌ川は朝の空を映して、あるいはオペラ座の屋根、あるいはアパルトマンの建物の群、あるいはオベリスクの広場の間を見え隠れしながら、きらきらと天の川のようにパリの街を浸している。
かすかに吹き寄せる馬車のひづめの音に目を凝らせば、いま一艘の川舟が、荷を橋のたもとへ漕ぎ寄せるところ。
対岸にはノートルダム大聖堂が、今にも東雲色の鐘の音を響かせようと聳えている。
(bravo!)
鍵一は小躍りして、胸いっぱいに朝の空気を吸い入れた。
(この美しい街で、ぼくは必ず、19世紀パリの音楽史を明らかにしてみせる。
一流の音楽家たちと交流して、ショパンさんのくれたキーワード『夢の浮橋』の謎を解いて……
そのためにはまず、ぼく自身が一流の場所に出入りできるように、実力をつけなくちゃ。
まだまだ道程は遠いけれど、きっと大丈夫。いざとなったら、三種の神器も使えるし)
鍵一は三種の神器を朝陽にかざして、つくづくと眺めてみた。
(まずは、音楽記号の詰まった福袋。
B先生が『ピンチの時は使え』と仰っていたけれど……あまりピンチには遭いたくないなあ。戸棚にしまっておこう。
それから、鍵盤ハーモニカ。
19世紀パリだけではなくて、他の国や時代にもワープできるかしら? 気になる……!
でも、ひとまずしまっておこう。今はサロン・デビュー修業の課題に集中しなきゃ。
リストさんから出された最初の課題、『1文無しで1年間パリに居座る方法』……難しいな。
B先生の『未完の音楽史』に、何かヒントがあるかしら?)
分厚い音楽史をひらきながらドサリと鍵一がベッドに座ると、はずみで白黒ねこのフェルマータがヒョイと起きた。
(これは凄いぞ、さすがB先生! アフリカで発見された有史以前の木琴の痕跡から、JAXAの宇宙音楽プロジェクト『moon score』※3まで、古今東西の音楽史を縦横無尽に記録し、かつ、付録の小論文で鋭い考察を……!)
夢中でページをめくる鍵一の傍へフェルマータが寄ってくると、
「ニャ♪」
と、ねこ手をページに差し入れた。
「なんだいフェルマータ、『キャットフィッシュ』の項かい」
鍵一がゆっくりとそのページを開いてみると、
『にっぽんピアノ黎明期』
と題して、B氏の筆が朗々と綴っている。
『1823年7月6日、医師シーボルトが長崎へピアノを持ち込み、これがにっぽんピアノ史の幕開けとなった。』
(なるほど。かくて、7月6日はピアノ記念日♪
初めてピアノの音色を聴いた江戸時代の日本人は、さぞびっくりしただろうなあ。異文化から受ける刺激は、相当なものだったはず。
待てよ。ここ19世紀パリではどうだろう?
昨日お会いしたヒラーさんはドイツ出身、ショパンさんはポーランド出身、リストさんはハンガリーの出身……パリでは外国人の音楽家が活躍してる。
アルカンさんはこう仰っていた、『今のパリなら、珍しいものを楽しむゆとりがある。日本人のきみがデビューするなら、今がベストだよ』って)
「おーいケンイチ、起きてたら顔洗って降りてこいよ」
陽気な声が階下から響いて、「はーい」と呼び返す鍵一の鼻先に、ふんわりとこうばしい匂いが流れてくる。
「朝飯のクロワッサン(croissant)、焼き上がったぞ」
「わっ、ありがとうございます♪」
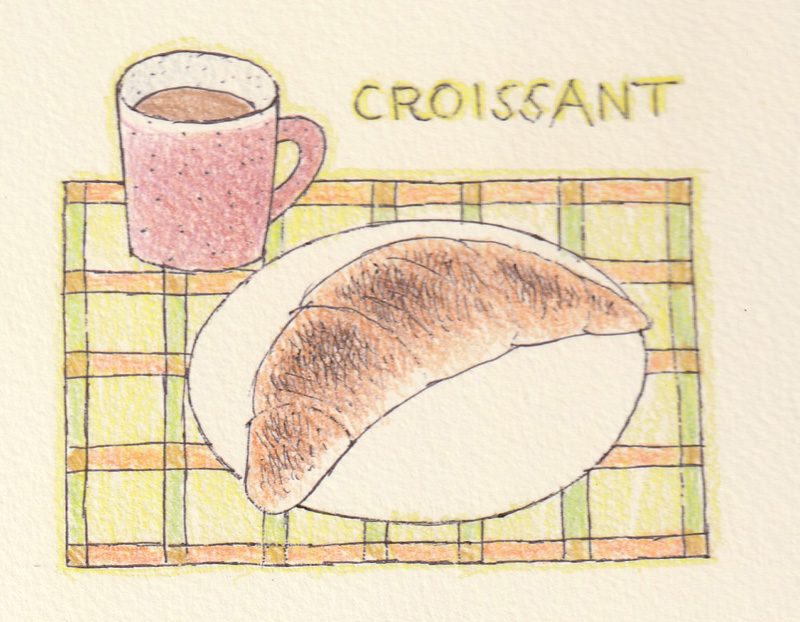
(ナイスな三日月のかたち。そういえば『クロワッサン』といえば、フランス語で『三日月』の意味だものな。熱ッ)
バターの染み出るクロワッサンにかぶりついた鍵一、
「bravo!」
椅子から跳ねてシェフに笑われた。
「美味しいです! 外はサクサク、中はもっちり。これ、フランスの伝統的なパンですよね」
「俺たち一般市民の口に入るようになったのは、わりと最近だけどな」
シェフは厨房の奥からバケツを提げて来て、鍵一の前へ気楽に腰かけた。
スズランの花束※4の茎が半分ほど水に漬かっているのを、ブンザアと引き揚げてハサミを入れ始める。
「ついでに言うとさ、昨日の夕食会に出した料理も、デザートの苺のミルフィーユ(=ナポレオン・パイ)も。俺たちの親世代では、王侯貴族しか食せない贅沢品だったんだぜ」
「えッ、そんな高級料理だったのですか」
「そもそも料理という文化自体が王侯貴族の独占物だったからな。俺の師匠のカレーム先生だって、国王の料理人だったんだ。ナポレオンのウェディング・ケーキなんかも創ってた」
「どうしてその高級料理が、今はこのレストランで頂けるのでしょうか?」
「大革命だよ。18世紀末のフランス革命が、すべてを変えたんだ」
チョキン、と小気味よい音をたてて、花の根元が落ちた。
「王侯貴族はギロチンに掛けられた!当然、雇われてた料理人たちは職を失った。宝石箱を逆さにぶちまけたみたいにさ、それまで厨房に閉じ込められていた料理人たちが、一斉に野に放たれたんだ。ある者は亡命し、ある者は職を変えた。中にはパリに残って独立して、自分のレストランを創る奴らがいた。俺もそのひとりさ」
「大変な時代でしたね……!」
「まあな。でも俺は革命に感謝してる。一時的に職は失ったけど、自分の店を持てて良かった。一国一城の主になるってのは、やっぱり良いもんだよ。楽しい連中にも会えたしさ」
ニカッと笑ってシェフが目配せする。その視線の先に、ドラクロワが描いたという芸術家たちの肖像画がまぶしい。あるいは今にも笑い出しそうに、あるいは憂いを湛えて、あるいは社交界の華やぎを纏いつつ、19世紀の芸術家たちはキャンバスの中に息づいている。
(ドラクロワ……子どものころ、京都の叔父さんのアトリエで画集をよく見ていたけれど。こういう小ぶりの肖像画も素敵だな。『キオス島の虐殺』や『民衆を率いる自由の女神』とはまた違ったエネルギーを感じる)
「皆、いい顔だろ」
言われて、鍵一は大きくうなづいた。
「俺がメシを食わせる相手は、もう王侯貴族じゃない。こういう清々しい顔をした連中なんだ。この国に新しい風を吹かせる芸術家や、すばしこくて賢い一般市民だよ」
と、スズランの葉のみずみずしく張りきっているのをシェフは面白そうに眺めて、それ以上は切らずにハサミを置いた。
「料理も芸術も、フランス文化はいま黎明期なんですね……!」
「時代が移り変わった後に、俺たちの創り上げたものがどこまで生き延びるかは分からんがね。今は前進あるのみさ」
シェフは立ち上がると、戸棚から花瓶をとりだして、ためつすがめつしている。
「なあケンイチ。俺がなぜ『外国人クラブ』を自分のレストランに受け入れたか、わかるか?」
「?」
「俺たち料理人は、時代に合った新しいフランス料理のスタイルを、自力で創らなきゃならねえ。そのためには、伝統的なフランス料理の枠に縛られてちゃダメだ」
(外国人の音楽家が活躍する19世紀パリ……あっ、そうか!)
「外国料理のアイディアをメニューに取り入れるため、ですね?」
「正解!それにあいつら、良きテスター(試食係)でもあるんだ」
「確かに皆さん、小さい頃から演奏活動をされていて、ヨーロッパ中の宮廷やサロンで演奏なさっているから」
「そうそう、そんじょそこらの大貴族より、よっぽど舌が肥えてるんだよ。
あいつらが満足してくれる料理なら、俺も自信持って客に出せるってわけ。
メニューもまだ開発中だからさ、時々とんでもなくマズイもん食わせたりはするけど」
笑うシェフにつられて鍵一も笑ってしまう。クロワッサンは冷めても美味しい。
「いずれ、俺もカレーム師匠みたいに、後世に残るレシピを創るんだ。
レシピさえちゃんと作っておけば、後世の人々もパリのうまいものを食えるわけだし。
でも、いつも即興で創ってるうちに書き留めるの忘れちまうんだよな。ハハハ、あとからじゃ分量なんて思い出せないしさ」
「レシピは、シェフにとって楽譜みたいなものなんですね」
「確かにそうだな。料理人にとってのレシピと、音楽家にとっての楽譜は同じ、か……おっと!」
シェフの危なっかしい手つきが花瓶を転がしそうになる、
「よければぼく、やりましょうか」
と、鍵一は思わず立って行った。
「少しですが、日本の生け花の心得がありますので」
「お、ありがたい。ヒラー君が置いてった花束なんだけど、どうも俺はこういうことはダメだな」
「涼しげな初夏のスズラン……風鈴みたいな花ですね」
「風鈴?」
「夏に涼をとるための、日本古来の文化です。
シェフさん、グラスを貸していただけますか? 昨晩リストさんたちが『大彗星のヴィンテージ』を飲んでいらした、あのシャンパーニュ・グラス」
「いいけど、どうするんだ」
「日本の生け花の特長は、素材の持ち味を活かすことにあります。
こういうスラリとした花は、重い丸っこい花瓶よりは、透き通った細長いグラスに活けて、シルエットをきれいに見せたほうが……はい、サササのサ♪」

「ケンイチ、おまえ……天才か!?」
「いえ滅相もない! 叔父からすこし習った程度ですが……お役に立てて嬉しいです♪」
「いいなあ、涼しげで。日本の夏も暑いのか?」
「そうですね、叔父の住む京都という街は、特に蒸し暑くて。だからこそ、涼をとる工夫はいろいろあります。
たとえば竹を橋のように架け渡して、冷たいそうめんを流したり……」
「ほう!」
「川辺に納涼床を造って、桟敷で涼みながら川魚をいただいたり……」
「ほほう!」
「あるいは金魚を鉢に泳がせて……」
「ニャーン♪」
と、魚の話題に白黒ねこも寄ってきた。シェフは「斬新!」と手を打って、手近な紙にアイディアを書き留めようとする。
「涼やかで、華やかで、季節を楽しめる新しい趣向!そういうのが欲しかったんだよ。
なあケンイチ、そのアイディア、うちの店で使っていいか?」
「どうぞ、どうぞ」
白黒ねこの背中をなでてやりながら、ふと鍵一の脳裏に閃光がひらめいた。
(外国人が活躍……異文化ならではのアイディア……1年間パリに居座る……
そうか、これだ!)
「シェフさん、ご提案があります。メニュー開発とレシピづくりを、ぼくにお手伝いさせてください。そのかわり、ぼくがサロン・デビューできるまで、この店の2階に泊めてもらえませんか?」
シェフが大きくうなづくのと同時に、白黒ねこが「ニャ♪」と鳴いた。
「よし、気に入った!好きなだけ泊まっていけ。まかないも付けてやる。店のピアノもどんどん弾いていいぞ」
「ありがとうございます!お世話になります。ではさっそく、日課の練習を……」
安堵の溜息とともに鍵一はピアノの椅子に座ると、ふたをそっとひらいた。
(良かった……!食事と寝床さえ確保できれば、やりたいことに集中できる。
19世紀パリでも、ピアノの練習は欠かさないようにしよう。
まずは、B先生が『噛めば噛むほど旨みの増す曲じゃ♪』と仰っていた、チェルニーのエチュードから)
♪チェルニー(ツェルニー) :フーガおよび多声音楽演奏のための教則本 Op.400
しかし最初の数小節を弾き出したところで、
(あれ?)
異変に気づいて、鍵一は手を止めた。
つづく
- 7月6日は『ピアノの日』
1823年7月6日、ドイツ人の医師シーボルトがオランダ商館医として来日し、イギリス製のスクエア・ピアノ(ウィリアムロルフ・アンド・サンズ)を長崎に持ち込みました。
この事に由来し、7月6日は『ピアノの日』とされています。
※記事中の「日本最古のピアノ」という表記について。「シーボルトのピアノ」は日本に初めて到着したピアノである可能性がありますが、後年、より古い年代の楽器が複数、日本に渡来しています。 - フェルマータ(fermata)
『楽曲の途中で、拍子の運動を止める』という意味の音楽記号。
フェルマータの付いた音符や休止符は、長く保って演奏されます。
白黒ねこの名付けの由来につきましては、連載第5話をご参照ください。 - JAXAの宇宙音楽プロジェクト『moon score』
- スズランの花束
フランスでは、5月にスズランの花を贈り合う習慣があります。

