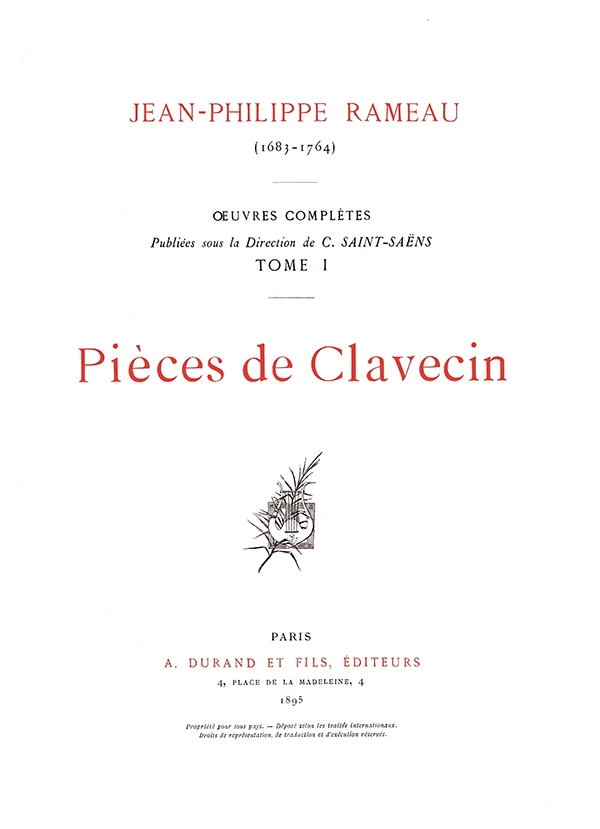第13回 古典と古楽

1895年5月、ベトナムからの長い旅行から帰ってきたサン=サーンス、もちろん仕事が溜まっています。《フレデゴンド》の準備に追われ、12月18日にパリのオペラ座での初演にこぎつけました。
そして、1895年にはピアノと古楽の分野で重要な仕事に取り掛かります。それがデュラン出版社から刊行された『ラモー全集』の監修でした。この全集はフランスにおける古楽の復興と関わってくるのですが、古楽に対する社会的な関心は19世紀前半から既に起こっており※1、1867年のパリ万博においては、実現しなかったものの古楽演奏会シリーズが企画されました※2。つまり、サン=サーンスの人生はフランスにおける古楽復興の歩みとちょうど重なっているのです。1878年のパリ万博においても古楽器の展示は行われましたが、1889年のパリ万博においては、ピアニストのルイ・デイエメル(1843-1919)らを中心に古楽器による室内楽の演奏会が行われ、「フランスの歴史」の紹介としてジャン=フィリップ・ラモー(1683-1764)やフランソワ・クープラン(1668-1733)の作品を演奏しました。展示においても、オリジナルで残っているものだけでなく、同時代のメーカーであるプレイエル・ヴォルフ社とマンシーニ社によるチェンバロのコピー楽器が出展され、楽器というハードの面でも環境が整いつつあったことが分かります。そしてこれを契機にディエメルらによって古楽器協会が設立され、古楽器の音を実際に耳にする機会が少しずつ増えていき、現代の古楽運動の源流の一つとなりました※3。
それでは、なぜサン=サーンスが古楽に興味を持ったかというと、後述の「ラモー」と題された評論においてピッチの問題に触れられていますが、パリには古くから存在する教会が多く、オルガンのピッチは改修されない限り昔のままなので、サン=サーンス自身子どものころからオルガンの演奏を聴いたり、自身で演奏したりする中で、自然と疑問がわいてきたからなのです※4。しかし古楽と一口に言っても、サン=サーンスも興味を持った西洋古典古代、すなわち古代ギリシアの旋法の復活からモーツァルトの18世紀まで、幅広い分野にわたるのですが、サン=サーンスがとりわけ熱心に取り組んだのがラモーの復権でした。既に本連載第4回で1865年のラモーの記念碑の話が出てきていましたが、早くからサン=サーンスは彼に関心を持っていました。『1637年から1790年のクラヴサン奏者たち』を編纂したピアニスト、アメデ・メロー(1802-1874)がパリで1844年の5月5日にラモーを演奏しており、子ども時代のサン=サーンスが聴いた可能性があります※5。ウィーン古典派に相当する楽派、世代を持たなかったフランス楽壇にとって、フランスの古典と仰ぐべき器楽作曲家としてラモーに注目していたのでしょう。ドビュッシーも《映像 第1集》(1905)において〈ラモーを讃えて〉を作曲するなど※6、当時の人々がフランスの偉大な古典として再認識し始めていたのは、サン=サーンスの尽力のおかげなのです。
1895年に始まる『ラモー全集』の記念すべき第一巻は『クラヴサン曲集』であり、サン=サーンスが序文を寄せました。
冒頭のこの文章がサン=サーンスの態度を全て物語っています。自ら作曲家であっただけに、過去の先人たちの作品に関しても、その意思を尊重した演奏、作曲家が意図した音を聴衆に届けたいという考えがあったのでしょうが、これは、まさに現在の原典版の楽譜出版の姿勢に相通じるものです。この続きでは昔とのテンポに対する考え方の違いや、チェンバロという楽器の特性から生じるニュアンスの問題、ピアノとの鍵盤のタッチの差による運指の問題について具体的に言及しており、大変興味深いですが長くなるので割愛します。ただ、このエディションも「実用譜」であることが前提で※8、例えば『クラヴサン曲集』に関しては、ピアノで演奏するためにはどうすればよいか、という視点で編纂されていました。これは19世紀当時には保存状態の良いチェンバロが残っておらず、製作技術も途絶えていた状況を考えると仕方がないとはいえ※9、現在の原典版の校訂基準から見れば不十分なのですが、方向性は間違っておらず、将来への道筋を付けたという点で、非常に記念碑的な業績と言えるでしょう。
その一方で、サン=サーンスは継続して演奏活動も積極的に行っておりましたが、彼の古楽研究の成果はどのように実践に取り入れられたのでしょうか。まず、マルセル・プルーストが1895年12月8日のサン=サーンスの演奏について記した批評を読んでみましょう。
サン=サーンスの演奏には、このまま続いたら卒倒してしまうのではと思うようなピアニッシモもなく、フォルテの個所でただ中断することで聴衆を元気づけるだけであり、何度も体に張り巡らされた神経を上から下まで一瞬にしてビリビリさせるような和音もなく、海水浴で波に向かっていく時に腕や脚がへし折られそうになるフォルテッシモもなく、ピアニストの身体のくねくねした動き、頭を振る動きに、髪の毛の揺れるさま、こういったものは音楽の純粋さに舞踊の官能性を混ぜ合わせるものであるが、[中略]サン=サーンスの演奏にはそういったものは一切なかった。しかしそれは王者の演奏であった。[中略]
この純粋性、この透明性にサン=サーンスの演奏が到達したのである※10。
プルーストは音楽家ではありませんが、小説家としての本能的かつ鋭敏な感覚で本質を見抜き、当時のサン=サーンスのピアノ演奏について観察し描写しています。まず、サン=サーンスはロマン派のヴィルトゥオーソ達の演奏に多く見られた、大げさな身振り手振りをしませんでした。古典的な均整の取れた美を重んじる高踏派の美学に影響を受けたサン=サーンスが、モーツァルトの演奏に派手な動作はいらないと判断したからと考えられますが、詳しい理由は後で考察することにして、いずれにせよ、オーバーアクションに慣れた当時の聴衆には、サン=サーンスの演奏が淡白過ぎてそっけなく見えたのでした。また、後に1915年6月1日にサンフランシスコで行った講演中で原典版について以下のように述べています。
現在の出版譜におけるもう一つの誤りはペダルの濫用です。モーツァルト自身ははっきりとそうとは書いていませんが、彼の音楽の特質の一つが純粋性という美的感覚であったことを考えると、おそらく彼はペダルをみだりに用いなかったでしょう※11。
プルーストの評論の中で述べられた「純粋性」が、まさにサン=サーンス自身モーツァルト演奏において意図したものであったわけです。この講演は「音楽、とりわけ古楽の演奏について」と題されており、その内容は単旋律聖歌に始まり、パレストリーナ、バロック音楽、ウィーン古典派を経てショパンの「テンポ・ルバート」の演奏にまで及んでいます※12。20世紀の初頭の時点で、サン=サーンスがラモーというミクロの視点の個別研究だけではなく、マクロの視点で音楽史の幅広い時代を俯瞰していたことに驚かされます。モーツァルトの演奏においては、サン=サーンスはロマン派的な誇張した表現、過度の身体的動作を排し、古典的な均整の取れた端正な演奏を心掛けたのですが、彼は現在のモーツァルトの演奏スタイルにつながる道筋を付けた先駆者の一人と言っても良いでしょう。
先ほどの章では全体的な印象として「純粋性」を取り上げ、ペダルの節度ある使用まで述べましたが、具体的にはどのような演奏をしていたか見ていきましょう。
1901年5月22日にフォーレに宛てた手紙には、このような記述があります。
私が光栄にも君の先生だった時には、このことを全く知らなかったのですよ、というのも誰も私に教えてくれなかったから……※14!
上記の手紙に捕捉する内容として、1909年にサン=サーンスは「ラモー」と題して彼に関する評論を発表します※15。
このように、サン=サーンスは原典研究を行い、古楽奏法の再現による正統的な演奏に取り組んでいました。父モーツァルトの時代の演奏習慣を子モーツァルトの作品の演奏に適用するとは何事か、という当時の批判記事もありましたが、この正統性をめぐる議論そのものが、その後の古楽運動における大きな課題となり※17、問いに答えることが活動の原動力となったことを考えると、サン=サーンスが荒野を切り拓いたことによって、彼の歩いた後に道ができたことは無視できません。
以上、サン=サーンスの古楽研究に基づく楽譜の解釈について述べましたが、それでは、実際のピアノのタッチや演奏姿勢はどうだったのか、気になるところかと思います。実は、サン=サーンスは長生きをしたおかげで技術の進歩が追いつき、録音、サイレント映画の到来に立ち会うことができました※18。彼は既に見てきたように科学技術に関心があり、望遠鏡を購入したように新しい機械に対して拒否反応を示すことなく、むしろ興味津々で積極的に受け入れたのです※19。録音に関してはピアノロールや蓄音機に残したものがCD化されています※20。そして映像ですが、動くサン=サーンスの姿を見ることができるのがサーシャ・ギトリ(1885-1957)によるドキュメンタリー映画『祖国の人々』(1915/1952)です※21。残念ながら、1915年の撮影時にはまだトーキーではありませんでしたので演奏の音は残っていませんが、1952年にギトリ本人が思い出話のコメントを追加しています※22。この映画の中でサン=サーンスが演奏しているピアノ曲が《かわいいワルツ op.104》で1896年に作曲されました。
そして、サン=サーンスは「ピアノ練習についての助言」と題した記事を1899年に発表しておりますので、次回それを読みながら、彼のピアノ演奏がどのようなものであったか、さらに探ってみることにいたしましょう。
- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.
CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p. - DANDELOT, Arthur, La vie et l'œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.
- DEBUSSY, Claude, « À propos d' "Hippolyte et Aricie" », Le Figaro, 54e Année, 3e Série, N° 129, 8 mai 1908, p. 1.
- ELLIS, Katharine, « Saint-Saëns and Rameau's Keyboard Music », Camille Saint-Saëns and His World, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. 266-274.
- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.
- GÉRARD, Yves, « Saint-Saëns et l'édition monumentale des œuvres de Rameau (Durand, 1895-1924) », Revue de la BnF, N° 46, 2014, p. 10-19.
- PROUST, Marcel, Contre Sainte-Beuve / Pastiches et mélanges / Essais et articles, Paris, Gallimard, 1971, 1022 p.
(マルセル・プルースト『プルースト評論選II芸術篇』保苅瑞穂編、東京:筑摩書房、2002年。) - SAINT-SAËNS, Camille, « Préface », Pièces de Clavecin, Jean-Philippe RAMEAU : Œuvres complètes, Tome I, Paris, Durand, 1895, p. v-vii.
- SAINT-SAËNS, Camille, BOWIE, Henry P. (tr.), On the execution of music, and principally of ancient music, San Francisco, The Blair-Murdock Company, 1915, 21 p.
(カミーユ・サン=サーンス「音楽、とりわけ古楽の演奏実践について」安川智子訳、『日本チェンバロ協会年報』第5号、2021年、80-85頁、第6号、2022年、94-101頁。) - SAINT-SAËNS, Camille, Au courant de la vie, Paris, Dorbon-Ainé, 1916, 115 p.
(カミーユ・サン=サーンス『音楽の十字街に立つ』馬場二郎訳、東京:新潮社、1925年。) - SAINT-SAËNS, Camille, SORET, Marie-Gabrielle (éd.), Écrits sur la musique et les musiciens 1870-1921, Paris, Vrin, 2012, 1160 p.
- SAINT-SAËNS, Camille et FAURÉ, Gabriel, NECTOUX, Jean-Michel (éd.), Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), 160 p.
(ジャン=ミシェル・ネクトゥー編『サン=サーンスとフォーレ 往復書簡集1862-1920』大谷千正他訳、東京:新評論、1993年。) - SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.
- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.
(ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。) - 井上さつき「古楽復興-19世紀前半のフランスを中心に」、『愛知県立芸術大学紀要』第23集、1993年、31-43頁。
- 井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』、東京:法政大学出版局、2009年。
- 安川智子「サン=サーンス監修『ラモー全集』(デュラン社)再考-古楽復興史の文脈から」『国立音楽大学 研究紀要』第51集、2017年、43-52頁。
- 安川智子「カミーユ・サン=サーンスにとっての「古楽」と「古典」-ピリオド奏法研究の先駆者として」『日本チェンバロ協会年報』第5号、2021年、72-79頁、第6号、2022年、90-93頁。
- 井上さつき「古楽復興-19世紀前半のフランスを中心に」、『愛知県立芸術大学紀要』第23集、1993年、31-43頁。
- 井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』、東京:法政大学出版局、2009年、104-109頁。
- 同上、300-303、 310頁
- Camille SAINT-SAËNS, Au courant de la vie, Paris, Dorbon-Ainé, 1916, p. 14.
- Katharine ELLIS, « Saint-Saëns and Rameau's Keyboard Music », Camille Saint-Saëns and His World, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. 266.
- Claude DEBUSSY, « À propos d' "Hippolyte et Aricie" », Le Figaro, 54e Année, 3e Série, N° 129, 8 mai 1908, p. 1.
ドビュッシーはラモーの歌劇《イポリートとアリシー》(1733)の1908年のオペラ座での再演に際し、「ラモーの神髄を聴こうではないか、これほどフランス的な響きは絶えて久しくオペラ座で聴いたことが無いのだから」と述べています。 - Camille SAINT-SAËNS, « Préface », Pièces de Clavecin, Jean-Philippe RAMEAU : Œuvres complètes, Tome I, Paris, Durand, 1895, p. v.
- 安川智子「サン=サーンス監修『ラモー全集』(デュラン社)再考-古楽復興史の文脈から」『国立音楽大学 研究紀要』第51集、2017年、49-50頁。
- Yves GÉRARD, « Saint-Saëns et l'édition monumentale des œuvres de Rameau (Durand, 1895-1924) », Revue de la BnF, N° 46, 2014, p. 12-13.
- Marcel PROUST, « [Camille Saint-Saëns, pianiste] », Contre Sainte-Beuve / Pastiches et mélanges / Essais et articles, Paris, Gallimard, 1971, p. 382-384.(訳は筆者による。)
- Camille SAINT-SAËNS, Marie-Gabrielle SORET (éd.), Écrits sur la musique et les musiciens 1870-1921, Paris, Vrin, 2012, p. 929. (訳は筆者による。)
- Camille SAINT-SAËNS, Henry P. BOWIE (tr.), On the execution of music, and principally of ancient music, San Francisco, The Blair-Murdock Company, 1915, 21 p.
- レオポルト・モーツァルト(1719-1787)の『ヴァイオリン奏法』(1756)のこと。
Leopold MOZART, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg, Johann Jacob Lotter, 1756, 264 p. - SAINT-SAËNS, Camille et FAURÉ, Gabriel, NECTOUX, Jean-Michel (éd.), Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), p. 89-90.(訳は筆者による。)
- Camille SAINT-SAËNS, Marie-Gabrielle SORET (éd.), Écrits sur la musique et les musiciens 1870-1921, Paris, Vrin, 2012, p. 656.
- Camille SAINT-SAËNS, Au courant de la vie, Paris, Dorbon-Ainé, 1916, p. 16-17. (訳は筆者による。)
- 安川智子「カミーユ・サン=サーンスにとっての「古楽」と「古典」-ピリオド奏法研究の先駆者として」『日本チェンバロ協会年報』第6号、2022年、91頁。
- サン=サーンスが作曲した、芸術作品としての映画音楽第1号の《ギーズ公の暗殺 op.128》(1908)は映画史の中でも有名です。
- 音楽における例としては、サン=サーンスのオーケストレーションが挙げられます。彼はベルリオーズの『管弦楽法』の影響を受け、19世紀の楽器製作技術、特に管楽器における改良、発明を積極的に取り入れました。カンタータ《プロメテの結婚 op.19》(1867)におけるサクソフォン属、《ノアの洪水》において洪水の波を表現するアドルフ・サックス製作の6本ピストンの金管楽器群、オペラ《エレーヌ》(1903)ではコントラバスクラリネットまで登場します。
- 入手しやすいのは、少し値段とかさが張りますが、サン=サーンス没後100周年を記念して発売された、ワーナーの34枚組のボックスセット『サン=サーンス・エディション』でしょう。
Camille Saint-Saëns Edition, Various Artists, Warner Classics, 9029674604. - 原題Ceux de chez nous。公式に動画配信しているサイトやアカウントは無く、DVDはかつてフランスで発売されていましたが2022年12月現在、廃盤になっています。
- このコメントで興味深いのがサン=サーンスが指揮をしているシーンです。ギトリによると「指揮者はいつも背中を客席に向けているので、正面から撮影した」とのことですが、それでは、カメラの後ろにいるのは誰でしょう。なんと、アルフレッド・コルトーただ一人でした。この映画は第一次世界大戦の時代に、フランスの偉大な芸術家の肖像を集めたもので、現在の我々にとっては各界の偉人の動く姿を収めた貴重な史料ですが、当時としてはフランス国民の愛国心を高めるための宣伝も担っていました。よって予算が無いのもさることながら、多くの音楽家は戦地に赴き、大オーケストラを編成することができません。歌劇《ヘンリー8世》のバレエ音楽を80人の大オーケストラで演奏するつもりだったサン=サーンスは、ギトリの説得により少しずつ譲歩を強いられ、編成を小さくすることに同意し、結局コルトーのピアノ独奏を指揮することとなり、たいそう不機嫌でした。そのようなしかめっ面のサン=サーンス、今となっては笑い話ですが、普段見ることのできない貴重な素顔を収めたものなのです。また、コルトーがいるのに画面に映らず、クレジットもされていないというのは、現代の我々にとっては非常に贅沢な映画でもあります。