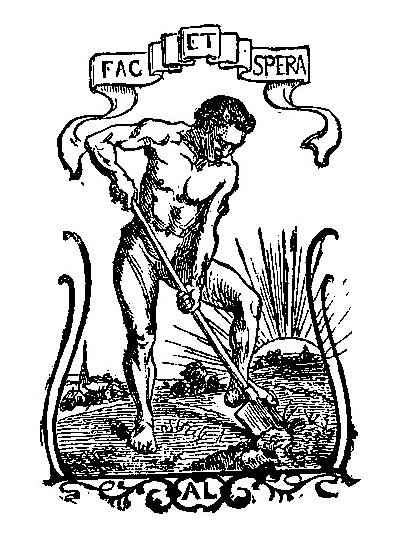第9回 富士山(サン=サーンスと日本3)

さて、作曲活動をほとんど行わなかったこの旅行において、サン=サーンスは何をして暮らしていたかというと、著作活動に専念していました。その中でも、後に『気取りのない詩』(1890)というタイトルの詩集として出版されることになる詩作が興味を引きます。というのも、この詩集の中には「富士山」と「日本」という詩が含まれているからです。いきなり日本が登場することに驚かれるかもしれませんが、なぜ日本をカナリア諸島で夢想したかというと、それは「光」が関わってきます。ジャポニスムとは日本趣味、すなわち日本への憧れということですが、一体ヨーロッパの人々は日本の何に憧れたのでしょうか。代表的な例は、フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)の日本への憧れでしょう。彼は浮世絵を買い集め、自身の作品『タンギー爺さん』(1887)の背景に数点の浮世絵を書き込んでいるのは美術ファンならずとも有名な話です。そして彼は南仏のアルルに移住するのですが、実は、南仏の陽光あふれる世界が、彼にとっての「日本」だったのです※1。なぜ太陽の光が日本につながるかというと、浮世絵には「影」が描かれなかったため、日本は日光が燦燦と降り注ぐまばゆい世界だと勘違いした、という説があります※2。
そして、サン=サーンスもゴッホと同じように照り付ける太陽の下、日本を夢想するのですが、まず一つ目が「富士山」と題された詩になります。
「富士山」
孤独は苦悩する魂に宿る
あらゆる快楽に倦み疲れ、幸福に先立たれ
もはや恐れるものとて無く、慣れてしまった
余りある不幸に彩られた、厳しい運命に対して。
苦しみ泣くお前よ、一人でいることを
恐れなくても良い。しかしお前の不幸を人は笑うかもしれない。
もしお前が陽気な遊び人の傍に座ったならば、
また、祈りを捧げる場所に月並みな輩が押し掛けたならば。
この山はかつて火山であった。時とともに山は荒廃し、
今は火を噴かない。時代は過ぎさった、溶岩が
急流のように美しい山肌に沿って流れていった時代は。
今や不死の美をまとい、
虚空に孤高を持し、重々しい面持ちの雪を頂いた巨人だ、
それはもはや静寂と不動でしかない※3。
富士山というのは今も昔も日本を代表する山ですので、当時のフランスにおいても「フジヤマ、ゲイシャ、ハラキリ」といったように知られていたわけですが、サン=サーンスはもちろん日本を訪れたことはありませんので、どのようにして富士山のイメージを描いたのでしょうか。それを考える上で、前回言及したディエップの資料が非常に重要となります。散逸しているものもあるとはいえ、多くのサン=サーンスの蔵書が残されているからです。その中には日本に関する書物も少なからずあり、1890年より前に所有したことが明らかなものが、エミール・ギメ(1836-1918)著、フェリックス・レガメ(1844-1907)画の『日本散策』(1878)で、その中に富士山の絵があります※4。サン=サーンスの友人テオドール・ビエ(1834-1889)が1879年に贈った献辞が付いています※5。ギメとレガメは1876年に来日し、豪華な挿絵入りの紀行文を残していますが、その一冊です。ギメは東洋美術の収集家として知られ、当時廃仏毀釈の嵐の中、破棄の危機にあった仏教美術をフランスへ持ち帰り、そのコレクションは現在フランス国立ギメ東洋美術館に収蔵されています。パリにはアンリ・セルニュスキ(1821-1896)が収集した目黒の大仏のあるパリ市立セルニュスキ美術館もあり、それだけ当時ジャポニスムが流行したことが窺われます。
サン=サーンスの日本趣味についてお話をすると、彼の交友関係について言及せざるを得ません。というのも「ジャポニザン(日本愛好家)は一日にしてならず」、インターネットなどない時代、いわゆる「口コミ」が日本に関する情報を媒介する重要な手段であり、友人のネットワークがサークルを形成していたからです。日本美術は流行の最先端でしたから、社交界のサロンでも話題となり、日本趣味が共有されていたことはプルーストの小説『失われた時を求めて』でも描かれています※6。しかし一番有名なのは美術商、林忠正(1853-1906)でしょう。彼の店はその名も「日本美術の情報と案内」と銘打たれ、先述のゴンクール兄弟を含む多くの日本美術収集家が出入りするようになり、情報基地である林の店を中心にネットワークが形成されました。ただ、サン=サーンスはオリエンタリストとして有名で研究も多いですが、彼の日本趣味に関してこれまで取り上げられることがほとんどなかったのは、美術品自体に興味があっても収集することにはそれほど関心が無く、林を中心とするサークルの中に登場しなかったからでしょう。
すでにサン=サーンスのジャポニザン仲間としてフレデリック・ヴィヨとアルベール・リボン、そしてルイ・ガレが登場しましたが、今回ご紹介するのはテオドール・ビエです。ビエ社は1782年創業の宮廷や教会向けの衣装や装飾品を製作する工房で、テオドールもその一族でした※7。彼は装飾やデザインに関わっていた人物ですので、当時の日本美術熱に敏感だったのもうなずけます。1868年頃出版のオルガン曲《婚礼の祝福 op.9》の表紙デザインを担当し、1869年作曲の行進曲《東洋と西洋 op.25》は彼に献呈されていますので、それ以前からの古い付き合いであることが分かります※8。《東洋と西洋》はその名の通り、第一部で和声・多声音楽の「西洋」、第二部は単声音楽でリズムに工夫を凝らした「東洋」、第三部で両者が結びつけられて東西融合が図られるという構成になっています※9。青年期の作品ですので、東洋音楽への理解が深いとは言えませんが、サン=サーンスは既に表層的な東洋趣味ではなく、東西交流を尊重しようとしていたことが分かります。
1883年4月2日付のビエからサン=サーンス宛の手紙では新聞の切り抜きが同封され、4月9日に開幕する美術史家のルイ・ゴンス(1846-1921)が企画した日本美術展の告知が記載されていました※10。1878年のパリ万国博覧会で展示された美術品に関し、ゴンスは新旧の美術の2巻に分けて紹介する報告書を出版しましたが、ビエは各巻で「記事、刺繡、タペストリー※11」「古いスペインの刺繍※12」という章を担当しており、古くからゴンスとの付き合いがあったことが分かります。さらに、この2冊ともサン=サーンスは所有し、現在もディエップの市立図書館に残されています※13。この万博では明治政府が代表団を派遣し、シャン・ド・マルスとトロカデロの各会場には日本の展示場が作られ、特にトロカデロの方は「日本の農家」と呼ばれ、またトロカデロの古美術展示会場では日本の古美術品の展示が行われて好評を博しました※14。さらに、この万博において中心的な殿堂として建設されたトロカデロ宮にカヴァイエ=コルの巨大なパイプオルガンが設置され、公式オルガン・コンサートのシリーズの一つとしてサン=サーンスはリサイタルを行い、音楽展委員会のメンバーにも名を連ねていました。公式オーケストラ・コンサートの第1回目においては《プロメテの結婚 op.19》が1867年万博の雪辱を果たすかのように、サン=サーンスの意志でプログラムに入れられ、万博褒章授与式においては《東洋と西洋》が演奏されたのでした※15。サン=サーンス~ビエ~ゴンスというジャポニザンのネットワークができていたことと、先ほどのギメの『日本散策』が1878年に出版されたことを考え合わせると、サン=サーンスが1878年のパリ万博の日本展示を訪れた可能性は高いと考えられます。
そして1886年5月29日のビエからサン=サーンス宛の手紙では、ロンドンで落ち合う日程の相談が書かれた後、「日本の村のどこで日本の刺繡が見られるだろうか?多分ポスターで案内してくれると思うけれど」との文章が続きます※16。実際に二人がロンドンで待ち合わせてブヒクロサンの「日本村」に行ったかどうかは、サン=サーンスの返信が現存していないため断言できませんが、ビエは日本趣味を共有した親しい友人であっただけに、この書簡もサン=サーンスがロンドンの「日本村」を訪れたことの有力な状況証拠となるでしょう。
さて、詩「富士山」において、サン=サーンスはゴッホに代表される当時のジャポニザンとは違った傾向を表明します。この「富士山」における描写は、当時の「フジヤマ、ゲイシャ、ハラキリ」のステレオタイプなイメージ、表層的な異国趣味とかけ離れ、サン=サーンスは孤独で静かな巨人の風格を富士山に見出しています。
それが高踏派の美学でした※17。以前ご紹介した歌曲《死の舞踏》(1872)の詩人、アンリ・カザリスも含まれる高踏派という文学運動は、ヴィクトル・ユゴーらのロマン主義文学の感情過多の表現に反発して生まれたもので、且つそれまでの外交的な政治運動の挫折に端を発した内向的な象牙の塔にこもる運動であったため、形式を尊重し職人仕事を重要視し、個性よりも仕上がりの良さに比重を置きました※18。代表的なスローガンが、テオフィル・ゴーティエ(1811-1872)の「芸術のための芸術」でした※19。その象徴として、西洋古典古代、すなわち古代ギリシアやローマの大理石の彫像の美を理想とします。プロポーションの取れたヴィーナスの白亜のともすれば冷たい美しさは、世俗の塵芥から超越した美として高踏派の詩人に称揚されました。そして、この彫像の美学、不動、孤高、超然、といったキーワードがサン=サーンスの考えるところの「富士山」に当てはめられたのでした。ちなみに、西洋古典古代の大理石のヴィーナス像の白く透き通るような、透徹した美しさは、日本の能面の小面の美とつながりはしないでしょうか。その意味で、普遍的な美しさとしてサン=サーンスは感じ取っていたのかもしれません。後年ですが、サン=サーンスは能に関するパンフレットを所有し※20、現在でもディエップのサン=サーンスのアーカイブに残されています※21。
形式の尊重とは詩においては、ソネといった定型詩を押韻などの詩法に則って彫琢することを指しましたが、サン=サーンスの場合も、ともすれば形式主義者と批判されるほどに古典形式を守った上で音楽を磨き上げました。そしてロマン派の時代にあって感情よりも知性が優先され、アルフレッド・コルトー(1877-1962)が「殺菌処理」と形容するほどに人間味に欠けるとみなされることもありました※22。とはいえサン=サーンスの場合、擬古典的な作品の他に、当時の新しい潮流であった交響詩や循環形式を取り入れていますので、必ずしも高踏派の一言では片づけられない面があります。ただ個性を強調しないがゆえに、柔軟に様々なものを取り入れることができる、折衷主義者でありました※23。
また、高踏派の特徴はその東洋趣味にあります。サン=サーンスが好んだユゴーは『東方詩集』(1829)を残しますが、その「東洋」は中近東にとどまっていたものの、高踏派の詩人たちはルコント・ド・リール(1818-1894)の『古代詩集』(1852)中のインド詩編などさらに遠くへ視線を伸ばし、ジョゼ=マリア・ド・エレディア(1842-1905)の『戦勝牌』(1893)において日本へ到達するのでした※24。
詩集『気取りのない詩』においては、「私の罪(ラテン語表記)」「(永遠の)さようなら」「死(ラテン語表記)」という厭世的な詩、ラテン語やギリシア語のタイトルによる西洋古典古代への憧れ、「グラナダにて」「スペインにて」などの東洋趣味といった高踏派の美学の典型とも言えるテーマを取り上げた詩が並んでいます。サン=サーンスにとって漂泊の旅、隠棲の生活が、まさに象牙の塔に籠った高踏派の詩人の思想と共鳴するものがあったのでしょう。サン=サーンスの音楽作品において彼の感情を読み解くことは困難ですが、このような詩作において、その文学的価値はさておき、作曲家研究としてその心の内を垣間見ることができます。
- BERTHOD, Bernard et HARDOUIN-FOUGIER, Élisabeth (éd.), Dictionnaire des arts liturgiques, XIXe-XXe siècle, Paris, Les Éditions de l’Amateurs, 1996, 462 p.
- BONNEROT, Jean, Camille Saint-Saëns ; Sa vie et son œuvre, Paris, Durand, 1922, 241 p.
- CHANTAVOINE, Jean, Camille Saint-Saëns, Paris, Richard-Masse, 1947, 117 p.
- CORTOT, Alfred, La Musique Française de Piano, 2ème série, Paris, Presses Universitaire de France, 1948, 252 p.
(アルフレッド・コルトー『フランス・ピアノ音楽2』安川定男、安川加壽子訳、東京:音楽之友社、1996年。) - DANDELOT, Arthur, La vie et l’œuvre de Saint-Saëns, Paris, Dandelot, 1930, 297 p.
- GALLOIS, Jean, Camille Saint-Saëns, Sprimont, Pierre Mardaga, 2004, 382 p.
- GOGH, Vincent van, Lettres de Vincent van Gogh à Émile Bernard, Paris, Ambroise Vollard, 1911, 152 p.
(『ファン・ゴッホの手紙』、二見史郎編訳、東京:みすず書房、2020(2001)年。) - GONSE, Louis (éd.), L’Art ancien à l’Exposition de 1878, A. Quantin, 1879, 566 p.
- GONSE, Louis (éd.), L’Art moderne à l’Exposition de 1878, A. Quantin, 1879, 510 p.
- GUIMET, Émile, (dessins par RÉGAMEY, Félix), Promenades Japonaises, Paris, G. Charpentier, 1878, 212 p.
(エミール・ギメ『1876ボンジュールかながわ』青木啓輔訳、横浜:有隣堂、1977年。) - ICKOWICZ, Pierre et JOVANOVIC, Cécile (éd.), Paris-Dieppe-Alger. Camille Saint-Saëns, 1835-1921, Dieppe, Musée de Dieppe, 2021, 119 p.
- MIYAMOTO, Heikouro, Le Nô Drame Lyrique du Japon, Paris, Bibliothèque de la Société, 1911, 14 p. (Extrait du Bulletin de la Société Franco-Japonaise de Paris. N° XXIII-IV. Sep.-Déc. 1911.)
- PROUST, Marcel, « Du côté de chez Swann », A la recherche du temps perdu, vol. I, Paris, Gallimard, 1946 (1913), 296 p.
(マルセル・プルースト『失われた時を求めて 1 (スワン家のほうへ 1)』吉川一義訳、東京:岩波書店、2010年。) - RATNER, Sabina Teller, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, 628 p.
- SAINT-SAËNS, Camille, Harmonie et Mélodie, Paris, Calmann-Lévy, 1885, 318 p.
- SAINT-SAËNS, Camille, Rimes familières, Paris, Calmann-Lévy, 1890, 131 p.
- SAINT-SAËNS, Camille, École buissonnière, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1913, 363 p.
- SAINT-SAËNS, Camille et FAURÉ, Gabriel, NECTOUX, Jean-Michel (éd.), Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), 160 p.
(ジャン=ミシェル・ネクトゥー編『サン=サーンスとフォーレ 往復書簡集1862-1920』大谷千正他訳、東京:新評論、1993年。) - SERVIÈRES, Georges, Saint-Saëns, Paris, Félix Alcan, 1930, 219 p.
- STEGEMANN, Michael, Camille Saint-Saëns, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch, 1988, 156 p.
(ミヒャエル・シュテーゲマン『大作曲家 サン=サーンス』西原稔訳、東京:音楽之友社、1999年。) - 饗庭孝男他(編)『新版 フランス文学史』、東京:白水社、1992年。
- 寺本敬子『パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生』、京都:思文閣出版、2017年。
- 西岡文彦『謎解きゴッホ』、東京:河出書房新社、2016年。
- 森英樹(訳)『パルナッシアン詩句抄』、東京:青山社、1994年。
- Vincent van GOGH, Lettres de Vincent van Gogh à Émile Bernard, Paris, Ambroise Vollard, 1911, p. 76.
1888年[3月18日頃](アルル)フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)よりエミール・ベルナール(1868-1941)宛
「君に手紙を書くと約束したので、まずはこの土地[=アルル]が僕には日本と同じように美しく見えると話すことから始めたい。とりわけ、空気が澄んで、明るい色彩の効果と言ったら。[中略]淡いオレンジ色の日没の光が大地を青く見せている。まばゆいほどの黄色い太陽だ。」(筆者訳) - 西岡文彦『謎解きゴッホ』、東京:河出書房新社、2016年、74頁。
- Camille SAINT-SAËNS, Rimes familières, Paris, Calmann-Lévy, 1890, p. 82-83.
- Émile GUIMET, (dessins par Félix RÉGAMEY), Promenades Japonaises, Paris, G. Charpentier, 1878, p. 129-131.
- フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。
Souvenirs bien affectueux. / Th. Biais / 1 Janvier 1879. - Marcel PROUST, « Du côté de chez Swann », A la recherche du temps perdu, vol. I, Paris, Gallimard, 1946 (1913), p. 69.
有名なマドレーヌの場面、記憶が蘇る様子がたとえられている比喩は、日本の水中花なのです。これが作品の根幹をなす「無意志的記憶」となっています。そして、何とサン=サーンスは日本の水中花の空箱を大事に保管していて、現在もディエップ市立博物館に残っています(下記カタログに写真あり)。
Pierre ICKOWICZ et Cécile JOVANOVIC (éd.), Paris-Dieppe-Alger. Camille Saint-Saëns, 1835-1921, Dieppe, Musée de Dieppe, 2021, p. 34. - Bernard BERTHOD et Élisabeth HARDOUIN-FOUGIER (éd.), Dictionnaire des arts liturgiques, XIXe-XXe siècle, Paris, Les Éditions de l’Amateurs, 1996, p. 31.
- Sabina Teller RATNER, Camille Saint-Saëns (1835-1921) / a thematic catalogue of his complete works, vol. 1, New York, Oxford University Press, 2002, p. 101, 243.
- Camille SAINT-SAËNS, Harmonie et Mélodie, Paris, Calmann-Lévy, 1885, p. 13-14.
「東洋人は旋律とリズムの研究を非常に発達させたが、和声の存在は知らなかった」というのが当時のサン=サーンスの東洋音楽に対する認識でした。(記事の初出は1879年。) - フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。
- Louis GONSE (éd.), L’Art moderne à l’Exposition de 1878, A. Quantin, 1879, p. 438-460.
- Louis GONSE (éd.), L’Art ancien à l’Exposition de 1878, A. Quantin, 1879, p. 459-463.
- フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。
- 寺本敬子『パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生』、京都:思文閣出版、2017年、278-279頁。
- 井上さつき『音楽を展示する パリ万博1855-1900』、東京:法政大学出版局、2009年、134、159-161、167、付録45頁。
- フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。
- 1971年のサン=サーンス没後50周年を記念したフランス国立図書館の企画展のタイトルが「サン=サーンス:高踏派の作曲家」でした。
サン=サーンスの声楽作品においては、初期はユゴーの詩に作曲されたものが多いですが、1890年代に入ると《愛し合おう》(1892)のように、高踏派のテオドール・ド・バンヴィル(1823-1891)の詩への作曲例が見られます。 - 饗庭孝男他(編)『新版 フランス文学史』、東京:白水社、1992年、219-221頁。
- サン=サーンスも自身の評論記事のタイトルに用いています。
Camille SAINT-SAËNS, École buissonnière, Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1913, p. 135. - Heikouro MIYAMOTO, Le Nô Drame Lyrique du Japon, Paris, Bibliothèque de la Société, 1911, 14 p. (Extrait du Bulletin de la Société Franco-Japonaise de Paris. N° XXIII-IV. Sep.-Déc. 1911.)
- フランス、ディエップ市立メディアテック・ジャン・ルノワール、サン=サーンス資料部所蔵。
- Alfred CORTOT, La Musique Française de Piano, 2ème série, Paris, Presses Universitaire de France, 1948, p. 66.
- Camille SAINT-SAËNS et Gabriel FAURÉ, Jean-Michel NECTOUX (éd.), Correspondance (1862-1920), Paris, Publications de la Société Française de Musicologie (Éditions Klincksieck), 1994 (1973), p. 35.
- 森英樹(訳)『パルナッシアン詩句抄』、東京:青山社、1994年。