第29回 秋山徹也先生


東京・文京区で「秋山徹也音楽研究所」を開いて、9年目を迎えられます。
「秋山徹也音楽研究所」の特徴は、「アナリーゼ」を重視し、「理論と演奏とが一致するように、総合的に音楽を捉える指導を行う」というところ。最終的に、生徒が「自力で音楽を分析・解釈し、音楽的に表現できるようになること」を目指されています。
現在では、小学1年生から50代まで、趣味の人からハイアマチュア、受験生やコンクール挑戦者まで、さまざまな生徒が長期間レッスンに通われ、また、ピアノの生徒以外にも、弦楽器や管楽器などの生徒が3割程度いらっしゃいます。
そんな「秋山徹也音楽研究所」の日常のレッスンの様子と、現在までの教室の展開を追いつつ秋山先生の指導理念について、レポートします。
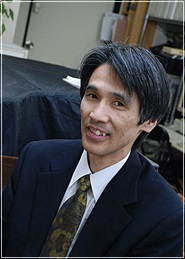
2.グランプリ金子一朗さんにきく(1)レッスンの目的
3.グランプリ金子一朗さんにきく(2)レッスンの効果
4.継続表彰50回中村香織さんにきく・本番までのレッスン過程
5.最年少金賞受賞者(F級)高尾奏之介さんにきく・小2から現在まで
6.ソルフェージュのグループレッスン
アナリーゼ重視のレッスンを行う総合音楽教室として、現在に至る経緯とは?
秋山:教室の創設当初から考えていたことは、「音楽を正しく理解し音楽的に演奏するには、曲の正しい理解とそれを可能にする総合的な能力訓練が必須だ」ということ、そのために、「ソルフェージュ力の養成・音楽理論などの指導をベースに、自力で音楽分析・解釈・表現をできるようにさせ、実際のピアノ演奏に結びつける指導をしていきたい」ということでした。しかし「総合的な訓練を」といっても当初理解されませんでしたし、「総合的なピアノレッスンを」といっても元来ピアノ専攻でない私のところをわざわざ選んでくる生徒は少ないわけで、実績のあった音楽学校受験用のソルフェージュ教室、が主体とならざるを得ませんでした。
流れが変わり始めたのは、アナリーゼが演奏する上で本当に必要なことである、と認識してくれる生徒が現われ始め、かつその効果がはっきりわかるようになってからです。アナリーゼの重要性を感じてくれる生徒が何人か現われると、教室全体の雰囲気が、そして内外の認識が、大きく変わったように思います。小学生など、まだ音楽学校受験を直接意識してはいない層が、積極的にソルフェージュ・アナリーゼの重要性を認識し始めたのです。まだまだ発展途上の教室ですが、ソルフェージュ指導から出発してアナリーゼを重視した総合的音楽指導に、ほぼ方向はかたまりつつあります。自らの経験・考え方・能力・適性に応じて、ゆきつくところにゆきつつある、という感じにはなってきました。

リサイタルを1ヶ月後に控えていらっしゃいますが、今日のレッスンで見ていただくポイントは?
金子:「とりあえず全曲聴いていただこう」と。自分で分析は全てしてきますので、それがどこまで音になっているのか、というところをきいてもらっています。やっぱり自分で考えている音楽と、ピアノから響いている音楽が、一致しない事がありますから。
解釈したことが、実際の演奏にどれくらい反映されているのか、ということですね。
金子:特に、各声部の意識の配分ですね。ピアノの曲は、声部が多く、互いにある程度セーブしているところに意味がある訳だけど、それを全部意識するのは、やはり困難じゃないですか。個々のことはある程度できていても、客観的に聴いてもらうとバランスのとり方も分かりやすくなるというか。ある意味、僕が「オーケストラ」で、秋山先生が「指揮者」というような関係ですね。
先ほどのレッスンでも、秋山先生と金子さんで、「ああではないか、こうではないか」みたいなやり取りをされながら、さかんに「バランス」の調整をされている印象を受けました。
秋山:聴く側としては、まずどういう解釈で弾いているかということをうまくきき出して、その解釈に即して意見を言うようにしています。でないと、演奏者の最初に考えた解釈がめちゃくちゃになってしまいますからね。その上でバランスを考える。その解釈ではこれはちょっとやり過ぎではないかとか、逆ではないかとか...。

金子:あとは、自分の解釈の修正、ですね。でも、解釈自体を根本から直されることは、あまり無いかなぁ・・。
秋山:無理に人を強制するのが好きではないんです。いろいろな解釈があるのだから、自分の解釈と違っても、それを言葉にはするかもしれないけれど、自分の解釈を絶対押し付けてこうしろとは言いません。ただ、どのような解釈で考えても、これはちょっとどうかなと思うことについては、修正をすすめますが・・。
金子:譜面を読みこんでいると、「ここの解釈はどっちなの?」と、何通りかの解釈ができて悩むことってあるじゃないですか。そんなときに、先生の考え方と自分の考え方と照らし合わせることができるというのは大きいですね。作曲家的立場の考え方が分かる先生だから。"もしここがこうだと考えるならば、こっちはこうあるべきでしょう"というように。
解釈の裏付けですね。
金子:解釈が割れる時にここに来ると、まあ、秋山先生も迷宮に入る事もたまにあって・・・。
秋山:ありますよ(笑)、すべて単純に割り切れるものでもないですから。
金子:「いや?、わっかんねーなー、これ・・」みたいな顔して、しばらくカチコチになってしまうこともあって。そういう時は、ああ、僕が悩んでいるのも当たり前だったんだ、と安心したり(笑)。
なるほど。金子さんの大切にしている部分を、さらに強く持っていらっしゃる。金子さんにとって、最大の共感者なんですね、秋山先生は。
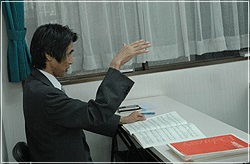
金子:そうですね。僕のこんなにこだわっていることを理解してくれない先生だと「何でそんな所にそんなにこだわる必要があるんだ」って言われてしまう・・(笑)。僕にとってはそれは大問題なんですけれど。逆に不遜な言い方かもしれないけど、僕が求めるものを求めるだけ教えてくれる先生だ、ということです。それを教えられない先生についても、意味がないと思うし。

秋山先生からみて、この2年で金子さんがいちばん成長されたのは、どのようなところですか?
秋山:なんか上手くなったなーと思いますね、私がいうのも何ですが(笑)。実際に聴こえる音楽のバランスがすごく良くなりました。これは間違いない。
金子さんご自身では?
金子:秋山先生のレッスン受けてから、「どの時代様式だろうが、どの作曲家だろうが、全てに根底に流れている共通の概念があって、同じ考え方で全てを表現できるものなんだ」ということを、自分の中で確信を持たせてもらえたということですね。バッハでもドビュッシーでも、弾く時に意識することや僕の頭の中で考えていること、つまり聴く方法や、アイテムや、要素というものは、何も変わらない。いろんな作曲家の作品を次から次へとレッスンに持ってきても、結局考える視点はあまり変わらないんだということを、実感させられました。
なるほど。それは、どのようなところで活かされますか?
金子:たとえば、聴いたことがない作品でも、人の演奏を聴いて、(ああ、この人はここが出来ていて、ここは出来てないんだな)というのが、パッと分かるようになってきましたね。誰がどんな作品の何を弾こうと、最初の何小節か聴いただけで、その人の演奏というのが透けて見えてしまう・・・。先日たまたまあるコンクールで秋山先生と居合わせたのですが、秋山先生の評価と僕の評価と照らし合わせたら、これがもう気持悪いほど一緒なんですよ(笑)。実際のコンクール側の結果も、極めてそれに近いものでした。ああ、結局聴いているところは、あまり変わらないんだな、という確信がもてました。

今まで特定の指導者につかず、大部分を独学でやってこられた金子さんですが、定期的にレッスンに通われるようになったわけは?
金子:やっぱり定期的に通っていると、次から次へと曲を仕上げないといけない。だから、新しい曲をレッスンに持ってくることが、自分にとってどんどんレパートリーを増やすエネルギーとなっています。1年で結構な分量なので、非常にキツイんですけど・・。
どれくらいですか?
秋山:多い時は、1週間で渡す曲が、ほかの人の1か月分くらいですね。
金子:3か月か4か月くらいで1リサイタル、だから年間で3リサイタルか4リサイタル分くらいの曲を、新曲でどんどんみてもらっています。不思議なことに、レッスン受けて、演奏が確定すると...忘れないんです。ちょっとそれを引きずり出して、何日か時間があれば、自分なりにしっかり再現することができる。だから、今現在頭の中にある、表現可能な作品のデータベースが、ここに通うようになってから膨大な量に膨れ上がって、今10リサイタル以上のレパートリーは、確実にあると思います。
単純な暗譜ではない、ということですよね。
金子:丸暗記ではなく、表現上の確信が、レッスンで完全に結びつくから、忘れないんですね。「あ、間違えた、これじゃないや、こっちだ」というレベルの間違えはありますが。
秋山:彼の場合、ペースは早過ぎるくらいですよ。
金子:何を持って来ても教えてくれますからね。シマノフスキのメトープとか、普通に教えてくれるし。
秋山:たとえ、あまり知らない曲でも、それは一緒に考えますよ。
金子:でも基本はやっぱり、構成とか和音とか音楽理論上の学問があった上で、ここでレッスンを受けても理解できるのだと思います。
秋山:周囲からときどき言われるのですが、われわれがレッスンで何を話しているのか分からない、横で聞いていると、何か宇宙語で会話しているようだ、と。そういったアナリーゼのバックボーンがない人だと、そのバックボーン自体を指導するところから始めていくわけです。それが、金子さんの場合は、全部ありますからね。

入門のきっかけは?
(前述の)金子一朗さんの持ち歩いている楽譜をみて、自分も楽曲分析ができるようになりたい!と思い立つも、一人ではどうにも歯がたたず、それで秋山先生の教室を探し当てたのが、3年前のことです。その金子さんが、私のホームページのレッスン日記をみて、逆に「なんだ?この先生、面白そうじゃん!」と言い始め、結局、彼も秋山先生の門下になられたわけですが・・。また、入門当時10歳だった高尾奏之介くんが、ふつうに楽曲の分析をしている様子をきいて、さらにショックを受けました。(笑)
秋山先生のレッスンには、どのように臨んでいらっしゃいますか?
初レッスンの前には、少しでもアナリーゼの予習をしていくようにしています。古典派ソナタなど和声分析しやすいものは、全小節の予習をしてから初レッスンにいきます。バッハの本格的なフーガになると、和声分析だけでは不十分なので、今度は主題や対旋律やその断片たちを何色かの色鉛筆で塗り分けるといった「構造」に関わる分析が予習の主体になります。近現代の作品、たとえばドビュッシー後期などは、予習しようにも私にはまだ調性の確定さえおぼつかず歯がたたないので、要所要所の転調などで色を変えるべきだろうと思われるところだけざっくりイメージして、他はなにも出来ずにいきなりレッスンに持って行ってしまうこともあります。
しかしどんなに予習して、秋山先生のレッスンにもっていったところで、実際自分の出した音が果たしてイメージしているように鳴っているかと言われると、初回レッスンはたいてい箸にも棒にもかからないひどい状態です・・・。
曲を仕上げるまでに、どのくらいみていただいていますか?

私の場合は、同じ曲をだいたい20回以上はレッスンしていただいていますね。最初の5回ぐらいまではとにかく、どこにどういう線を引かなければいけないのか、どこにどういう色を塗る予定なのか、つまり絵画でいうところの素描(デッサン)を描きながら確認する作業がレッスンの主体になります。曲が仕上がって本番が近づいてくるとデッサンもほとんど確定し、そうなると今度は個々のパーツの入念なバランス調整がレッスンの主体になってくるように思います。
同じ作曲家の作品をいくつか続けてやると、だんだん作曲者の語法に慣れて応用が効いてくるので、楽曲分析そのものはスピードが速くなります。でも最後のバランス調整は、やはり自分一人の耳ではまだ相当に限界があるようで、先生の耳を借りてフィードバックにつぐフィードバックの繰り返し作業。こうして本番(主にコンクールなど)を迎える、というのが、だいたいのレッスンの過程です。
秋山先生のレッスンで、もっとも効果絶大だったのは?
バッハですね、それも対位法の究極の形態であるフーガのレッスンです。とにかく、徹底して各パーツの構成を追求したあと、それに基づいて微に入り細にわたる猛烈なバランス調整を要求されます。「主題と対旋律のバランスを5対4、ないしは6対5ぐらいで。」とか平気でおっしゃいます。「3対2では調整がかえって困難だから、せめて5対4か、6対5ぐらいがいいでしょう」とか、そういう厳密な世界です。ともすると、そこまで厳密な音量のバランスを演奏中に自分で聞き分ける耳さえ持てていない気がします。秋山先生はこの手のバランス調整に関しては猛烈な地獄耳!です。多分5対4かと6対5の違いでも聞き分けられる先生だと思います。私は野放しで演奏すると、いつもソプラノばかりワンワンと大きく弾いてしまう癖があるので、バッハのレッスンはそのソプラノ優位の矯正も含めて、まさにやってもやっても底なし沼!(笑)でも、バッハが課題曲になるコンクールでここ数年まあまあの成績が出せていることを振り返ると、ソプラノしか意識できていなかったバッハ音痴な自分も、ここ数年でずいぶん矯正されてきたかなぁと、嬉しく思います。
秋山先生のレッスンの通いやすさは、どこにありますか?
基本的に、曲を解釈するうえで答えが一通りではないもの、つまり自由度がある部分については、先生はいっさい考えを押し付けてくることはありません。先生が答えを押し付けて来ないかわりに、こちらが自分なりの答えを持っていなければいけないわけですが・・・。自由度が無い部分、つまり、どこからどう解釈しても「それは無理があるんじゃないの?」ということについては直されるという感じなので、テンポや歌い回しを直される事はほとんど皆無であると思います。私は演奏におけるテンポや歌い回しは生理的な個人趣味の幅が相当あると思っているのでこれを直される先生だと精神的にすごく辛いのですが、解釈の自由度の範疇である場合はそういうものに矯正の声がかかることはまずないので、すごく精神的に楽ですね。
秋山先生には、ソルフェージュのレッスンも受けていらっしゃるそうですね。

私、実は絶対音感も相対音感も「無い」のです。訓練をうけていないので。じつは、これが、本番で「暗譜がわからなくなった」ときに非常に危険だと気付いたんです。ほんの5~6年前のことですが、演奏本番中、ハッ!と次が分からなくなったとき、次の音が頭のなかに鳴っていても、それが鍵盤のどこの音かわからない。当然、そこで手が止まってしまいます。あるいは、えいっままよ!と一瞬の判断で分からないまま、あてずっぽうで鍵盤を押すと、これがぜんぜん見当はずれなとんちんかんな変な音をガーン!と押してしまい、演奏が台無しになるどころか、客席から爆笑されて半泣きになった経験さえもあります。
秋山先生も、私が、音がわかっていないままドビュッシーなんか弾いていることに対して、「よくこんな恐ろしい状態で弾いてるもんだ・・・綱渡りだ。」と半ば呆れておられました(笑)。絶対音感は当然おありの秋山先生には、とくと説明して、絶対音感も相対音感も欠如した人間がとんちんかんな音を出して落ちるメカニズムというものを、知っていただきました。音感を身につけるのは時間もかかることなので、徐々に訓練していかないと仕方がないね、ということで、ソルフェージュのレッスンもこうして続けているのです。

小2というと、ピティナのコンチェルト部門で最年少で最優秀賞を受賞した年でしたね。
高尾:はい、この頃から、秋山先生に音楽分析を教わり始めました。自分自身で曲を深く理解した演奏をするためには、ピアノだけでなく、「音楽の考え方」を学びたいと思ったので。はじめは厳しい先生かなと思いましたが、とてもやさしい先生で、やや数学の塾みたいなレッスン室ですが(笑)、大好きなところです。
かなり高度な分析もされているそうですが、最初は難しくなかったですか?
高尾:最初は先生も「小学生の低学年に和声を教えるのは初めてだけど、まずはやってみるか」みたいなことを話されていましたが、いつも(小学生である)僕と同じ目線で教えていただいて、とてもわかりやすかったのを覚えています。ソルフェージュや和声から始め、その後、楽典も勉強しています。ピアノの松崎伶子先生も、秋山先生に和声を習っているおかげで、ピアノのレッスンがスムースで非常にやりやすいと言ってくださっています。
秋山:もともと表現力養成の基本は和声にあると思っていたので、最初から和声を重点的にやってみたいと考えていました。手頃な教材を見いだせなかったため、大人が用いるテキストを説明しながら使うことにしましたが、理解が早く、意外にできるものだと感心しながら進めたように記憶しています。ソルフェージュは、早くから訓練した方が良いですから、当然こちらも平行して行いました。

このような基礎訓練は、やはりコンクールでの演奏などにもいかされていますか?
高尾:特に、近現代に向かうにつれて、型から離れ自由さが増して、曲の理解が難解になるので、分析することの大切さを改めて実感しています。昨年の学生音楽コンクールなどで、フォーレのノクターンを演奏したのですが、内容が濃くて奥の深いといわれるフォーレの最晩年の曲を理解するのは、はじめはとても難しいと思っていました。でも、先生方と一緒に考えていくうちに、曲が体の中にしみこんで来るような感じがしました。分析して、作曲家の想いを読み取って、それを音にしていくにつれて、フォーレのこの曲がとても好きになりました。(小学校の部で全国一位を受賞)

秋山:学生コンクールの頃には、和音の種類をひととおり覚え、すでに相応の表現方法をかなりわかっていたので、いちいち説明しなくても、分析によって適切でバランス良い表現をできるだけの力は持っていたと思います。学生コンクールは、選曲段階と仕上げ段階で深く関わることになりましたが、派手なパフォーマンスやテクニック、パワーで魅せる曲ではなく、地味で渋く、さりげなく多彩な色分けが必要な曲を選んだため、和音の理解がなければ良い演奏は不可能だったと思います。
秋山先生のレッスンでは、アンサンブルの勉強もされるそうですね。
高尾:はい、アンサンブルのレッスンも、とても楽しいです。(教室内の)生徒同士でオーケストラのパートを分担し、ピアノや電子ピアノで初見演奏するという訓練があって、そこでは、ベートーヴェンの交響曲などをやりまし
秋山:キーボードアンサンブルは一種遊び感覚の訓練ですが、弾き直しできないし常に先を読まなくてはならないので初見の力がつきますし、ハ音記号を用いた楽譜や移調楽器の楽譜にも慣れます。それに、いろいろな名曲をオーケストラの楽譜と音の両面から知ることもできます。勉強会では実際に、いろいろな楽器でアンサンブルしました。アンサンブルすることによる効果は想像以上に大きいと思っていますよ。
高尾:室内楽との共演の場があることも、とてもありがたいです。昨年は、ベートーヴェンやモーツァルトのピアノトリオを、バイオリンとチェロとはじめて共演しました(新宿ステップ)。今年は、7名編成のオーケストラと一緒に、ショパンのピアノ協奏曲第1番の1、2楽章を演奏しました(文京春日春季ステップ)。普段のピアノ独奏とは違って、共演いただく皆さんに合わせる難しさがあって、でも、演奏が上手く行った時に一緒に喜べる感覚もあって、とてもよい勉強になりました。
秋山:オーケストラは、教室出身の音大生主体に編成しました。弦楽器と実際に合わせての協奏曲を体験することは、弦楽器の演奏習慣などを理解できる、非常に貴重な機会だと考えています。トリオは教室内の生徒同士で演奏することにこだわっています。一人の表現がかわると全体に与える影響が協奏曲以上に大きく、個人の意志が強く出てくることになります。演奏者間で自由に意見を出し合うことができるよう、師弟関係でない方が良いですね。バランスをとる練習過程で、否応なしに聴く耳が養われたと思います。


適切な和音進行をつけられる音楽的な教材を選んで実施。単に書き取るだけでなく、書き取った後は和音伴奏をつけて歌うが、その伴奏は生徒にその場でつけてもらうことも多く、伴奏づけの練習としても活用。

できるだけ美しい伴奏のついた教材を歌う。伴奏部分は、ピアノ初見視奏としても用いることが多く、ハ音記号を用いた楽譜も積極的に歌っている。

リズムだけを打つ練習、歌いながらリズムをうつ練習に加え、リズムアンサンブルも行う。途中で拍子が変わるような曲にも挑戦される。



今日の曲目は、モーツァルト交響曲39番。パートに分かれ、また、適宜交代しながら、オーケストラスコアを、ピアノや電子ピアノで視奏していく。生徒の中でも大人気のレッスンのようだ。弦楽四重奏?五重奏なども含め、1ヶ月に2曲くらいのペースで皆で選曲して演奏する。勉強会では、実際に楽器で演奏発表することも。



<河合実咲さん&お母様>
ピアノを習っている先生から、「実咲ちゃんにピッタリな先生だと思うわよ」と紹介されたのが、小1のとき。すぐに、秋山先生にピタッとなじみ、ソルフェージュのレッスンは丸2年になる。「私もピアノを習ってきましたので、小さい時期にこそ、基礎能力を育てるのは大事だと痛感していました。」とお母様。背丈も小さくあどけない姿から想像もできない音楽を見せる実咲ちゃん。大人の生徒さんからも、ペットのように可愛がられているという。
<黒沼香恋さん&お母様>
入門して8ヶ月。「私がピアノをやってきていないので、1曲1曲どう弾くかというのを自宅でサポートしきれなくなり、自立して曲を理解してもらわないと、と思って、先生を探したのがきっかけでした。」とお母様。耳がよく、耳から覚えて弾けてしまっていた香恋ちゃんも、ソルフェージュの基礎訓練により、読譜力が上がり、今や初見視奏が得意になってきた。また、今までピアノ曲ばかり聴いていたのが、交響曲や室内楽と、自ら進んで聴くジャンルも拡がってきたという。「アンサンブルの訓練が特に楽しい。ヴァイオリンとか他の楽器もやりたくなります。今度は、ベートーヴェンの交響曲7番をピアノで演奏してみたいです。」

秋山:いろいろな音楽体験をしてもらう目的で冬に勉強会を開いています。ピアノ独奏以外に、教室内ピアノトリオなど室内楽や弦楽アンサンブル、弦楽アンサンブルでのピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ即興演奏、新曲発表、歌曲、ソルフェージュアンサンブルの発表、などを行ってきました。弦楽器や管楽器、声楽、作曲などの生徒がいるからこそできる独自の企画ではないかと存じます。このうち、弦楽アンサンブルでのピアノ協奏曲を、今年5月の文京春日春季ステップの企画に取り込みました。今後もさらにいろいろな体験をしてもらおうと考えています。
秋山:理論や分析というと、どうしても頭でっかちの... と思われがちで、音楽性とは相容れないことのように言われやすいのですが、そうではありません。音色表現は大事だし、レガート表現も大事です。これらを節度をもってバランス良く表現するためにこそ、理論の裏づけが必要なわけです。今後とも、感性や音楽性を大事にした総合訓練に携わりたいと考えています。

