第7回(最終回)ピアノを通して何を学ぶのか
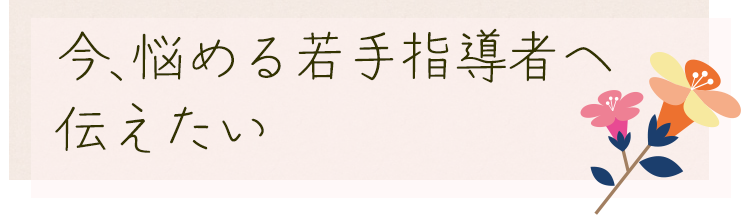
この連載では、お若い先生方へ私の経験をお話してきました。やはり一番重要なのは生徒さんがピアノレッスンに通って「何を得るか(=目的)」ではないでしょうか。
私がピアノレッスンを通して何を学んでいただきたいかは後ほどお話しするとして、例を挙げながらお話ししていきましょう。
例えば、コンクールにおいても目的を見失わないということはとても大切なことです。
金賞という結果を求めることは「目標」であり「目的」ではないはずです。今自分が目指している音楽や学習している内容を深めるために参加することが目的です。賞を取る為にコンクールに出ることを目的としてしまうと大きな落とし穴に陥ってしまうことを経験しました。
指導者と生徒さんが今取り組むべき課題をより深く学び、それに対して評価を得ること。それを成長につなげることがコンクールに参加する目的なのだと思います。だからこそ、ここでも常にコミュニケーションが重要であり、「何の為に」「なぜ」という会話を続けることが大切です。
日頃のレッスンにおいても段階的に音楽的にも人としても成長してほしいと思っています。一足飛びで与える課題ではなく、無理をさせない一歩一歩の積み重ねが大切だと思います。コンクールに出ていない生徒も発表会で輝けるように演奏を磨きます。その生徒の「少し頑張れば届く目標」を設定して達成する喜びを感じてもらうように工夫しています。
私はピアノのレッスンを通してピアノの技術や音楽の知識を深めることはもちろんのこと、「生徒一人一人の性格や環境から成る個性が音色を作る」音楽の楽しみを知ってもらいたいと願っています。多くの出来事を全身全霊で「体感」することを通じて、生徒一人一人の心が豊かになると信じています。
「心の豊かさ」と言いましたが、そこには一言ではとても表しきれない、喜怒哀楽の全てが詰め込まれています。ピアノを続けていると「いいこと」ばかりではないかもしれません。時には悲しいことや辛いことも経験するかもしれません。それでも、それらはすべて心の豊かさに繋がっていくはずです。
私も指導を続けて多くの年月が経ちましたが、数年前にもこのようなことがありました。とあるコンクールで思うような結果が出ず親子で大泣きしていました。私はそれまでの努力が足りないことを知っていたので会場で人目も憚らず叱咤しました。
しかし2年後、同じコンクール、同じ会場で金賞を取りました。その2年前に伝えたことは「その涙に見合うだけの努力が出来ていたのか?」「悔しいと思うなら本気で努力をしなさい」ということでした。その親子とも日頃から本気で向き合っていたからこそ伝わってくれたのだと思います。結果が出たことも嬉しいですが目標を持って努力をし続けた事、それこそがコンクールに参加する目的だと改めて感じた機会となりました。彼女はこの経験から「音楽をもっと学びたい」「自分もこういう事を伝えられる先生になりたい」と、音楽の高校へ進学してくれました。とても嬉しいことです。
こういう経験は学校生活や普段の生活でもとても役に立つことだと思います。元生徒には音大を出ている人もいますが、他の分野で活躍している人も数多くいます。海上自衛隊に勤めている元生徒も制服を着てたまに挨拶に来てくれます。いつも「厚地先生との厳しいレッスンに耐えてきたからこそ訓練にも耐えられています」と笑いながら言ってくれます。
他にも、当時高校の強豪野球部に所属しながらピアノのレッスンに来てくれていた生徒は監督から厳しい指導で部員たちが泣きながら練習していた時も一人だけ泣かずに「厚地先生のレッスンの方が厳しかった」と話してくれていました。
では私のレッスンがどのように厳しいかというと・・・
生徒さんがわからない事、出来ない事で叱ったりすることはありません。一方で、音楽の1音や1小節を徹底的に追求する姿勢が欠けているときや、練習に対する取り組み方の甘さは許しません。前の章でもお話ししたように「やる」と約束したにも関わらず「やらなかった」場合などには檄が飛びます。だから私の生徒さんはみんな一生懸命やることに慣れています。「妥協しない」ことをレッスンを通して覚えていくのです。私はレッスンの時間は徹底的に、他での厳しさを凌ぐ程生徒に向き合っています。結果として、自衛隊や強豪野球部といった「厳しい」とされる環境に進んで飛び込む生徒も出てくるのでしょう。
しかしながらレッスンが終わる(ありがとうございました、のご挨拶の後)と精一杯のハグをして良く頑張ったねと褒めます。ここでは先生と生徒という立場も超えて、人対人という立場で最大級の愛を持って接します。
オンとオフの使い分けはとても重要だと思います。
それも前の章で述べた「目線に下りる」ということにも繋がります。
とあるコンクールでの演奏中に失敗しそうになったところで「背中に厚地先生の気配を感じてそこから演奏が上手くいった」と言ってくれた生徒がいました。
そのようにレッスンでは徹底的に、レッスンを離れたら愛を持って接することが私への安心感や信頼感に繋がり、二人で作り上げた演奏になります。音楽を楽しんでくれていることも感じています。
その為にも疑問を残したままにしない、丁寧なコミュニケーションが必要です。「先生に怒られないように練習しよう」ではなく、「褒められたい、認められたいから練習していこう」というようなマインドに持っていくよう心掛けています。
他人から見れば些細なことに見えるかもしれなくとも、変化や努力が見えた時にはすぐに褒めます。生徒本人も、褒められた内容に意識が働いて自分の音を聞くようになったり、人の話に耳を傾けてくれるようになります。
このようなことを通じて、私の教室に未就学児の頃から通い始めると、高校生くらいになるとレッスンでも1を言うと先回りして10を感じてくれる生徒になります。そうなるとお互いの信頼関係はしっかりとしていますし、音楽の楽しみ方もわかってきます。私も生徒の音楽が楽しめている状態になります。
こういった積み重ねによって、自ら考えて行動出来る人間になっていくことを嬉しく思います。それこそ私がピアノを通して身に付けてほしい能力でもありますし、社会に出た時に役に立つ力です。
最近では指導をなさっている先生方でも私のレッスンを受けに来てくださったり、色々な悩みを相談しに来られる先生が増えてきました。生徒さんや保護者も同様ですが、先生方にも「素の自分」で向き合うようにしています。お一人お一人への言葉がけや言い回しもそれぞれに合わせて変えるようにしていますし、同じ目線でお話しようと心がけています。いつもお話しているのは「あなたにしか出来ないレッスン、あなたにしか育てられない生徒さんがいるんだよ」ということです。
これまで沢山の話にお付き合いいただき、ありがとうございました。
私も多くの失敗を重ねてきました。
私のやり方が絶対に正しいかどうかはわかりませんし、他にも良い方法がたくさんあると思います。
皆さんお一人お一人がそれぞれに合ったやり方を見つけることも大切ですから、そのやり方に自信を持ってやってみてください。自分を信じて、好きになってください。
そして、私たちの仕事は子どもを光らせることです。自分ではなく生徒を「光らせる」人になりたいと思います。謙虚に頑張りましょう。


