第6回 ピアノ指導の土台作り:十人十色な生徒たちに相対するには…
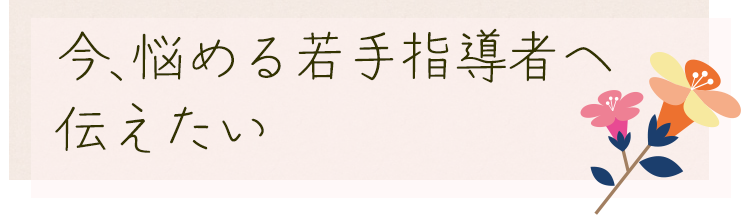
ピアノ指導において、まずは挨拶に始まり挨拶に終わることが大前提です。私の場合、レッスン室へ入って来た時の雰囲気や声色で「生徒が今日はどのような状況か」という事を見極めることから始めます。これは毎回のレッスン毎に必ず行なうルーティンとなっています。
例えば、明るい調子で入ってきた生徒さんはこちらも笑顔でそのままレッスンへ移行できますが、暗い雰囲気や声色で入ってきた生徒さんは、学校で何かあったとか何かしらの原因があります。そういう場合はレッスンでの集中力も散漫になります。そういうことが続くとピアノももちろん上手くいきませんし学校でも上手くいかないものです。
私自身はピアノのレッスンだけでなく、生徒さんの話を聞くことを大切にしています。何があったのかを一緒に原因を見つけ出し、一緒に悩み解決するようにとことん話しを聞きます。生徒さんの話を聞き、悩みを解決することは30分や60分のレッスン時間の中で、ピアノを弾くことよりも、もっと重要だと考えています。
しかし、レッスン歴がまだ少ない生徒さんの中には「この悩みを言ったらお母さんにも伝わってしまうのかな…」と心配する子どもさんもいます。そのような時は「お母さんに言って欲しくないことは言わないから聞かせて」という風に生徒さんにも安心感を持って話してもらえるように心掛けています。指導者が生徒さんとの約束を守るという事も大切ではないでしょうか。
上記で述べたように寄り添う姿勢を示すのがこの『目で話す』ことです。生徒さんと話す時に楽譜を見ながら他へ目線をやって話すのではなく、生徒さんの目を見て話す事がとても重要です。これはレッスン中でも同様です。
指導者自身がまず生徒さんの目をしっかりと見て話す事、生徒さんも私の目をしっかりと見ているのかどうかが大切です。「目は口ほどに物を言う」というように目が虚ろな生徒さんは何かあります。練習しなかったことをごまかそうとしている、といったことです。目を見ないで「今日練習して来た?」、「はい」などと会話をしたところで中身のない会話になってしまいます。
大人として身に付いた癖で難しい言葉を使ったり、これぐらいわかるだろうと思って話してしまいがちです。例えば、スラーでドレミファソと繋げて弾くという私たち指導者にとっては簡単な事でも、小さい子どもさんにとっては簡単ではない事です。
それを教えようとする時に、指導者の私たちがその生徒さんの目線に下りてお話しやわかりやすい例えを使って教える事がとても重要です。そう考えていくと小学1年生の生徒さんと5年生の生徒さんでは話す中身が違ってくる事は当然です。
ここで1点だけ注意してほしいことは、レッスンの際に『生徒の目線におりる』というのはあくまでも、話を聞く(分かり易くレクチャーする)ということであり、主導権は指導者がキープしておかなければいけないということです。経験の浅い(若い)指導者の中には、生徒さんや保護者へ気を遣い過ぎて安易に謝る方もおられると思いますが、そうなると主導権が損なわれ、かえって信頼関係に亀裂が生じる場合もあります。


