「質」と「量」の交差点で、ピアノ練習・熟達化を科学する(前編)
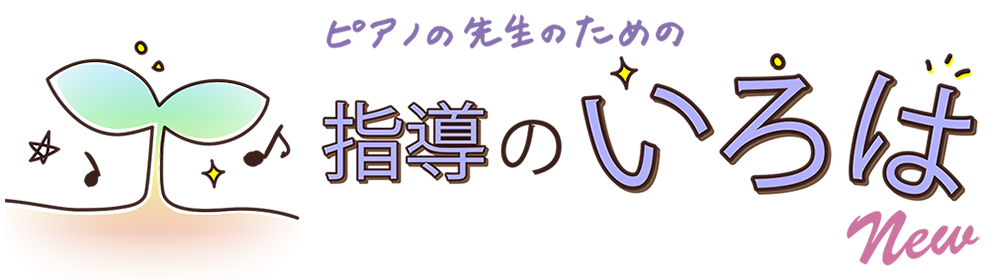
執筆:大澤 智恵
「練習は量より質」「……などと言っていないでやっぱり量をこなしたほうがよい」……こんなお話をされたことがある方は多いのではないかと思います。どちらにも一理あるように思えますし、一方を推したいという方も多いかもしれません。「量」と「質」とは何を表しているのか、ふと立ち止まって考えてみると、だんだんわからなくなってくることがありませんか?
例えば「質の高い練習」の「質」が指すものは、何でしょうか。集中していること、たくさん考えていること、検討された適切な内容、時間あたりに弾く音の数……? といろいろな種類のものが思い浮かびます。
そして、「量をこなす」という場合の「量」も、時間であったり、回数であったり、曲数であったり、あるいは音の総数であったり……。
今回は、こうした日常での使い方からちょっと離れて、研究で「質」と「量」がどのように使われているかを少しみてみたいと思います。指導の中で、「質」と「量」を語るときのヒントになるかもしれません。
練習に関する議論で、よく登場する「1万時間の法則」。これは、ある分野でプロになれるような熟達には、のべ1万時間以上のトレーニングが決め手となる、というものです。1993年にエリクソンらが発表した研究で、様々なレベルの演奏者への練習時間に関する調査の結果、「意図的で緻密な、入念な練習」、“delibarate practice” の総時間が熟達の決め手になると述べられました(Ericsson et al., 1993)。
才能ある人は長時間の練習を要さないのではないかと考えられていた当時、この研究は注目を集め、「1万時間の法則」は一躍有名になり、様々な分野で引用されて、もてはやされるようになりました。
半ばひとり歩きを始めたこの法則は「量」の側面に強く光を当てたものと理解されていましたが、実際の研究や、その後の批判的研究、そしてそれを踏まえたエリクソンの補足と反論をたどると、単に「時間が多ければ上達する」というだけの話ではありません。「どんな練習を、どういう意図で、どのように行ったか」という、「質」的な側面が常に関わっています。
このように考えていくと、物事を説明するとき、「量」と「質」はそもそも切り離せない関係にあるといえそうです。
さて、研究でいう「質」「量」とはそもそもどういう意味でしょうか。
たとえば、ある現象を言葉で表すとき、私たちはそれが「何」であるか、またその出来事の「性質」や「特徴」などが「どのような」ものであるかを、多くは主に言葉で、記述します。これが「質(qualitative)」の側面です。
一方で、その現象についてよく知りたいとき、私たちは「いくつ」「どのくらい」「どのような頻度で」などといった、数値で表すことのできるような側面に注目します。これが「量(quantitative)」の側面です。
つまり、「質」と「量」は、「何」が「どのくらい」あるかを示す「情報」の2つの側面で、物事を記述する上ではどちらが欠けても十分に意味をなすことができません。一方、同じ現象を観察するのにも、どちらの側面をじっくりと見ようとするかで、見えてくる風景が変わってきます。
音楽の練習で考えると、「何をどう弾いたか」「どんな目的でその練習方法を選んだか」などは質的側面にあたります。
「何分間弾いたか」「何回繰り返したか」「1回で何小節続けて弾けたか」「音符をいくつ弾いたか」など、数量で表せるのが、量的側面です。
「Aさんは、最初しばらくゆっくり練習し、少し休憩して、その後テンポを上げて短時間弾きました。」
と書いた場合、その状況を質的に記述しています。
ここに量的な情報をいくつか足すと、例えば次のようになります。
「Aさんは、最初の24分間、平均テンポ♩= 55 で練習し、3分休憩した後、テンポを♩= 70に上げて7分間弾きました。」
教育学や心理学、認知科学などの分野では、「質的情報」「量的情報」どちらに注目した研究もたくさん行われています。それぞれの特長をまとめてみましょう。これから先生方の関心に応じて研究論文や学術的な資料を読まれる際に、どちらの性格の強い論文だろう?と少し考えてみてから読み始めると、読みやすくなるかもしれません。
「質」を主に興味の対象とする「質的研究」・・・練習についての研究であれば、練習中の思考や意図や、細かく「何」をしていたか、また、指導者と学習者の関わりなど、書く人が注目したものについて事象を多角的かつ丁寧に記述します。これまでに注目されていなかったけれど新たに研究の対象にしてみたい新しい行動や現象などを探索するのにも優れています。
「量」を主に興味の対象とする「量的研究」・・・注目すべきものをあらかじめ決めておいた定義に沿ってある意味淡々と、測定したり、数えたりして、ある程度たくさんのデータを揃えたうえで、「こんな関係がある」「こんな因果関係がありそう」という判断は確率論的に、数学的に行います。研究者の主観と独立した分析・判定ができるので、単に「私はこう考えた」と主張するよりも強力に、例えば「そう思うのはあなただけでは?」という反論に強い記述ができます。
「質」と「量」を対立的に考えると、「どちらが大事か」という議論になりがちです。
けれども、研究の言葉でいうと、「どちらも大事」であり単なる情報の2側面とも言えます。
たとえば、練習時間を数値として記録する(量的)だけでは、練習の中身や意図は分かりません。そして練習内容の詳細な記述(質的)だけでは、どのくらい反復したか、どの程度のばらつきがあるかは見えてきません。
一方で、「質」「量」どちらかの側面に一貫してしっかりと焦点をあてると、それぞれにおいて、新たな発見を得ることができます。
さて、「質」と「量」の話をしていましたら、予告でお伝えしていた「2つの研究」の紹介に入る前にかなり字数をオーバーしてしまいました。
次回の「後編」では、ピアノ練習を対象にした二つの草分け的研究、Gruson(1988)とWilliamon(2002)の研究を取り上げます。
同じくさまざまなレベルにある演奏者・学習者の練習過程を追いかけた研究ですが、前者はどちらかというと「質的側面」に注目して、さまざまにカテゴライズされる練習の現れ方がどのように変化していくかを分析しています。
一方、後者は「量的側面」に徹底して焦点をあて、どのくらいの単位でまとめて弾いていたかという「練習のまとまり」を数値化した実験から得られた発見を報告しています。
一見、対照的に見える二つの研究が、実はひとつの「練習行動にみる熟達のプロセス」を別の角度から照らしている——。
その交差点を、一緒に見ていきましょう。
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363-406.
APA PsycNet - Gruson, L. M. (1988). Rehearsal skill and musical competence: Does practice make perfect? In J. A. Sloboda (Ed.), Generative processes in music: The psychology of performance, improvisation, and composition (pp. 91–112). Oxford University Press.
- Williamon, A., Valentine, E., & Valentine, J. (2002). Shifting the focus of attention between levels of musical structure. European Journal of Cognitive Psychology, 14(4), 493–520.
Taylor & Francis online

音楽教育学者・音楽心理学者。信州大学教育学部卒業、同大学院修士課程修了、東京学芸大学連合学校教育学研究科において論文提出による博士(教育学)。演奏中の知覚認知と運動制御に注目して基礎技能研究を進めている。武庫川女子大学音楽学部応用音楽学科准教授。
次回も大澤先生のご担当です。「質」と「量」 それぞれの角度から、いかにしてピアノ練習が語られるのか。研究を通して新たに見えてくる景色とは……!? お楽しみに!

