子どもの発達特性に合わせたレッスンの工夫
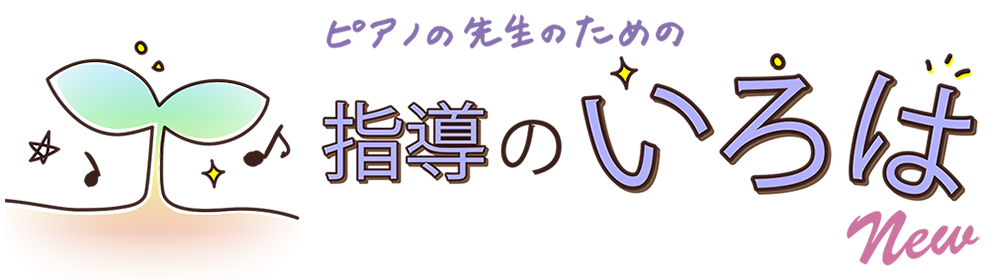
回答:金井智恵子
第10回は、演奏以外の場面で感じる「指導のむずかしさ」や「子どもとの向き合い方」に焦点を当て、先生方の日常的な「困った!」へのヒントをQ&Aの形式でいただきます。
通常、課題がある部分について、何が問題なのかを説明して、生徒がいまどう演奏しているかを誇張して真似た上で、模範演奏(お手本)を示す、という方法を取っています。でも、説明中や模範演奏を示している間に、すぐ自分で弾こうとしてしまうなど、とにかく集中して説明を聞くのが難しい生徒がいます。「まずは聞いてね」と伝え、音は出さずにこちらを向いてくれても、どこかソワソワしていて、ちゃんと聞いてくれているのかわからず、伝わっていない感じがします。小学校低学年です。
小学校低学年の子どもは、「話を聞く」より「自分でやってみたい」という気持ちが強い時期です。例えば、「ここは小さく弾こうね」と言ったそばから弾き始めてしまうのは、よくみられる光景です。そんな時は「先生の音をよく聴いて、次にまねっこしてね」と遊びのルールのように伝えると入りやすくなります。説明は短く区切り、「右手だけ一緒にやってみよう」など小さな動作に分けて巻き込むことが効果的です。
また、「まず聞いて」と言うより、「今の音、どんな感じだった?」と子どもの感想を引き出す問いかけを入れることで、主体的に耳を傾ける力が育っていきます。
レッスン以前の問題かもしれないのですが、私の感覚では、小学校1年生にもなれば、30分のレッスンの間はピアノの椅子にじっと座って、演奏したり先生と話したりできると思うのですが、すぐに立ち歩き、部屋の写真や置き物を見たり、犬の声の方に向かっていったりする生徒がいます。「まずは座ろう」と声をかける時間ばかりが長くなっていて、これではピアノのレッスンが成り立ちません。音楽は好きそうで、自分の好きな曲を弾いている時は楽しそうですので、レッスンが嫌で逃げている感じはしません。とにかく落ち着きのない子どもを前にした時、どんな工夫ができるのか、また、何に留意したら良いのかなど、ヒントがいただきたいです。
30分のレッスンをじっと座って受けるのは、就学して間もない多くの子どもにとって実は大変なことです。置き物や外の音などに注意が向いてしまう時は、「今日は3つのことをやろう」と小さなホワイトボードや紙に書くと安心感が生まれます。
「①指ならし(基礎練習) ②ドレミの歌 ③好きな曲」などと書き、できたら「はなまる」や「シール」をつけると、達成感が目に見える形で残ります。
途中で立ち歩いても「この次の音でピアノに戻ろう」と肯定的な言葉掛けで誘導すると、自己否定感を持たずに注意を戻せます。リズム遊びなど体を動かす時間をあえて入れると、集中が自然に戻っていきます。
小学1年生のレッスンについて悩んでいます。自宅ではのびのび表現ゆたかに演奏しているらしいのですが、レッスンでは音量や表現の変化がない平坦な演奏をします。どこか遠慮しているように見え、うつむきがちで、ほとんど声を聞いたことがありません。何か尋ねたい時は、見学の保護者を通して話すしかなく、本人との直接の対話は望めません。学校でも、特定の先生以外とは話さないようです。
レッスンでは、部分練習をしたり、途中から弾いたりといった指導には応えられるので、理解力は問題ないように思います。高圧的な接し方はしておらず、他の生徒にも、怒られた記憶はないと言ってもらえるため、優しく接することができていると思うのですが……。まずはレッスン室が過剰な緊張の場にならず、遠慮なく会話ができたり、演奏できたりできる場にしたいのですが、どうすれば、そのような関係を築けるのか、できることを知りたいです。
家庭ではのびのび弾けるのに、レッスンではうつむきがちになる子どももいます。大切なのは「弾く」よりもまず「安心していられる」場を作ることです。
最初の5分ほどは「どんな音が好き?」と聞きながら、自由に鍵盤を触れる時間を設けると表情がやわらいでくるのではないかと思います。
また、「静かに聴いてくれているね」「今の音、とてもやさしいね」といった小さな変化や努力をその都度言葉にして伝えることも大切です。無理に話しかけず、「今日はこの曲を一緒に弾こう」と並んで弾く経験を重ねるうちに、子どもは少しずつ自信を取り戻していきます。
小学5年生の男児について、「うちの子は自閉スペクトラム症と診断されています。音楽の授業は好きで、よく自宅のピアノの鍵盤を触っているので、演奏を学ばせてみたいと思うのですが、レッスンに通えますか?」と保護者から相談を受けています。自閉症の方への指導経験がなく、受け入れられるのかが不安です。でも、これを機に勉強しながら、ピアノを演奏したい子への門戸を閉ざさずにいたいとも思います。どんなことに気をつけたり、保護者から事前に提供いただいた方が良い情報や、どのような連携の取り方をしていったら良いかなど、受け入れるとしたら留意するべきことを知りたいです。
自閉スペクトラム症のある子どもは、次に何が起こるかが分からないと不安になりやすい傾向があります。レッスンでは、「順番」や「時間の見通し」を共有できる工夫が有効です。
例えば、「この曲を弾いたら休憩」「3回弾いたらおしまい」など、数や順序で区切りを明確に伝えると安心して取り組めます。必要に応じて、写真やイラストを使った簡単なスケジュールカードを用いるのも効果的です。
また保護者には、「集中が続く時間」「苦手な刺激」「落ち着く対応」などを事前に伺うと良いでしょう。レッスンの中で「できた」「楽しい」を一緒に味わうことが、音楽を通じた学びと信頼関係の第一歩になります。
視野が狭く、焦点を定めることが苦手という5歳さんへのレッスンをしています。リズムが誤っている時など、楽譜をよくみて、と指差ししても、とんちんかんな場所を見ています。また、リズムや音が誤っていることを指摘すると、パニックを起こしたように頭を掻きむしってしまいますので、誤りを指摘するのを躊躇してしまいます。どんな関わり方の工夫が考えられるでしょうか。
視覚的な焦点合わせが難しい子どもは、「見て理解する」より「聴いて・感じて理解する」方が得意な場合があります。
誤ったリズムを指摘するより、「この部分を手拍子で一緒に感じてみよう」と体感的に直す方法が効果的です。
楽譜の場所を指す時も、色付き付箋やマーカーで視覚的手がかりを増やすとわかりやすくなります。
間違えた時に頭をかきむしるような反応は、「失敗」への怒りではなく「混乱」からくるものだと思います。そんな時は「ここ少し難しいね」「一緒にやってみよう」と安心を伝える言葉を添えることで、再挑戦する力が育っていきます。
子どもたちはそれぞれ異なるリズムで、異なる方法で世界を感じています。
「集中できない」「落ち着かない」と見える行動の背景には、発達の特性、不安、感覚の違いが隠れていることもあります。
少しの工夫で、「できた!」「楽しい!」という経験が増えていくことを、日々の臨床や支援の中で感じています。
ピアノのレッスンも同じです。見える工夫と安心の関係づくりを通して、子どもの心が音とともに伸びていく時間を、大切にしていきたいものです。

東京医科歯科大学大学院(現・東京科学大学大学院)医歯学総合研究科博士課程修了。医学博士。専門は臨床発達心理学。子どもから大人までの発達障害に関する研究をテーマとしている。現在、和洋女子大学人文学部こども発達学科教授。
次回からは、「演奏をめぐる科学」を共通テーマに、いろいろなアプローチで演奏に迫った研究を紹介します。日々のレッスンへの「なるほど!」が散りばめられているはず。まずは、熟達化の意外な側面に迫ります。大澤智恵先生がご担当です。お楽しみに!

「質より量」「量より質」——よく耳にするこの言葉。
練習について考えるときにも、きっと一度は意識したことがあるのではないでしょうか。でも、「質」と「量」を研究の言葉として定義し直してみると、ちょっと違った見方や発見ができるかもしれません。
次回は、ピアノ練習と熟達化をこの2つの側面から見つめた研究をご紹介します。

