「できる喜び」を積み重ねるレッスンの工夫—注意力と集中力の課題を乗り越える視点—
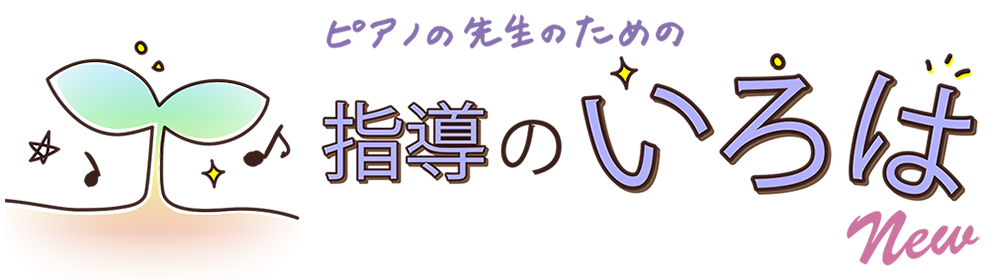
執筆:大滝恵
「ピアノの前に座ってくれない」「話をしている間も鍵盤を触っていて聞いてくれない」―ピアノを指導する中で、このような悩みを耳にすることは少なくありません。発達に凸凹がある生徒さんや、発達がゆったりな生徒さんの場合、「レッスン以前の問題」として語られるこれらの行動が、より顕著に現れることがあります。これは単にやる気がないということではなく、脳の発達特性や注意の仕組みによるものである場合も多いのです。とりわけADHD(注意欠陥多動性障害)の場合、不注意、多動性、衝動性などの不適切行動は中枢神経系の障害によるものであり、子どもがやりたくてやっているわけではないと理解することが大切です。
脳が一度に処理できる情報量には限りがあります。心理学では、たくさんの情報の中から、状況に応じて必要なものに集中し、それ以外を無視する力を「選択的注意」と呼びます。この選択的注意の下支えにより、私達は効率的に注意をコントロールして情報の取捨選択を行うことができます。しかし、脳の特に前頭前野がまだ発達段階にある幼児期や発達に凸凹がある子どもでは、一時的に情報を保持しながら物事を処理する脳の働き(ワーキングメモリ)がまだ弱い上に、多数の情報を詰め込もうとして収拾がつかなくなったり、強い刺激に注意を奪われたりしやすくなります。テレビを観ている子どもに声をかけても気づかないことがあるのと同じで、ピアノの前では「先生の話」より「鍵盤」に注意が向いてしまうのです。さらに、発達に凸凹のある子どもには視覚優位のタイプが多く、なおのこと目で見えているものに注意を引き寄せられやすい傾向にあるため、鍵盤を触りたくなってしまうのです。
注意は「スポットライト」のように働きます。焦点を当てた対象の処理は促進されますが、その外にある情報の処理は抑制されます。つまり「先生の声」に焦点を向けて欲しい時には、余計な刺激を減らす環境調整や、注意を切り替えるきっかけづくりが大切になります。例えば鍵盤の蓋を閉める、話をする前に「これから大事なことを言うから、先生を見てね」と視線を誘導する工夫が有効です。ピアノという楽器の特性から、指導者と生徒は横並びの位置関係になることが多く、生徒の視線は自然とピアノの方に向かってしまいます。注目を促す声かけがあることで、視覚優位であっても「先生の声」に耳を傾けやすくなるのです。また、言葉での説明は短くし、実際に「やって見せる」等の視覚を活かす工夫をすることで、理解しやすくなります。
もちろんピアノの鍵盤だけでなく、レッスンで使用する打楽器やグッズなども、使用する時以外は箱に入れたり布をかけたりして見えないようにする、ピアノのハンマー等の楽器内部が見えにくいように譜面台位置を調整しておくことも、注意の持続への助けとなります。
持続的に座って取り組むことが苦手な生徒さんのレッスンでは、座って行う活動を減らすのも一つの方法です。ずっと同じ姿勢でいると、前頭前野の覚醒度が下がりやすいですが、リズム課題やメロディー暗唱を立って行ったり、お手玉や腕の体操等のピアノ演奏に繋がる動きを伴う活動を行ったりすることで、脳の血流がよくなり、集中しやすくなります。また、海馬近くにあるグリッド細胞は「移動」によって活性化されることが知られています。記憶をつかさどる海馬とグリッド細胞は連携して働くため、場所や身体の向きを変えること自体が、学習の定着を促すきっかけになるともいわれています。
さらに大切なのは、子ども自身の「やってみたい」と思う気持ちです。指導者の感覚では「今のこの子ならできるはずの課題」であっても、子どもが「できそう」と思えなければ、取り組もうとしないことも少なくありません。脳内では成功を予感した瞬間にドーパミンが放出され、意識や集中のスイッチが入ります。そのため、この「できそう」という感覚は、やる気と集中力を引き出す上で非常に重要なのです。スモールステップを大切にするだけでなく、その課題の提示の仕方にもコツがあります。「ゆっくりやって見せる」ことが効果的で、「できそうだからやってみたい」気持ちを引き出すことができます。1フレーズでなくて良いのです。たった2音を違う指で弾くことだけでも、その生徒さんにとっては「できた!」と自信をもつきっかけになるかも知れません。その自信が、次の挑戦への原動力となります。小さく細分化した課題であっても抵抗が見られる場合は無理に続けず、一旦得意な活動・好きな活動に切り替えて、レッスンの最後に「そういえばさっきの〇〇やってみる?」と持ち掛けまたゆっくりやって見せると、生徒さんの気持ちも整っていて「やってみる!」と言ってくれることも多くあります。※注釈1
座れなかった子が1分座って取り組めたなら、それ自体を褒めてあげましょう。1分が2分になり、3分になり……30回目のレッスンでは、30分座ってピアノを弾いているかもしれません。
小さな小さな成功体験の積み重ねが、新しい挑戦につながっていきます。「できる喜び」を何度も経験し次のチャレンジをしながら、子どもたちは少しずつ集中力や注意力を育んでいきます。それとともに、必ず音楽的スキルも発達していきます。指導者がその歩みに寄り添う時、ピアノ教室は「ピアノ演奏の技能を習得する場」にとどまらず、自己肯定感や自己効力感といった、子どもの心の成長を支え、生きる力を育む大切な場となるでしょう。
- 以下の記事で指導上の工夫例を具体的に説明しています。併せてご覧ください。
「障がいのある生徒へ「個」を理解したレッスンを」
https://license.piano.or.jp/news/2023/04/iroha_015.html
- 苧阪直行編(2013)『注意をコントロールする脳―神経注意学からみた情報の選択と統合』新曜社.
- 北西卓磨・松尾直毅(2015)『海馬体―嗅内皮質における空間認知システム』[オンライン]https://leading.lifesciencedb.jp/4-e001(2025/10/10最終閲覧)
- 永江誠司(2004)『脳と発達の心理学』ブレーン出版.

京都市立芸術大学ピアノ専攻卒業後、東京藝術大学大学院修士課程修了。大学院では音楽教育研究室にて広汎性発達障がい児のピアノレッスンに関する研究を行い、応用音楽研究室にて、音楽療法の理論と実践を学ぶ。白梅学園大学・短期大学、東京工学院専門学校非常勤講師。
次回は、演奏以外の場面で感じる「指導のむずかしさ」や「子どもとの向き合い方」に焦点を当て、臨床発達心理学の専門家である金井智恵子先生に、レッスン運営のヒントを伺います。お楽しみに!

子どもの集中が続かない、落ち着かない、言葉を交わすのが難しい…。
そんな場面に出会った時、指導者はどのように関わればよいのでしょうか?
臨床発達心理学の視点から、発達特性に合わせたレッスンの工夫と、子どもとの信頼関係づくりのヒントを紹介します。

