自分で「できた!」が生まれるピアノレッスン—モンテッソーリ教育のアプローチに学ぶ、子どもの意欲を育む関わり方—(後編)
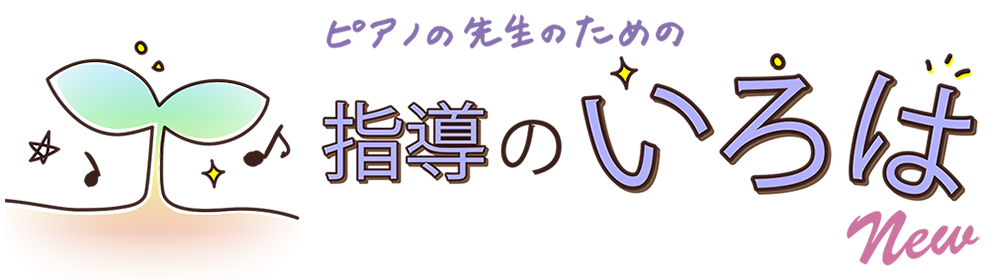
執筆:藤尾かの子
前回に引き続き、今回もモンテッソーリ教育の視点から、子どもの主体性を大切にするピアノレッスンの工夫を考えていきます。前回の記事では、モンテッソーリ教育の根底に、「子どもは自ら育つ力を持っている」という考えがあることを紹介しました。私たち大人に求められるのは、子どもの潜在的な力が自然に発揮されるように、適切な援助を行い、「環境」を整えることです。 ピアノレッスンにおいては、つまずきやすい子どもに対して「もっと丁寧に教えよう」と思いがちですが、教えること以上に大切なことは、「何を、どのように、どこまで伝えるか」です。
今回は、モンテッソーリ教育で特に重視される「提示」というアプローチを中心に、その土台となる「課題の難しい部分を一つに絞り込む」という考え方も交えながら、ピアノレッスンに活かせる具体的な工夫を探っていきます。
ピアノレッスンで、子どもがうまく弾けない場面は、多くの先生が日々経験していることでしょう。ピアノの演奏は、「譜読み」「指の動き」「ペダル」など、多くの要素が複雑に絡み合っています。それゆえ、音を間違える、リズムがずれる、指づかいを誤るなど…。そのような時、先生はつい、「この部分もできていないから教えよう」と、一度に複数の指導をしてしまいがちです。
しかし、良かれと思っての熱心な指導が、実は子どもの混乱を招いていることも少なくありません。先生は課題を明確に把握できていても、子どもは「たくさん言われすぎて、どこに注意すればいいのか分からない」と感じているかもしれません。子どもは「できない」のではなく、「すべきことが多すぎて整理できない」——この視点に立つことで、子どものつまずきへのアプローチが大きく変わってきます。
モンテッソーリ教育では、子どもが理解しやすいように、大人がやってみせる「提示」という方法を大切にしています。ポイントは、「言葉数を最小限にし、モノの扱いを美しく、明確に見せること」です※注釈1。子どもは年齢が低いほど、言葉による複雑な説明を理解することが難しいです。そのため、指導者は「見せること」を通して、子どもが直感的に学び取る力を最大限に尊重する必要があります。
そして、この「提示」をより効果的に行うために、その前提として「教えたいことを一つだけに絞り込む」という準備が欠かせません。多くの要素が絡み合った難しさの中から、伝えるべきことを一つだけ取り出すのです。例えば、
- 指づかいを提示するなら、音を鳴らさずに指の動きだけを見せる。
- リズムを提示するなら、鍵盤を使わず、手拍子だけで体感させる。
このように課題がシンプルになると、子どもは「何に集中すればよいのか」が明確に分かり、安心して音楽に向き合えます。
大切なのは、子どもが「一度に全部できるようになる」ことではなく、「今、一つの課題に集中して乗り越える」ことです。「提示」を用いた小さな成功体験は、子ども自身に「できた!」という達成感をもたらし、次への意欲を自然に引き出すきっかけとなるでしょう。
こうした「提示」や、その背景にある「難しい部分を一つに絞る」という考え方は、技術的な指導法であると同時に、「子どもの潜在的な力を信じる」という指導者としての姿勢の現れでもあります。レッスンをする中で、「ここもできていない」とか、「あそこも直さなければ」と思うのが先生の自然な感覚です。しかし、子どもが安心して学ぶには、「今日はこれができたら良い」と課題を絞って示すことが必要です。そして、「あなたなら、これに集中すればきっとできる」と静かに背中を押してあげることが、子ども自身の成長の足場になります。
こうした関わりを続ける中で、モンテッソーリ教育で言う「自己教育力」——すなわち、「自ら学び、自分で育とうとする力」が少しずつ育まれていきます。小さな成功体験を重ねた子どもは、自分で次の課題を選び、「もっとやってみたい」という前向きな意欲を高めていきます。
レッスンにおける先生の役割は、すべてを教えることではなく、子どもが自分の力で成長していけるような関わり方を心掛けることです。課題を1つに絞り、すべきことを明確に提示し、できると信じて待つ——その一連の関わりが、子どもの中に「自分でできた!」という体験を積み重ねていきます。
レッスンが「受け身で取り組む時間」から「納得しながら、自分の力を発揮できる場」に変わると、子どもは自発的に音楽に向き合い始めます。ピアノの音の響きに触れながら、自分なりの「美しさ」や「音楽的感性」を働かせ、どのように弾けば理想の音が出せるかを試行錯誤していく中で、自然と音楽的な感覚や美的感性が育まれていきます。また、こうした過程を経て、タッチや指の使い方、音の出し方といった技術的な工夫にも意識が向き始めます。そして、思い描いた音に少しずつ近づけたという実感が、自己肯定感や達成感へとつながっていくのです。 ピアノを通して育まれたこれらの感覚や、試行錯誤の中で身につけた技術は、ピアノ演奏の場面のみならず、人生のさまざまな場面でも活きる、自分を支える内面的な力となるのではないでしょうか。
- モンテッソーリ教育の「提示」(または「提供」と訳されることもあります。)についてより具体的に学びたい方には、以下の書籍を推薦します。
相良敦子(2013)『お母さんの「発見」―モンテッソーリ教育で学ぶ子どもの見方・たすけ方—』文春文庫.

音楽教育学者。エリザベト音楽大学卒業、同大学修士課程修了。広島大学博士後期課程修了(博士(教育学))。専門はモンテッソーリ教育と幼児音楽教育学。兵庫教育大学学校教育学部講師。
次回は、「自分の力を発揮できる場」としてのレッスンづくりと関連して、具体的な展開に焦点が当たります。ピアノ講師で音楽教育研究者の大滝恵先生がご担当です。ご自身のご経験と科学的見地から語られるレッスンづくりの工夫とは!? お楽しみに!

発達に凸凹がある生徒さんや、発達がゆったりな生徒さんの指導に悩んだことはありませんか?
次回の記事では「集中力」と「注意力」に焦点を当て、脳科学の知見を交えながら「学びの効果を高める工夫」「子どもの心の成長を支えるために心がけたいこと」この2つの視点から考えてみたいと思います。

