「教えすぎない」ことの大切さ—モンテッソーリ教育に学ぶ指導のヒント—(前編)
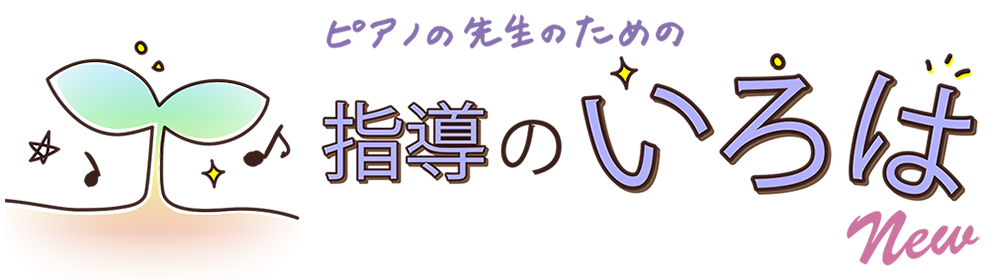
執筆:藤尾かの子
レッスンをしていると、「もっとこの子に合った教え方はないだろうか」とか、「少しでも早く上達できるように助けたい」と思うことがあるのではないでしょうか。とりわけ、年齢の低い子どもを教える場合、発達上の難しさ——例えば、集中力が続きにくい、大人の言葉の意味や意図を十分に理解できないなど——に直面することがよくあります。それゆえに、大人が先回りしてサポートしたくなるのは自然なことです。しかし、丁寧に教えても、子どもに指導内容がなかなか定着しない、あるいは、子どもが自分から進んでピアノに向かおうとしない、という実態に直面することがあるのではないでしょうか。
そのような時、「どうすれば子どもがもっと主体的にピアノと関われるだろう?」と悩む先生は少なくないと思います。今回の記事では、こうした悩みを考える上でのひとつの手がかりとして、「モンテッソーリ教育」に注目します。
モンテッソーリ教育は、20世紀初頭、イタリアの医師であるマリア・モンテッソーリ(Maria Montessori, 1870-1952)によって提唱されました。「子どもは生まれながらに自分で自分を育てる力を持っている」という理念を中心に据えた教育法であり、子どもの主体性を尊重する姿勢が特徴です。幼児教育を中心として、世界中で実践されてきています。
音楽教育においても、子どもを主体とした教育法は数多く存在します。例えば、ダルクローズ(1865-1950)のリトミックは、身体の動きを通して音楽的感覚、特にリズム感覚の育成を目的としており、感覚と動きの統合を重視するアプローチです。《カルミナ・ブラーナ》の作曲者として有名なオルフ(1895 - 1982)の音楽教育は、言葉や身体を用いたリズム遊びを起点として、オルフ楽器を用いた即興演奏による表現活動を重視しています。特に合唱曲の作曲家として知られているコダーイ(1882-1967)のメソッドにおいては、母国語による歌唱(日本の場合はわらべうた遊び)を通して、音感や読譜力の発達が図られています。
これら三大音楽教育法とも呼ばれるメソッドは、いずれも、学習者である子どもの主体性を尊重し、自ら学ぼうとする姿勢を促進する教育理念です。モンテッソーリ教育は音楽に特化してはいないものの、「環境を整えることで、子どもの自発的な学びを支援する」という教育哲学を基本としている点において、これらのメソッドと親和性があります。音楽指導においても、正しい演奏技術を教えることに留まらず、子どもが自ら音に触れ、感じ、考える体験こそが、より深い学びにつながっていきます。
このような大人が子どもに「教えすぎない」という姿勢は、ピアノ指導にも応用することができます。モンテッソーリ教育の根本には、自分で自分を育てる力を意味する「自己教育力(※原語:autoeducazione=自己教育)」という概念があります。これは、大人が教え込まなくても、「適切な環境」が整えられていることで、子どもは自分のペースで思考錯誤しながら成長するという考え方です。
レッスンでも同様に、子どもは先生から指導を受けるだけではなく、「自分で弾いてみたい」とか、「この鍵盤を押したらどんな音がするのだろう?」といった好奇心や探究心に基づいて学んでいくことが大切です。こうした内発的な動機付けは、まさにモンテッソーリが説く「自己教育力」の表れと言えます。
「教えなければ弾けるようにならない」と思いがちですが、教え過ぎず、子どもが自ら探究する余白を残すことで、より主体的な学びが促されます。すぐに思うようにできない中で、様々な試行錯誤を通してこそ、子どもは自分の力で育っていくのです。
では、子どもの主体的な学びを促すために、先生にはどのような配慮が求められるのでしょうか?モンテッソーリ教育において、大人の役割は知識を伝えることではなく、「環境を準備すること」とされています。この「環境」とは、教材や空間といった物理的なものに限らず、大人の子どもへの接し方や態度も含みます。
レッスンにおいても、正解をすぐに教えるのではなく、子どもが自分で発見できるような「余白」を残すことが重要です。例えば、子どもが間違えそうな時、すぐに訂正するのではなく、少し黙って見守ってみましょう。たとえ間違ったとしても、その経験をもとに本人が考え直し、再び挑戦するプロセスにこそ、受け身の学習では得られない深い学びの価値があります。
この「待つ」という姿勢は、一見簡単そうですが、実際には先生自身の勇気と子どもへの信頼が必要です。けれども、大人のその静かで辛抱強い見守りが、子どもに「先生は自分を信じてくれている」という安心感をもたらします。この信頼関係が、子どもの主体性をさらに引き出す原動力となるのです。
モンテッソーリ教育から学べる最大のポイントは、「子どもは本来、自ら学び、成長しようとする力を持っている」という視点です。そして、私たち大人に求められているのは、手取り足取り教えることではなく、子どもが自ら動き出す環境の整備ときっかけ作りです。レッスンにおいても、教えることに偏らず、「見守る」や「待つ」という選択肢を持つことで、子どもへの関わり方がぐっと良くなるかもしれません。子どもの主体性が育つレッスンは、子どもと指導者の双方にとって、豊かで実りある時間となるでしょう。
次回も引き続きモンテッソーリ教育を切り口に、「子どもが主体的にピアノを学びやすくなるのか」について、より具体的な工夫を紹介します。どうぞお楽しみに!
- Montessori, M. (1916) L'autoeducazione: nelle Scuole Elementari, Roma: P. Maglione & C. Strini.
https://archive.org/details/lautoeducazionen00montuoft/page/n1/mode/2up?ref=ol&view=theater(accessed:2025/08/05)

音楽教育学者。エリザベト音楽大学卒業、同大学修士課程修了。広島大学博士後期課程修了(博士(教育学))。専門はモンテッソーリ教育と幼児音楽教育学。兵庫教育大学学校教育学部講師。
夏休みも明け「指導のいろはnew」も再開しました。次回も藤尾かの子先生のご執筆です。子どもの自ら学ぶ力を支えるポイントとは? 次回もおたのしみに!

