「正しさ」を前に音が止まるとき──保育者・教員養成課程のエピソードから音楽と教育を考える
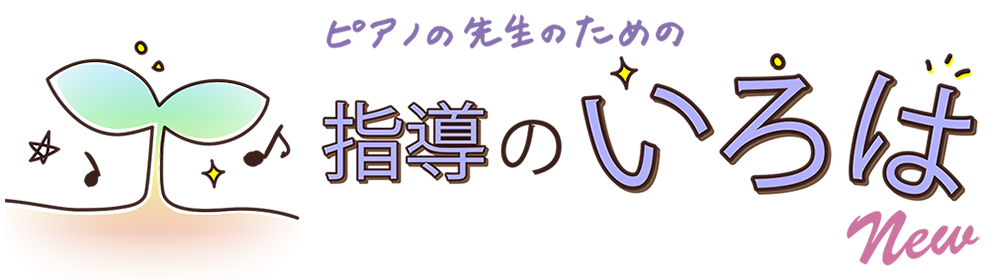
執筆:山辺未希
「先生,これはどうやって使うんですか?」「使い方がわからないから,使えない」——大学で授業をしていると,楽器について,学生からこのような声が度々聴こえてきます。
音を試す前に正しさを考える。その姿勢は,音楽を「自分の外側にある正解」として捉えるようにいざなった教育の副作用ではないか?
つまり,赴くままに音を生み出すよりも,どんな音を出せば「合っている」のかを気にしすぎてしまう。まるで,音楽は他者が絶対的な評価をくだすもので,それに近づけることが音を出す目的であるかのような認識が,知らず知らずのうちに身についてしまっているのではないか——そう感じる場面が,授業の中で何度もありました。
教室に並んだ楽器を目にした瞬間,思わず手に取り,音を生み出す学生がいる一方で,鍵盤にも打楽器にも手を伸ばせず,音を「試す」ことができない学生もいます。もちろん,楽器を大切にしているからこそのためらいもあるでしょう。しかしその背景には,子どもの頃から「正解の音」を教わってきた学びの積み重ねがあるのかもしれません。音楽を自分の耳で判断し,試行錯誤することが難しくなっているのです。音を出す前に,「これで合っているか?」と自問し,立ち止まってしまう学生の姿に,筆者は音楽教育の課題を感じています。音を出すというシンプルな行為の背後に,それぞれの人が積み重ねてきた経験と記憶が,こんなにも静かに,けれど確かに折り重なっていることに,改めて気付かされます。
音を「試す」ことができるかどうかは,単なる技能や性格の問題ではありません。それは,音や音楽とどのように関わってきたかに深く関係しています。たとえば,保育の営みでは,子どもが自発的に音と関わる姿を肯定的に捉え,その営みを受け止めようとするまなざしが大切にされています。このような理念は,子どもの主体的な音楽経験を支える重要な出発点となります。
一方で,保育や学校教育を含む我々の生活では「正確さ」や「評価」が意識されやすくなる傾向も否めません。慣例的な演奏の正しさや完成度が重視される場面が多くなることで,「表現の探究」よりも「決められた正解への接近」が先立つ学び方が生まれることがあります。そのような環境では,「音は教えられるもの」「自分で判断するより,正解に効率的に辿り着くことが大切」と感じてしまうこともあるでしょう。
筆者は大学の授業で,複数人で即興的に音を出す活動を行うことがあります。誰かが音を出し,それを誰かが受けとめ,また誰かが重ねる。そこでは,一人ひとりが自分の音に集中するというよりも,周囲の音に耳を澄ませながら,いつ,どのように音を添えるかを探り合うような関係性がうっすらと立ち上がってきます。
はじめは,各自が戸惑いやためらいを含みながら音を出していても,徐々に,音のあいだにわずかな呼応やゆるやかな変化の気配が見えはじめることがあります。はっきりとした変化が起こるわけではないけれど,何かが変わりそうな,演奏が少しずつ変わっていきそうな,そんな芽生えのような空気が,場のなかに微かに漂うこともあります。
それは誰かが変わった,というよりも,演奏という営み自体が,その場の関係性と共にゆるやかに移ろいでいるように思える瞬間です。
それが「うまくいった」と言えるのか,あるいは何かの「変化」と呼べるのかはわかりません。ただ,その場の音の中に,言葉では言い表せないような呼吸やまなざしが生まれていたことは確かで,その空気に,音楽を学ぶということの根源的な意味がにじんでいたように感じられることさえあります。もちろん,これは授業者としての筆者の視点であり,演奏に参加していた学生たちはまたさまざまなことを感じていることでしょう。
誰かと音を通してつながることで,自分の音が「許される」。この経験は,評価される・教わるといった文脈では得難い,音楽の原初的な喜びとつながっているのではないでしょうか。
即興的な関わりのなかで,演奏が関係性のなかでゆるやかに移ろう気配を感じたとき,筆者は「指導する」とは本来どのようなことだったのか,改めて考えさせられます。
音を整えることでも,促すことでもなく,いまここにある響きをそのままに受けとめる。何かを伝えるのではなく,ただその時間に共にいる,という感覚です。
この感覚は,保育における子どもへのまなざしとも重なります。そこでは,「教える」よりも,「何が生まれようとしているかを待ち,見守り,共にいようとする関わり」が大切にされています。
それが音楽であるかどうかは,さほど重要ではないのかもしれません。けれど,子どもが音に触れ,身体でその間合いを味わおうとするとき,私たちは,そのそばで何を感じ,どのようにその時間と関係を築いているのでしょうか。そのような時間に,私たちはどんな顔で,どんな耳で,共にいるのでしょうか。
音楽を教えるという営みの中で,私たちはつい,楽譜や奏法,表現の方法といった「伝えるべきこと」に意識を向けがちです。しかし,音を「試す」ことをためらわず,自分の耳で聴いて,自分の音を信じて鳴らしてみる——その「迷ってもいい」という手触りにこそ,音楽をするよろこびの原点があるように思います。
私たちにとって,音を鳴らすことは,本来,怖いことではないはずです。けれど,「これで合っているか?」という問いが先に立つとき,音楽は私たちの手元から遠のいてしまいます。音楽は,そっと始まるもの。そう思えるような時間のなかに,私たちにとっても新しい音楽の「はじまり」がふと立ち上がってくるのかもしれません。
そのような時間の積み重ねが,どのような未来の音の風景につながっていくのか——。
本稿では,保育者や教員の養成課程でのエピソードをもとに,筆者自身が教育と音楽について感じ,考えたことを言葉にしようとしてみました。何かの結論を導いたり,特定の方針を示したりすることが本稿の目的ではありません。一人称の語りを通して,読んでくださる方ご自身のご経験やご実践にも,ふと何かを照らし返すようなきっかけがあればと思っています。

音楽教育学者。香川大学教育学部学校教育教員養成課程卒業、広島大学大学院教育学研究科教科教育学博士課程前期終了(修士(教育学))。領域「表現」や音楽科に係る保育者・教員養成課程のカリキュラムおよび授業について研究を行っている。横浜国立大学教育学部助教。
近年特に関心が高まっているモンテッソーリ教育。名前は耳にするものの,何を提唱した人なのかはよく知られていないかもしれません。モンテッソーリ教育のエッセンスとレッスンづくりへのヒントとは? 第一人者の藤尾かの子先生が2回にわたってご担当くださいます。
「指導のいろはnew」も,しばらく夏休み。次回は9月公開です。お楽しみに!

子どもの上達を願うあまり,つい手厚く教えすぎてしまう——そんな経験はありませんか? 特に年齢の低い子どもは,教える側の関わりが強すぎると,自分で弾こうとする力を発揮しにくくなることがあります。次回の記事では,「子どもは自ら育つ力を持つ」という考え方を土台とするモンテッソーリ教育の視点から,ピアノ指導における「教えすぎない」ことの意味と,その実践へのヒントを探ります。

