練習室の外からのインスピレーション
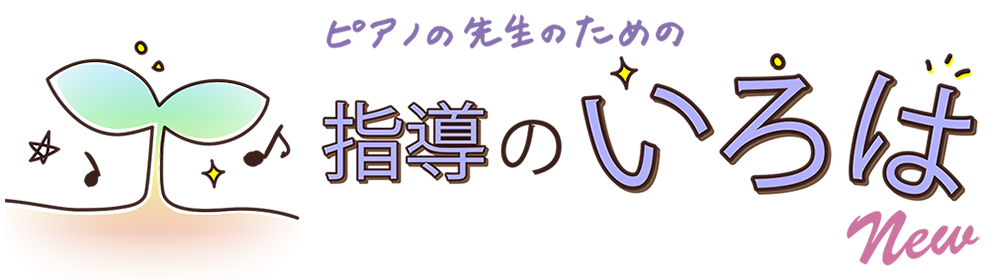
執筆:甲斐万里子
7月に入り,夏休みが見えてきました。ピアニストのみなさんは,どのように過ごす予定ですか? 一部コンクールは本選が控えているタイミングですが,ひとまず一段落,といったところでしょうか。
コンクールや発表会で期待していた結果でなかったり,力が十分に発揮できなかったりすると,次の練習へとモチベーションを保つのが難しいことがあります。そうした時の学習者へは,先生方も最大限配慮なさって声をかけられていることと思います。時にはストイックに「落ち込んでいる暇があったら練習を」と,次なる目標に向けて二人三脚でピアノに向かわれるかもしれません。筆者も「そうなれればなあ」と憧れます。
でも,頭では分かっていても,どうしても練習に身が入らない時や,また,どんなに頑張っていても乗り越えられない壁に押しつぶされそうな時もありますよね。そんな時は,即座に気持ちを切り替えてピアノに向かえなかったとしても,悪いことばかりでないかもしれません。新たな視点を得るべく一旦ピアノから離れてみる,そんな機会が有効に働くことがあります。
今回は,未だ理論的枠組みが十分に確立されていないテーマですが,これから追究,整理していきたいと筆者が考えている研究メモの中から,練習室の外側での学習を取り上げたいと思います。
第2回で轟千尋先生から指摘があったように,楽譜には,作曲家がどうしても記号で表現しきれなかった「行間」が含まれます。音色だったり,音量やニュアンス,そしてそれらの前後のバランスだったり。その「行間」をどう解釈し,全体として辻褄が合うようにまとめあげるのかという点で,演奏家の腕が試されますし,その「行間」があるからこそ,演奏家の独自性,独創性が際立ちます。クラシック音楽の面白い部分です。
そういった緻密な解釈には,音楽理論の基本的な知識や作曲家の書法の学習にとどまらず,底知れぬ「作曲家作品研究」が不可欠です。ですから,そもそも練習室の中だけで学習が成立しないことは,専門家のみなさんにとっては周知の事実でしょう。
でも,考えうる努力をもってしても,どうしてもうまくいかないということもあります。そうした時に思い切って外に出かけてみると,思いがけないところからヒントが得られることがあります。
筆者が以前の研究で追いかけていたピアニストが,美術館での絵画鑑賞から着想を得た体験について,次のように語ってくれたことがあります。
絵に関しては素人だから,きれいだなーとか,こんな色があるんだ,とか,動いている感じがするなあとか(いったことを思う)。でも,絵に関して思うのは,近づいた時に見たときの感じと,遠くからとでは全然違ってて,それがどうやってそういう風に見せているのかな,とか,こう,作り方みたいなのを(中略)音楽に生かせるかなっていうのは思う。
構図を見た時に,すごくおっきい絵だった時とかに,ここ(の一部分)を描いている時でも,きっと(作者には)全体が見えているんだろうな,とか。良い構図で,音楽も勉強しなくちゃいけないなとか。(中略)絵だとよくわかるというか,止まってるし。(甲斐 2017,p. 42)
音楽はよく「時間芸術」と言われますし,基本的には最初から最後に向かって演奏する性格もあってか,全体の構図(演奏でいうと構成でしょうか)を把握して,各部分の演奏表現をどうするべきかを細部まで検討し,バランスを調整していく視点が抜け落ちがちです。
上で紹介したピアニストは,絵画を近づいて鑑賞した時の印象と,一定の距離から鑑賞した時の印象の違いから,弾き手がステージ上で奏でている演奏が客席でどう聴こえるのか,その間にある印象の差分を考慮した表現をどうすれば実現できるのか,という課題を設定することができました。そして,その方略を編み出すための具体的な練習計画を立てることに成功したのです。
「表現力を養うために,良いものを食べて,良い景色を見て,心を豊かにしましょう」といった言葉を,誰もが1度は耳にしたことがあると思います。これは,日常的にさまざまな経験を通して感受性を刺激することが演奏に有効な基礎づくりに貢献する,ということでしょう。そういった意味で先述のピアニストの絵画鑑賞の例を捉えることもできると思います。
でも,特に着目したいのは,行き詰まりを感じている大きな課題がある時に,その課題に引き付けて対象を捉えているという点です。つまり,先の例だと,漠然と絵画を鑑賞していたわけでなく,乗り越えられない壁を念頭に置いた状態で,演奏時の手続きと関連させながら分析的に絵画を鑑賞していたことがポイントなのです。その鑑賞の視点をもっていたことが,課題解決へのインスピレーションを得る助けとなっていることが窺えます。
学校や教室のように組織化,体系化されていない日常的経験や環境との触れ合いから知識,技術,態度,識見を獲得し蓄積していく学習を,インフォーマルな学習と言ったりします。先の例も,インフォーマルな学習に位置付けられるでしょう。一見すると単なる息抜きに見える活動も,れっきとしたインフォーマルな学習になり得,その鍵となるのが,「乗り越えるべき課題に引き付けて考える癖」のようなものだと筆者は睨んでいます。
ピアノ演奏をフィールドにして,インフォーマルな学習が課題解決にどう影響するのかに直接答えるような研究は,まだまだ途上にある印象です。関連するものだと,GauntとHallam(2009)が個人の音楽的スキルの発達に影響を与える相互作用の複雑さを示したモデルがあります。少し複雑ですが内容を説明すると,音楽的なスキルの獲得には,多層的な要因が伴い,また,個人の音楽的な発達および音楽的な環境の変化の両方を刺激することで時に相互変容する相互作用が起こる多層的な要因を含む,といったものです。これはBronfenbrenner(1979)とHettemaとKenrick(1992)の有名なモデルに依拠しています。筆者がこれから解明してきたいのは,この「個人の音楽的な発達」への環境の影響のうち,課題解決にフォーカスしたメカニズム,といったことになります。
近年,筆者が紹介した例のように,エピソードのレベルでは類似した報告も見られ,環境,特に日常場面での学習の重要性に研究者の関心が向けられつつあります。
と,今回はぼんやりした動向紹介にとどまりましたが,普段はご自身にとって外側にあるものを,みなさんそれぞれの課題に引き付けて捉えてみる提案をしたいと思います。立ちはだかる課題に手立てが見つからない時は,せっかくの夏休み。レッスン室を飛び出して,少し羽を伸ばしてみてはいかがでしょうか。
- 甲斐万里子(2017)『ピアニストの熟達化過程-省察内容、演奏表現、レッスンに着目した縦断的な検討を通して-』東京藝術大学大学院音楽研究科博士論文.
- Bronfenbrenner, Urie(1979)The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press: Cambridge.
- Gaunt, H. and Hallam, S. (2009) Individuality in the learning of musical skills. In: Hallam, S. and Cross, I. and Thaut, M., (eds.) Oxford Handbook of Music Psychology. (pp. 274-284). Oxford University Press: Oxford.
- Hettema, P.J. and Kenrick, D.T. (1992) Models of person-situation interactions. In: G.V. Caprara and G.L. Van Heck (Eds) Modern personality psychology: Critical reviews and new directions. Hemel Hampstead, UK: Harvester-Wheatsheaf, pp. 393–417.

音楽教育学者。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学修士課程および博士課程修了(博士(音楽学))。レッスン研究、特に、ピアニストの熟達化を専門とする。和洋女子大学人文学部こども発達学科准教授。
次回からは,ピアノレッスンの多様な対象や場に目を向けます。まずは,音楽と向き合う楽しさについて原点回帰。保育者や教員の養成に携わる山辺未希先生からの問題提起です。お楽しみに!

音を出す,という行為が,当たり前ではなくなる瞬間があります。「これで合っているか?」と,音を出す前に立ち止まる学生たち。音を「試す」ことへのためらいは,いつ,どこで生まれるのでしょうか。保育者・教員養成課程での学生とのエピソードを手がかりに,音楽教育の可能性を探ってみたいと思います。

