音楽コンクールについて考える(後編)
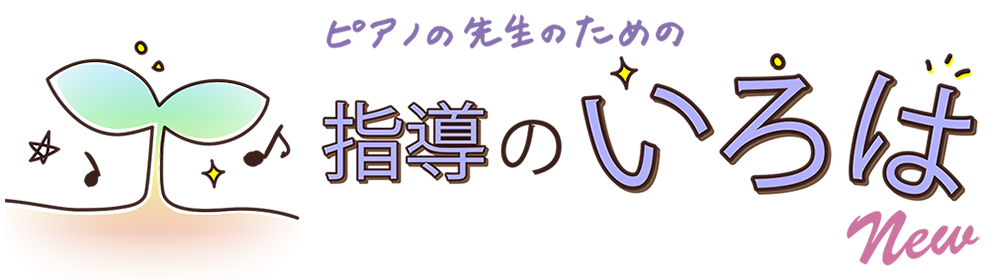
執筆:長谷川諒
前回に引き続き,本稿でも音楽コンクールについて考えてみたいと思います。
前回は,音楽とスポーツを比較したうえで,「音楽には競技性が内在しない」ことを確認しました。野球においては「よいピッチング=試合に勝てるピッチング」という等式を多くの場合認めることができますが,音楽においては「よい演奏=コンクールで勝てる演奏」とは必ずしもなりません。また,野球から競技性を取り去ってしまったらそもそも野球ではなくなってしまいますが,音楽の素晴らしさはコンクールでなくても成立します。スポーツと比較することで「音楽には競技性が内在しない」ことが浮き彫りになりました。
では,音楽に競技性を持ち込むコンクールに価値はないのか,というと筆者はそう考えているわけではありません。コンクール独特の空気のなかで音楽を楽しむことは確かに可能ですし,それはそれで素晴らしいことです。ここで考えてみたいのは,「どうすればコンクールを価値ある体験として楽しむことができるのか」ということです。
みなさんはコンクールに参加される際,審査員の先生の名前を確認しているでしょうか? 審査員の名前があらかじめ明らかにされているコンクールもあればそうでないコンクールもあるでしょう。ピティナ・ピアノコンペティションの場合は,当日入手できるプログラムに審査員の先生のお名前が記載されているそうです。いずれにせよ,ほとんどの場合コンクールが一旦始まれば審査員の方の名前が公表されることが多いのではないかと思います。
さて,多くの人は自分が参加したコンクールでの結果,すなわち賞の色や点数については記憶しているでしょう。では,はたして審査員の先生の名前は覚えているでしょうか? その先生はどんな演奏をする方で,どんなレパートリーが得意で,どんな音楽教育観を持っている方でしょうか? 筆者も学生時代に何回かコンクールを受けましたが(そしてあまり結果は振るわなかったのですが)正直誰が審査員だったのか全く覚えていません。コンクールの結果が振るわずものすごくショックだったのに,それが誰からなされた評価だったのか全く思い出せない──これはいったいどういうことでしょうか。
日常生活において怒られたり褒められたりすれば,それが「誰からの評価だったのか」当然記憶しているはずです。それが自分にとって特別思い入れのある何かについての評価である場合はなおさらでしょう。「評価の価値や意味は,評価する人との人間関係によって大きく変わる」ということを私たちは経験的に理解しています。知らない年上の異性から「素敵な髪型をされていますね」と言われたら多くの場合恐怖を感じそうですが,好意を持っている異性から同じ言葉をかけられたらその言葉に対する印象は全く変わってきます。要するに,「誰に評価されるのか」は「どのような結果を下されるのか」と同じくらい大事なファクターなのです。しかし,音楽コンクールにおいて私達は無意識に審査員の先生を匿名化してしまうところがあるように思います。
コンクール参加者にとって,審査員の先生はある意味において絶対的な権威です。審査員に良い点数をつけられれば報われた気持ちになり,悪い点数をつけられれば落ち込みます。しかし,そもそも評価とは「誰に評価されるのか」が大事なのではないでしょうか。コンクールで評価しているのは冷徹なまでに客観的で絶対に正しい評価を下すことのできる「匿名的な審査員」ではありません。それぞれに個性的で多様な音楽観を持ち多様な音楽を愛する血の通った「顕名的な審査員」なのです。「すべての人から愛されたい」という気持ちも一般論として当然理解できますが,現実にはそうはいきません。必然的に私達は「誰から愛されたいのか」を考えざるを得ないでしょう。同様に,「誰にとっても素晴らしい音楽表現」を目指すことは現実的ではありません。漠然と「素晴らしい演奏」を目指すのではなく「自分の音楽を誰に評価してもらいたいのか」考えてみてもいいかもしれません。
そのためのステップとして,受けるコンクールを決める際にはまず審査員の先生の名前を見て,その先生のプロフィールや演奏をチェックしてみてはいかがでしょうか。あるいはコンクールの結果が出たあとで「この先生はどんなことを大切に音楽している方なのだろうか」と調べてみても良いかもしれません。とにかく,審査員の先生は冷徹で匿名的な機械ではなく個性豊かな人格と音楽観を持った主体である,と考えてみましょう。そうすると,コンクールの結果を相対化して捉えることができるのではないでしょうか。
音楽はその場限りの一回性をもった表現です。どれだけ同じように演奏しようとしても,二度とまったく同じ音楽は生まれません。そしてそれは,審査もまた同じです。どれだけ同じ曲を同じように演奏しても,審査する人が違えば結果も変わる。コンクールとは「一回性と一回性が出会う場」だとも言えるでしょう。
このように捉えれば,結果に一喜一憂するだけのコンクールの見方から少し距離を取ることができるかもしれません。今回はこの先生方がこういう演奏を「美しい」と評価したんだな──それ以上でも以下でもなく,その結果を大切に受け取るということ。そこに絶対的な正しさや普遍的な価値を読み込もうとせず「今回はこういう出会いだった」とピュアに受け止めること。それができれば,結果への納得度やコンクール体験の充実度はぐっと上がるはずです。
音楽に「唯一の正解」がないように,コンクールの評価にも「唯一の正しさ」はありません。音楽コンクールを「異質な他者との邂逅の場」として捉えることができれば,本質的な意味で音楽コンクールを楽しむことができるでしょう。
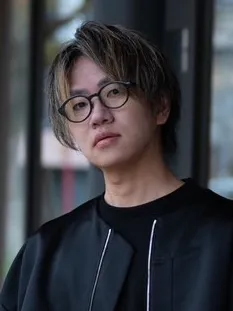
音楽教育学者、博士(教育学)。音楽科教育のあるべき姿を模索すべく、音楽と公共の接点について研究している。主著『音楽科教育はなぜ存在しなければならないのか』発売中。エリザベト音楽大学専任講師。
本連載も次回は第5回。楽しんでいただけていますか? 次回は夏休み目前。練習室の外での学びについて取り上げてみたいと思います。執筆は甲斐です。お楽しみに!

ストイックなピアニストのみなさんほど抱きがちな「まだまだ未熟なのに,関係ないことに時間を使っていて良いのかな」という罪悪感。次回はこの「関係ないこと」に焦点を当てて演奏との関係を考えたいと思います。お楽しみに!

