「指導のいろは」リニューアルスタートのお知らせ
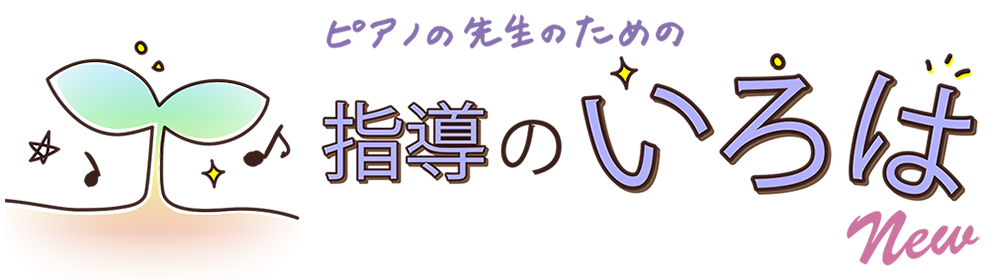
執筆:甲斐万里子
「指導のいろは」がリニューアルしてスタートします。2022年以来、たくさんのエキスパートが率いてこられた本連載の場をお借りして、「レッスン室に横のつながりを!」を目標に、新体制でお届けします。
音楽教育に熱い眼差しをもって研究している専門家が、様々な視点からみなさんの疑問に答えたり、問題提起を行ったりしていきます。音楽教育学や音楽心理学、認知科学、脳科学などなど、さまざまな専門分野の研究者から、演奏家、作曲家、ベテラン指導者まで、バリエーション豊かな専門家が、それぞれの視点から語ってくれます。
中心となって連載を率いてくれる執筆者を紹介します。

先生方の「本当?」「困った!」を大切に、「かゆいところに手が届く」、そんな内容を目指します。連載を通じて先生方とコミュニケーションを取らせていただくのを楽しみにしています。読者のみなさんに、横のつながりが生まれるきっかけになれば嬉しいです。

音高に対応したキーが順に並び、指を一本一本動かしてそれらを操作し、意図した旋律や和音を実現していく…ある程度弾ける人には何気なくできてしまうそのスキルのしくみに光を当てるような記事を書けたらと思います。

作曲家の心のうちを明かすことで、先生方と楽譜(=作曲家)との距離が縮まり、時空を超えた対話がしやすくなればいいなと思っています。
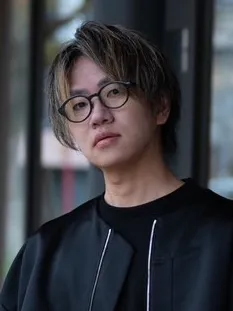
ピアノ教室におけるレッスンは、教育とビジネスを横断する難しくも面白い営為です。その面白さについて語り合うきっかけを作れるよう頑張ります!

モンテッソーリ教育や子どもの発達の視点から、先生方のお悩みを解決する糸口となるような記事を提供したいと考えています。

みなさまと一緒に「目の前の子どもにとって」「私にとって」の文脈から音や音楽との関わりを考えるような連載をめざします。
演奏や指導のエキスパートである先生方からは、「本当はもっと音楽的なことを伝えたいのに、なかなかそこまで指導が深まらない」とか「最近は、昔と比べてレッスンが進めにくい気がする」といった声が時々聞こえてきます。こうした、日頃落ち着いて向き合う余裕がないものの気がかりなジレンマや疑問について、背後にどのような問題が潜んでいそうか、また、どこに解決の糸口がありそうかについて、一緒に可能性を探っていきます。
もしかすると演奏の本質ではない内容で退屈に感じられるかもしれませんが、レッスンを構成している小さな、しかし重要な疑問を丁寧に取り上げ考えることで、レッスンづくりの創意工夫のヒントになり、演奏指導の充実につながれば嬉しく思います。
そう考えると、「指導のいろはnew」は「いろは」というよりも、「指導のいろは〜寄り道〜」とか「指導のいろは〜ひと息〜」いったニュアンスが近いかもしれません。
バリエーション豊かな専門家が、独自の視点で自由に語る連載ですので、同じようなテーマでも、全く異なる考えが展開される可能性もあります。その違いを楽しんで、読者の先生方それぞれの課題に引き付けて読んでください。ご自身のレッスンづくりに取り入れられそうな内容はヒントに、そうでない内容は、批判的に深く考えるきっかけにしていただけるはずです。
「指導のいろはnew」は、先生方にどんどん育てていただきたいと考えています。記事に対して「それって本当?」「現場の実態とかけ離れている」そんな印象をもたれたら、ぜひご意見をお寄せください。先生方の横のつながりの活性化や議論のきっかけになる場として連載を活用していただき、一緒に盛り上げていきましょう!
第1回は、各種セミナーでも大人気の作曲家、轟千尋先生がご担当です! お楽しみに!

コンクールが差し迫る5月。子どもたちは曲に飽きはじめ、指導にも行き詰まりを感じる頃かもしれません。今年は拙作が課題曲になっていることもあり「この曲はどんな気持ちで書かれたのですか?」と聞かれる機会が増え、実はそのたびに言葉に詰まってしまう自分がいます。そんな中、先生方との対話を通して改めて感じたこと、そして作曲家として考え続けていることを、ここに綴ってみたいと思います。

