第26話『惑星の庭(Ⅰ)♪』

「どうして牡蠣が」
「まるで職業見本市」
ふたり同時に言い出して、鍵一と『名無しの詩人』は顔を見合わせて笑ってしまった。
帆船の進みが
accelerando
※2するにつれて、雨は少しずつ小降りになった。今や糸雨が船全体をやわらかく覆って、遠く山間には大量の霧がたちこめている。農村には人影も見えない。冬枯れの麦畑が、どこまでも黒々と広がっている。……鍵一はいま隣に話相手のあることを、あらためて心強く感じた。
「ケンイチ君からどうぞ」
「『名無しの詩人』さんが牡蠣をきっかけに筆を折った、というのは……?」
「牡蠣はバルザック先生の好物なんだよ。ケンイチ君、牡蠣を食ったことあるかい」
「ええ」
「僕は18歳でジヴェルニーの田舎からパリへ出て、生まれて初めて牡蠣を見たんだ。殻のまま山積みになってるのを市場で見て、なんてブキミなかたちのタワシだろうと思ったよ」
「たしかに、焼肉網の焦げなどを取るのによいかもしれませんね」
『名無しの詩人』は鍵一の差し出したパテ・アンクルートへカブりついて、「こりゃうまいや」と目を剥いた。
「ロシェ・ド・カンカル※3……バルザック先生御用達のレストランね、そこより腕が上かも。パテの練りが丁寧。七面鳥、豚、兎、ブラックオリーブ、栗にクルミか。よくぞ個性の強い具材ばっかり集めて、これだけ品良く纏めるねえ。冷めてもしっとりしてるッてことは、パイの焼き上げにムラがないんだね。
高いんじゃないの、これ? もらっていいの?」
「どうぞ、どうぞ。ぼくはパリで半年間、とあるレストランに居候しておりまして」
「噂に聞く、『外国人クラブ』ッてとこ?」
「えッ、ご存じなんですか」
「オペラ座へ出入りする方々の間では有名だよ。でも、一流の芸術家たちは絶対に部外者へ場所を教えないんだ。彼らのああいう結束の固さって、なんだかすごく……羨ましいよ」
うなづいて、鍵一はレストラン『外国人クラブ』の風景をなつかしく思い起こした。夕暮れ時になると、生徒のレッスンを終えたアルカンが音楽雑誌を携えて来る。協奏曲の大作を書き上げたヒラーが、上機嫌にブルゴーニュ・ワインのボトルを持って来る。ベルジョヨーゾ大公妃の音楽サロン※4から抜け出してきたリストが花束をどっさり抱えて来る。ドラクロワがギターごとベルリオーズを担いで来る。シャンパーニュの栓が抜かれ、即興のピアノが鳴り、詩が歌われ、芸術談義に花の咲くところへ、シェフが厨房から湯気立つ大皿料理を運んで来る。洒落のスパイスをふりかけて、親しい食事は夜更けまで続く……
(まるで百年前の出来事みたいだ)
今や遠く離れた『外国人クラブ』の存在を証明できるものは、鍵一と『名無しの詩人』がいちまいずつ食べているパテ・アンクルートしか無かった。
「これはシェフのスペシャリテです。ぼくの旅立ちに際して、餞別にくださったもので」
「不思議な薫りがする」
と、『名無しの詩人』は味わっていた。
「かすかに……なにか珍しいもの」
「シソ(Perilla)です。仕上げの香りづけに少々」
「シソ? あの、川原の土手に生えてる雑草?」
「日本では、生魚にシソの花を添えていただくことが多いんです。パテ・アンクルートにも応用できるかなと思いまして、シェフに話したら採用してくださって。お店で食用に栽培していたんですよ。レストランでお客様に出すときは、シソの花も添えていました。幸い、音楽家のみなさまにも好評で」
「斬新! 日本人ならではのアイディアだね。ラベンダーにちょっと似ていて、でも独特の風味」
「詳しいんですね、お料理……!」
「バルザック先生の『食』の描写※5に魅せられた人間だから、僕は。それに……」
『名無しの詩人』は湿った栗色の髪を掻き上げて笑った。その蒼白い顔に、ちらりと自嘲の影がさした。
「この4年間、カフェやレストランの厨房でも随分働いたからね……パリで食いつなぐために。ほら、なまじ手先が器用なもんだから、五百個のジャガイモを半刻もかけずに剥いたり、ニンジンを薔薇の花のかたちに細工したり、それくらいは朝飯前なんだ。料理を彩りよく盛り付けるのも好き。お客が喜んでくれれば嬉しいし、もっと美しいものを創ってみせたいなアと思う。不本意だけど、そういうとこは庭師の親譲りかな。
生活のために、他にもいろんな仕事をしたよ。乗合馬車の御者、石炭の荷揚げ屋、水売り、ネズミ捕り、郵便配達夫、オペラ座のドアマン……僕はまるで、パリの職業見本市みたいだった」
猫のフェルマータが鍵一の懐からヒョイと顔を出して、聴き耳を立てている。そのあごを『名無しの詩人』はコショコショとくすぐって、
「あッ、そうそう。牡蠣の話ね」
薄墨を流したような空を仰いで、おどけた仕草で肩をすくめた。
「初めてパリの地を踏んだ日、18歳の僕はさっそく出版社の門を叩いた……!」
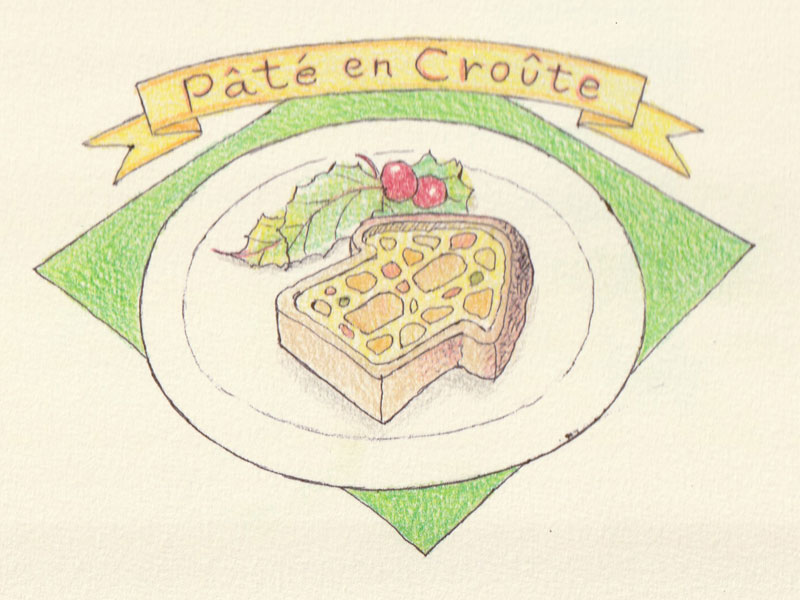
「出版社の門番は僕を見るなり『靴磨きなら間に合ってるよ』ッて鼻先でドアを閉めようとするんだ。食い下がって、自分が詩人志望で、先日送った原稿の評価が知りたくてジヴェルニーの田舎から遥々パリへ来たという事情を必死に説明して、なんとか応接室に通してもらえた。
編集長という人が出てきた。意外に親切で、言葉づかいも丁寧だった。僕に、自作の詩の暗唱はできるかと尋ねた。出版社には日々何十という原稿が送られてきて、それを数人で手分けして読んでいるから、もしかすると読み落としていたかもしれない、という事で。僕が勇んで暗誦をはじめると、二、三行もゆかないうちに『ああ、それなら読んだよ!』と編集長はひざを打って、いったん編集室に引っ込んだ。まな板の上のナマズ※6というのは、まさにああいう事だね。寿命がちぢんだよ。
……しばらくして編集長は戻ってきて、ぼくのために熱い珈琲を淹れてくれた。言葉で言い尽くせないほど複雑な薫りの、とびきり上等の珈琲だった。
『語彙が弱い。ロジックが甘い。バルザック作品の劣化版。とてもじゃないが商品にはならない。でも変な書き癖がついていないだけ、今後の伸びしろはあるとみた』
というのが、出版社がぼくに下した評価だった。続けて編集長はこう言ってくれた、
『うちで働きながら、詩作の腕を磨いたらどうだね。あの原稿は預かっておく。いつかきみがデビューを飾るときに、改稿して世に出せばいい』
僕はありがたくその提案を受けた。近所の安宿の屋根裏に寝泊まりしながら、毎日せっせとその出版社で下働きをつとめたんだ」
「どんな詩だったんですか」
と、思わず鍵一は口を挟んだ。
「その、ジヴェルニーから投稿なさった作品というのは」
「『惑星の庭』」
相手はパテ・アンクルートの残りを口へ放り込んで、照れくさそうにそのタイトルを噛んだ。
「宇宙に漂う惑星の一角に美しい庭があり……月の女神が選りすぐりの美しい花だけをその庭に住まわせる……という。田舎育ちの僕にしてはロマンティックな産物」
「すてきです。『詩情(La Poésie)』と『ハーモニー(L'Harmonie)』を感じます」
鍵一はふと、華やかなグランド・オペラの調べとともに、オペラ座の美しいひとときを思い出した。光に満ちた夕暮れに、馬車が次つぎに沓音を響かせて来る。ほっそりとした白い指を紳士の腕に預けて、ふんわりとドレスをなびかせてゆく貴婦人たちは、花の妖精のように儚く輝いていた。
(選ばれし紳士淑女の庭……)
♪ラバール作曲 :マイアベーアの「悪魔のロベール」による二重奏曲のメランジュ

「ところが、3ヵ月ほど経ったころにさ」
「ええ」
「編集長から、倉庫の屑紙をまとめて屑屋に売ってくるよう言われて。屑紙の山を整理していたら、見覚えのある原稿が」
「……!」
「『惑星の庭』だよ。僕が3年掛かりで書き上げた詩集だ」
笑って『名無しの詩人』は、ワインの小瓶を飲んだ。
「編集長に悪気はないんだ。出版社ではよくある事でさ。忙しい編集者のデスクってたいてい散らかっていて、大物の先生の原稿だって、うっかり紛失しかねないんだから。ましてや無名の詩人志望の、日の目を見るかどうかもわからない原稿なんて、ほかの屑紙に紛れてポイと捨てられちゃってもしょうがない。
……でも、そのときはあたまがまっしろになっちゃって。出版社を飛び出して、気づいたらポン・デザール(『芸術橋』)の上にいた。夏の初めの、風の涼しい午後だった。橋を行き交うパリの人々は、女工も、学生も、辻音楽師も、みんな明るい顔をしてた。僕だけがパリの初夏にふさわしくなかった。
ぼんやりとセーヌ川の流れを見ているうち、死のうかなと思ったよ。あの水をくぐれば、もっと楽しい世界があるのかな……なんて。
でも、いざとなると人間ッて、なかなか死ねないもんだね。欄干に手をかけては脂汗をかき、エイヤと土手から飛ぼうとしてはスッ転び……さて、橋の上を行ったり来たりしているうち、だんだんと日が暮れて。
自分の影がながく伸びて、ふりむけばポン・ヌフ(『新しい橋』)に夕陽が沈むところだった。辺りいちめん茜色に輝いて、空はもう夜の青に覆われて、灯の燈った両岸の建物が、セーヌ川の水面にゆらゆら映って……
喩えようもなく美しい光景だった。そのとき思ったんだ。この景色を美しいと思えるうちは、僕はまだ、文学への夢を諦めちゃいけないんじゃないか……と」

つづく


ル・アーヴルは英仏海峡を臨む港町です。1836年から、蒸気船によるパリ⇔ル・アーヴルの定期運航が始まりました。
音楽用語で『だんだん速く』の意。accel.と略記。対義語『だんだん遅く』はritardando(リタルダンド)。rit.またはritard.と略記。
バルザックやアレクサンドル・デュマ、テオフィル・ゴーティエといった、19世紀パリの文人が集う人気レストランでした。バルザックの著した傑作小説群『人間喜劇』にも、何度も登場します。
イタリアからの亡命貴族であったベルジョヨーゾ大公妃は熱烈な音楽愛好家で、多くの音楽家を自身のサロンに招きました。
バルザックは『食』の描写を通じて、人間や社会の真実を克明に描き出そうとしました。これは当時の文学における画期的な手法であり、現代においても非常に読み応えがあります。
もとい、『まな板の上の鯉』。相手に生死を握られ、逃げ場がない状態であること。