第24話『たゆたえども沈まず♪』

巨きな白鳥のように、帆船は1838年の大晦日をすすんでいた。セーヌ川は深緑色の水をたっぷりと湛えて、鍵一と猫のフェルマータが甲板からそッと水面を覗きこむと、ふたつの影が明るく映った。
(さて、この景色を曲にするとしたら……?)
寒さに足踏みしながら、鍵一は流れゆく水辺の景色を眺めた。
(ドラクロワさんには色彩のちからがある、ジョルジュ・サンドさんには言葉のちからがある。ぼくは音楽のちからがほしい。見聞きしたものを音楽に変換できる能力が……)
船はパリ郊外の街をゆるやかに蛇行しながら、まだ雪の残るブローニュの森に差し掛かっていた。ようよう朝霧が晴れわたると、冬枯れの枝々の間から澄んだ青空が見える。切り立った崖のツララが長い。小さな湾には手漕ぎボートが幾隻も結びつけられて、春夏のなごやかな舟遊びを思わせた。クシャッとくしゃみをして、鍵一は可笑しくなった。
(それにしても、ぼくはまだ19世紀パリの楽しみをなんにも知らない。5月から半年間もパリに居たのに、ブローニュの森でピクニックをしたことも、ボートを漕いだことも、キャンバス ※2を抱えてセーヌ川を散歩したこともなかった。よし、次に来たときはもっと……)
「ニャ♪」
鍵一の腕から跳び下りたフェルマータが、船室へと続く階段をトコトコと降りてゆく。鍵一をふりむいて、しっぽをふわりと揺らした。
「そうだね、探検しよう♪」
頭上に白い帆がはためくのを眩しく仰ぎ見て、鍵一も甲板を降りて行った。

ふるさと横浜の港町で舟遊びには慣れた鍵一も、この19世紀の帆船を探検するのはじつに楽しかった。
長い廊下を歩いてゆきながら、鍵一は遊戯室の白熱するチェス・ゲームを覗いたり(4人制のチェスはなかなかの名勝負ながら、船が傾いて駒が滑ると最初からやりなおしになるので、まったく勝敗がつかなかった)、食堂で焼き立てのチキンをツマんだり(一等客室の乗船切符をみせると、数枚のバゲットとともに香ばしい一皿をもらえた。猫好きのコックは、フェルマータのためにスモーク・サーモンを薔薇の花のかたちに折り重ねてくれた)、うっかり開けてしまったシガールームに噎せたりして(ジョルジュ・サンドのくゆらせていた紫の薫りと違って、紳士のふかす煙はなぜあんなに不味いのかしらと、鍵一はいつも不思議に思う)、狭い廊下でお互い身体をななめにして乗客とすれ違うたび、「Bonne année!(良いお年を)」と笑い合った。レヴェイヨン※3を待ちきれない人々はチーズやワインを手に手に、手持ちの衣装のなかで一番カラフルな恰好をして笑いさんざめいて、鍵一のいでたちを誰も気に留めない。船内のあちこちからグラスとグラスのぶつかり合う音が、「Santé!(乾杯)」の声と共に咲いていた。
一等客室は書斎の奥に在った。
扉の前で様子を窺っていると、
「お待ちしておりました」
腕ッぷしの強そうな水兵がぬッと直立したので、鍵一は腰をぬかした。
「……あやしい者ではありません、ぼくは」
「ケンイチ様ですね。シャルル=ヴァランタン・アルカン様より、くれぐれも丁重にと仰せ付かっております」
と、武骨な手つきで談話室へ通してくれる。船内ながら上等なしつらえの八角形のその部屋は、一瞬にして身体が溶けるほど暖かかった。正面に大理石の暖炉があかあかと燃えて、天井のシャンデリアに桃橙色の光を映している。
(さすが、一等客室は豪華だな……!アルカンさん、お心遣いに感謝します)
奥のソファに一見して貴族と分かる、白いドレスの貴婦人がひとり。傍らに立派な口髭の紳士がひとり。彼らは鍵一に目もくれず、美しい彫像のように、レースのカーテン越しに外の景色を眺めていた。気後れして鍵一がウロウロと見まわすと、長椅子にしなやかな足を投げ出している眠り人あり。
(きれいな男の子……女の子?)
帽子で顔を隠して寝息をたてるその人の、つまさきが水色の絹の靴下につつまれているのを、鍵一は気恥ずかしいような心地で見た。……結局、一等客室にはトランクだけ預けて、にぎやかな二等客室のほうへ行ってみることにした。
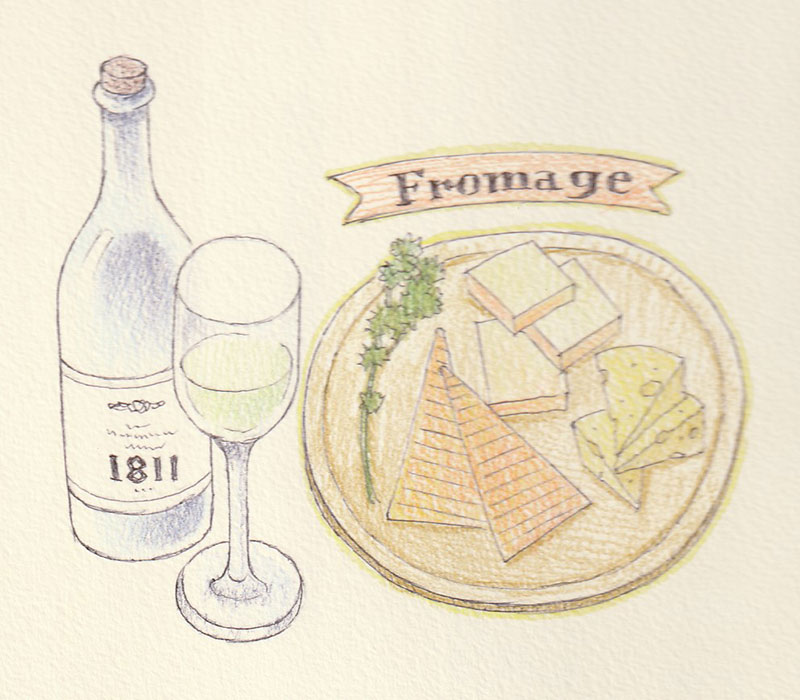
階段を上がるなり、アコーディオンのフォルティッシモに額を殴られる。鍵一は目を剥いて、だだッ広い談話室を見わたした。この大部屋では、すきま風の冷たさより人々の熱気のほうが勝っていた!
二等客のざっかけない人々は薪ストーブのまわりにくつろいで、あるいは珈琲を片手に噂話で盛り上がり、あるいはカードゲームに一喜一憂し、あるいはピクニックよろしく持ち寄った食べ物(小さくとも真っ赤な林檎たち、黒いまんまるのライ麦パン、濁ったびんづめの炭酸水など)を大判のハンカチーフにひろげて、即席の歳末バザールをひらいたりしている。その人いきれのムッと湧き立つなかを、小柄なアコーディオン奏者がひとり跳ね回りながら、人々から曲の注文を受けると、ロッシーニの『セビリアの理髪師』だろうが、パガニーニの『ラ・カンパネッラ』だろうが、マイアベーアの『悪魔のロベール』※4だろうが、なんでもかんでも
allegro con brio
※5で弾いてしまう。作曲者の意図もヘッタクレもないムチャクチャなこの演奏が、なぜだか今この場にはぴったり合っている気がして、鍵一は思わず声を出して笑ってしまった。
……と、アコーディオン奏者と目が合った。すぐさま相手は鍵一のところへピョーンと跳んで来て、おどけた手つきで自分の楽器を示して、曲の注文を催促する。
「すみません、ぼく、あんまりお金がなくて……あッ、これでよろしければ」
と、鍵一は急いでパテ・アンクルートをひときれ差し出した。相手は大げさに低頭して受け取ってみせて、ひとくち齧ってニッコリとうなづいた。交渉、成立。
「アルカンさんの『舟遊び』をぜひ」
と鍵一が言うやいなや、アコーディオン奏者は大きくうなづくと左胸に手を当て、ピーンと背筋を伸ばした。そうして意外にも
adagio
※6で弾き始めた。
それは決して巧い演奏ではなかった。指はもつれ、大切な和音はぽろぽろとこぼれ落ちて、たやすく川風にさらわれて行った。
(でも)
と、鍵一は自分がチェルニー氏の前でベートーヴェンのソナタを弾いたときのことを、我知らず思い出した。
(この人は、アルカンさんのこの曲が好きなんだ。わかる。愛着が伝わってくる)
Bravo、と声を掛けようとして、しかし船がぐらりと揺れて「ワッ」鍵一は柱にしがみついた。アコーディオン奏者は笑って、
「『たゆたえども沈まず(Fluctuat nec mergitur)』※7」
平気で楽器を弾き続けながら、大部屋の人々のなかへ戻って行った。
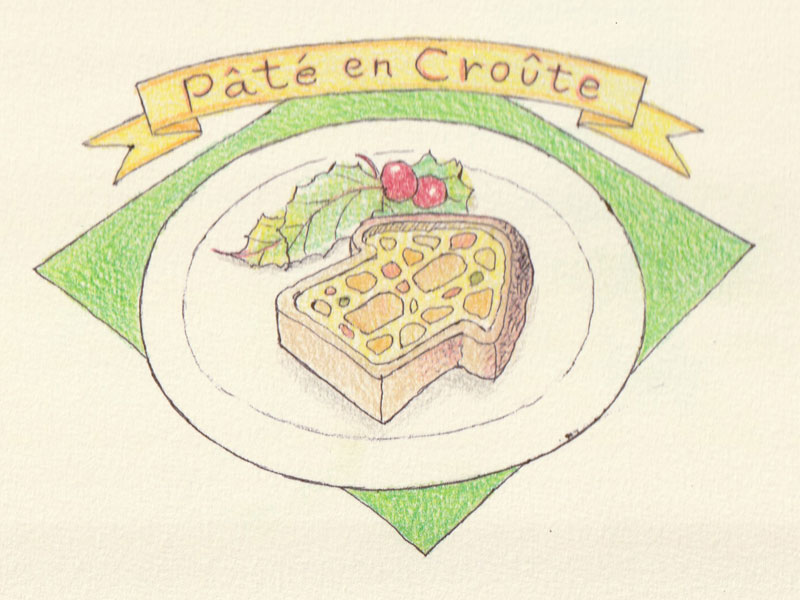
つづく


ル・アーヴルは英仏海峡を臨む港町です。1836年から、蒸気船によるパリ⇔ル・アーヴルの定期運航が始まりました。
船の帆布。または、油絵を描くときに用いられる布。
フランスの慣習となっている、大晦日の晩餐会。フランスの人々は日が暮れるとすぐ友人同士で集まり、夜更けまで豪華な食事を楽しみます。
クリスマスをレヴェイヨン・ド・ノエル(Réveillon de Noël)、大晦日をレヴェイヨン・ド・サンシルヴェストル(Réveillon de Saint Sylvestre)と呼び分けることもあるようです。
音楽用語で『新鮮な動きをもって速く』の意。
音楽用語で『ゆるやかに』の意。
パリ市の標語。元々は水上商人組合の船乗りたちの言葉でした。16世紀から現在に至るまで、パリ市の紋章には帆船の絵と共に、このラテン語の標語が掲げられています。