第23話『歌の翼に♪』

さても1838年パリの大晦日は賑わしかった……!人々はみな薔薇色の頬をして、新年のプレゼントらしき大きな包みを抱えてゆく。新聞屋の店先にリボンが山と積まれている。あちこちから焼き立てのパイの匂いが流れて来る。仕立屋の前に馬車が列をなしている。パティスリーのワゴンにきらきらひかる砂糖菓子。子供らがキャッキャと笑い騒ぐ。犬がほえる。猫は屋根に丸くなる。花屋は籠いっぱいに色とりどりの花をあふれさせて、オペラ座でもカフェでも、ギャルソンが熱心に窓ガラスを磨いている。……鍵一が目をぱちぱちさせながらポン・ヌフのたもとへ走り出ると、セーヌ川はパリの活気を映して光の川であった。
(普段より船が多い……!ル・アーヴル港ゆきの船※1はどれかしら?)

人垣の後ろから伸び上がって眺めるほどに、両岸の船着き場にはじつに大小さまざまの船が浮かんでいた。街の喧騒は川風に吹き流されて、対岸に停泊する優美な客船の帆をはためかせている。その船影から小走りに蒸気船が出航すると、外輪の立てる波が川面を白く輝き渡らせて、岸に着けた小さな手漕ぎ船の群をようようと揺らした。と見るや、こちらの船着き場にはいま、大型蒸気船が黒煙を噴き上げて錨を下ろすところ。若い水夫たちが荒縄を抱えて
sfogato
※2に桟橋を走ってゆく。
橋詰には見送りの人、出迎えの人、見物するだけの人々がぎっしり詰めかけて、ハンカチで鼻をかんだり、帽子を振ったり、外国からのめずらしい荷揚げ品を見つけては笑い興じたりする中を、馬を引いた水夫たちが荒ッぽく叫びながら、積み荷や乗客を通そうとする。
「おお」と人々からどよめきが漏れて、太陽の色をしたまんまるのオレンジがいくつか、馬の背に載せた木箱から転がり落ちたのであった。
(スペインから輸入したのかしら。ショパンさんとジョルジュ・サンドさんの旅先の)
と鍵一が思う間もなく、この南国のかぐわしいフルーツは人々にすばやく拾われ、堂々とネコババされた。今日ばかりは果物商もおおらかに、福の神のように馬上でニコニコしながら、黄金色の商品が手に手に拾われるに任せている。
(いけない、忘れるところだった)
鍵一は川沿いの遊歩道を進むと、郵便ポスト※3へジョルジュ・サンド宛の手紙を投函した。船着き場に向かおうとして、石段の途中で踏みとどまる。スタタと駆け上がって郵便ポストの前に背筋を伸ばすと、大きく2回、カシワデを打った。そのまましばらく栗の樹にもたれて、大晦日の船着き場の景色を眺めていた。……
じつのところ、当初の計画では、鍵一は船に乗るつもりはなかった。パリの街角の、どこか人目につかぬところで鍵盤ハーモニカを吹いて、すぐにでも2019年12月31日の京都へワープしようと思っていたのである。
(まさかアルカンさんが、これを下さるなんて)
懐から取り出したのは、いかにもル・アーヴル港ゆきの、大型帆船の乗船切符に違いなかった。冬の陽にかざせば、一等客室を表す星のしるしが白く浮かび上がる。……数日前、鍵一が洗濯物を担いで※4レストランへ帰ると、入れ違いにこの切符が届けられていた。すぐ引き返してアパルトマンを訪ねたものの、相手は先ごろ亡くなった父親の喪に服して、鍵一はしずかに面会を拒まれた。
(やはり、海まで旅してゆくべきかしら?ぼくは……)
ふと音楽を感じてふりむくと、辻音楽師のヴァイオリンがメンデルスゾーンを弾き出している。おぼつかない指が紡ぎ出すメロディに、鍵一は心の中でそっと伴奏を付けた。
♪メンデルスゾーン作曲 :6つのリート 第2番 歌の翼に Op.34-2
リスト編曲版

突如けたたましく鐘が鳴り響いて、鍵一は身をのりだした。
「ル・アーヴルゆき、まもなく出航……!」
の呼び声に、人波がどっと動く。猫のフェルマータが「ニャッ」と跳ねたのを鍵一は抱き上げて、「よし、あの帆船だな」トランクを提げて桟橋へ駆け下りた。仰げば空いっぱいに白い帆が張っている。水夫の訝しげな視線を足早にすりぬけて、鍵一はまっすぐに甲板へ上った。青。白。赤。ポン・ヌフから人々が小さな旗を振っている、そのトリコロールが目に染みる。吹き飛びそうになるカンカン帽を押さえて、……ふいに鍵一は、なつかしい感覚にとらわれた。
歓声を上げている人ひとりひとりの表情がくっきりと見える。ほほえむ紳士の口髭の片方がピンと撥ねている。若い女工が口に手をあてて、なにか叫んでいる真珠のような歯並び。連れ合いに耳打ちしている銀髪の老婦人の目の下のホクロ。
(この光景、ずっと前にも見たことがあるような)
鍵一のこめかみが変拍子で脈を打ち始める。ひざこぞうがガクガクと笑い出す。
(そう、コンクール決勝の舞台を弾き終えて客席へ向き直った、あの瞬間だ……!客席の人ひとりひとりの顔がこんなふうにハッキリ見えた。心臓がドキドキして、ひざのふるえが止まらなかった。あのとき、ぼくは……)
と、出航の合図の鐘が打ち鳴らされて、はっと鍵一は岸辺を見た。白波を盛り立てて、ゆっくりと船が動いてゆく。ふるえているのは自分のひざではなかった。船全体の振動であった。
(ぼくはただ……)
鍵一は猫のフェルマータをギュッと抱えなおして、モフモフの毛皮が温かい。岸を離れた船はポン・ヌフの下をくぐり、また陽にさらされたかと思えば、すばらしい速さで進み始めた。風に吹きちぎれた波しぶきが痛いほど頬に当たる。19世紀パリがみるみるうちに遠ざかる。
(ただ、ただ、嬉しかったんだ。自分の音楽を、だれかと共有できたことが……)
ショパンに出会ったオペラ座が、リストにぶつかッたパリ音楽院の角が、ドラクロワと肝試しに行った芸術橋が、ベルリオーズのかき鳴らすギターの音色が、ヒラーの乗せてくれた馬車が、アルカンのアパルトマンが、ジョルジュ・サンドへ一輪のラベンダーを買い求めた花屋が、洗濯物を抱えてまいにち往復した道が、つい三十分前までクロワッサンが湯気をたてていた『外国人クラブ』のレストランが、なつかしい歌になり、淡い絵になり、やがて朝霧の遠い影になった。
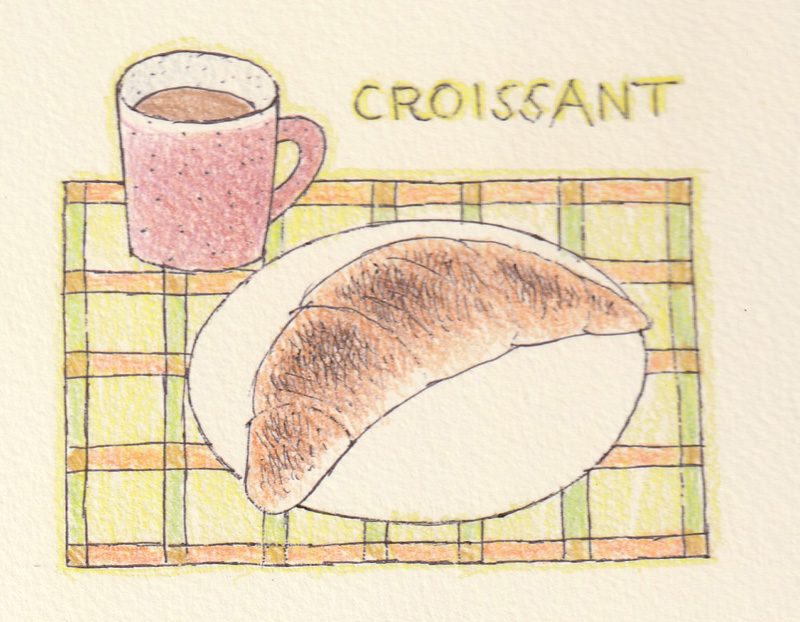
つづく


ル・アーヴルは英仏海峡を臨む港町です。1836年から、蒸気船によるパリ⇔ル・アーヴルの定期運航が始まりました。
音楽用語で『軽快に』の意。
パリの郵便博物館では、19世紀に使用されていた青い郵便ポストを見ることができます。
1838年パリでは上下水道がまだ整っておらず、多くの市民はセーヌ川沿いの公衆洗濯場を利用していました。