第21話『ふるさとは、遠きにありて♪』

♪ショパン作曲 :エチュード集(練習曲集) 第3番「別れの曲」 Op.10-3 CT16 ホ長調
(なつかしい……この曲)
鍵一がそっと耳を浸すままに、フランツ・リストの弾く『別れの曲』が1838年パリの冬をうるおして、この『外国人クラブ』のレストランにも、朝の光が満ちて来る。ごくアッサリと弾きこなすその音楽が、夜の間に結露した景色をほどいて、パリの朝は眩しい。
指先が焦げるほど熱い黄金色のクロワッサンを頬張りながら、鍵一には懐かしさの正体がわからなかった。それは幼いころの幸せな誕生日の記憶のようでもあり、初めてこの曲を人前で弾いたときの緊張のようでもあり、このさき一生を懸けて届かぬ儚い夢のようでもあり、つい半年前にこの19世紀パリへワープして来てからの、さまざまの人と出会った道筋を辿るようでもあった。
(ぼくのたった18年の人生にも、いろいろな種類のなつかしさが埋まっている……)
鍵一がしんと背筋を伸ばして聴き入るのを、隣でヒラー氏が「おおーう」熊のような伸びをして、かまわず喋り出した。
「この曲を聴くと、むしょうに故郷が恋しくなるなあ。どう、ケンイチ君」
口ごもって鍵一がピアノのほうを見遣ると、弾き手は澄まして、かまわず弾き続けている。
「ヒラーさんのふるさとは……ドイツ、ですよね」
テーブルクロスにたゆたう音色を気にしながら鍵一が声をひそめると、
「フランクフルト。かの文豪、ゲーテ大先生と同郷が自慢」
快活な返事が来た。鍵一はうなづいてふと、尋ねてみたくなった。
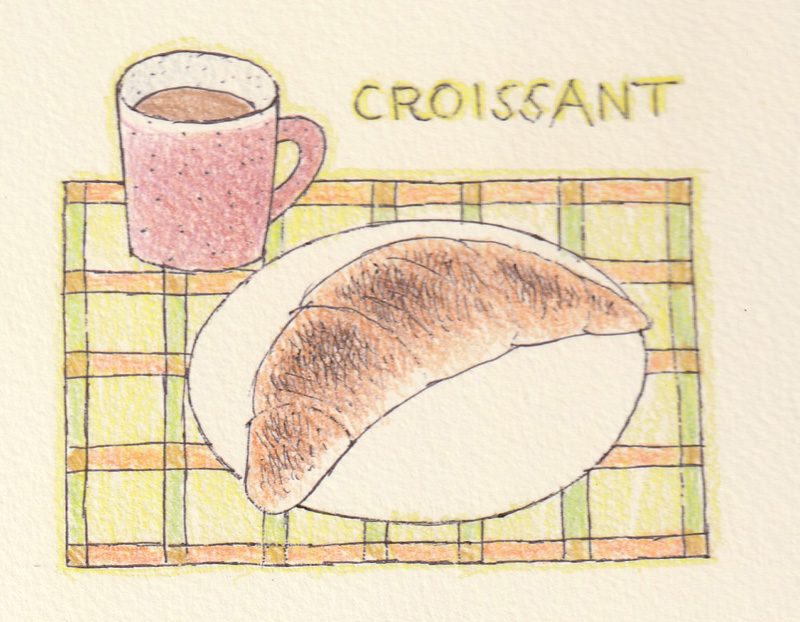
「ヒラーさん、お正月はどう過ごされるんですか?」
「明日からフランクフルトへ帰るよ。久々に、家族とのんびり過ごすさ。フランス土産の最高級シャンパーニュを雪で冷やして、一生分ほど乾杯するんだ。Prost(プロースト)!で、二日酔いにはカートッフェルズッペ※1」
「楽しそうですね」
「ケンイチ君もいつか遊びに来なよ」
と言うなり懐から五線紙を取り出して、このヴィルトゥオーゾは故郷の地図を描き始めた。五線譜を川に見立てて、橋や舟をすらすらと描き出してゆく。猫のフェルマータがヒョイと椅子に跳び乗って、筆の動きをおもしろそうに眼で追っている。
「大きな川の流れている街でね。子どものころはよく、この橋のあたりで川遊びをしたよ。今は亡き親父殿と一緒に、パガニーニのヴァイオリン・ケースぐらいある巨大ナマズを釣り上げたこともあったっけなア。……さて、この川沿いの散歩道をどんどん下ると、シュテーデル美術館※2。今年で開館20周年だったかな?中庭に自生してるラズベリーが美味い。すばやくこっそりつまむべし。東門から街へ抜けると、のんびりした商店街。このパン屋は仕事が大雑把で味はイマイチだけど、おかみさんのシャベリは一級品。おれの友達だと言えば、パサパサの自家製バームクーヘンをオマケしてくれるよ。付け合わせにジャムが欲しければ、三軒先の八百屋へ」
と、八分音符をチョンチョンと書き連ねた。
するとリストが
alla tedesca
※3にアレンジして弾き始めたのが、
♪ショパン作曲:エチュード集(練習曲集) 第1番 「エオリアンハープ」 Op.25-1 CT26 変イ長調
「オヤッ、名曲」と笑って、ヒラーの筆が地図に家々を描き加えている。
「菩提樹の広場から坂道をずうッと上って……赤い屋根に不格好な風見鶏を見つけたら、それがおれの家だよ」
鍵一は五線紙に描かれた風見鶏を見つめた。高らかに鳴くその鶏の、身体がまるで竪琴のように見える。
「なんだか楽器みたいですね」
「ご名答。風見鶏のかたちをしたエオリアン・ハープ※4だよ。18歳の春におれが創った。いよいよ明日はパリへ移住、という前の晩にさ。旅支度をして早めに床に就いたんだけど、眠れなくて。窓を開けて、しばらく夜を眺めてた」
筆を置くとヒラーは珈琲をすすって、この人にはめずらしく、少し言い澱んだ。鍵一はそっと尋ねた。
「何を考えていらしたんです」
「自分は生まれ故郷に何か痕跡を残せたんだろうか、と考えていた」
(痕跡……)
鍵一はうつむきざまに珈琲カップの底を覗いて、18歳のフェルディナント・ヒラー青年の、今より幾分スリムで、今と同じように瞳を煌めかせた姿を思い描いてみる。

「パリでデビューするまでは故郷に帰らないつもりだった。デビュー出来なくても、帰らないつもりだった。フンメル先生に合わせる顔がないしさ」
「デビュー出来たら……?」
「やっぱり帰って来ないつもりだった。ハハハ。音楽家として身を立てられるようならパリに拠点を置いて、行けるところまで行ってやろう、ッてつもり。『故郷に錦を飾る』ってそういう事だと、18歳のおれはかたく信じていたよ。で、この夜も見納めかなア……なんて、まだ出発してもいないのに、家の窓辺でノスタルジアに浸ってた。
すると夜を透かして、聴こえてきたんだよ、その音楽が。
風の神が、熱々のカートッフェルズッペ※1をそッと吹いているような……何とも言えず温かな、美しい音だった。たぶん、何かの夜鳥の声なんだけれどね。
これだッと思いついて、ありあわせの材料で一心不乱に創ったよ。夜明け、まだ近所のニワトリさえまどろんでいるうちに、屋根によじのぼって取り付けておいた。おれが何処へ行こうとも、おれのほうへ故郷の音を響かせてくれるように、とね」
鍵一は想像する。常に吉方を向く風見鶏。川を渡って来た風神がそッと息を吹きかけると、赤い屋根の『痕跡』は羽をふるわせて、故郷を奏で続ける。……フェルマータの猫耳がヒョイと動いた。
「聴いてみたいです、いつかぜひ」
「ハハハ、自己満足の産物だけどね。……でも時々、このパリの雑踏の中で、それらしき音を耳にすることはあるよ。後ろから遠く響いて来る」
「夜ですね」
「そう。でも、振り返ると音は止むんだ。だから振り返らない」
ふいにリストが「ふるさと、ふるさと……か!」弾き続けながら独りごちた。
「帰る国があるというのんは、うらやましいもんやなア」※5
「何言ってんの。世界中どこでも、リスト君の家みたいなもんでしょうが」
答える代わりに軽やかに弾き出された音楽が、珈琲の薫りに溶け混じりながら流れてゆく。鍵一はふたたび、珈琲カップの底を覗いてみた。18歳のフェルディナント・ヒラー青年の肖像はゆるやかに崩れて、未だ見ぬ、けれども2020年には確実に存在しているであろう彼の墓のかたちに変わった。
「ケンイチ君はどこか、行ってみたいところはある?ドイツで」
ふいに尋ねられて鍵一、『このヴィルトゥオーゾの墓を磨いてみたい』という気持ちがかすめて思わず、
「お墓参り」
と言ってしまった。相手が「わかる」と大きくうなづいたので、なおさらばつが悪くなった。
「わかる。おれもワイマールでフンメル先生に付いてたころ、レッスンの合間によく墓地を散歩してた。落ち着くんだよねえ」
「ええ、励まされます。ワイマールの墓地は美しいでしょうね」
「静かで、緑が美しくて、空から小鳥の声が眩しく響いてさ。いいよね、墓地。行き詰まったときにゲーテ先生の墓石に相談したり、嬉しいことがあればシラー先生の墓前で乾杯したり。昨年お亡くなりになったフンメル先生の墓もワイマールに在るよ」
「この地図、いただいてもいいですか」
と、鍵一は急いで手を伸ばす。自分から言い出したくせに、墓参りの話を早く止めてしまいたかった。「おう、いいよ。こんな物でよければ」と故郷の地図を笑って手渡してくれる、目の前の人がもうとっくに故人なのだと、今は認めたくなかった。厨房からシェフが大皿を担いで来て、
「ケンイチ、弁当包んでやるよ」
見ればレストラン『外国人クラブ』のスペシャリテ、家のかたちのパテ・アンクルート。
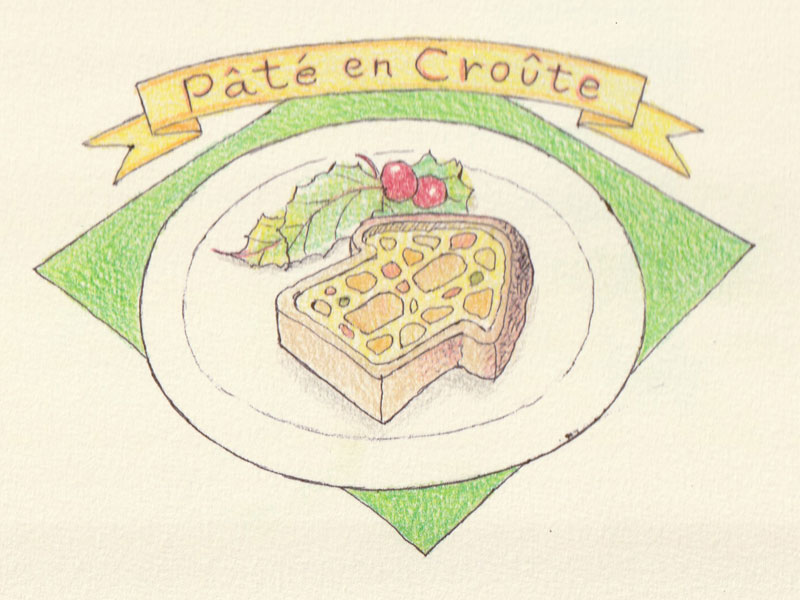
つづく


ジャガイモのスープ。ドイツ/オーストリアの郷土料理。鍵一の師・B氏の得意料理(通称『B級グルメ』)でもあります。
1818年に設立された、ドイツ・フランクフルトの美しい美術館です。
音楽用語で『ドイツ舞曲風に』の意。
19世紀に流行した、自然の風によって音が奏でられる弦楽器。浜松市楽器博物館にて、実物を見ることができます。
ハンガリー出身のリストですが、ドイツ語を話す両親の元で育ち、パリを拠点に音楽活動をおこなったことから、生涯ハンガリー語を習得する事はありませんでした。
しかし故郷への愛は深かったようです。1838年のドナウ川氾濫の際には多額の寄付をおこない、1875年にはブダペストに音楽大学を設立する等、祖国のために尽くしました。