2.《30のメカニズム練習曲》作品849~タイトルの解読
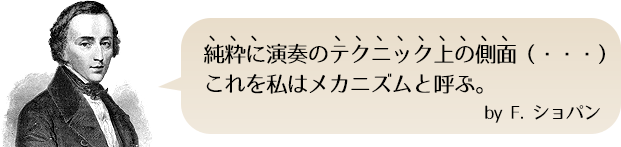
さて、チェルニーの原題に戻りましょう。「30のメカニズムのエチュード30 Études de Mécanisme Op.849」―ここから、何を読み取ることができるでしょうか。
まず、「849」という作品番号が指し示すのは、チェルニーが出版した849番目の作品、ということです。849!同時代の他の作曲家を見ても、流石にここまで多くの番号を書いた作曲家はいません。チェルニーの作品番号はさらにこのあと861番まで続きます。ということは、この練習曲はチェルニー作品の中でも比較的後期作品ということになります。ウィーンの初版が何年かはまだ確認できませんが、少なくともパリで出版されたのは1856年、チェルニーがなくなる一年前のことです。
一般的に「メカニズム」という言葉は、物事が起こる仕組みのことを言いますね。しかし、じつはこれ、19世紀のフランスではれっきとした「音楽用語」で、1870年代には辞書にも音楽の専門用語として意味が掲載されています(ちなみにフランス語の正しい発音では「メカニスム」と濁りません)。1874年に出版されたE. リトレ編纂のフランス語辞書項目から引用します。
そう、既にお分かりのとおり、「メカニズム」とは、指や腕の動作といった、演奏の客観的な側面を意味するのです。「メカニズム」という言葉が、いつごろから音楽的な文脈の中で使われるようになったのかは定かではありません。しかし、少なくとも19世紀のごく初期には、ルイ・アダン教授のパリ国立音楽院公式メソッドに掲載された院長サレットの報告文書の中に、形容詞の形(「メカニック」)で登場しています。
もう少し年代を下ってみると、カルクブレンナーが1831年に出版したメソッドで「メカニズム」という用語を用いています。
つまり、中途半端に音階練習その他の訓練をしないでベートーヴェンを弾くと、正しい指使いができない、つまりはフレーズを上手につくれなかったり、さまざまなニュアンスをつけられなくなったりしますよ、ということです。
一時期、カルクブレンナーに傾倒していたショパンも1844年から46年にかけて書いたとされるメソッドの草稿で、やはりこの言葉を同様の意味で用いて言います。ショパンは、ちょうど後のリトレの辞書で定義されているように、「メカニズム」を「様式」の対義語として捉えています。
いくつかの用例を通して、「メカニズム」の意味がいよいよはっきり見えてきました。どうやら、メカニズムとは、先に引用した末吉先生の解釈「音楽と演奏を成り立たせているしくみ」というよりは、もっと意味は限定的で、「演奏を成り立たせるテクニックのしくみ」と言ったほうが適切であるようです。もちろん、「30番」には、冒頭で述べたように作曲上の細やかな配慮がみられるにせよ、テクニックに重点を置いた練習曲だ、ということをチェルニーはこのタイトルで言わんとしているのです。


